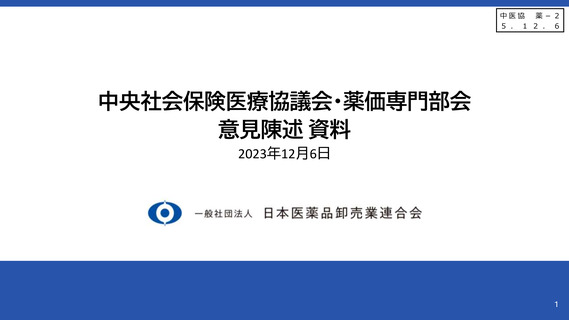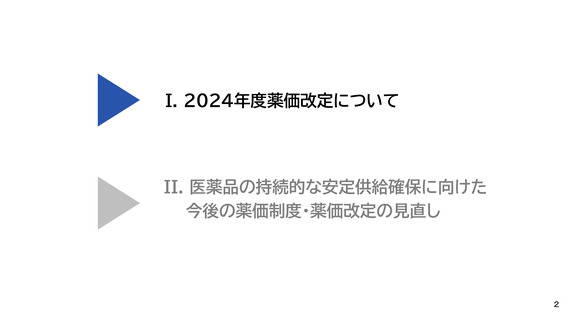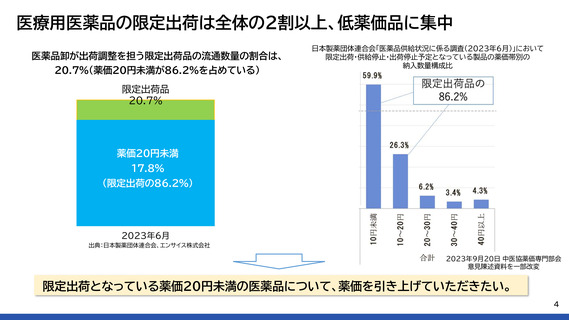よむ、つかう、まなぶ。
薬-2○関係業界からの意見聴取について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00083.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第219回 12/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現行の薬価制度・薬価改定の問題点と見直しの必要性
現行制度では、公定価格として薬価を決め、市場実勢価主義により改定を行っているが、以下の点が通
常の競争市場とは大きく異なっており、それにより様々な弊害が生じている。
• 製品(医療用医薬品)の価格(薬価)が公定されており、それが保険償還額となっているため、自由競争下では必然
的に薬価差が発生する。
• 現実の価格交渉においては、取引先から前年度の薬価との乖離率を反映した金額をベースに交渉を求められる
ことが多く、薬価差を大きく縮小することは難しい。
• 公定価格が上限として機能しており、物価上昇に伴うコストアップがあっても価格転嫁することが難しい。
• 生命関連製品を対象とし、価格が公定されていることから、市場の需給調整機能が働きにくい。
市場実勢価主義そのものを否定するのではなく、この10年で従来の医薬品とは商品特性や流通方式が
異なる医薬品が増える等により、現行の市場実勢価主義に馴染まなくなっている。
今後、現行の薬価制度・薬価改定の見直しが必要である。
7
現行制度では、公定価格として薬価を決め、市場実勢価主義により改定を行っているが、以下の点が通
常の競争市場とは大きく異なっており、それにより様々な弊害が生じている。
• 製品(医療用医薬品)の価格(薬価)が公定されており、それが保険償還額となっているため、自由競争下では必然
的に薬価差が発生する。
• 現実の価格交渉においては、取引先から前年度の薬価との乖離率を反映した金額をベースに交渉を求められる
ことが多く、薬価差を大きく縮小することは難しい。
• 公定価格が上限として機能しており、物価上昇に伴うコストアップがあっても価格転嫁することが難しい。
• 生命関連製品を対象とし、価格が公定されていることから、市場の需給調整機能が働きにくい。
市場実勢価主義そのものを否定するのではなく、この10年で従来の医薬品とは商品特性や流通方式が
異なる医薬品が増える等により、現行の市場実勢価主義に馴染まなくなっている。
今後、現行の薬価制度・薬価改定の見直しが必要である。
7