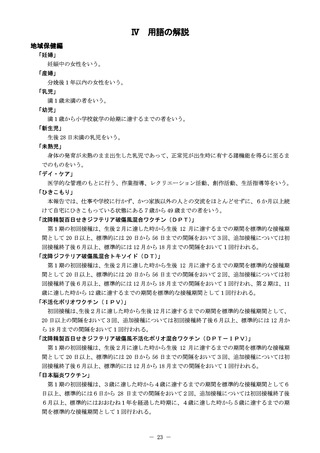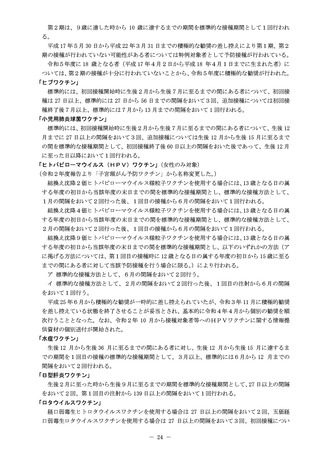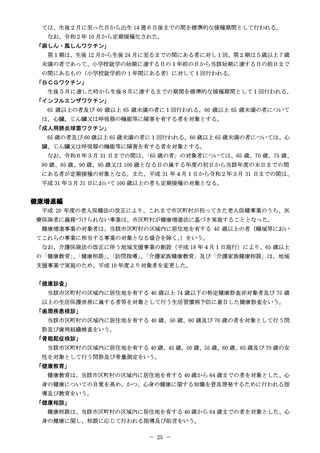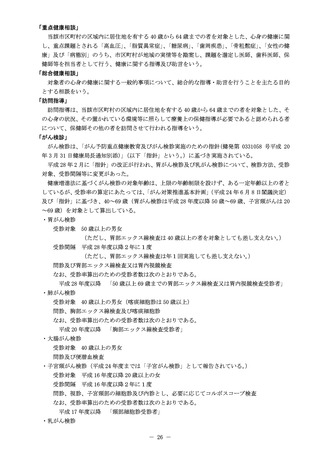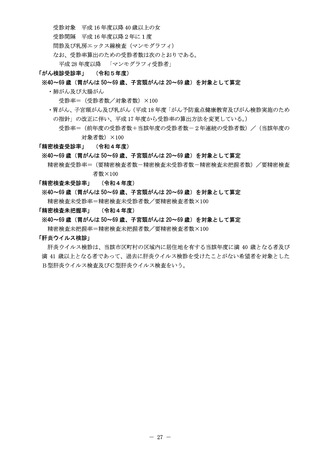よむ、つかう、まなぶ。
用語の解説 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/23/index.html |
| 出典情報 | 令和5年度地域保健・健康増進事業報告の概況(3/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第2期は、9歳に達した時から 10 歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行われ
る。
平成 17 年5月 30 日から平成 22 年3月 31 日までの積極的な勧奨の差し控えにより第1期、第2
期の接種が行われていない可能性がある者については特例対象者として予防接種が行われている。
令和5年度に 18 歳となる者(平成 17 年4月2日から平成 18 年4月1日までに生まれた者)に
ついては、第2期の接種が十分に行われていないことから、令和5年度に積極的な勧奨が行われた。
「ヒブワクチン」
標準的には、初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者について、初回接
種は 27 日以上、標準的には 27 日から 56 日までの間隔をおいて3回、追加接種については初回接
種終了後7月以上、標準的には7月から 13 月までの間隔をおいて 1 回行われる。
「小児用肺炎球菌ワクチン」
標準的には、初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者について、生後 12
月までに 27 日以上の間隔をおいて3回、追加接種については生後 12 月から生後 15 月に至るまで
の間を標準的な接種期間として、初回接種終了後 60 日以上の間隔をおいた後であって、生後 12 月
に至った日以降において1回行われる。
「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン」
(女性のみ対象)
(令和2年度報告より「子宮頸がん予防ワクチン」から名称変更した。)
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属
する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、
1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行われる。
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属
する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、
2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行われる。
組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属
する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、以下のいずれかの方法(ア
に掲げる方法については、第1回目の接種時に 12 歳となる日の属する年度の初日から 15 歳に至る
までの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。
)により行われる。
ア 標準的な接種方法として、6月の間隔をおいて2回行う。
イ 標準的な接種方法として、2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔
をおいて1回行う。
平成 25 年6月から積極的な勧奨が一時的に差し控えられていたが、令和3年 11 月に積極的勧奨
を差し控えている状態を終了させることが妥当とされ、基本的に令和4年4月から個別の勧奨を順
次行うこととなった。なお、令和2年 10 月から接種対象者等へのHPVワクチンに関する情報提
供資材の個別送付が開始された。
「水痘ワクチン」
生後 12 月から生後 36 月に至るまでの間にある者に対し、生後 12 月から生後 15 月に達するま
での期間を1回目の接種の標準的な接種期間として、3月以上、標準的には6月から 12 月までの
間隔をおいて2回行われる。
「B型肝炎ワクチン」
生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間を標準的な接種期間として、27 日以上の間隔
をおいて2回、第1回目の注射から 139 日以上の間隔をおいて1回行われる。
「ロタウイルスワクチン」
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合は 27 日以上の間隔をおいて2回、五価経
口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合は 27 日以上の間隔をおいて3回、初回接種につい
- 24 -
る。
平成 17 年5月 30 日から平成 22 年3月 31 日までの積極的な勧奨の差し控えにより第1期、第2
期の接種が行われていない可能性がある者については特例対象者として予防接種が行われている。
令和5年度に 18 歳となる者(平成 17 年4月2日から平成 18 年4月1日までに生まれた者)に
ついては、第2期の接種が十分に行われていないことから、令和5年度に積極的な勧奨が行われた。
「ヒブワクチン」
標準的には、初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者について、初回接
種は 27 日以上、標準的には 27 日から 56 日までの間隔をおいて3回、追加接種については初回接
種終了後7月以上、標準的には7月から 13 月までの間隔をおいて 1 回行われる。
「小児用肺炎球菌ワクチン」
標準的には、初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者について、生後 12
月までに 27 日以上の間隔をおいて3回、追加接種については生後 12 月から生後 15 月に至るまで
の間を標準的な接種期間として、初回接種終了後 60 日以上の間隔をおいた後であって、生後 12 月
に至った日以降において1回行われる。
「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン」
(女性のみ対象)
(令和2年度報告より「子宮頸がん予防ワクチン」から名称変更した。)
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属
する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、
1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行われる。
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属
する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、
2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行われる。
組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属
する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、以下のいずれかの方法(ア
に掲げる方法については、第1回目の接種時に 12 歳となる日の属する年度の初日から 15 歳に至る
までの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。
)により行われる。
ア 標準的な接種方法として、6月の間隔をおいて2回行う。
イ 標準的な接種方法として、2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔
をおいて1回行う。
平成 25 年6月から積極的な勧奨が一時的に差し控えられていたが、令和3年 11 月に積極的勧奨
を差し控えている状態を終了させることが妥当とされ、基本的に令和4年4月から個別の勧奨を順
次行うこととなった。なお、令和2年 10 月から接種対象者等へのHPVワクチンに関する情報提
供資材の個別送付が開始された。
「水痘ワクチン」
生後 12 月から生後 36 月に至るまでの間にある者に対し、生後 12 月から生後 15 月に達するま
での期間を1回目の接種の標準的な接種期間として、3月以上、標準的には6月から 12 月までの
間隔をおいて2回行われる。
「B型肝炎ワクチン」
生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間を標準的な接種期間として、27 日以上の間隔
をおいて2回、第1回目の注射から 139 日以上の間隔をおいて1回行われる。
「ロタウイルスワクチン」
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合は 27 日以上の間隔をおいて2回、五価経
口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合は 27 日以上の間隔をおいて3回、初回接種につい
- 24 -