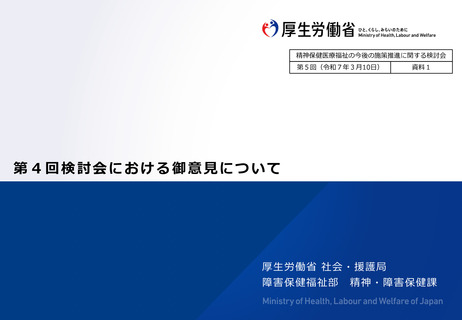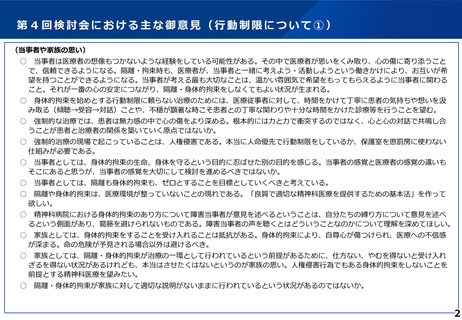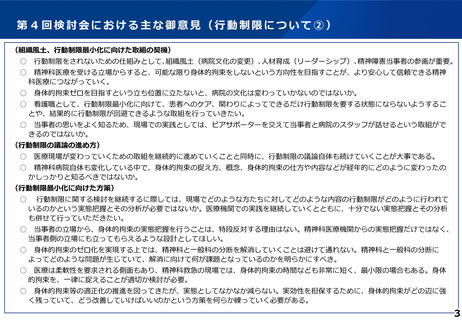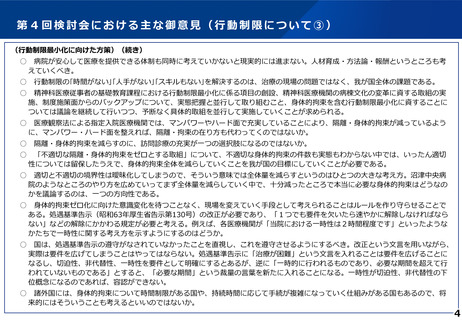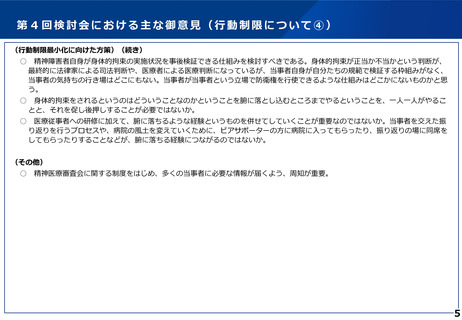よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】第4回検討会における主な御意見について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53883.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第5回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4回検討会における主な御意見(行動制限について①)
(当事者や家族の思い)
○
当事者は医療者の想像もつかないような経験をしている可能性がある。その中で医療者が思いをくみ取り、心の傷に寄り添うこと
で、信頼できるようになる。隔離・拘束時も、医療者が、当事者と一緒に考えよう・活動しようという働きかけにより、お互いが希
望を持つことができるようになる。当事者が考える最も大切なことは、温かい雰囲気で希望をもってもらえるように当事者に関わる
こと。それが一番の心の安定につながり、隔離・身体的拘束をしなくてもよい状況が生まれる。
○
身体的拘束を始めとする行動制限に頼らない治療のためには、医療従事者に対して、時間をかけて丁寧に患者の気持ちや想いを汲
み取る(傾聴→受容→対話)ことや、不穏が顕著な時こそ患者との丁寧な関わりや十分な時間をかけた診療等を行うことを望む。
○
強制的な治療では、患者は無力感の中で心の傷をより深める。根本的には力と力で衝突するのではなく、心と心の対話で共鳴し合
うことが患者と治療者の関係を築いていく原点ではないか。
○
強制的治療の現場で起こっていることは、人権侵害である。本当に人命優先で行動制限をしているか、保護室を懲罰房に使わない
仕組みが必要である。
○
当事者としては、身体的拘束の生命、身体を守るという目的に忍ばせた別の目的を感じる。当事者の感覚と医療者の感覚の違いも
そこにあると思うが、当事者の感覚を大切にして検討を進めるべきではないか。
○
当事者としては、隔離も身体的拘束も、ゼロとすることを目標としていくべきと考えている。
○
隔離や身体的拘束は、医療環境が整っていないことの現れである。「良質で適切な精神科医療を提供するための基本法」を作って
欲しい。
○
精神科病院における身体的拘束のあり方について障害当事者が意見を述べるということは、自分たちの縛り方について意見を述べ
るという側面があり、葛藤を避けられないものである。障害当事者の声を聴くとはどういうことなのかについて理解を深めてほしい。
○
家族としては、身体的拘束をすることを受け入れることは抵抗がある。身体的拘束により、自尊心が傷つけられ、医療への不信感
が深まる。命の危険が予見される場合以外は避けるべき。
○
家族としては、隔離・身体的拘束が治療の一環として行われているという前提があるために、仕方ない、やむを得ないと受け入れ
ざるを得ない状況があるけれども、本当はさせたくはないというのが家族の思い。人権侵害行為でもある身体的拘束をしないことを
前提とする精神科医療を望みたい。
○ 隔離・身体的拘束が家族に対して適切な説明がないままに行われているという状況があるのではないか。
2
(当事者や家族の思い)
○
当事者は医療者の想像もつかないような経験をしている可能性がある。その中で医療者が思いをくみ取り、心の傷に寄り添うこと
で、信頼できるようになる。隔離・拘束時も、医療者が、当事者と一緒に考えよう・活動しようという働きかけにより、お互いが希
望を持つことができるようになる。当事者が考える最も大切なことは、温かい雰囲気で希望をもってもらえるように当事者に関わる
こと。それが一番の心の安定につながり、隔離・身体的拘束をしなくてもよい状況が生まれる。
○
身体的拘束を始めとする行動制限に頼らない治療のためには、医療従事者に対して、時間をかけて丁寧に患者の気持ちや想いを汲
み取る(傾聴→受容→対話)ことや、不穏が顕著な時こそ患者との丁寧な関わりや十分な時間をかけた診療等を行うことを望む。
○
強制的な治療では、患者は無力感の中で心の傷をより深める。根本的には力と力で衝突するのではなく、心と心の対話で共鳴し合
うことが患者と治療者の関係を築いていく原点ではないか。
○
強制的治療の現場で起こっていることは、人権侵害である。本当に人命優先で行動制限をしているか、保護室を懲罰房に使わない
仕組みが必要である。
○
当事者としては、身体的拘束の生命、身体を守るという目的に忍ばせた別の目的を感じる。当事者の感覚と医療者の感覚の違いも
そこにあると思うが、当事者の感覚を大切にして検討を進めるべきではないか。
○
当事者としては、隔離も身体的拘束も、ゼロとすることを目標としていくべきと考えている。
○
隔離や身体的拘束は、医療環境が整っていないことの現れである。「良質で適切な精神科医療を提供するための基本法」を作って
欲しい。
○
精神科病院における身体的拘束のあり方について障害当事者が意見を述べるということは、自分たちの縛り方について意見を述べ
るという側面があり、葛藤を避けられないものである。障害当事者の声を聴くとはどういうことなのかについて理解を深めてほしい。
○
家族としては、身体的拘束をすることを受け入れることは抵抗がある。身体的拘束により、自尊心が傷つけられ、医療への不信感
が深まる。命の危険が予見される場合以外は避けるべき。
○
家族としては、隔離・身体的拘束が治療の一環として行われているという前提があるために、仕方ない、やむを得ないと受け入れ
ざるを得ない状況があるけれども、本当はさせたくはないというのが家族の思い。人権侵害行為でもある身体的拘束をしないことを
前提とする精神科医療を望みたい。
○ 隔離・身体的拘束が家族に対して適切な説明がないままに行われているという状況があるのではないか。
2