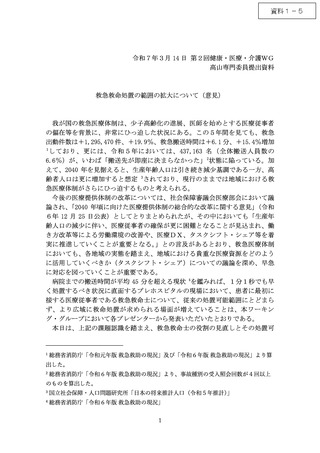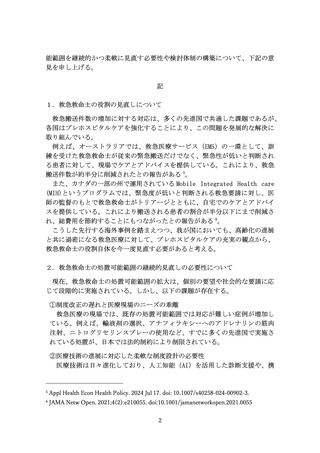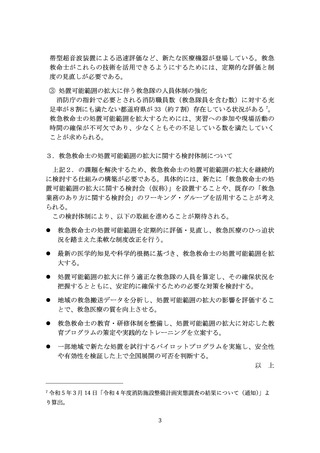よむ、つかう、まなぶ。
資料1ー5 高山専門委員 御提出資料 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
能範囲を継続的かつ柔軟に見直す必要性や検討体制の構築について、下記の意
見を申し上げる。
記
1.救急救命士の役割の見直しについて
救急搬送件数の増加に対する対応は、多くの先進国で共通した課題であるが、
各国はプレホスピタルケアを強化することにより、この問題を発展的な解決に
取り組んでいる。
例えば、オーストラリアでは、救急医療サービス(EMS)の一環として、訓
練を受けた救急救命士が従来の緊急搬送だけでなく、緊急性が低いと判断され
る患者に対して、現場でケアとアドバイスを提供している。これにより、救急
搬送件数が約半分に削減されたとの報告がある 5。
また、カナダの一部の州で運用されている Mobile Integrated Health care
(MIH)というプログラムでは、緊急度が低いと判断される救急要請に対し、医
師の監督のもとで救急救命士がトリアージとともに、自宅でのケアとアドバイ
スを提供している。これにより搬送される患者の割合が半分以下にまで削減さ
れ、総費用を節約することにもつながったとの報告がある 6。
こうした先行する海外事例を踏まえつつ、我が国においても、高齢化の進展
と共に過密になる救急医療に対して、プレホスピタルケアの充実の観点から、
救急救命士の役割自体を今一度見直す必要があると考える。
2.救急救命士の処置可能範囲の継続的見直しの必要性について
現在、救急救命士の処置可能範囲の拡大は、個別の要望や社会的な要請に応
じて段階的に実施されている。しかし、以下の課題が存在する。
①制度改正の遅れと医療現場のニーズの乖離
救急医療の現場では、既存の処置可能範囲では対応が難しい症例が増加し
ている。例えば、輸液剤の選択、アナフィラキシーへのアドレナリンの筋肉
注射、ニトログリセリンスプレーの使用など、すでに多くの先進国で実施さ
れている処置が、日本では法的制約により制限されている。
②医療技術の進展に対応した柔軟な制度設計の必要性
医療技術は日々進化しており、人工知能(AI)を活用した診断支援や、携
5
Appl Health Econ Health Policy. 2024 Jul 17. doi: 10.1007/s40258-024-00902-3.
6
JAMA Netw Open. 2021;4(2):e210055. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.0055
2
見を申し上げる。
記
1.救急救命士の役割の見直しについて
救急搬送件数の増加に対する対応は、多くの先進国で共通した課題であるが、
各国はプレホスピタルケアを強化することにより、この問題を発展的な解決に
取り組んでいる。
例えば、オーストラリアでは、救急医療サービス(EMS)の一環として、訓
練を受けた救急救命士が従来の緊急搬送だけでなく、緊急性が低いと判断され
る患者に対して、現場でケアとアドバイスを提供している。これにより、救急
搬送件数が約半分に削減されたとの報告がある 5。
また、カナダの一部の州で運用されている Mobile Integrated Health care
(MIH)というプログラムでは、緊急度が低いと判断される救急要請に対し、医
師の監督のもとで救急救命士がトリアージとともに、自宅でのケアとアドバイ
スを提供している。これにより搬送される患者の割合が半分以下にまで削減さ
れ、総費用を節約することにもつながったとの報告がある 6。
こうした先行する海外事例を踏まえつつ、我が国においても、高齢化の進展
と共に過密になる救急医療に対して、プレホスピタルケアの充実の観点から、
救急救命士の役割自体を今一度見直す必要があると考える。
2.救急救命士の処置可能範囲の継続的見直しの必要性について
現在、救急救命士の処置可能範囲の拡大は、個別の要望や社会的な要請に応
じて段階的に実施されている。しかし、以下の課題が存在する。
①制度改正の遅れと医療現場のニーズの乖離
救急医療の現場では、既存の処置可能範囲では対応が難しい症例が増加し
ている。例えば、輸液剤の選択、アナフィラキシーへのアドレナリンの筋肉
注射、ニトログリセリンスプレーの使用など、すでに多くの先進国で実施さ
れている処置が、日本では法的制約により制限されている。
②医療技術の進展に対応した柔軟な制度設計の必要性
医療技術は日々進化しており、人工知能(AI)を活用した診断支援や、携
5
Appl Health Econ Health Policy. 2024 Jul 17. doi: 10.1007/s40258-024-00902-3.
6
JAMA Netw Open. 2021;4(2):e210055. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.0055
2