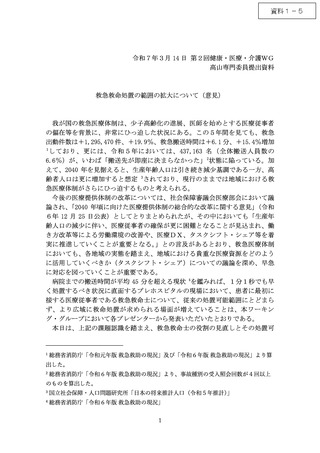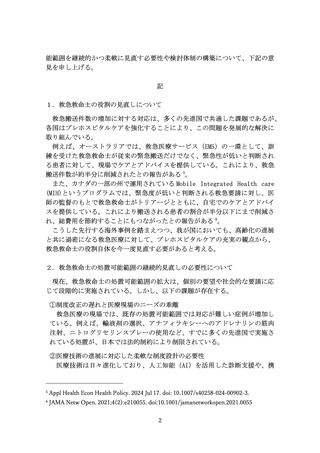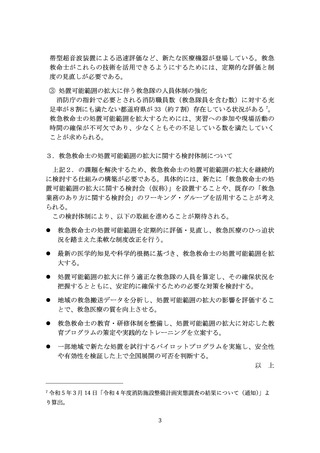よむ、つかう、まなぶ。
資料1ー5 高山専門委員 御提出資料 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
帯型超音波装置による迅速評価など、新たな医療機器が登場している。救急
救命士がこれらの技術を活用できるようにするためには、定期的な評価と制
度の見直しが必要である。
③ 処置可能範囲の拡大に伴う救急隊の人員体制の強化
消防庁の指針で必要とされる消防職員数(救急隊員を含む数)に対する充
足率が8割にも満たない都道府県が 33(約7割)存在している状況がある 7。
救急救命士の処置可能範囲を拡大するためには、実習への参加や現場活動の
時間の確保が不可欠であり、少なくともその不足している数を満たしていく
ことが求められる。
3.救急救命士の処置可能範囲の拡大に関する検討体制について
上記2.の課題を解決するため、救急救命士の処置可能範囲の拡大を継続的
に検討する仕組みの構築が必要である。具体的には、新たに「救急救命士の処
置可能範囲の拡大に関する検討会(仮称)」を設置することや、既存の「救急
業務のあり方に関する検討会」のワーキング・グループを活用することが考え
られる。
この検討体制により、以下の取組を進めることが期待される。
救急救命士の処置可能範囲を定期的に評価・見直し、救急医療のひっ迫状
況を踏まえた柔軟な制度改正を行う。
最新の医学的知見や科学的根拠に基づき、救急救命士の処置可能範囲を拡
大する。
処置可能範囲の拡大に伴う適正な救急隊の人員を算定し、その確保状況を
把握するとともに、安定的に確保するための必要な対策を検討する。
地域の救急搬送データを分析し、処置可能範囲の拡大の影響を評価するこ
とで、救急医療の質を向上させる。
救急救命士の教育・研修体制を整備し、処置可能範囲の拡大に対応した教
育プログラムの策定や実践的なトレーニングを立案する。
一部地域で新たな処置を試行するパイロットプログラムを実施し、安全性
や有効性を検証した上で全国展開の可否を判断する。
以 上
7
令和5年3月 14 日「令和 4 年度消防施設整備計画実態調査の結果について(通知)
」よ
り算出。
3
救命士がこれらの技術を活用できるようにするためには、定期的な評価と制
度の見直しが必要である。
③ 処置可能範囲の拡大に伴う救急隊の人員体制の強化
消防庁の指針で必要とされる消防職員数(救急隊員を含む数)に対する充
足率が8割にも満たない都道府県が 33(約7割)存在している状況がある 7。
救急救命士の処置可能範囲を拡大するためには、実習への参加や現場活動の
時間の確保が不可欠であり、少なくともその不足している数を満たしていく
ことが求められる。
3.救急救命士の処置可能範囲の拡大に関する検討体制について
上記2.の課題を解決するため、救急救命士の処置可能範囲の拡大を継続的
に検討する仕組みの構築が必要である。具体的には、新たに「救急救命士の処
置可能範囲の拡大に関する検討会(仮称)」を設置することや、既存の「救急
業務のあり方に関する検討会」のワーキング・グループを活用することが考え
られる。
この検討体制により、以下の取組を進めることが期待される。
救急救命士の処置可能範囲を定期的に評価・見直し、救急医療のひっ迫状
況を踏まえた柔軟な制度改正を行う。
最新の医学的知見や科学的根拠に基づき、救急救命士の処置可能範囲を拡
大する。
処置可能範囲の拡大に伴う適正な救急隊の人員を算定し、その確保状況を
把握するとともに、安定的に確保するための必要な対策を検討する。
地域の救急搬送データを分析し、処置可能範囲の拡大の影響を評価するこ
とで、救急医療の質を向上させる。
救急救命士の教育・研修体制を整備し、処置可能範囲の拡大に対応した教
育プログラムの策定や実践的なトレーニングを立案する。
一部地域で新たな処置を試行するパイロットプログラムを実施し、安全性
や有効性を検証した上で全国展開の可否を判断する。
以 上
7
令和5年3月 14 日「令和 4 年度消防施設整備計画実態調査の結果について(通知)
」よ
り算出。
3