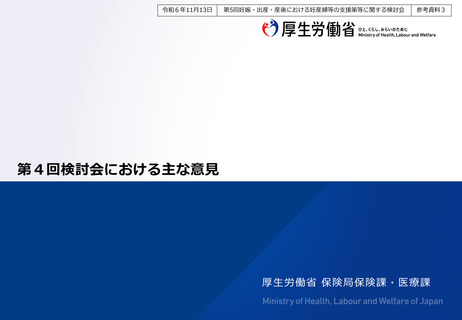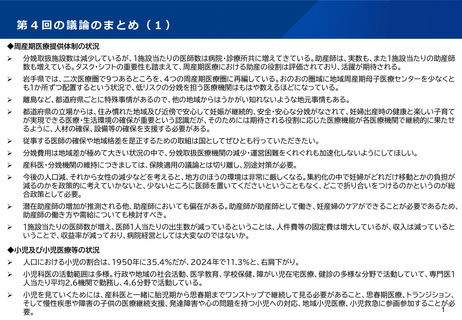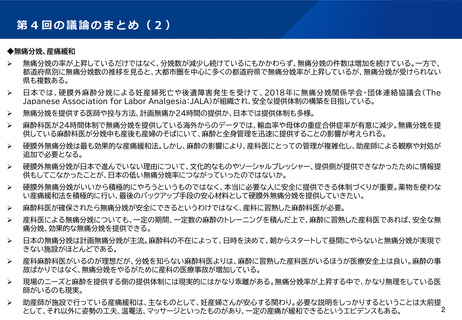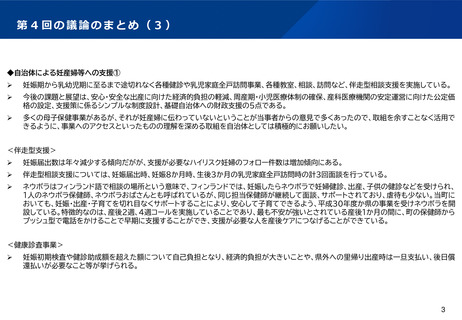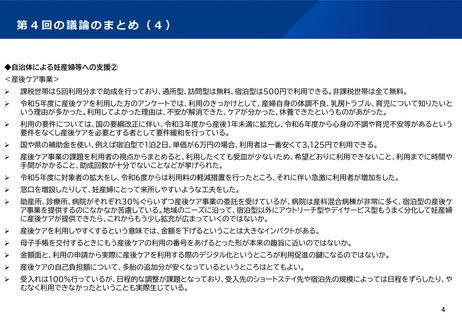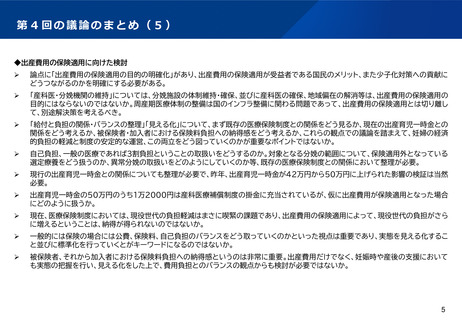よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 第4回検討会における主な意見 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html |
| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4回の議論のまとめ(4)
◆自治体による妊産婦等への支援②
<産後ケア事業>
➢
課税世帯は5回利用分まで助成を行っており、通所型、訪問型は無料、宿泊型は500円で利用できる。非課税世帯は全て無料。
➢
令和5年度に産後ケアを利用した方のアンケートでは、利用のきっかけとして、産婦自身の体調不良、乳房トラブル、育児について知りたいと
いう理由が多かった。利用してよかった理由は、不安が解消できた、ケアが分かった、休養できたというものがあがった。
➢
利用の要件については、国の要綱改正に伴い、令和3年度から産後1年未満に拡充し、令和6年度から心身の不調や育児不安等があるという
要件をなくし産後ケアを必要とする者として要件緩和を行っている。
➢
国や県の補助金を使い、例えば宿泊型で1泊2日、単価が6万円の場合、利用者は一番安くて3,125円で利用できる。
➢
産後ケア事業の課題を利用者の視点からまとめると、利用したくても受皿が少ないため、希望どおりに利用できないこと、利用までに時間や
手間がかかること、助成回数が十分でないことなどが挙げられた。
➢
令和5年度に対象者の拡大をし、令和6度からは利用料の軽減措置を行ったところ、それに伴い急激に利用者が増加をした。
➢
窓口を増設したりして、妊産婦にとって来所しやすいような工夫をした。
➢
助産所、診療所、病院がそれぞれ30%ぐらいずつ産後ケア事業の委託を受けているが、病院は産科混合病棟が非常に多く、宿泊型の産後ケ
ア事業を提供するのになかなか苦慮している。地域のニーズに沿って、宿泊型以外にアウトリーチ型やデイサービス型もうまく分化して妊産婦
に産後ケアが提供できたら、これからもう少し拡充が広まっていくのではないか。
➢
産後ケアを利用しやすくするという意味では、金額を下げるということは大きなインパクトがある。
➢
母子手帳を交付するときにもう産後ケアの利用の番号をあげるとった形が本来の趣旨に近いのではないか。
➢
金額面と、利用の申請から実際に産後ケアを利用する際のデジタル化というところが利用促進の鍵になるのではないか。
➢
産後ケアの自己負担額について、多胎の追加分が安くなっているというところはとてもよい。
➢
受入れは100%行っているが、日程的な調整が課題となっており、受入先のショートステイ先や宿泊先の規模によっては日程をずらしたり、や
むなく利用できなかったということも実際生じている。
4
◆自治体による妊産婦等への支援②
<産後ケア事業>
➢
課税世帯は5回利用分まで助成を行っており、通所型、訪問型は無料、宿泊型は500円で利用できる。非課税世帯は全て無料。
➢
令和5年度に産後ケアを利用した方のアンケートでは、利用のきっかけとして、産婦自身の体調不良、乳房トラブル、育児について知りたいと
いう理由が多かった。利用してよかった理由は、不安が解消できた、ケアが分かった、休養できたというものがあがった。
➢
利用の要件については、国の要綱改正に伴い、令和3年度から産後1年未満に拡充し、令和6年度から心身の不調や育児不安等があるという
要件をなくし産後ケアを必要とする者として要件緩和を行っている。
➢
国や県の補助金を使い、例えば宿泊型で1泊2日、単価が6万円の場合、利用者は一番安くて3,125円で利用できる。
➢
産後ケア事業の課題を利用者の視点からまとめると、利用したくても受皿が少ないため、希望どおりに利用できないこと、利用までに時間や
手間がかかること、助成回数が十分でないことなどが挙げられた。
➢
令和5年度に対象者の拡大をし、令和6度からは利用料の軽減措置を行ったところ、それに伴い急激に利用者が増加をした。
➢
窓口を増設したりして、妊産婦にとって来所しやすいような工夫をした。
➢
助産所、診療所、病院がそれぞれ30%ぐらいずつ産後ケア事業の委託を受けているが、病院は産科混合病棟が非常に多く、宿泊型の産後ケ
ア事業を提供するのになかなか苦慮している。地域のニーズに沿って、宿泊型以外にアウトリーチ型やデイサービス型もうまく分化して妊産婦
に産後ケアが提供できたら、これからもう少し拡充が広まっていくのではないか。
➢
産後ケアを利用しやすくするという意味では、金額を下げるということは大きなインパクトがある。
➢
母子手帳を交付するときにもう産後ケアの利用の番号をあげるとった形が本来の趣旨に近いのではないか。
➢
金額面と、利用の申請から実際に産後ケアを利用する際のデジタル化というところが利用促進の鍵になるのではないか。
➢
産後ケアの自己負担額について、多胎の追加分が安くなっているというところはとてもよい。
➢
受入れは100%行っているが、日程的な調整が課題となっており、受入先のショートステイ先や宿泊先の規模によっては日程をずらしたり、や
むなく利用できなかったということも実際生じている。
4