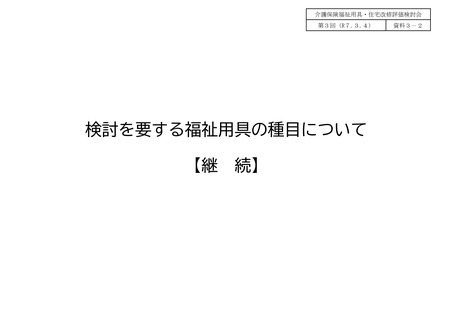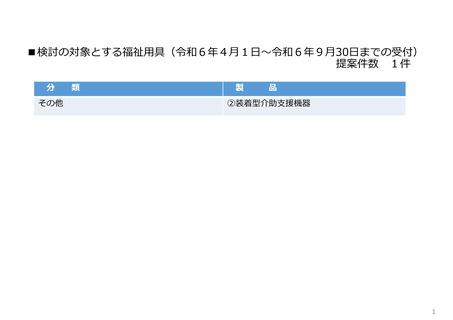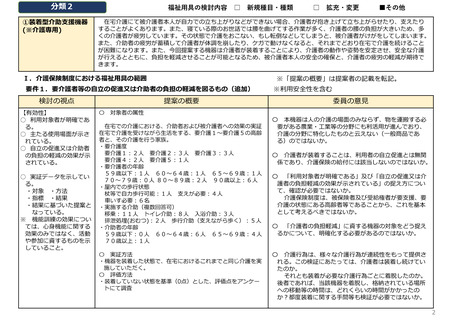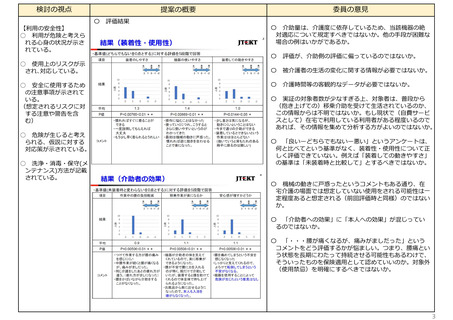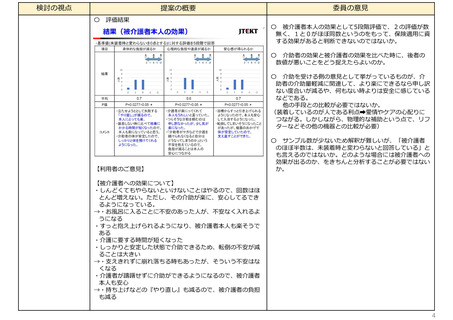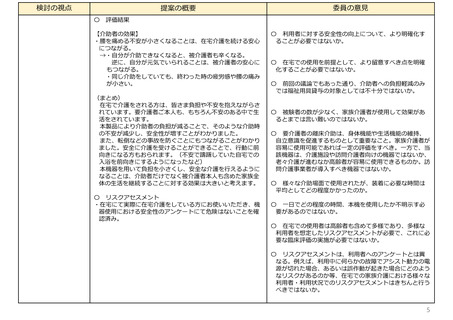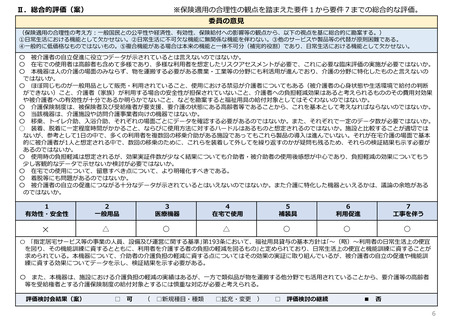よむ、つかう、まなぶ。
資料3-2 検討を要する福祉用具の種目について(継続提案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429960.pdf |
| 出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
検討の視点
提案の概要
委員の意見
【介助者の効果】
・腰を痛める不安が小さくなることは、在宅介護を続ける安心
につながる。
→・自分が介助できなくなると、被介護者も辛くなる。
逆に、自分が元気でいられることは、被介護者の安心に
もつながる。
・同じ介助をしていても、終わった時の疲労感や腰の痛み
が小さい。
〇 利用者に対する安全性の向上について、より明確化す
ることが必要ではないか。
〇
評価結果
(まとめ)
在宅で介護をされる方は、皆さま負担や不安を抱えながらさ
れています。要介護者ご本人も、もちろん不安のある中で生
活をされています。
本製品により介助者の負担が減ることで、そのような介助時
の不安が減少し、安全性が増すことがわかりました。
また、転倒などの事故を防ぐことにもつながることがわかり
ました。安全に介護を受けることができることで、行動に前
向きになる方もおられます。(不安で躊躇していた自宅での
入浴を前向きにするようになったなど)
本機器を用いて負担を小さくし、安全な介護を行えるように
なることは、介助者だけでなく被介護者本人も含めた家族全
体の生活を継続することに対する効果は大きいと考えます。
〇 リスクアセスメント
・在宅にて実際に在宅介護をしている方にお使いいただき、機
器使用における安全性のアンケートにて危険はないことを確
認済み。
〇 在宅での使用を前提として、より留意すべき点を明確
化することが必要ではないか。
〇 前回の議論でもあった通り、介助者への負担軽減のみ
では福祉用具貸与の対象としては不十分ではないか。
〇 被験者の数が少なく、家族介護者が使用して効果があ
るとまでは言い難いのではないか。
〇 要介護者の離床介助は、身体機能や生活機能の維持、
自立意識を促進するものとして重要なこと。家族介護者が
容易に使用可能であれば一定の評価をすべき。一方で、当
該機器は、介護施設や訪問介護者向けの機器ではないか、
老々介護が進むなか高齢者が容易に使用できるものか。訪
問介護事業者が導入すべき機器ではないか。
〇 様々な介助場面で使用されたが、装着に必要な時間は
平均としてどの程度かかったのか。
〇 一日でどの程度の時間、本機を使用したか不明示す必
要があるのではないか。
〇 在宅での使用者は高齢者も含めて多様であり、多様な
利用者を想定したリスクアセスメントが必要で、これに必
要な臨床評価の実施が必要ではないか。
〇 リスクアセスメントは、利用者へのアンケートとは異
なる。例えば、利用中に何らかの故障でアシスト動力の電
源が切れた場合、あるいは誤作動が起きた場合にどのよう
なリスクがあるのか等、在宅での家族介護における様々な
利用者・利用状況でのリスクアセスメントはきちんと行う
べきではないか。
5
提案の概要
委員の意見
【介助者の効果】
・腰を痛める不安が小さくなることは、在宅介護を続ける安心
につながる。
→・自分が介助できなくなると、被介護者も辛くなる。
逆に、自分が元気でいられることは、被介護者の安心に
もつながる。
・同じ介助をしていても、終わった時の疲労感や腰の痛み
が小さい。
〇 利用者に対する安全性の向上について、より明確化す
ることが必要ではないか。
〇
評価結果
(まとめ)
在宅で介護をされる方は、皆さま負担や不安を抱えながらさ
れています。要介護者ご本人も、もちろん不安のある中で生
活をされています。
本製品により介助者の負担が減ることで、そのような介助時
の不安が減少し、安全性が増すことがわかりました。
また、転倒などの事故を防ぐことにもつながることがわかり
ました。安全に介護を受けることができることで、行動に前
向きになる方もおられます。(不安で躊躇していた自宅での
入浴を前向きにするようになったなど)
本機器を用いて負担を小さくし、安全な介護を行えるように
なることは、介助者だけでなく被介護者本人も含めた家族全
体の生活を継続することに対する効果は大きいと考えます。
〇 リスクアセスメント
・在宅にて実際に在宅介護をしている方にお使いいただき、機
器使用における安全性のアンケートにて危険はないことを確
認済み。
〇 在宅での使用を前提として、より留意すべき点を明確
化することが必要ではないか。
〇 前回の議論でもあった通り、介助者への負担軽減のみ
では福祉用具貸与の対象としては不十分ではないか。
〇 被験者の数が少なく、家族介護者が使用して効果があ
るとまでは言い難いのではないか。
〇 要介護者の離床介助は、身体機能や生活機能の維持、
自立意識を促進するものとして重要なこと。家族介護者が
容易に使用可能であれば一定の評価をすべき。一方で、当
該機器は、介護施設や訪問介護者向けの機器ではないか、
老々介護が進むなか高齢者が容易に使用できるものか。訪
問介護事業者が導入すべき機器ではないか。
〇 様々な介助場面で使用されたが、装着に必要な時間は
平均としてどの程度かかったのか。
〇 一日でどの程度の時間、本機を使用したか不明示す必
要があるのではないか。
〇 在宅での使用者は高齢者も含めて多様であり、多様な
利用者を想定したリスクアセスメントが必要で、これに必
要な臨床評価の実施が必要ではないか。
〇 リスクアセスメントは、利用者へのアンケートとは異
なる。例えば、利用中に何らかの故障でアシスト動力の電
源が切れた場合、あるいは誤作動が起きた場合にどのよう
なリスクがあるのか等、在宅での家族介護における様々な
利用者・利用状況でのリスクアセスメントはきちんと行う
べきではないか。
5