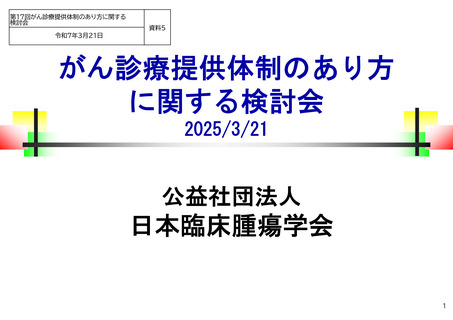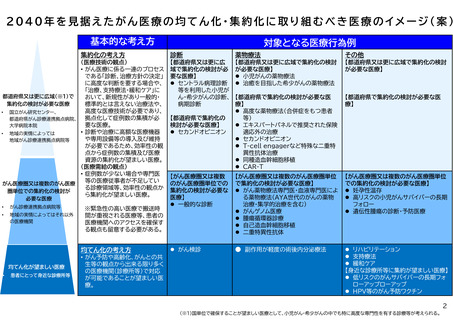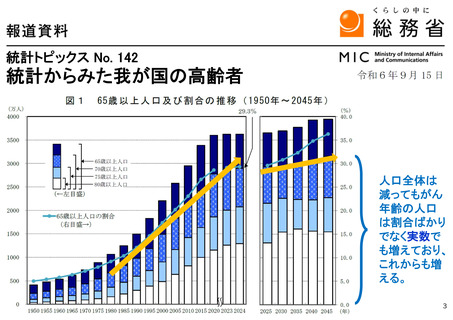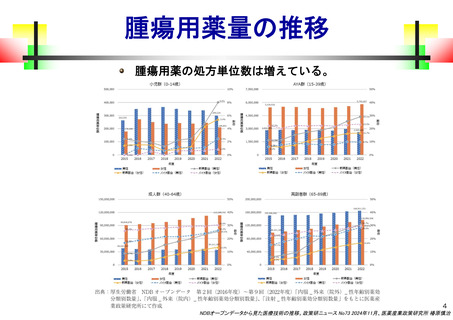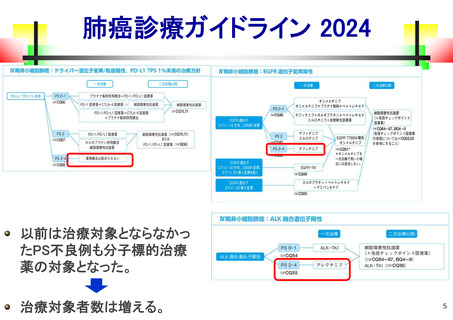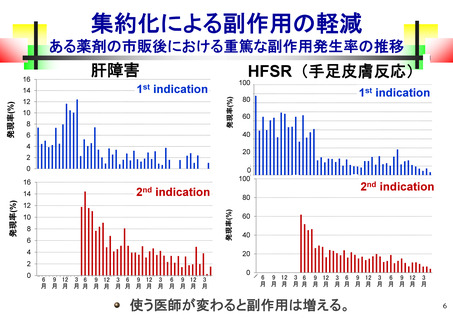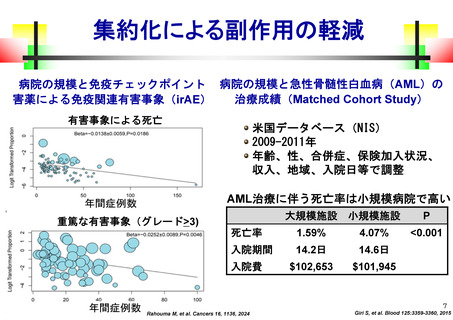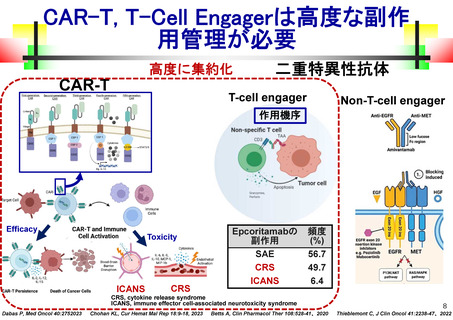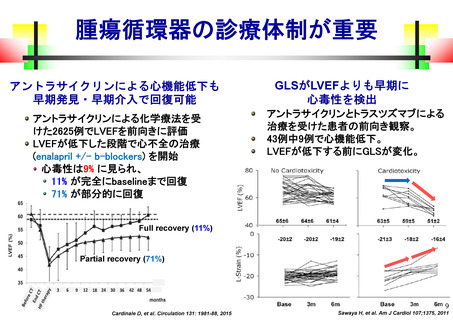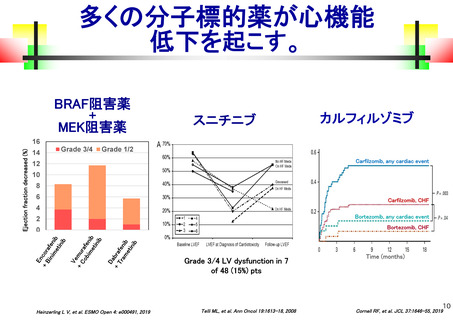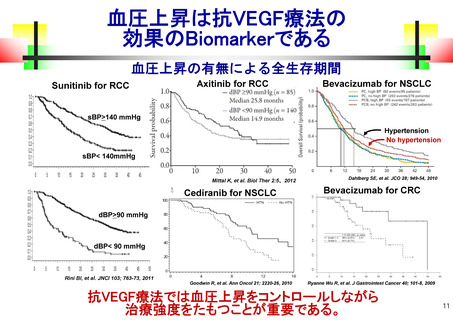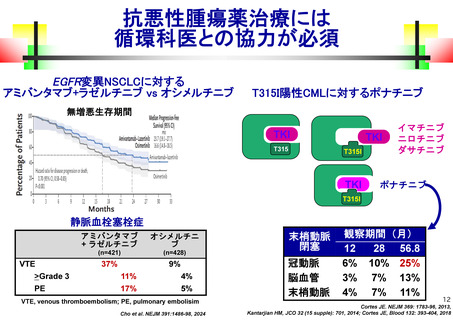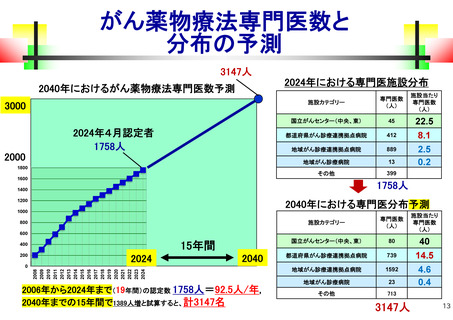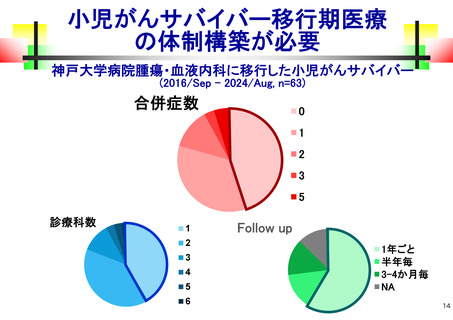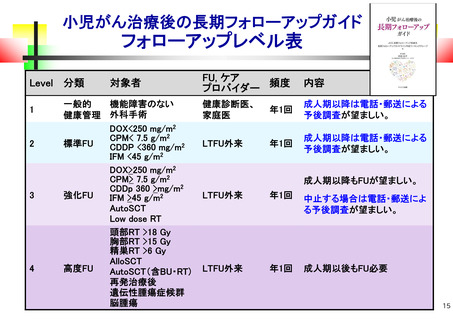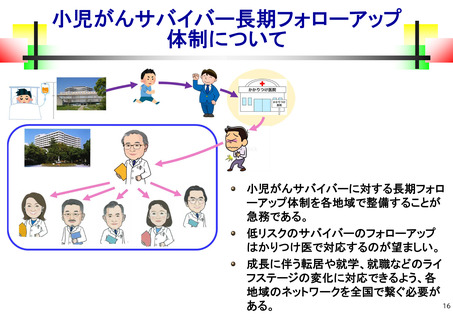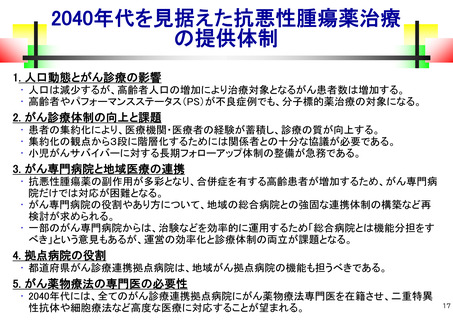よむ、つかう、まなぶ。
資料5 日本臨床腫瘍学会 提出資料 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55468.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第17回 3/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2040年代を見据えた抗悪性腫瘍薬治療
の提供体制
1. 人口動態とがん診療の影響
人口は減少するが、高齢者人口の増加により治療対象となるがん患者数は増加する。
• 高齢者やパフォーマンスステータス(PS)が不良症例でも、分子標的薬治療の対象になる。
•
2. がん診療体制の向上と課題
患者の集約化により、医療機関・医療者の経験が蓄積し、診療の質が向上する。
• 集約化の観点から3段に階層化するためには関係者との十分な協議が必要である。
• 小児がんサバイバーに対する長期フォローアップ体制の整備が急務である。
•
3. がん専門病院と地域医療の連携
抗悪性腫瘍薬の副作用が多彩となり、合併症を有する高齢患者が増加するため、がん専門病
院だけでは対応が困難となる。
• がん専門病院の役割やあり方について、地域の総合病院との強固な連携体制の構築など再
検討が求められる。
• 一部のがん専門病院からは、治験などを効率的に運用するため「総合病院とは機能分担をす
べき」という意見もあるが、運営の効率化と診療体制の両立が課題となる。
•
4. 拠点病院の役割
•
都道府県がん診療連携拠点病院は、地域がん拠点病院の機能も担うべきである。
5. がん薬物療法の専門医の必要性
•
2040年代には、全てのがん診療連携拠点病院にがん薬物療法専門医を在籍させ、二重特異
性抗体や細胞療法など高度な医療に対応することが望まれる。
17
の提供体制
1. 人口動態とがん診療の影響
人口は減少するが、高齢者人口の増加により治療対象となるがん患者数は増加する。
• 高齢者やパフォーマンスステータス(PS)が不良症例でも、分子標的薬治療の対象になる。
•
2. がん診療体制の向上と課題
患者の集約化により、医療機関・医療者の経験が蓄積し、診療の質が向上する。
• 集約化の観点から3段に階層化するためには関係者との十分な協議が必要である。
• 小児がんサバイバーに対する長期フォローアップ体制の整備が急務である。
•
3. がん専門病院と地域医療の連携
抗悪性腫瘍薬の副作用が多彩となり、合併症を有する高齢患者が増加するため、がん専門病
院だけでは対応が困難となる。
• がん専門病院の役割やあり方について、地域の総合病院との強固な連携体制の構築など再
検討が求められる。
• 一部のがん専門病院からは、治験などを効率的に運用するため「総合病院とは機能分担をす
べき」という意見もあるが、運営の効率化と診療体制の両立が課題となる。
•
4. 拠点病院の役割
•
都道府県がん診療連携拠点病院は、地域がん拠点病院の機能も担うべきである。
5. がん薬物療法の専門医の必要性
•
2040年代には、全てのがん診療連携拠点病院にがん薬物療法専門医を在籍させ、二重特異
性抗体や細胞療法など高度な医療に対応することが望まれる。
17