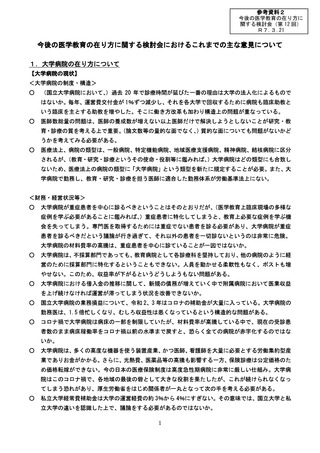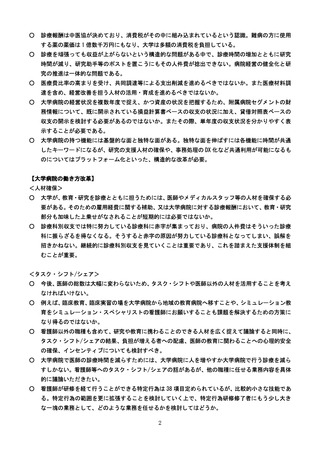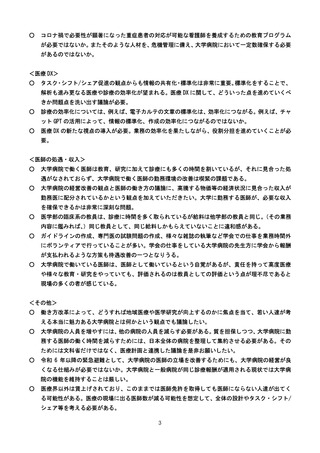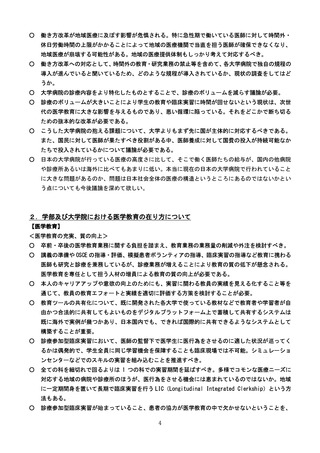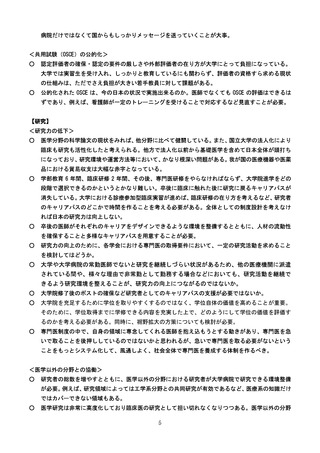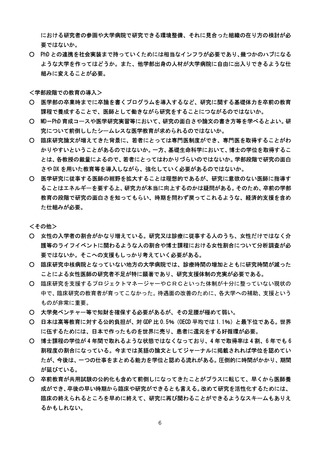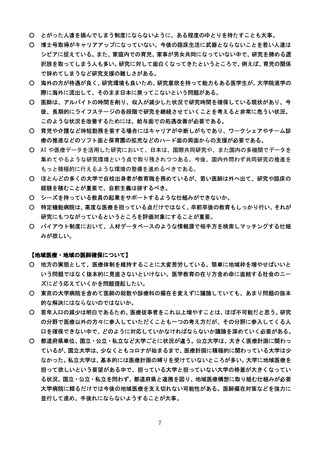よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_今後の医学教育の在り方に関する検討会におけるこれまでの主な 意見について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00015.html |
| 出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会(第12回 3/21)《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
診療報酬は中医協が決めており、消費税がその中に組み込まれているという認識。難病の方に使用
する薬の薬価は 1 億数千万円にもなり、大学は多額の消費税を負担している。
○
診療を頑張っても収益が上がらないという構造的な問題がある中で、診療時間の増加とともに研究
時間が減り、研究助手等のポストを置こうにもその人件費が捻出できない。病院経営の健全化と研
究の推進は一体的な問題である。
○
医療費比率の高まりを受け、共同調達等による支出削減を進めるべきではないか。また医療材料調
達を含め、経営改善を担う人材の活用・育成を進めるべきではないか。
○
大学病院の経営状況を複数年度で捉え、かつ資産の状況を把握するため、附属病院セグメントの財
務情報について、既に開示されている損益計算書ベースの収支の状況に加え、貸借対照表ベースの
収支の開示を検討する必要があるのではないか。またその際、単年度の収支状況を分かりやすく表
示することが必要である。
○
大学病院の持つ機能には基盤的な面と独特な面がある。独特な面を伸ばすには各機能に時間が共通
したキーワードになるが、研究の支援人材の確保や、事務処理の DX 化など共通利用が可能になるも
のについてはプラットフォーム化といった、構造的な改革が必要。
【大学病院の働き方改革】
<人材確保>
○
大学が、教育・研究を診療とともに担うためには、医師やメディカルスタッフ等の人材を確保する必
要がある。そのための雇用経費に関する補助、又は大学病院に対する診療報酬において、教育・研究
部分も加味した上乗せがなされることが短期的には必要ではないか。
○
診療科別収支では特に努力している診療科に赤字が集まっており、病院の人件費はそういった診療
科に振らざるを得なくなる。そうすると赤字の原因が努力している診療科となってしまい、誤解を
招きかねない。継続的に診療科別収支を見ていくことは重要であり、これを踏まえた支援体制を組
むことが重要。
<タスク・シフト/シェア>
○
今後、医師の総数は大幅に変わらないため、タスク・シフトや医師以外の人材を活用することを考え
なければいけない。
○
例えば、臨床教育、臨床実習の場を大学病院から地域の教育病院へ移すことや、シミュレーション教
育をシミュレーション・スペシャリストの看護師にお願いすることも課題を解決するための方策に
なり得るのではないか。
○
看護師以外の職種も含めて、研究や教育に携わることのできる人材を広く捉えて議論すると同時に、
タスク・シフト/シェアの結果、負担が増える者への配慮、医師の教育に関わることへの心理的安全
の確保、インセンティブについても検討すべき。
○
大学病院で医師の診療時間を減らすためには、大学病院に人を増やすか大学病院で行う診療を減ら
すしかない。看護師等へのタスク・シフト/シェアの話があるが、他の職種に任せる業務内容を具体
的に議論いただきたい。
○
看護師が研修を経て行うことができる特定行為は 38 項目定められているが、比較的小さな技能であ
る。特定行為の範囲を更に拡張することを検討していく上で、特定行為研修修了者にもう少し大き
な一塊の業務として、どのような業務を任せるかを検討してはどうか。
2
診療報酬は中医協が決めており、消費税がその中に組み込まれているという認識。難病の方に使用
する薬の薬価は 1 億数千万円にもなり、大学は多額の消費税を負担している。
○
診療を頑張っても収益が上がらないという構造的な問題がある中で、診療時間の増加とともに研究
時間が減り、研究助手等のポストを置こうにもその人件費が捻出できない。病院経営の健全化と研
究の推進は一体的な問題である。
○
医療費比率の高まりを受け、共同調達等による支出削減を進めるべきではないか。また医療材料調
達を含め、経営改善を担う人材の活用・育成を進めるべきではないか。
○
大学病院の経営状況を複数年度で捉え、かつ資産の状況を把握するため、附属病院セグメントの財
務情報について、既に開示されている損益計算書ベースの収支の状況に加え、貸借対照表ベースの
収支の開示を検討する必要があるのではないか。またその際、単年度の収支状況を分かりやすく表
示することが必要である。
○
大学病院の持つ機能には基盤的な面と独特な面がある。独特な面を伸ばすには各機能に時間が共通
したキーワードになるが、研究の支援人材の確保や、事務処理の DX 化など共通利用が可能になるも
のについてはプラットフォーム化といった、構造的な改革が必要。
【大学病院の働き方改革】
<人材確保>
○
大学が、教育・研究を診療とともに担うためには、医師やメディカルスタッフ等の人材を確保する必
要がある。そのための雇用経費に関する補助、又は大学病院に対する診療報酬において、教育・研究
部分も加味した上乗せがなされることが短期的には必要ではないか。
○
診療科別収支では特に努力している診療科に赤字が集まっており、病院の人件費はそういった診療
科に振らざるを得なくなる。そうすると赤字の原因が努力している診療科となってしまい、誤解を
招きかねない。継続的に診療科別収支を見ていくことは重要であり、これを踏まえた支援体制を組
むことが重要。
<タスク・シフト/シェア>
○
今後、医師の総数は大幅に変わらないため、タスク・シフトや医師以外の人材を活用することを考え
なければいけない。
○
例えば、臨床教育、臨床実習の場を大学病院から地域の教育病院へ移すことや、シミュレーション教
育をシミュレーション・スペシャリストの看護師にお願いすることも課題を解決するための方策に
なり得るのではないか。
○
看護師以外の職種も含めて、研究や教育に携わることのできる人材を広く捉えて議論すると同時に、
タスク・シフト/シェアの結果、負担が増える者への配慮、医師の教育に関わることへの心理的安全
の確保、インセンティブについても検討すべき。
○
大学病院で医師の診療時間を減らすためには、大学病院に人を増やすか大学病院で行う診療を減ら
すしかない。看護師等へのタスク・シフト/シェアの話があるが、他の職種に任せる業務内容を具体
的に議論いただきたい。
○
看護師が研修を経て行うことができる特定行為は 38 項目定められているが、比較的小さな技能であ
る。特定行為の範囲を更に拡張することを検討していく上で、特定行為研修修了者にもう少し大き
な一塊の業務として、どのような業務を任せるかを検討してはどうか。
2