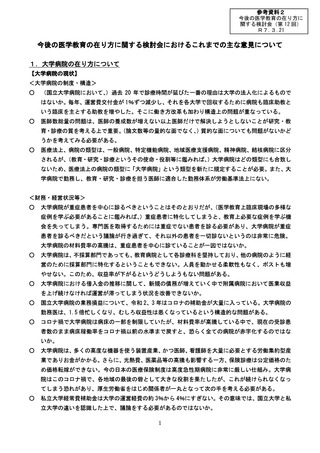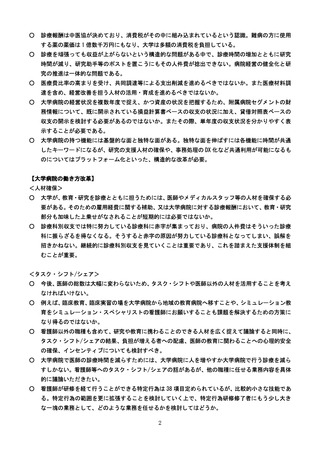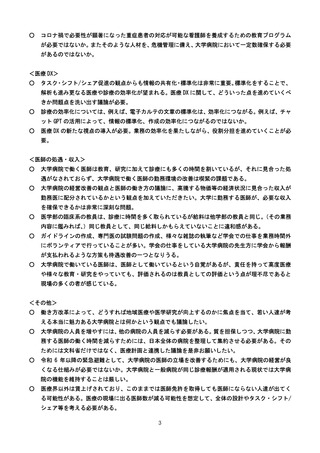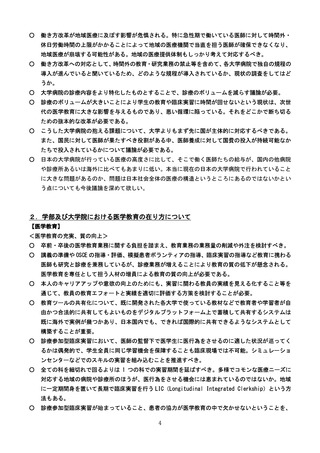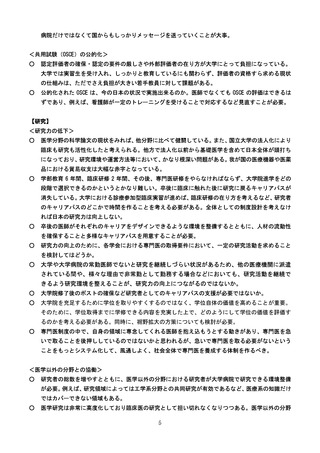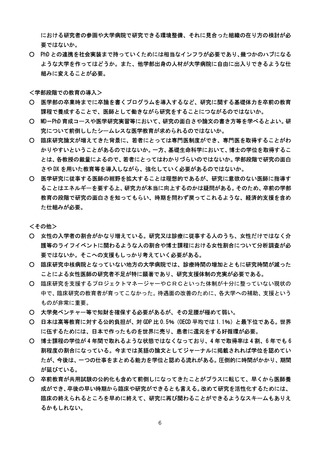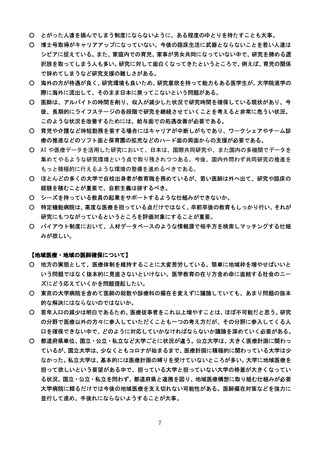よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_今後の医学教育の在り方に関する検討会におけるこれまでの主な 意見について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00015.html |
| 出典情報 | 今後の医学教育の在り方に関する検討会(第12回 3/21)《文部科学省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
における研究者の参画や大学病院で研究できる環境整備、それに見合った組織の在り方の検討が必
要ではないか。
○
PhD との連携を社会実装まで持っていくためには相当なインフラが必要であり、幾つかのハブになる
ような大学を作ってはどうか。また、他学部出身の人材が大学病院に自由に出入りできるような仕
組みに変えることが必要。
<学部段階での教育の導入>
○
医学部の卒業時までに卒論を書くプログラムを導入するなど、研究に関する基礎体力を卒前の教育
課程で養成することで、医師として働きながら研究をすることにつながるのではないか。
○
MD-PhD 育成コースや医学研究実習等において、研究の面白さや論文の書き方等を学べるとよい。研
究について前倒ししたシームレスな医学教育が求められるのではないか。
○
臨床研究論文が増えてきた背景に、若者にとっては専門医制度ができ、専門医を取得することがわ
かりやすいということがあるのではないか。一方、基礎生命科学において、博士の学位を取得するこ
とは、各教授の裁量によるので、若者にとってはわかりづらいのではないか。学部段階で研究の面白
さや DX を用いた教育等を導入しながら、強化していく必要があるのではないか。
○
医学研究に従事する医師の裾野を拡大することは理想的であるが、研究に意欲のない医師に指導す
ることはエネルギーを要する上、研究力が本当に向上するのかは疑問がある。そのため、卒前の学部
教育の段階で研究の面白さを知ってもらい、時期を問わず戻ってこれるような、経済的支援を含め
た仕組みが必要。
<その他>
○
女性の入学者の割合がかなり増えている。研究又は診療に従事する人のうち、女性だけではなく介
護等のライフイベントに関わるような人の割合や博士課程における女性割合について分析調査が必
要ではないか。そこへの支援もしっかり考えていく必要がある。
○
臨床研究中核病院となっていない地方の大学病院では、診療時間の増加とともに研究時間が減った
ことによる女性医師の研究者不足が特に顕著であり、研究支援体制の充実が必要である。
○
臨床研究を支援するプロジェクトマネージャーやCRCといった体制が十分に整っていない現状の
中で、臨床研究の教育者が育ってこなかった。待遇面の改善のために、各大学への補助、支援という
ものが非常に重要。
○
大学発ベンチャー等で知財を確保する必要があるが、その足腰が極めて弱い。
○
日本は高等教育に対する公的負担が、対 GDP 比 0.5%(OECD 平均では 1.1%)と最下位である。世界
に伍するためには、日本で作ったものを世界に売り、患者に還元をする好循環が必要。
○
博士課程の学位が 4 年間で取れるような状態ではなくなっており、4 年で取得率は 4 割、6 年でも 6
割程度の割合になっている。今までは英語の論文としてジャーナルに掲載されれば学位を認めてい
たが、今後は、一つの仕事をまとめる能力を学位と認める流れがある。圧倒的に時間がかかり、期間
が延びている。
○
卒前教育が共用試験の公的化も含めて前倒しになってきたことがプラスに転じて、早くから医師養
成ができ、卒後の早い時期から臨床や研究ができるとも言える。改めて研究を活性化するためには、
臨床の終えられるところを早めに終えて、研究に再び関わることができるようなスキームもありえ
るかもしれない。
6
要ではないか。
○
PhD との連携を社会実装まで持っていくためには相当なインフラが必要であり、幾つかのハブになる
ような大学を作ってはどうか。また、他学部出身の人材が大学病院に自由に出入りできるような仕
組みに変えることが必要。
<学部段階での教育の導入>
○
医学部の卒業時までに卒論を書くプログラムを導入するなど、研究に関する基礎体力を卒前の教育
課程で養成することで、医師として働きながら研究をすることにつながるのではないか。
○
MD-PhD 育成コースや医学研究実習等において、研究の面白さや論文の書き方等を学べるとよい。研
究について前倒ししたシームレスな医学教育が求められるのではないか。
○
臨床研究論文が増えてきた背景に、若者にとっては専門医制度ができ、専門医を取得することがわ
かりやすいということがあるのではないか。一方、基礎生命科学において、博士の学位を取得するこ
とは、各教授の裁量によるので、若者にとってはわかりづらいのではないか。学部段階で研究の面白
さや DX を用いた教育等を導入しながら、強化していく必要があるのではないか。
○
医学研究に従事する医師の裾野を拡大することは理想的であるが、研究に意欲のない医師に指導す
ることはエネルギーを要する上、研究力が本当に向上するのかは疑問がある。そのため、卒前の学部
教育の段階で研究の面白さを知ってもらい、時期を問わず戻ってこれるような、経済的支援を含め
た仕組みが必要。
<その他>
○
女性の入学者の割合がかなり増えている。研究又は診療に従事する人のうち、女性だけではなく介
護等のライフイベントに関わるような人の割合や博士課程における女性割合について分析調査が必
要ではないか。そこへの支援もしっかり考えていく必要がある。
○
臨床研究中核病院となっていない地方の大学病院では、診療時間の増加とともに研究時間が減った
ことによる女性医師の研究者不足が特に顕著であり、研究支援体制の充実が必要である。
○
臨床研究を支援するプロジェクトマネージャーやCRCといった体制が十分に整っていない現状の
中で、臨床研究の教育者が育ってこなかった。待遇面の改善のために、各大学への補助、支援という
ものが非常に重要。
○
大学発ベンチャー等で知財を確保する必要があるが、その足腰が極めて弱い。
○
日本は高等教育に対する公的負担が、対 GDP 比 0.5%(OECD 平均では 1.1%)と最下位である。世界
に伍するためには、日本で作ったものを世界に売り、患者に還元をする好循環が必要。
○
博士課程の学位が 4 年間で取れるような状態ではなくなっており、4 年で取得率は 4 割、6 年でも 6
割程度の割合になっている。今までは英語の論文としてジャーナルに掲載されれば学位を認めてい
たが、今後は、一つの仕事をまとめる能力を学位と認める流れがある。圧倒的に時間がかかり、期間
が延びている。
○
卒前教育が共用試験の公的化も含めて前倒しになってきたことがプラスに転じて、早くから医師養
成ができ、卒後の早い時期から臨床や研究ができるとも言える。改めて研究を活性化するためには、
臨床の終えられるところを早めに終えて、研究に再び関わることができるようなスキームもありえ
るかもしれない。
6