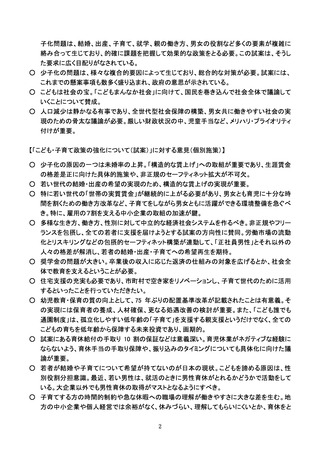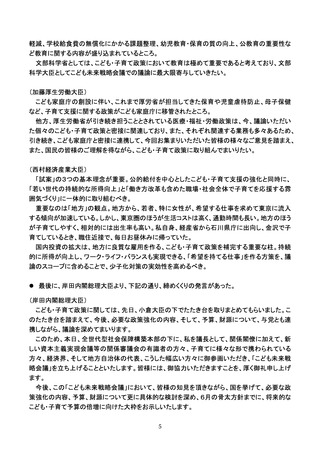よむ、つかう、まなぶ。
第1回こども未来戦略会 議議事要旨 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/dai1/kodomo_mirai_1.pdf |
| 出典情報 | 第1回こども未来戦略会 議議事要旨(4/11)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○
○
○
○
○
った場合の補充人材の確保が難しいとの課題もある。130 万円の壁のために働きたいけど働
けないという問題について、共働きの時代に配偶者控除というのは無理があるとの声も聞く。
柔軟な働き方の推進や、多様な働き方と子育ての両立支援は重要だが、事実上女性のみに
向けた取組とならないよう注意が必要。男女が共に働き、共に子育てしていくという視点で働
き方改革を進めるべき。
ジェンダーバイアスは根深く、 「子育てと仕事との両立が難しい」 という声が多い。さらに、生
活が苦しい中で頑張っているひとり親世帯への支援も喫緊の課題。誰もが「日本は子育てし
やすい社会」だと実感できるようにすることが必要。
海外で子育てしていた時、当初は不安だったが、どこにでもベビーカーを持っていくことができ、
みんな優しかった。帰国後、ギャップに驚き、これが日本の現状なのかと考えさせられた。
約7人に1人とも言われる貧困の解消は、社会全体への便益が大きく、重点を置くべき。その
際、国や行政が提供するサービスでは限界があり、民間のノウハウを活用した、NPO などに
よる「共助」の取組を広げることを考えるべき。
価値観が多様化する中で、こどもを持ってもらうためには、多様な結婚や家庭の在り方が受
容される社会を築く必要があるのではないか。例えば、「事実婚」の夫婦やそのこどもが不利
にならない税制といったところまで含めて検討すべき。 様々な方々に対し、インクルーシブな
子育て支援だと理解していただくことが重要。
【総合的な制度体系について】
○ 現在の制度は、つぎはぎで国民に分かりにくく、全ての子育て世帯を切れ目なく支援する「統
合的な制度体系」も構築すべき。
○ 試案で、総合的な制度体系を構築するとされている点は、縦割りの制度体系から、取り残され
る人を出さない社会保障の構築が求められる中で重要な視点。制度を再構築し、妊娠・出産・
子育てを通じた切れ目ない包括的支援を構築するとともに、恒久的な財源を確保していかな
ければならない。
○ 施策を総動員して、全てのこどもや子育て世帯が気兼ねなく柔軟に利用できる給付体制づくり
を目指し、財源問題にも躊躇なく踏み込んだ議論に期待したい。
○ こども・子育て支援制度は、既存制度の枠組みをベースに充実させた結果、財源構成を含め
て複雑な仕組みになっている。総合的な制度体系の構築に向けて、支援や給付の拡充を行う
にあたっては、財源は様々な選択肢を念頭に、白地で整理すべき。
○ 医療、介護、年金保険など高齢期の生活の費用の社会化による少子化の進行に対する解決
策は、高齢期向けの社会保障をなくしていくこと、出産と育児に関する消費を介護のように社
会化していくことの二つしかないが、スウェーデンのミュルダール夫妻は、少子化の予防策と
して、全てのこどもを対象とする「普遍的福祉政策」を唱えた。
○ 地方創生の取組等を通して、地域の振興発展と持続可能性を追求している全国自治体によ
る主体的な取組の積み重ねが我が国の少子化対策にもつながる。また、自治体の財政力に
かかわらず、全国どこに住んでいても基本的なサービスが受けられるよう、必要な財政措置と
人材確保に向けた支援が必要。
3
○
○
○
○
った場合の補充人材の確保が難しいとの課題もある。130 万円の壁のために働きたいけど働
けないという問題について、共働きの時代に配偶者控除というのは無理があるとの声も聞く。
柔軟な働き方の推進や、多様な働き方と子育ての両立支援は重要だが、事実上女性のみに
向けた取組とならないよう注意が必要。男女が共に働き、共に子育てしていくという視点で働
き方改革を進めるべき。
ジェンダーバイアスは根深く、 「子育てと仕事との両立が難しい」 という声が多い。さらに、生
活が苦しい中で頑張っているひとり親世帯への支援も喫緊の課題。誰もが「日本は子育てし
やすい社会」だと実感できるようにすることが必要。
海外で子育てしていた時、当初は不安だったが、どこにでもベビーカーを持っていくことができ、
みんな優しかった。帰国後、ギャップに驚き、これが日本の現状なのかと考えさせられた。
約7人に1人とも言われる貧困の解消は、社会全体への便益が大きく、重点を置くべき。その
際、国や行政が提供するサービスでは限界があり、民間のノウハウを活用した、NPO などに
よる「共助」の取組を広げることを考えるべき。
価値観が多様化する中で、こどもを持ってもらうためには、多様な結婚や家庭の在り方が受
容される社会を築く必要があるのではないか。例えば、「事実婚」の夫婦やそのこどもが不利
にならない税制といったところまで含めて検討すべき。 様々な方々に対し、インクルーシブな
子育て支援だと理解していただくことが重要。
【総合的な制度体系について】
○ 現在の制度は、つぎはぎで国民に分かりにくく、全ての子育て世帯を切れ目なく支援する「統
合的な制度体系」も構築すべき。
○ 試案で、総合的な制度体系を構築するとされている点は、縦割りの制度体系から、取り残され
る人を出さない社会保障の構築が求められる中で重要な視点。制度を再構築し、妊娠・出産・
子育てを通じた切れ目ない包括的支援を構築するとともに、恒久的な財源を確保していかな
ければならない。
○ 施策を総動員して、全てのこどもや子育て世帯が気兼ねなく柔軟に利用できる給付体制づくり
を目指し、財源問題にも躊躇なく踏み込んだ議論に期待したい。
○ こども・子育て支援制度は、既存制度の枠組みをベースに充実させた結果、財源構成を含め
て複雑な仕組みになっている。総合的な制度体系の構築に向けて、支援や給付の拡充を行う
にあたっては、財源は様々な選択肢を念頭に、白地で整理すべき。
○ 医療、介護、年金保険など高齢期の生活の費用の社会化による少子化の進行に対する解決
策は、高齢期向けの社会保障をなくしていくこと、出産と育児に関する消費を介護のように社
会化していくことの二つしかないが、スウェーデンのミュルダール夫妻は、少子化の予防策と
して、全てのこどもを対象とする「普遍的福祉政策」を唱えた。
○ 地方創生の取組等を通して、地域の振興発展と持続可能性を追求している全国自治体によ
る主体的な取組の積み重ねが我が国の少子化対策にもつながる。また、自治体の財政力に
かかわらず、全国どこに住んでいても基本的なサービスが受けられるよう、必要な財政措置と
人材確保に向けた支援が必要。
3