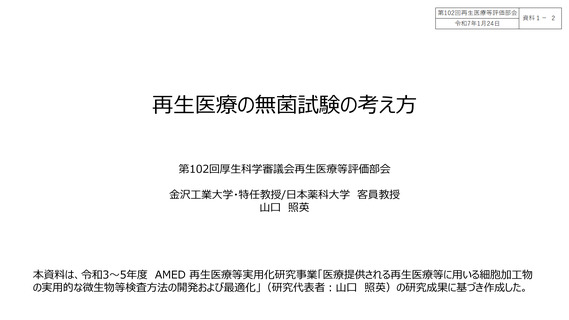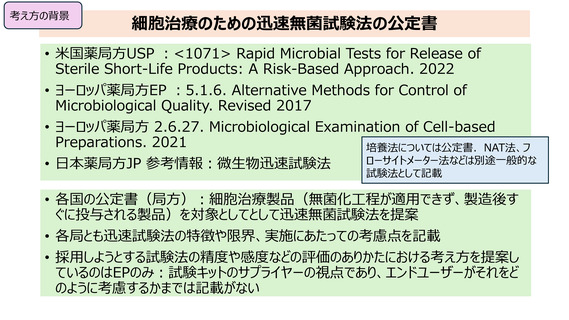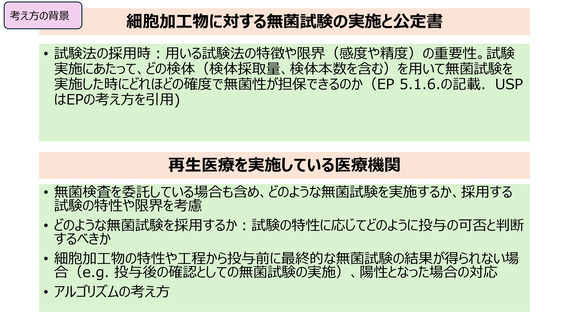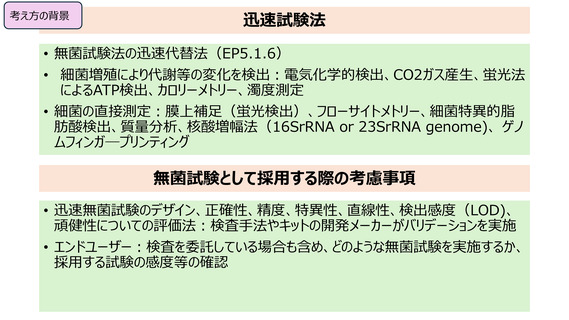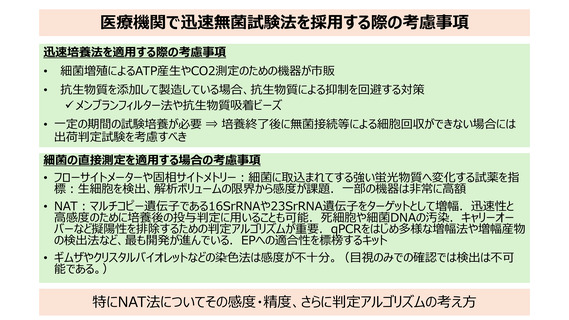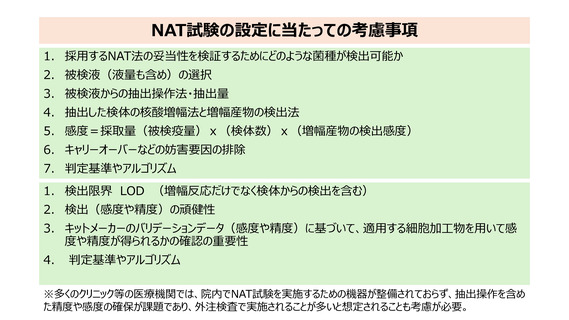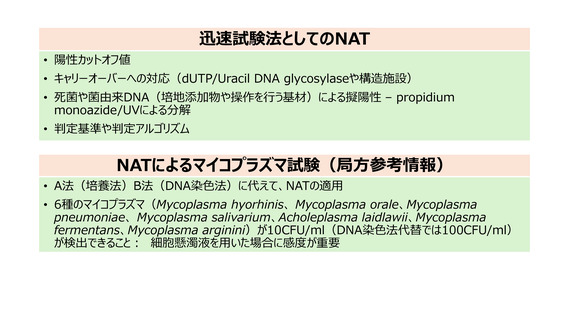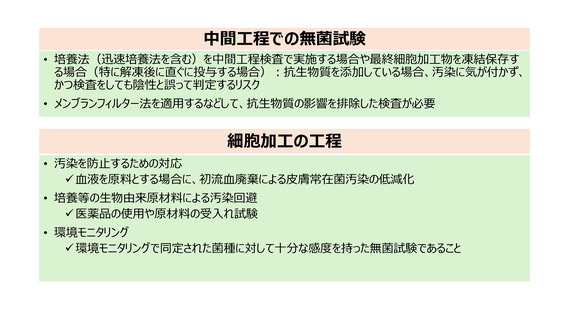よむ、つかう、まなぶ。
「再生医療の無菌試験の考え方」 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49713.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第102回 1/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療機関で迅速無菌試験法を採用する際の考慮事項
迅速培養法を適用する際の考慮事項
•
細菌増殖によるATP産生やCO2測定のための機器が市販
•
抗生物質を添加して製造している場合、抗生物質による抑制を回避する対策
✓ メンブランフィルター法や抗生物質吸着ビーズ
• 一定の期間の試験培養が必要 ⇒ 培養終了後に無菌接続等による細胞回収ができない場合には
出荷判定試験を考慮すべき
細菌の直接測定を適用する場合の考慮事項
• フローサイトメーターや固相サイトメトリー:細菌に取込まれてする強い蛍光物質へ変化する試薬を指
標:生細胞を検出、解析ボリュームの限界から感度が課題.一部の機器は非常に高額
• NAT:マルチコピー遺伝子である16SrRNAや23SrRNA遺伝子をターゲットとして増幅.迅速性と
高感度のために培養後の投与判定に用いることも可能.死細胞や細菌DNAの汚染.キャリーオー
バーなど擬陽性を排除するための判定アルゴリズムが重要.qPCRをはじめ多様な増幅法や増幅産物
の検出法など、最も開発が進んでいる.EPへの適合性を標榜するキット
• ギムザやクリスタルバイオレットなどの染色法は感度が不十分。(目視のみでの確認では検出は不可
能である。)
特にNAT法についてその感度・精度、さらに判定アルゴリズムの考え方
迅速培養法を適用する際の考慮事項
•
細菌増殖によるATP産生やCO2測定のための機器が市販
•
抗生物質を添加して製造している場合、抗生物質による抑制を回避する対策
✓ メンブランフィルター法や抗生物質吸着ビーズ
• 一定の期間の試験培養が必要 ⇒ 培養終了後に無菌接続等による細胞回収ができない場合には
出荷判定試験を考慮すべき
細菌の直接測定を適用する場合の考慮事項
• フローサイトメーターや固相サイトメトリー:細菌に取込まれてする強い蛍光物質へ変化する試薬を指
標:生細胞を検出、解析ボリュームの限界から感度が課題.一部の機器は非常に高額
• NAT:マルチコピー遺伝子である16SrRNAや23SrRNA遺伝子をターゲットとして増幅.迅速性と
高感度のために培養後の投与判定に用いることも可能.死細胞や細菌DNAの汚染.キャリーオー
バーなど擬陽性を排除するための判定アルゴリズムが重要.qPCRをはじめ多様な増幅法や増幅産物
の検出法など、最も開発が進んでいる.EPへの適合性を標榜するキット
• ギムザやクリスタルバイオレットなどの染色法は感度が不十分。(目視のみでの確認では検出は不可
能である。)
特にNAT法についてその感度・精度、さらに判定アルゴリズムの考え方