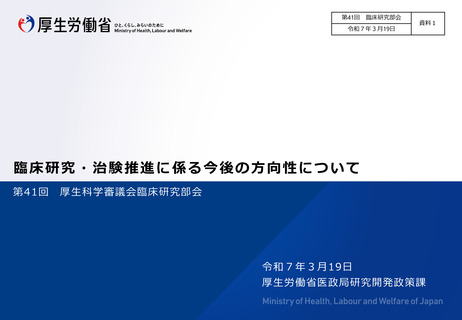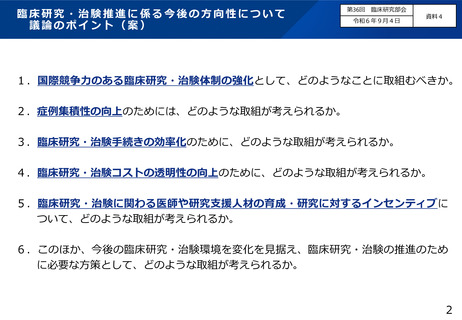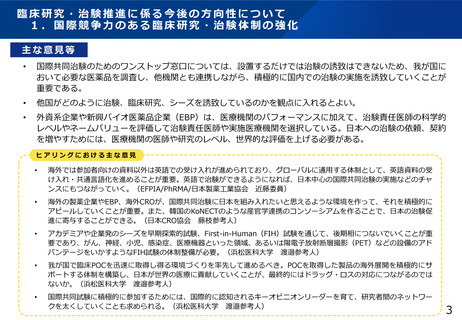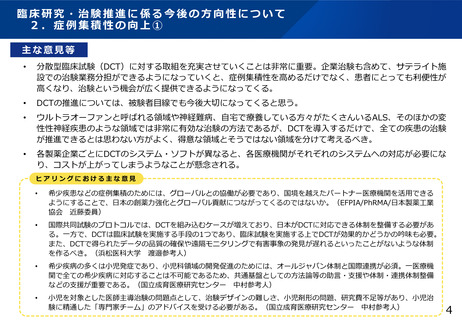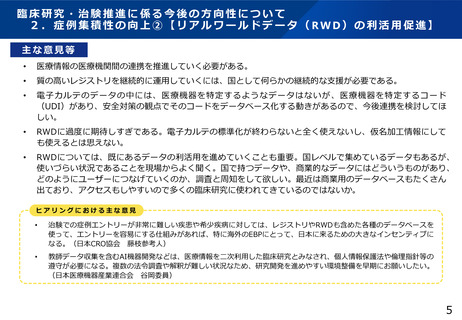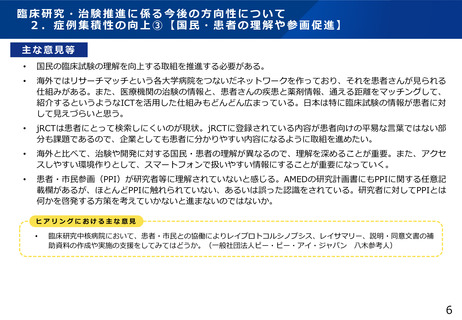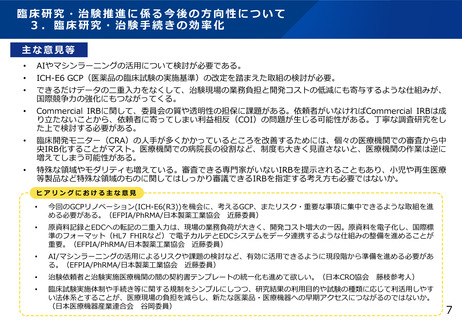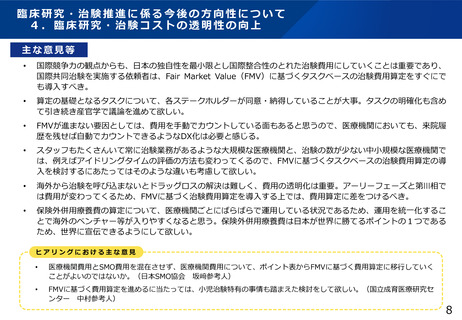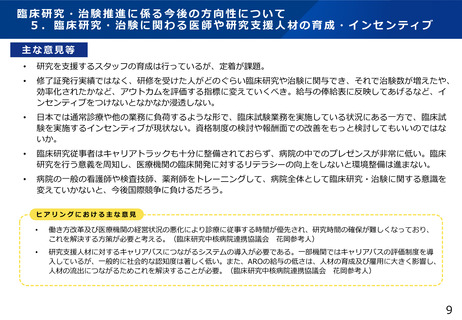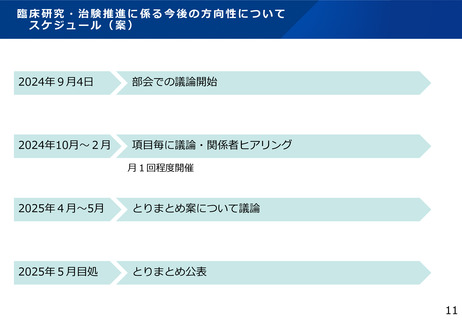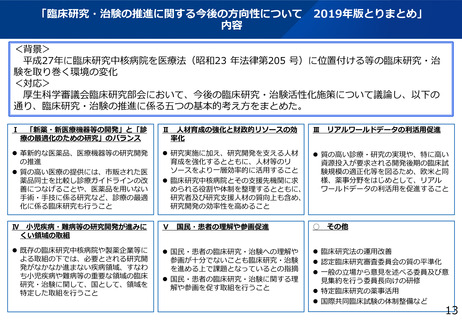よむ、つかう、まなぶ。
資料1:臨床研究・治験の推進に係る今後の方向性について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55079.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第41回 3/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
臨床研究・治験推進に係る今後の方向性について
1.国際競争力のある臨床研究・治験体制の強化
主な意見等
•
国際共同治験のためのワンストップ窓口については、設置するだけでは治験の誘致はできないため、我が国に
おいて必要な医薬品を調査し、他機関とも連携しながら、積極的に国内での治験の実施を誘致していくことが
重要である。
•
他国がどのように治験、臨床研究、シーズを誘致しているのかを観点に入れるとよい。
•
外資系企業や新興バイオ医薬品企業(EBP)は、医療機関のパフォーマンスに加えて、治験責任医師の科学的
レベルやネームバリューを評価して治験責任医師や実施医療機関を選択している。日本への治験の依頼、契約
を増やすためには、医療機関の医師や研究のレベル、世界的な評価を上げる必要がある。
ヒアリングにおける主な意見
•
海外では参加者向けの資料以外は英語での受け入れが進められており、グローバルに通用する体制として、英語資料の受
け入れ・共通言語化を進めることが重要。英語で治験ができるようになれば、日本中心の国際共同治験の実施などのチャ
ンスにもつながっていく。(EFPIA/PhRMA/日本製薬工業協会 近藤委員)
•
海外の製薬企業やEBP、海外CROが、国際共同治験に日本を組み入れたいと思えるような環境を作って、それを積極的に
アピールしていくことが重要。また、韓国のKoNECTのような産官学連携のコンソーシアムを作ることで、日本の治験促
進に寄与することができる。(日本CRO協会 藤枝参考人)
•
アカデミアや企業発のシーズを早期探索的試験、First-in-Human(FIH)試験を通じて、後期相につないでいくことが重
要であり、がん、神経、小児、感染症、医療機器といった領域、あるいは陽電子放射断層撮影(PET)などの設備のアド
バンテージをいかすようなFIH試験の体制整備が必要。(浜松医科大学 渡邉参考人)
•
我が国で臨床POCを迅速に取得し得る環境づくりを率先して進めるべき。POCを取得した製品の海外展開を積極的にサ
ポートする体制を構築し、日本が世界の医療に貢献していくことが、最終的にはドラッグ・ロスの対応につながるのでは
ないか。(浜松医科大学 渡邉参考人)
•
国際共同試験に積極的に参加するためには、国際的に認知されるキーオピニオンリーダーを育て、研究者間のネットワー
クを太くしていくことも求められる。(浜松医科大学 渡邉参考人)
3
1.国際競争力のある臨床研究・治験体制の強化
主な意見等
•
国際共同治験のためのワンストップ窓口については、設置するだけでは治験の誘致はできないため、我が国に
おいて必要な医薬品を調査し、他機関とも連携しながら、積極的に国内での治験の実施を誘致していくことが
重要である。
•
他国がどのように治験、臨床研究、シーズを誘致しているのかを観点に入れるとよい。
•
外資系企業や新興バイオ医薬品企業(EBP)は、医療機関のパフォーマンスに加えて、治験責任医師の科学的
レベルやネームバリューを評価して治験責任医師や実施医療機関を選択している。日本への治験の依頼、契約
を増やすためには、医療機関の医師や研究のレベル、世界的な評価を上げる必要がある。
ヒアリングにおける主な意見
•
海外では参加者向けの資料以外は英語での受け入れが進められており、グローバルに通用する体制として、英語資料の受
け入れ・共通言語化を進めることが重要。英語で治験ができるようになれば、日本中心の国際共同治験の実施などのチャ
ンスにもつながっていく。(EFPIA/PhRMA/日本製薬工業協会 近藤委員)
•
海外の製薬企業やEBP、海外CROが、国際共同治験に日本を組み入れたいと思えるような環境を作って、それを積極的に
アピールしていくことが重要。また、韓国のKoNECTのような産官学連携のコンソーシアムを作ることで、日本の治験促
進に寄与することができる。(日本CRO協会 藤枝参考人)
•
アカデミアや企業発のシーズを早期探索的試験、First-in-Human(FIH)試験を通じて、後期相につないでいくことが重
要であり、がん、神経、小児、感染症、医療機器といった領域、あるいは陽電子放射断層撮影(PET)などの設備のアド
バンテージをいかすようなFIH試験の体制整備が必要。(浜松医科大学 渡邉参考人)
•
我が国で臨床POCを迅速に取得し得る環境づくりを率先して進めるべき。POCを取得した製品の海外展開を積極的にサ
ポートする体制を構築し、日本が世界の医療に貢献していくことが、最終的にはドラッグ・ロスの対応につながるのでは
ないか。(浜松医科大学 渡邉参考人)
•
国際共同試験に積極的に参加するためには、国際的に認知されるキーオピニオンリーダーを育て、研究者間のネットワー
クを太くしていくことも求められる。(浜松医科大学 渡邉参考人)
3