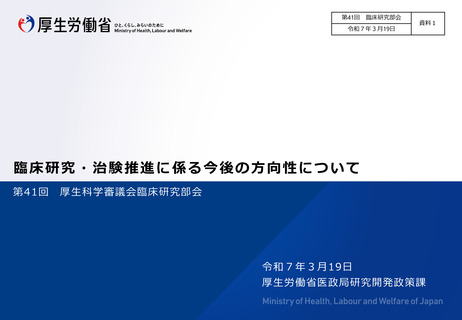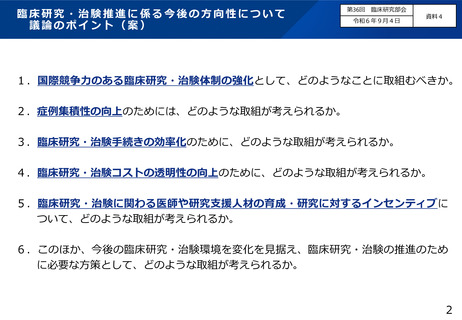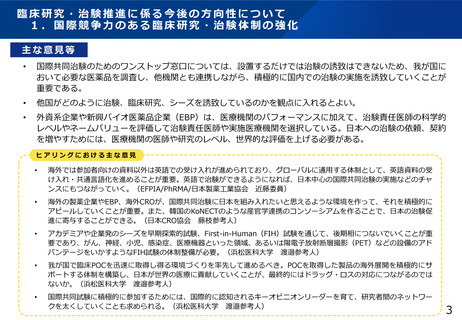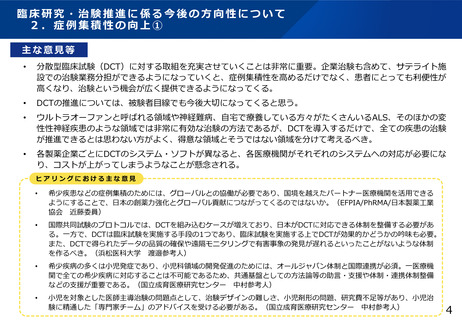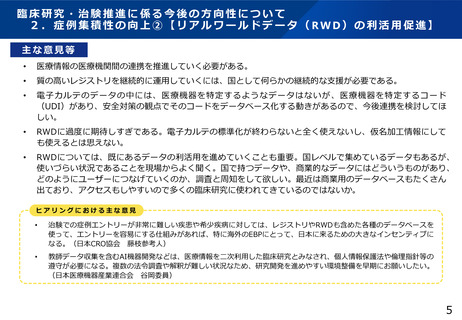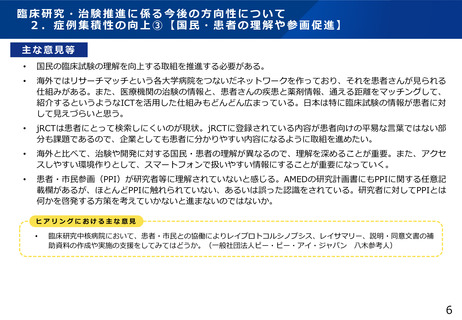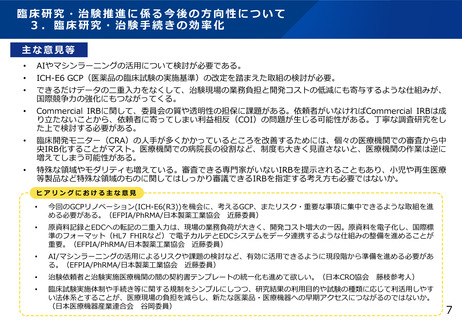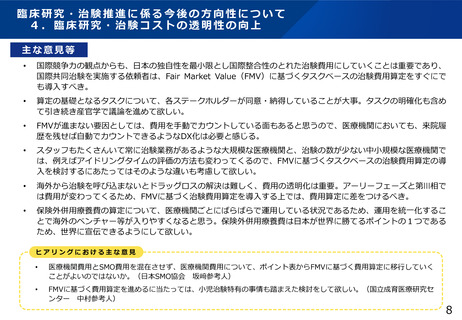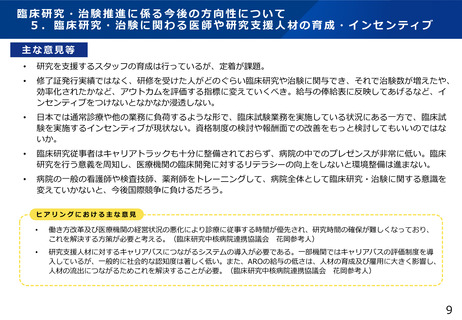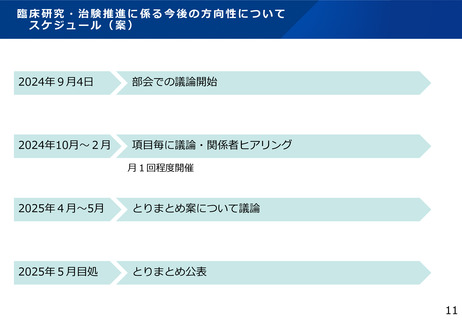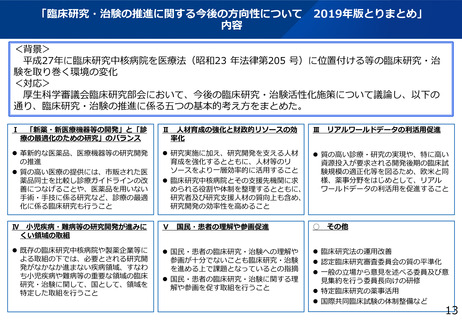よむ、つかう、まなぶ。
資料1:臨床研究・治験の推進に係る今後の方向性について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55079.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第41回 3/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
臨床研究・治験推進に係る今後の方向性について
2.症例集積性の向上①
主な意見等
•
分散型臨床試験(DCT)に対する取組を充実させていくことは非常に重要。企業治験も含めて、サテライト施
設での治験業務分担ができるようになっていくと、症例集積性を高めるだけでなく、患者にとっても利便性が
高くなり、治験という機会が広く提供できるようになってくる。
•
DCTの推進については、被験者目線でも今後大切になってくると思う。
•
ウルトラオーファンと呼ばれる領域や神経難病、自宅で療養している方々がたくさんいるALS、そのほかの変
性性神経疾患のような領域では非常に有効な治験の方法であるが、DCTを導入するだけで、全ての疾患の治験
が推進できるとは思わない方がよく、得意な領域とそうではない領域を分けて考えるべき。
•
各製薬企業ごとにDCTのシステム・ソフトが異なると、各医療機関がそれぞれのシステムへの対応が必要にな
り、コストが上がってしまうようなことが懸念される。
ヒアリングにおける主な意見
•
希少疾患などの症例集積のためには、グローバルとの協働が必要であり、国境を越えたパートナー医療機関を活用できる
ようにすることで、日本の創薬力強化とグローバル貢献につながってくるのではないか。(EFPIA/PhRMA/日本製薬工業
協会 近藤委員)
•
国際共同試験のプロトコルでは、DCTを組み込むケースが増えており、日本がDCTに対応できる体制を整備する必要があ
る。一方で、DCTは臨床試験を実施する手段の1つであり、臨床試験を実施する上でDCTが効果的かどうかの吟味も必要。
また、DCTで得られたデータの品質の確保や遠隔モニタリングで有害事象の発見が遅れるといったことがないような体制
を作るべき。(浜松医科大学 渡邉参考人)
•
希少疾病の多くは小児発症であり、小児科領域の開発促進のためには、オールジャパン体制と国際連携が必須。一医療機
関で全ての希少疾病に対応することは不可能であるため、共通基盤としての方法論等の助言・支援や体制・連携体制整備
などの支援が重要である。(国立成育医療研究センター 中村参考人)
•
小児を対象とした医師主導治験の問題点として、治験デザインの難しさ、小児剤形の問題、研究費不足等があり、小児治
験に精通した「専門家チーム」のアドバイスを受ける必要がある。(国立成育医療研究センター 中村参考人)
4
2.症例集積性の向上①
主な意見等
•
分散型臨床試験(DCT)に対する取組を充実させていくことは非常に重要。企業治験も含めて、サテライト施
設での治験業務分担ができるようになっていくと、症例集積性を高めるだけでなく、患者にとっても利便性が
高くなり、治験という機会が広く提供できるようになってくる。
•
DCTの推進については、被験者目線でも今後大切になってくると思う。
•
ウルトラオーファンと呼ばれる領域や神経難病、自宅で療養している方々がたくさんいるALS、そのほかの変
性性神経疾患のような領域では非常に有効な治験の方法であるが、DCTを導入するだけで、全ての疾患の治験
が推進できるとは思わない方がよく、得意な領域とそうではない領域を分けて考えるべき。
•
各製薬企業ごとにDCTのシステム・ソフトが異なると、各医療機関がそれぞれのシステムへの対応が必要にな
り、コストが上がってしまうようなことが懸念される。
ヒアリングにおける主な意見
•
希少疾患などの症例集積のためには、グローバルとの協働が必要であり、国境を越えたパートナー医療機関を活用できる
ようにすることで、日本の創薬力強化とグローバル貢献につながってくるのではないか。(EFPIA/PhRMA/日本製薬工業
協会 近藤委員)
•
国際共同試験のプロトコルでは、DCTを組み込むケースが増えており、日本がDCTに対応できる体制を整備する必要があ
る。一方で、DCTは臨床試験を実施する手段の1つであり、臨床試験を実施する上でDCTが効果的かどうかの吟味も必要。
また、DCTで得られたデータの品質の確保や遠隔モニタリングで有害事象の発見が遅れるといったことがないような体制
を作るべき。(浜松医科大学 渡邉参考人)
•
希少疾病の多くは小児発症であり、小児科領域の開発促進のためには、オールジャパン体制と国際連携が必須。一医療機
関で全ての希少疾病に対応することは不可能であるため、共通基盤としての方法論等の助言・支援や体制・連携体制整備
などの支援が重要である。(国立成育医療研究センター 中村参考人)
•
小児を対象とした医師主導治験の問題点として、治験デザインの難しさ、小児剤形の問題、研究費不足等があり、小児治
験に精通した「専門家チーム」のアドバイスを受ける必要がある。(国立成育医療研究センター 中村参考人)
4