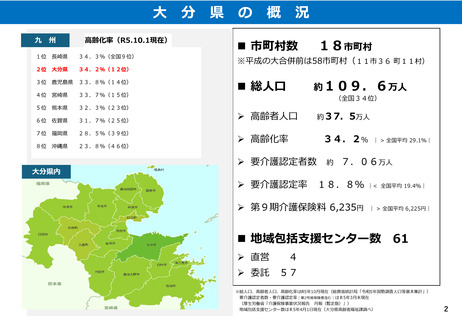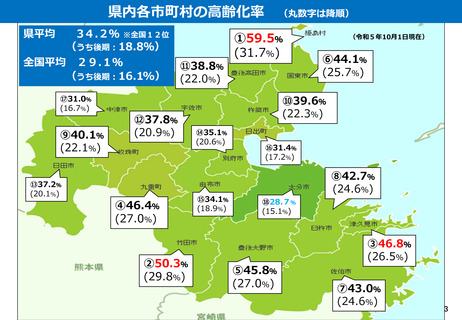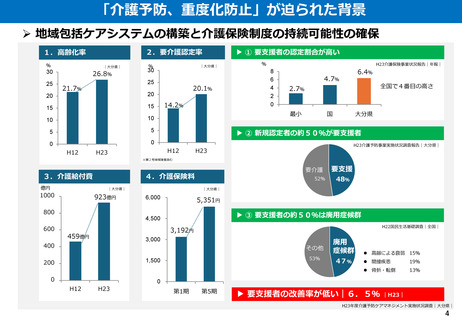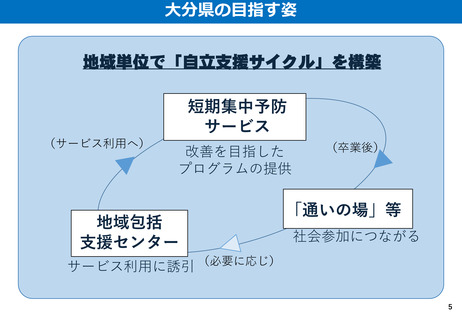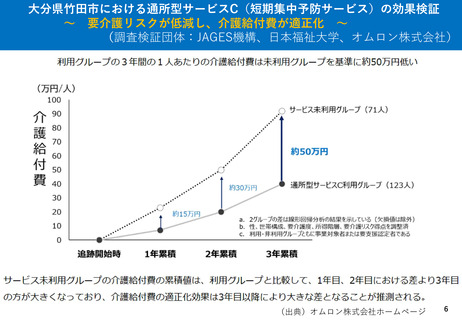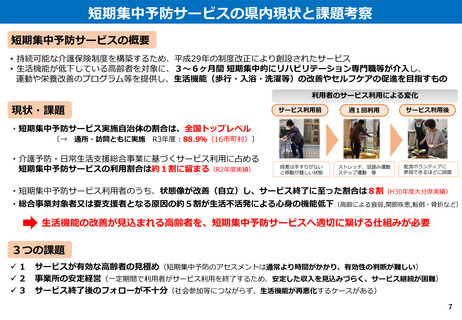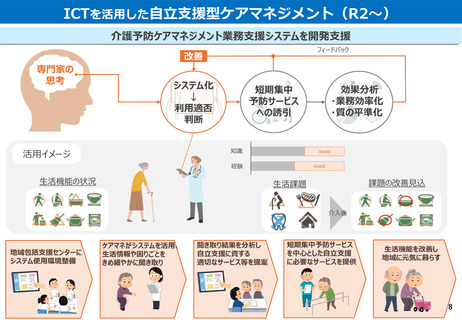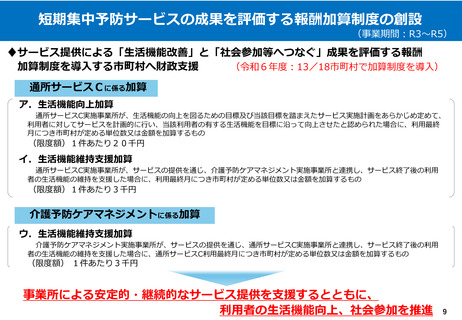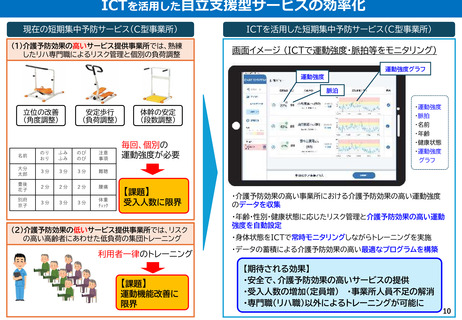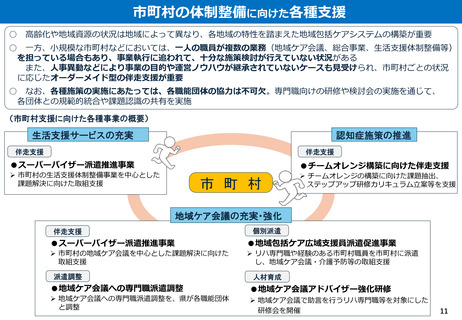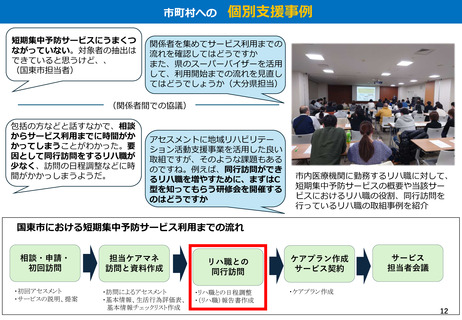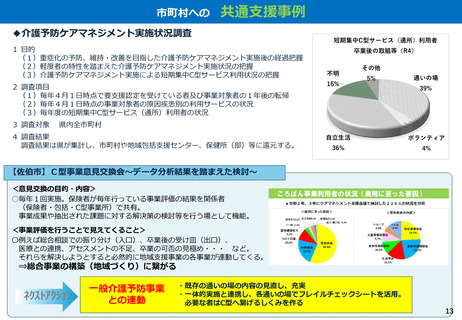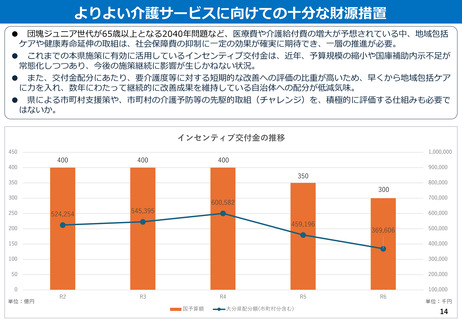よむ、つかう、まなぶ。
資料4 大分県提出資料 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49259.html |
| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第2回 2/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
短期集中予防サービスの県内現状と課題考察
短期集中予防サービスの概要
• 持続可能な介護保険制度を構築するため、平成29年の制度改正により創設されたサービス
• 生活機能が低下している高齢者を対象に、3~6ヶ月間 短期集中的にリハビリテーション専門職等が介入し、
運動や栄養改善のプログラム等を提供し、生活機能(歩行・入浴・洗濯等)の改善やセルフケアの促進を目指すもの
利用者のサービス利用による変化
現状・課題
サービス利用前
週1回利用
サービス利用後
段差は手すりがない
と移動が難しい状態
ストレッチ、足踏み運動
ステップ運動 等
配食ボランティアに
参加できるほどに回復
・短期集中予防サービス実施自治体の割合は、全国トップレベル
〔→
通所・訪問ともに実施
R3年度:88.9%(16市町村)〕
・介護予防・日常生活支援総合事業に基づくサービス利用に占める
短期集中予防サービスの利用割合は約1割に留まる(R2年度実績)
・短期集中予防サービス利用者のうち、状態像が改善(自立)し、サービス終了に至った割合は8割(H30年度大分県実績)
・総合事業対象者又は要支援者となる原因の約5割が生活不活発による心身の機能低下(高齢による衰弱,関節疾患,転倒・骨折など)
生活機能の改善が見込まれる高齢者を、短期集中予防サービスへ適切に繋げる仕組みが必要
3つの課題
1 サービスが有効な高齢者の見極め(短期集中予防のアセスメントは通常より時間がかかり、有効性の判断が難しい)
2 事業所の安定経営(一定期間で利用者がサービス利用を終了するため、安定した収入を見込みづらく、サービス継続が困難)
3 サービス終了後のフォローが不十分(社会参加等につながらず、生活機能が再悪化するケースがある)
7
短期集中予防サービスの概要
• 持続可能な介護保険制度を構築するため、平成29年の制度改正により創設されたサービス
• 生活機能が低下している高齢者を対象に、3~6ヶ月間 短期集中的にリハビリテーション専門職等が介入し、
運動や栄養改善のプログラム等を提供し、生活機能(歩行・入浴・洗濯等)の改善やセルフケアの促進を目指すもの
利用者のサービス利用による変化
現状・課題
サービス利用前
週1回利用
サービス利用後
段差は手すりがない
と移動が難しい状態
ストレッチ、足踏み運動
ステップ運動 等
配食ボランティアに
参加できるほどに回復
・短期集中予防サービス実施自治体の割合は、全国トップレベル
〔→
通所・訪問ともに実施
R3年度:88.9%(16市町村)〕
・介護予防・日常生活支援総合事業に基づくサービス利用に占める
短期集中予防サービスの利用割合は約1割に留まる(R2年度実績)
・短期集中予防サービス利用者のうち、状態像が改善(自立)し、サービス終了に至った割合は8割(H30年度大分県実績)
・総合事業対象者又は要支援者となる原因の約5割が生活不活発による心身の機能低下(高齢による衰弱,関節疾患,転倒・骨折など)
生活機能の改善が見込まれる高齢者を、短期集中予防サービスへ適切に繋げる仕組みが必要
3つの課題
1 サービスが有効な高齢者の見極め(短期集中予防のアセスメントは通常より時間がかかり、有効性の判断が難しい)
2 事業所の安定経営(一定期間で利用者がサービス利用を終了するため、安定した収入を見込みづらく、サービス継続が困難)
3 サービス終了後のフォローが不十分(社会参加等につながらず、生活機能が再悪化するケースがある)
7