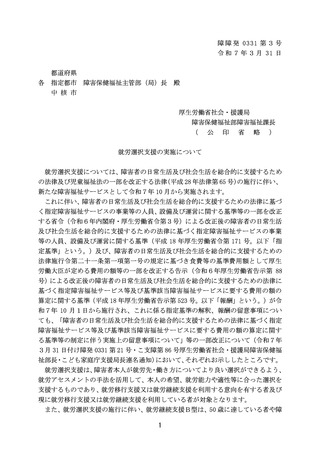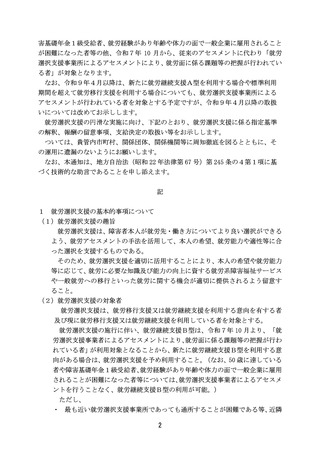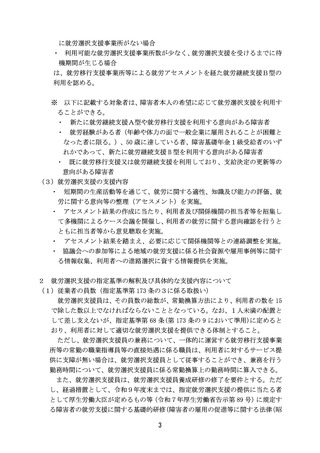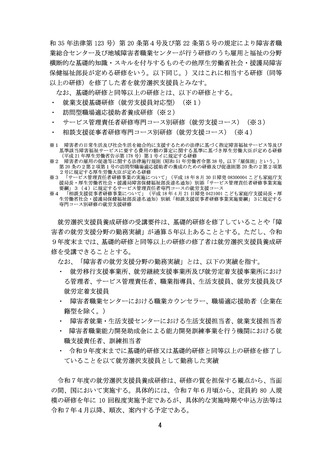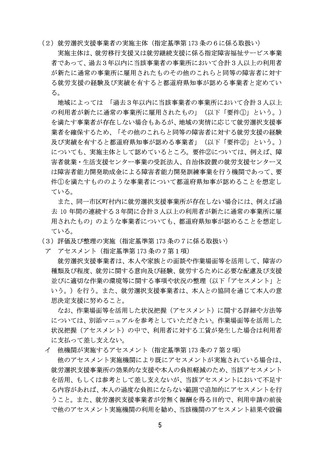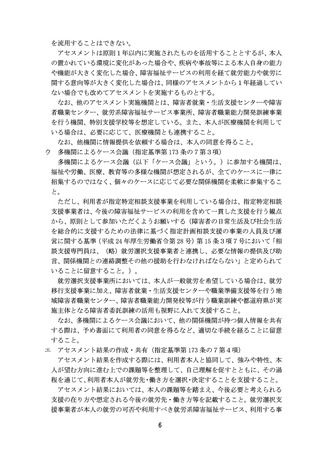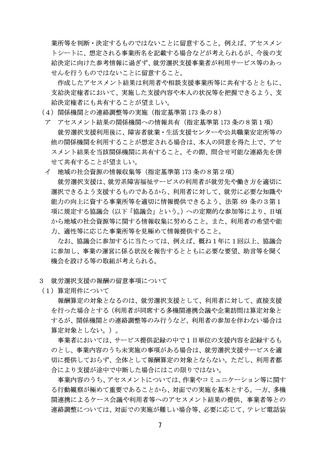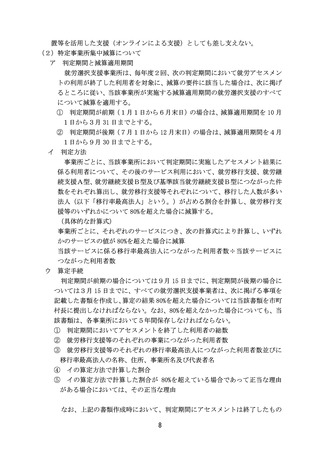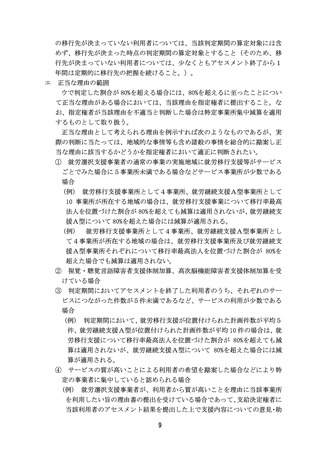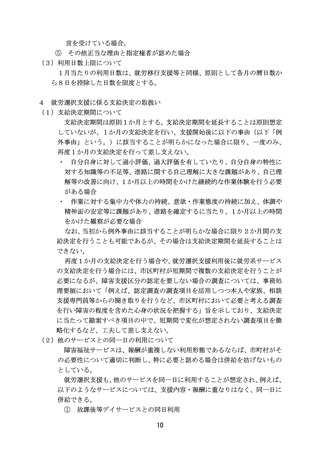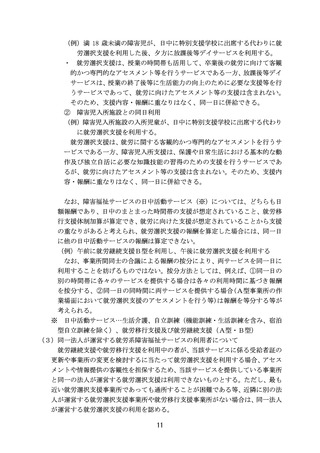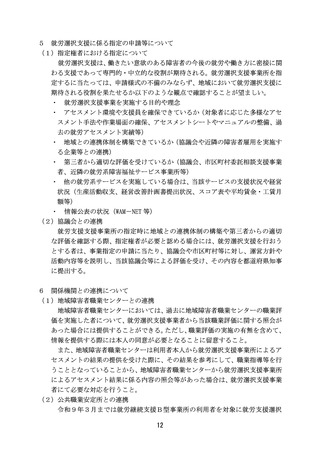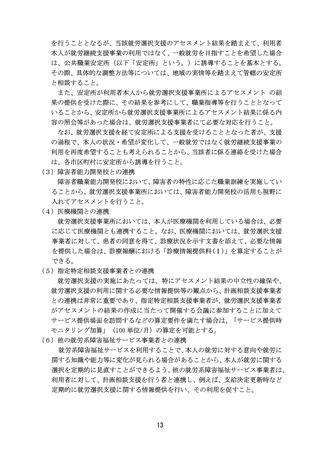よむ、つかう、まなぶ。
就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf |
| 出典情報 | 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を行うこととなるが、当該就労選択支援のアセスメント結果を踏まえて、利用者
本人が就労継続支援事業の利用ではなく、一般就労を目指すことを希望した場合
は、公共職業安定所(以下「安定所」という。)に誘導することを基本とする。
その際、具体的な調整方法等については、地域の実情等を踏まえて管轄の安定所
と相談すること。
また、安定所が利用者本人から就労選択支援事業所によるアセスメント の結
果の提供を受けた際に、その結果を参考にして、職業指導等を行うこととなって
いることから、安定所から就労選択支援事業所によるアセスメント結果に係る内
容の照会等があった場合は、就労選択支援事業者にて必要な対応を行うこと。
なお、就労選択支援を経て安定所による支援を受けることとなった者が、支援
の過程で、本人の状況・希望が変化して、一般就労ではなく就労継続支援事業の
利用を再度希望することも考えられることから、当該者に係る連絡を受けた場合
は、各市区町村に安定所から誘導を行うこと。
(3)障害者能力開発校との連携
障害者職業能力開発校において、障害者の特性に応じた職業訓練を実施してい
ることから、就労選択支援事業所においては、障害者能力開発校の活用も視野に
入れてアセスメントを行うこと。
(4)医療機関との連携
就労選択支援事業所においては、本人が医療機関を利用している場合は、必要
に応じて医療機関とも連携すること。なお、医療機関においては、就労選択支援
事業者に対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて、必要な情報
を提供した場合は、診療報酬における「診療情報提供料(Ⅰ)」を算定することが
できる。
(5)指定特定相談支援事業者との連携
就労選択支援の実施にあたっては、特にアセスメント結果の中立性の確保や、
就労選択支援の利用に関する必要な情報提供等の観点から、計画相談支援事業者
との連携は非常に重要であり、指定特定相談支援事業者が、就労選択支援事業者
がアセスメントの結果の作成に当たって開催する会議に参加することに加えて
サービス提供場面を訪問するなどの算定要件を満たす場合は、「サービス提供時
モニタリング加算」(100 単位/月)の算定を可能とする。
(6)他の就労系障害福祉サービス事業者との連携
就労系障害福祉サービスを利用することで、本人の就労に対する意向や就労に
関する知識や能力等に変化が見られる場合があることから、本人が就労に関する
選択を定期的に見直すことができるよう、他の就労系障害福祉サービス事業者は、
利用者に対して、計画相談支援を行う者と連携し、例えば、支給決定更新時など
定期的に就労選択支援に関する情報提供を行い、その利用を促すこと。
13
本人が就労継続支援事業の利用ではなく、一般就労を目指すことを希望した場合
は、公共職業安定所(以下「安定所」という。)に誘導することを基本とする。
その際、具体的な調整方法等については、地域の実情等を踏まえて管轄の安定所
と相談すること。
また、安定所が利用者本人から就労選択支援事業所によるアセスメント の結
果の提供を受けた際に、その結果を参考にして、職業指導等を行うこととなって
いることから、安定所から就労選択支援事業所によるアセスメント結果に係る内
容の照会等があった場合は、就労選択支援事業者にて必要な対応を行うこと。
なお、就労選択支援を経て安定所による支援を受けることとなった者が、支援
の過程で、本人の状況・希望が変化して、一般就労ではなく就労継続支援事業の
利用を再度希望することも考えられることから、当該者に係る連絡を受けた場合
は、各市区町村に安定所から誘導を行うこと。
(3)障害者能力開発校との連携
障害者職業能力開発校において、障害者の特性に応じた職業訓練を実施してい
ることから、就労選択支援事業所においては、障害者能力開発校の活用も視野に
入れてアセスメントを行うこと。
(4)医療機関との連携
就労選択支援事業所においては、本人が医療機関を利用している場合は、必要
に応じて医療機関とも連携すること。なお、医療機関においては、就労選択支援
事業者に対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて、必要な情報
を提供した場合は、診療報酬における「診療情報提供料(Ⅰ)」を算定することが
できる。
(5)指定特定相談支援事業者との連携
就労選択支援の実施にあたっては、特にアセスメント結果の中立性の確保や、
就労選択支援の利用に関する必要な情報提供等の観点から、計画相談支援事業者
との連携は非常に重要であり、指定特定相談支援事業者が、就労選択支援事業者
がアセスメントの結果の作成に当たって開催する会議に参加することに加えて
サービス提供場面を訪問するなどの算定要件を満たす場合は、「サービス提供時
モニタリング加算」(100 単位/月)の算定を可能とする。
(6)他の就労系障害福祉サービス事業者との連携
就労系障害福祉サービスを利用することで、本人の就労に対する意向や就労に
関する知識や能力等に変化が見られる場合があることから、本人が就労に関する
選択を定期的に見直すことができるよう、他の就労系障害福祉サービス事業者は、
利用者に対して、計画相談支援を行う者と連携し、例えば、支給決定更新時など
定期的に就労選択支援に関する情報提供を行い、その利用を促すこと。
13