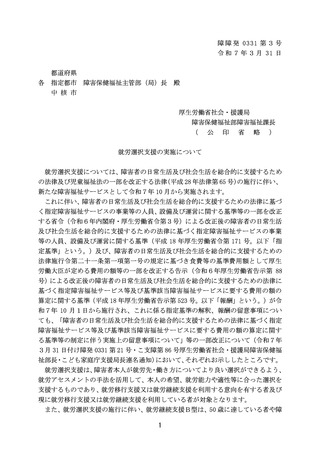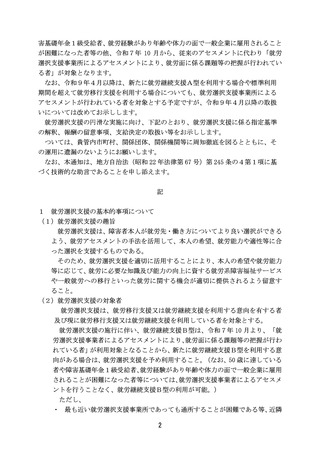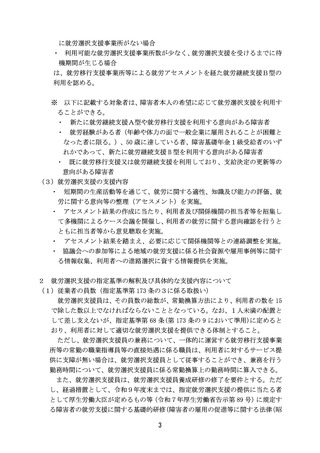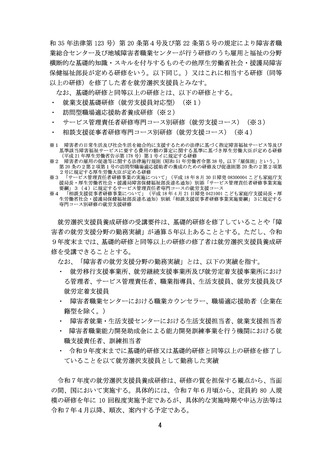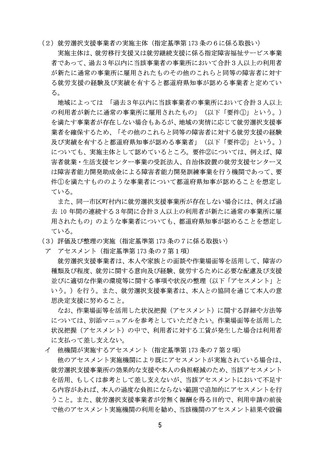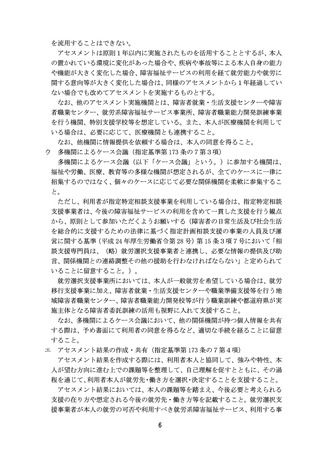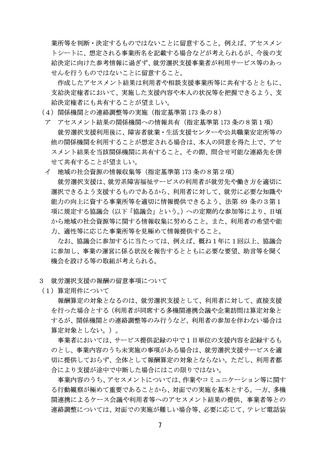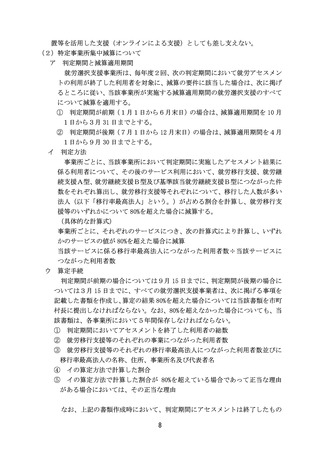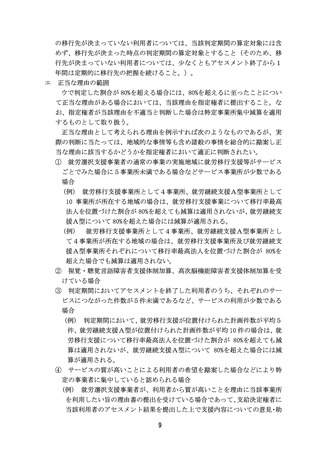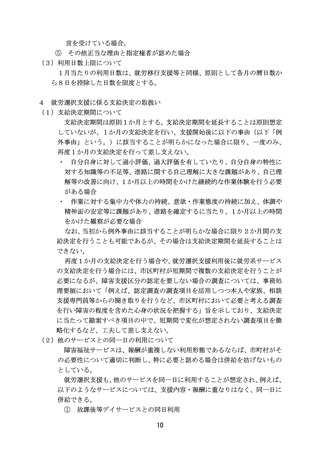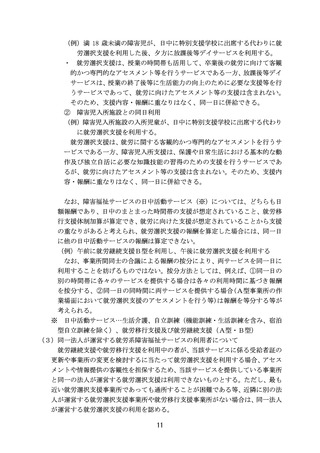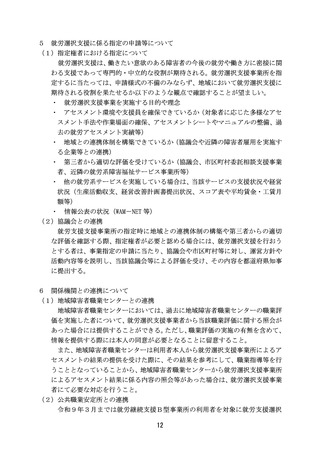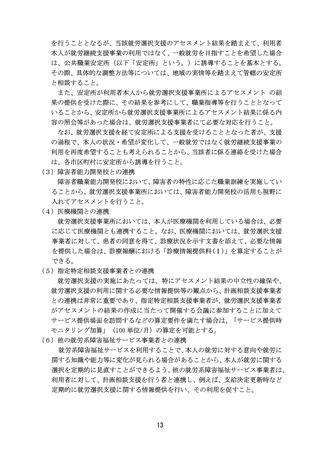よむ、つかう、まなぶ。
就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf |
| 出典情報 | 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
業所等を判断・決定するものではないことに留意すること。例えば、アセスメン
トシートに、想定される事業所名を記載する場合などが考えられるが、今後の支
給決定に向けた参考情報に過ぎず、就労選択支援事業者が利用サービス等のあっ
せんを行うものではないことに留意すること。
作成したアセスメント結果は利用者や相談支援事業所等に共有するとともに、
支給決定権者において、実施した支援内容や本人の状況等を把握できるよう、支
給決定権者にも共有することが望ましい。
(4)関係機関との連絡調整等の実施(指定基準第 173 条の8)
ア アセスメント結果の関係機関への情報共有(指定基準第 173 条の8第1項)
就労選択支援利用後に、障害者就業・生活支援センターや公共職業安定所等の
他の関係機関を利用することが想定される場合は、本人の同意を得た上で、アセ
スメント結果を当該関係機関に共有すること。その際、問合せ可能な連絡先を併
せて共有することが望ましい。
イ 地域の社会資源の情報収集等(指定基準第 173 条の8第2項)
就労選択支援は、就労系障害福祉サービスの利用者が就労先や働き方を適切に
選択できるよう支援するものであるから、利用者に対して、就労に必要な知識や
能力の向上に資する事業所等を適切に情報提供できるよう、法第 89 条の3第1
項に規定する協議会(以下「協議会」という。)への定期的な参加等により、日頃
から地域の社会資源等に関する情報収集に努めること。また、利用者の希望や能
力、適性等に応じた事業所等を見極めて情報提供すること。
なお、協議会に参加するに当たっては、例えば、概ね1年に1回以上、協議会
に参加し、事業の運営に係る状況を報告するとともに必要な要望、助言等を聞く
機会を設ける等の取組が考えられる。
3
就労選択支援の報酬の留意事項について
(1)算定用件について
報酬算定の対象となるのは、就労選択支援として、利用者に対して、直接支援
を行った場合とする(利用者が同席する多機関連携会議や企業訪問は算定対象と
するが、関係機関との連絡調整等のみ行うなど、利用者の参加を伴わない場合は
算定対象としない。)。
事業者においては、サービス提供記録の中で1日単位の支援内容を記録するも
のとし、事業内容のうち未実施の事項がある場合は、就労選択支援サービスを適
切に提供しておらず、全体として報酬算定の対象とならない。ただし、利用者都
合により支援が途中で中断した場合にはこの限りではない。
事業内容のうち、アセスメントについては、作業やコミュニケーション等に関す
る行動観察が極めて重要であることから、対面での実施を基本とする。一方、多機
関連携によるケース会議や利用者等へのアセスメント結果の提供、事業者等との
連絡調整については、対面での実施が難しい場合等、必要に応じて、テレビ電話装
7
トシートに、想定される事業所名を記載する場合などが考えられるが、今後の支
給決定に向けた参考情報に過ぎず、就労選択支援事業者が利用サービス等のあっ
せんを行うものではないことに留意すること。
作成したアセスメント結果は利用者や相談支援事業所等に共有するとともに、
支給決定権者において、実施した支援内容や本人の状況等を把握できるよう、支
給決定権者にも共有することが望ましい。
(4)関係機関との連絡調整等の実施(指定基準第 173 条の8)
ア アセスメント結果の関係機関への情報共有(指定基準第 173 条の8第1項)
就労選択支援利用後に、障害者就業・生活支援センターや公共職業安定所等の
他の関係機関を利用することが想定される場合は、本人の同意を得た上で、アセ
スメント結果を当該関係機関に共有すること。その際、問合せ可能な連絡先を併
せて共有することが望ましい。
イ 地域の社会資源の情報収集等(指定基準第 173 条の8第2項)
就労選択支援は、就労系障害福祉サービスの利用者が就労先や働き方を適切に
選択できるよう支援するものであるから、利用者に対して、就労に必要な知識や
能力の向上に資する事業所等を適切に情報提供できるよう、法第 89 条の3第1
項に規定する協議会(以下「協議会」という。)への定期的な参加等により、日頃
から地域の社会資源等に関する情報収集に努めること。また、利用者の希望や能
力、適性等に応じた事業所等を見極めて情報提供すること。
なお、協議会に参加するに当たっては、例えば、概ね1年に1回以上、協議会
に参加し、事業の運営に係る状況を報告するとともに必要な要望、助言等を聞く
機会を設ける等の取組が考えられる。
3
就労選択支援の報酬の留意事項について
(1)算定用件について
報酬算定の対象となるのは、就労選択支援として、利用者に対して、直接支援
を行った場合とする(利用者が同席する多機関連携会議や企業訪問は算定対象と
するが、関係機関との連絡調整等のみ行うなど、利用者の参加を伴わない場合は
算定対象としない。)。
事業者においては、サービス提供記録の中で1日単位の支援内容を記録するも
のとし、事業内容のうち未実施の事項がある場合は、就労選択支援サービスを適
切に提供しておらず、全体として報酬算定の対象とならない。ただし、利用者都
合により支援が途中で中断した場合にはこの限りではない。
事業内容のうち、アセスメントについては、作業やコミュニケーション等に関す
る行動観察が極めて重要であることから、対面での実施を基本とする。一方、多機
関連携によるケース会議や利用者等へのアセスメント結果の提供、事業者等との
連絡調整については、対面での実施が難しい場合等、必要に応じて、テレビ電話装
7