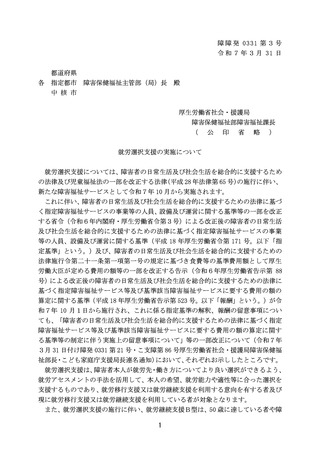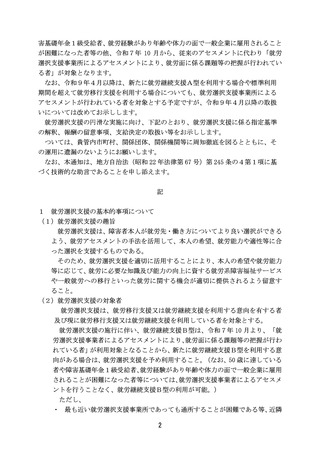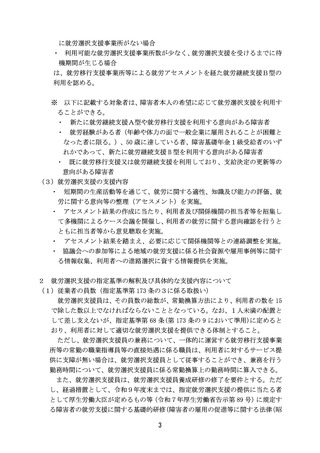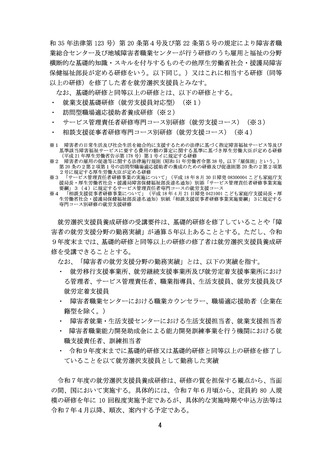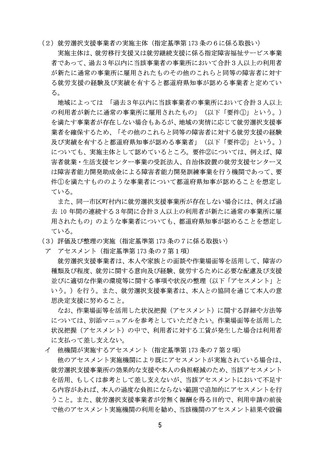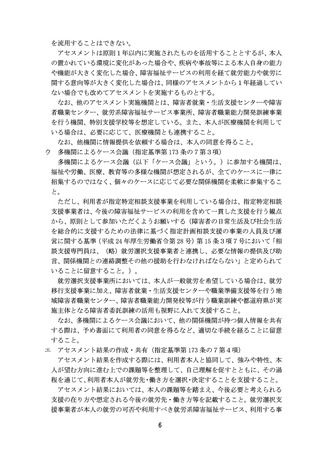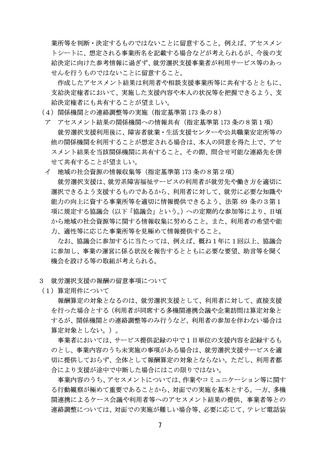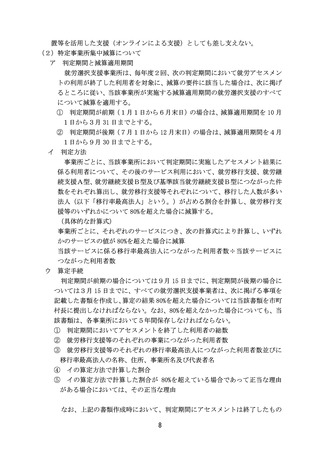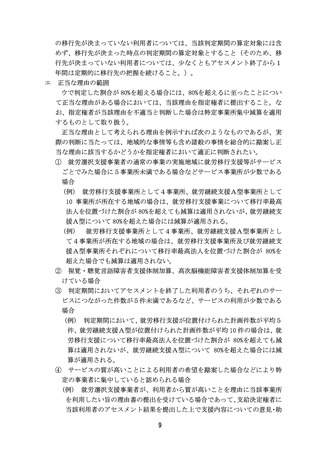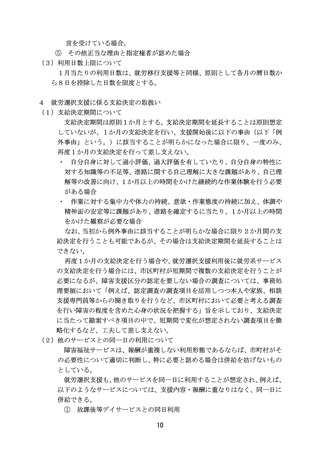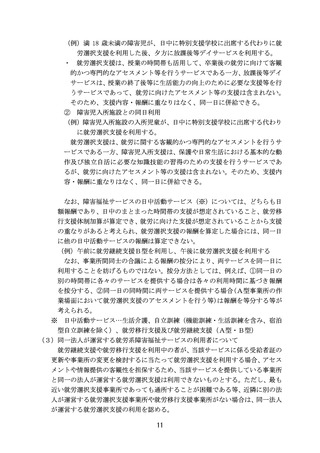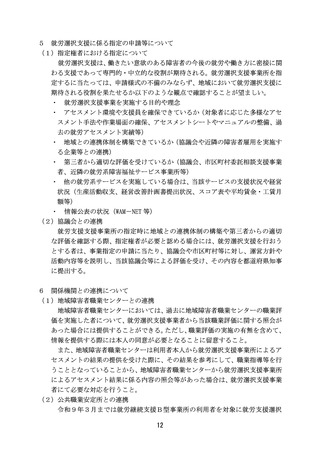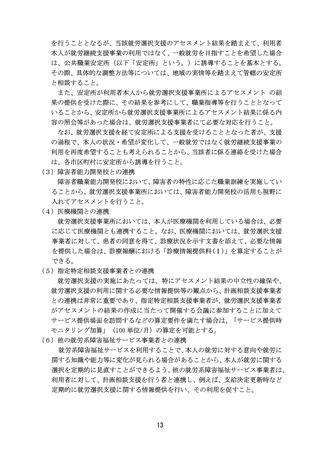よむ、つかう、まなぶ。
就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf |
| 出典情報 | 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
に就労選択支援事業所がない場合
・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待
機期間が生じる場合
は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の
利用を認める。
※ 以下に記載する対象者は、障害者本人の希望に応じて就労選択支援を利用す
ることができる。
・
新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある障害者
・ 就労経験がある者(年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難と
なった者に限る。)、50 歳に達している者、障害基礎年金1級受給者のいず
れかであって、新たに就労継続支援 B 型を利用する意向がある障害者
・ 既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等の
意向がある障害者
(3)就労選択支援の支援内容
・ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価、就
労に関する意向等の整理(アセスメント)を実施。
・ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集し
て多機関によるケース会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うと
ともに担当者等から意見聴取を実施。
・
アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
・ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関す
る情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。
2
就労選択支援の指定基準の解釈及び具体的な支援内容について
(1)従業者の員数(指定基準第 173 条の3に係る取扱い)
就労選択支援員は、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を 15
で除した数以上でなければならないこととなっている。なお、1人未満の配置と
して差し支えないが、指定基準第 68 条(第 173 条の 9 において準用)に定めると
おり、利用者に対して適切な就労選択支援を提供できる体制とすること。
ただし、就労選択支援員の兼務について、一体的に運営する就労移行支援事業
所等の常勤の職業指導員等の直接処遇に係る職員は、利用者に対するサービス提
供に支障が無い場合は、就労選択支援員として従事することができ、兼務を行う
勤務時間について、就労選択支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入できる。
また、就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。ただ
し、経過措置として、令和9年度末までは、指定就労選択支援の提供に当たる者
として厚生労働大臣が定めるもの等(令和7年厚生労働省告示第 89 号)に規定す
る障害者の就労支援に関する基礎的研修(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭
3
・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待
機期間が生じる場合
は、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の
利用を認める。
※ 以下に記載する対象者は、障害者本人の希望に応じて就労選択支援を利用す
ることができる。
・
新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある障害者
・ 就労経験がある者(年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難と
なった者に限る。)、50 歳に達している者、障害基礎年金1級受給者のいず
れかであって、新たに就労継続支援 B 型を利用する意向がある障害者
・ 既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等の
意向がある障害者
(3)就労選択支援の支援内容
・ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価、就
労に関する意向等の整理(アセスメント)を実施。
・ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集し
て多機関によるケース会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うと
ともに担当者等から意見聴取を実施。
・
アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
・ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関す
る情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。
2
就労選択支援の指定基準の解釈及び具体的な支援内容について
(1)従業者の員数(指定基準第 173 条の3に係る取扱い)
就労選択支援員は、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を 15
で除した数以上でなければならないこととなっている。なお、1人未満の配置と
して差し支えないが、指定基準第 68 条(第 173 条の 9 において準用)に定めると
おり、利用者に対して適切な就労選択支援を提供できる体制とすること。
ただし、就労選択支援員の兼務について、一体的に運営する就労移行支援事業
所等の常勤の職業指導員等の直接処遇に係る職員は、利用者に対するサービス提
供に支障が無い場合は、就労選択支援員として従事することができ、兼務を行う
勤務時間について、就労選択支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入できる。
また、就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。ただ
し、経過措置として、令和9年度末までは、指定就労選択支援の提供に当たる者
として厚生労働大臣が定めるもの等(令和7年厚生労働省告示第 89 号)に規定す
る障害者の就労支援に関する基礎的研修(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭
3