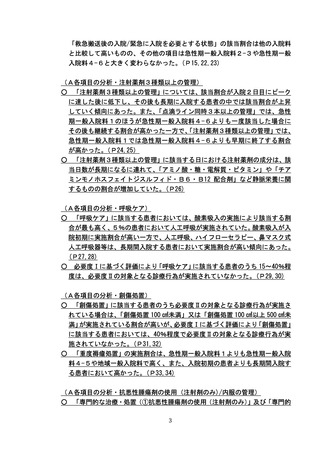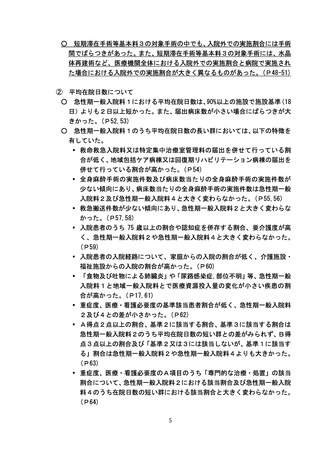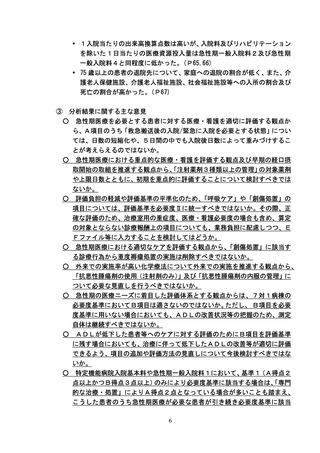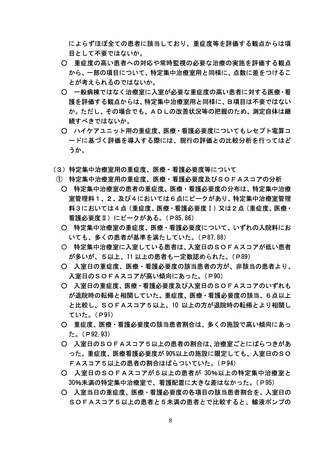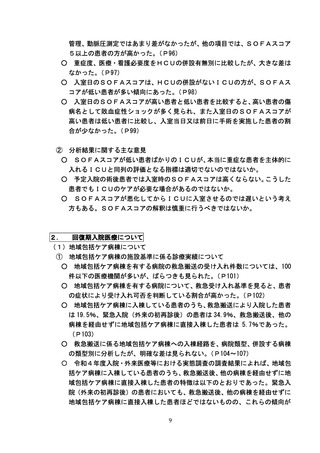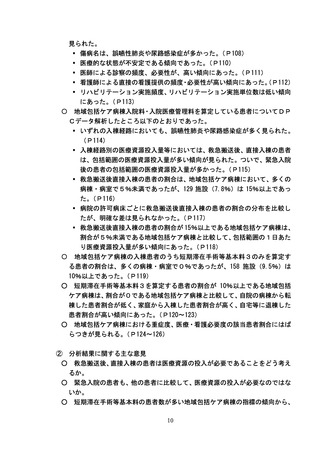よむ、つかう、まなぶ。
入-2 2.診療情報・指標等作業グループからの最終報告について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00215.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第9回 10/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の場合の点数に代えて、医療区分2の場合に相当する点数を算定することと
された。(P168)
○ 療養病棟における中心静脈栄養の実施状況については、各調査対象施設(597
施設)における3か月間の中心静脈栄養の実施患者数の中央値は、令和4年度
診療報酬改定前後で大きな変化は見られなかった。(P169)
○ 療養病棟における中心静脈栄養に関連した患者の状況として、中心静脈カテ
ーテルを挿入して病棟に転棟した患者のうち、中心静脈栄養から経口摂取へ
移行した患者は 4.1%であった。
(P170)
○ 中心静脈栄養を実施している状態にある者に対する摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制の整備状況について、体制がない医療機関は 32.7%であ
った。(P171)
○
消化管が機能している場合は、経腸栄養を選択することが基本であり、経腸
栄養が禁忌となるのは、汎発性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、麻痺性イレウス、
難治性下痢、活動性の消化管出血などに限定される。(P172)
○ 療養病棟における経腸栄養は、中心静脈栄養と比較し、生命予後が良好で、
抗菌薬の使用が少ない。医療区分の導入に伴い、中心静脈栄養の患者が増加し
たとの報告がある。(P173)
○ 入院後・入院中に中心静脈栄養を中止・終了した患者数が 40 床あたり1名
を超える施設の割合は、摂食嚥下機能または嚥下機能の回復に必要な体制が
ある施設では 23.2%、体制がない施設では 12.1%だった。(P174)
○ 消化管が機能している場合は、中心静脈栄養ではなく、経腸栄養を選択する
ことを基本であるとされている一方で、入院後から中心静脈栄養を実施開始
した患者数が 40 床あたり 10 名以上いるものの、中心静脈栄養を中止・終了し
た患者数が4名未満の施設が 2.4%であった。(P175)
③ 分析結果に関する主な意見
○ 医療区分について、同一の医療区分においても医療資源投入量にばらつきが
あることや、疾患・状態等と処置等の医療区分によって医療資源投入量の分布
や内訳が異なることなどから、医療の提供内容に応じた適切な指標となるよ
うに見直しを行ってはどうか。
○ 医療区分を精緻化する場合、評価及び記入に係る負担に十分配慮すべき。
○ 経口摂取が不可能な場合や中心静脈栄養から胃ろうや腸ろうなどへ栄養方
法を変更する場合の、医療者からの患者・家族への情報提供や意思決定支援が
重要。
○ 中心静脈栄養は経管栄養が実施できない限られた病態に応じて実施される
べきであることや、経管栄養と比べて生命予後が不良であることから、医療区
分3としての評価について、適切な指標となるよう見直してはどうか。
13
された。(P168)
○ 療養病棟における中心静脈栄養の実施状況については、各調査対象施設(597
施設)における3か月間の中心静脈栄養の実施患者数の中央値は、令和4年度
診療報酬改定前後で大きな変化は見られなかった。(P169)
○ 療養病棟における中心静脈栄養に関連した患者の状況として、中心静脈カテ
ーテルを挿入して病棟に転棟した患者のうち、中心静脈栄養から経口摂取へ
移行した患者は 4.1%であった。
(P170)
○ 中心静脈栄養を実施している状態にある者に対する摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制の整備状況について、体制がない医療機関は 32.7%であ
った。(P171)
○
消化管が機能している場合は、経腸栄養を選択することが基本であり、経腸
栄養が禁忌となるのは、汎発性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、麻痺性イレウス、
難治性下痢、活動性の消化管出血などに限定される。(P172)
○ 療養病棟における経腸栄養は、中心静脈栄養と比較し、生命予後が良好で、
抗菌薬の使用が少ない。医療区分の導入に伴い、中心静脈栄養の患者が増加し
たとの報告がある。(P173)
○ 入院後・入院中に中心静脈栄養を中止・終了した患者数が 40 床あたり1名
を超える施設の割合は、摂食嚥下機能または嚥下機能の回復に必要な体制が
ある施設では 23.2%、体制がない施設では 12.1%だった。(P174)
○ 消化管が機能している場合は、中心静脈栄養ではなく、経腸栄養を選択する
ことを基本であるとされている一方で、入院後から中心静脈栄養を実施開始
した患者数が 40 床あたり 10 名以上いるものの、中心静脈栄養を中止・終了し
た患者数が4名未満の施設が 2.4%であった。(P175)
③ 分析結果に関する主な意見
○ 医療区分について、同一の医療区分においても医療資源投入量にばらつきが
あることや、疾患・状態等と処置等の医療区分によって医療資源投入量の分布
や内訳が異なることなどから、医療の提供内容に応じた適切な指標となるよ
うに見直しを行ってはどうか。
○ 医療区分を精緻化する場合、評価及び記入に係る負担に十分配慮すべき。
○ 経口摂取が不可能な場合や中心静脈栄養から胃ろうや腸ろうなどへ栄養方
法を変更する場合の、医療者からの患者・家族への情報提供や意思決定支援が
重要。
○ 中心静脈栄養は経管栄養が実施できない限られた病態に応じて実施される
べきであることや、経管栄養と比べて生命予後が不良であることから、医療区
分3としての評価について、適切な指標となるよう見直してはどうか。
13