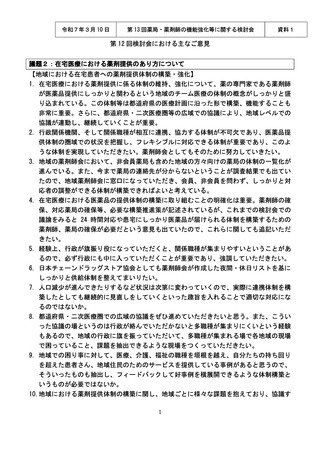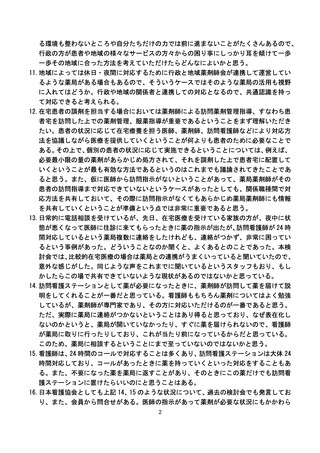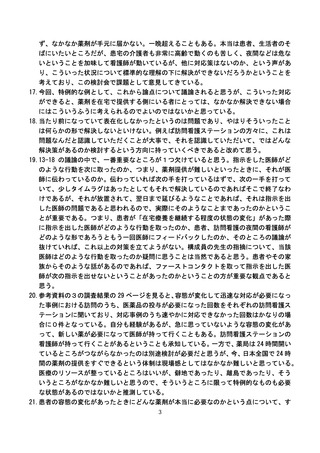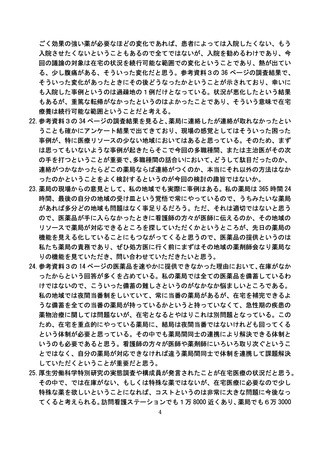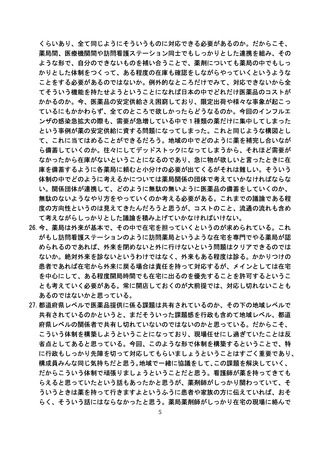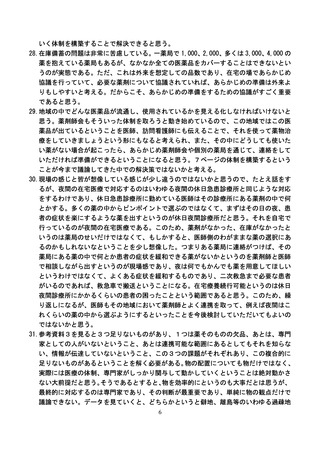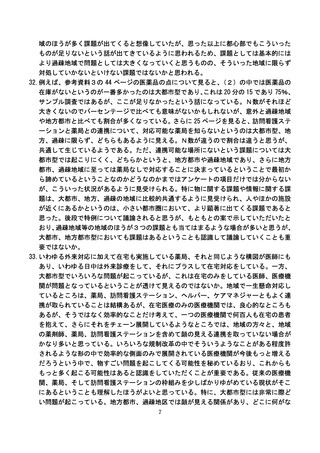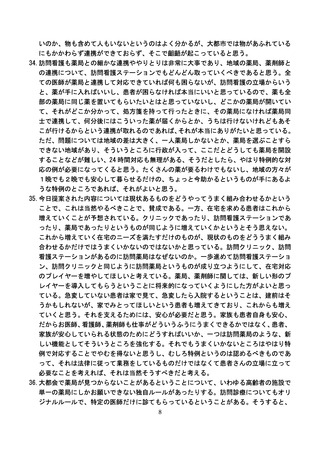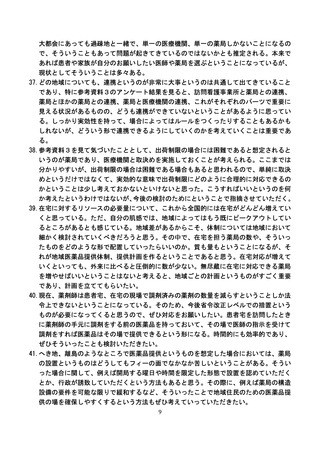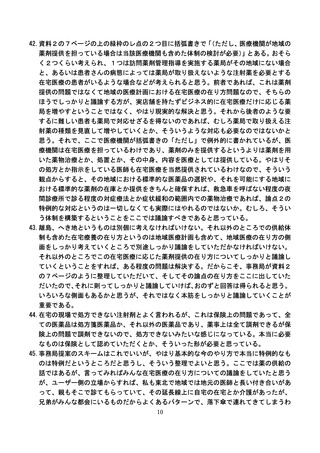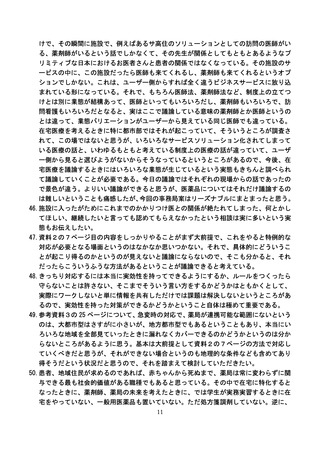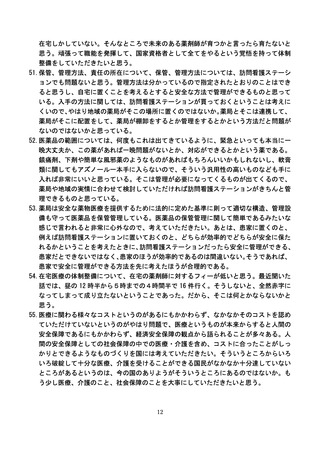よむ、つかう、まなぶ。
資料1_第12回検討会の主なご意見 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
42.資料2の7ページの上の緑枠のレ点の2つ目に括弧書きで「(ただし、医療機関が地域の
薬剤提供を担っている場合は当該医療機関も含めた体制の検討が必要)」とある。おそら
く2つくらい考えられ、1つは訪問薬剤管理指導を実施する薬局がその地域にない場合
と、あるいは患者さんの病態によっては薬局が取り扱えないような注射薬を必要とする
在宅医療の患者がいるような場合などが考えられると思う。前者であれば、これは薬剤
提供の問題ではなくて地域の医療計画における在宅医療の在り方問題なので、そちらの
ほうでしっかりと議論する方が、実店舗を持たずビジネス的に在宅医療だけに応じる薬
局を増やすということではなく、やはり現実的な解決と思う。それから後者のような要
するに難しい患者も薬局で対応せざるを得ないのであれば、むしろ薬局で取り扱える注
射薬の種類を見直して増やしていくとか、そういうような対応も必要なのではないかと
思う。それで、ここで医療機関が括弧書きの「ただし」で例外的に書かれているが、医
療機関は在宅医療を担っているわけであり、薬剤のみを提供するというよりは薬剤を用
いた薬物治療とか、処置とか、その中身、内容を医療としては提供している。やはりそ
の処方とか指示をしている医師も在宅医療を当然提供されているわけなので、そういう
観点からすると、その地域における標準的な医薬品の選択や、それを可能にする地域に
おける標準的な薬剤の在庫とか提供をきちんと確保すれば、救急車を呼ばない程度の夜
間診療所で診る程度の対症療法とか症状緩和の範囲内での薬物治療であれば、論点2の
特例的な対応というのは一切しなくても実際にはやれるのではないか。むしろ、そうい
う体制を構築するということをここでは議論すべきであると思っている。
43.離島、へき地というものは別個に考えなければいけない。それ以外のところでの供給体
制も含めた在宅療養の在り方というのは地域医療計画も含めて、地域医療の在り方の側
面をしっかり考えていくところで別途しっかり議論をしていただかなければいけない。
それ以外のところでこの在宅医療に応じた薬剤提供の在り方についてしっかりと議論し
ていくということをすれば、ある程度の問題は解決する。だからこそ、事務局が資料2
の7ページのように整理していただいて、そしてその論点の在り方をここに出していた
だいたので、それに則ってしっかりと議論していけば、おのずと回答は得られると思う。
いろいろな側面もあるかと思うが、それではなく本筋をしっかりと議論していくことが
重要である。
44.在宅の現場で処方できない注射剤とよく言われるが、これは保険上の問題であって、全
ての医薬品は処方箋医薬品か、それ以外の医薬品であり、薬事上は全て調剤できるが保
険上の問題で調剤できないので、処方できないみたいな感じになっている。本当に必要
なものは保険として認めていただくとか、そういった形が必要と思っている。
45.事務局提案のスキームはこれでいいが、やはり基本的な今のやり方で本当に特例的なも
のは特例だというところだと思うし、そういう整理でよいと思う。ここでは薬の供給の
話ではあるが、言ってみればみんな在宅医療の在り方についての議論をしていたと思う
が、ユーザー側の立場からすれば、私も東北で地域では地元の医師と長い付き合いがあ
って、親もそこで診てもらっていて、その延長線上に自宅の在宅とか介護があったが、
兄弟がみんな都会にいるものだからよくあるパターンで、落下傘で連れてきてしまうわ
10
薬剤提供を担っている場合は当該医療機関も含めた体制の検討が必要)」とある。おそら
く2つくらい考えられ、1つは訪問薬剤管理指導を実施する薬局がその地域にない場合
と、あるいは患者さんの病態によっては薬局が取り扱えないような注射薬を必要とする
在宅医療の患者がいるような場合などが考えられると思う。前者であれば、これは薬剤
提供の問題ではなくて地域の医療計画における在宅医療の在り方問題なので、そちらの
ほうでしっかりと議論する方が、実店舗を持たずビジネス的に在宅医療だけに応じる薬
局を増やすということではなく、やはり現実的な解決と思う。それから後者のような要
するに難しい患者も薬局で対応せざるを得ないのであれば、むしろ薬局で取り扱える注
射薬の種類を見直して増やしていくとか、そういうような対応も必要なのではないかと
思う。それで、ここで医療機関が括弧書きの「ただし」で例外的に書かれているが、医
療機関は在宅医療を担っているわけであり、薬剤のみを提供するというよりは薬剤を用
いた薬物治療とか、処置とか、その中身、内容を医療としては提供している。やはりそ
の処方とか指示をしている医師も在宅医療を当然提供されているわけなので、そういう
観点からすると、その地域における標準的な医薬品の選択や、それを可能にする地域に
おける標準的な薬剤の在庫とか提供をきちんと確保すれば、救急車を呼ばない程度の夜
間診療所で診る程度の対症療法とか症状緩和の範囲内での薬物治療であれば、論点2の
特例的な対応というのは一切しなくても実際にはやれるのではないか。むしろ、そうい
う体制を構築するということをここでは議論すべきであると思っている。
43.離島、へき地というものは別個に考えなければいけない。それ以外のところでの供給体
制も含めた在宅療養の在り方というのは地域医療計画も含めて、地域医療の在り方の側
面をしっかり考えていくところで別途しっかり議論をしていただかなければいけない。
それ以外のところでこの在宅医療に応じた薬剤提供の在り方についてしっかりと議論し
ていくということをすれば、ある程度の問題は解決する。だからこそ、事務局が資料2
の7ページのように整理していただいて、そしてその論点の在り方をここに出していた
だいたので、それに則ってしっかりと議論していけば、おのずと回答は得られると思う。
いろいろな側面もあるかと思うが、それではなく本筋をしっかりと議論していくことが
重要である。
44.在宅の現場で処方できない注射剤とよく言われるが、これは保険上の問題であって、全
ての医薬品は処方箋医薬品か、それ以外の医薬品であり、薬事上は全て調剤できるが保
険上の問題で調剤できないので、処方できないみたいな感じになっている。本当に必要
なものは保険として認めていただくとか、そういった形が必要と思っている。
45.事務局提案のスキームはこれでいいが、やはり基本的な今のやり方で本当に特例的なも
のは特例だというところだと思うし、そういう整理でよいと思う。ここでは薬の供給の
話ではあるが、言ってみればみんな在宅医療の在り方についての議論をしていたと思う
が、ユーザー側の立場からすれば、私も東北で地域では地元の医師と長い付き合いがあ
って、親もそこで診てもらっていて、その延長線上に自宅の在宅とか介護があったが、
兄弟がみんな都会にいるものだからよくあるパターンで、落下傘で連れてきてしまうわ
10