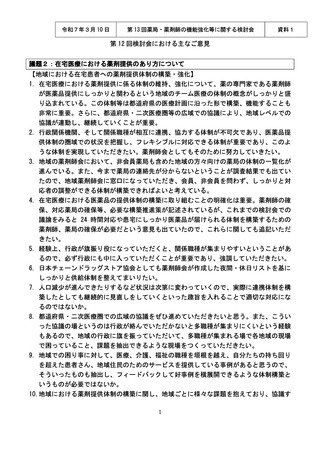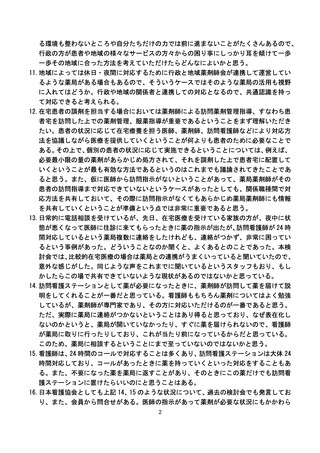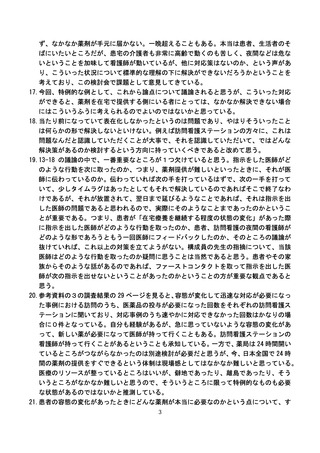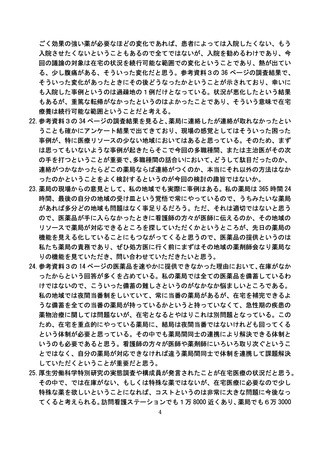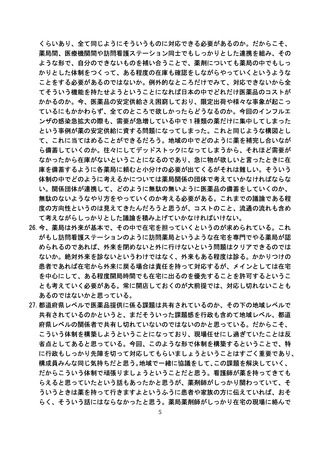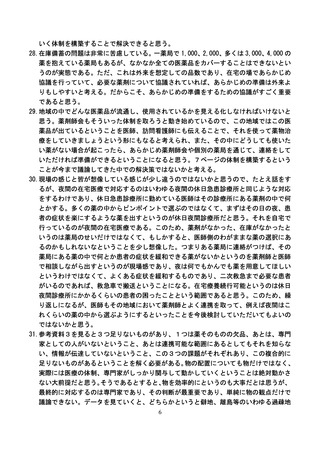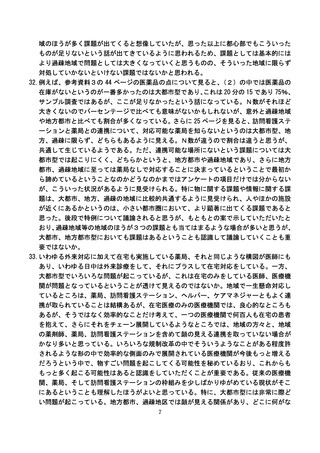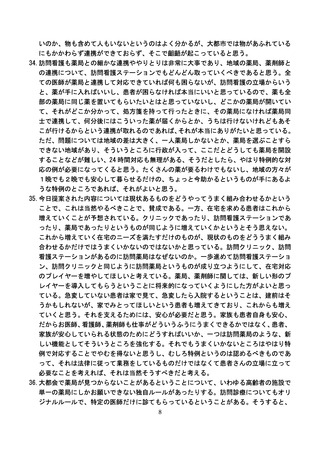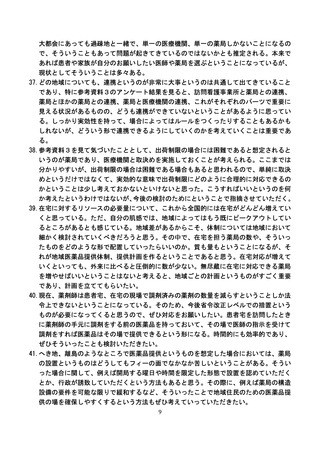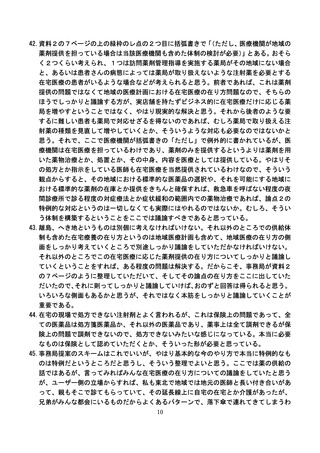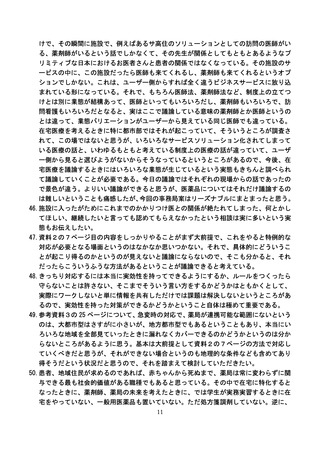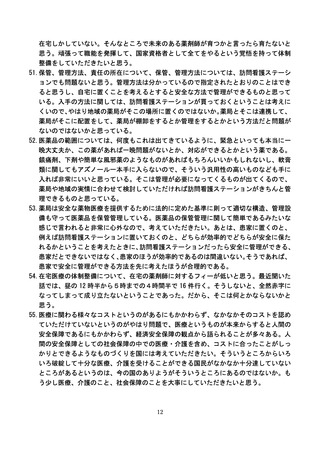よむ、つかう、まなぶ。
資料1_第12回検討会の主なご意見 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ず、なかなか薬剤が手元に届かない。一晩超えることもある。本当は患者、生活者のそ
ばにいたいところだが、患宅の介護者も非常に高齢で動くのも苦しく、夜間などは危な
いということを加味して看護師が動いているが、他に対応策はないのか、という声があ
り、こういった状況について標準的な理解の下に解決ができないだろうかということを
考えており、この検討会で課題として意見してきている。
17.今回、特例的な例として、これから論点について議論されると思うが、こういった対応
ができると、薬剤を在宅で提供する側にいる者にとっては、なかなか解決できない場合
にはこういうふうに考えられるのでよいのではないかと思っている。
18.当たり前になっていて表在化しなかったというのは問題であり、やはりそういったこと
は何らかの形で解決しないといけない。例えば訪問看護ステーションの方々に、これは
問題なんだと認識していただくことが大事で、それを認識していただいて、ではどんな
解決策があるのか検討するという方向に持っていくべきであると改めて思う。
19.13-18 の議論の中で、一番重要なところが1つ欠けていると思う。指示をした医師がど
のような行動を次に取ったのか、つまり、薬剤提供が難しいといったときに、それが医
師に伝わっているのか。伝わっていれば次の手を打っているはずで、次の一手を打って
いて、少しタイムラグはあったとしてもそれで解決しているのであればそこで終了なわ
けであるが、それが放置されて、翌日まで延びるようなことであれば、それは指示を出
した医師の問題であると思われるので、実際にそのようなことまであったのかというこ
とが重要である。つまり、患者が「在宅療養を継続する程度の状態の変化」があった際
に指示を出した医師がどのような行動を取ったのか、患者、訪問看護の夜間の看護師が
どのような形であろうともう一回医師にフィードバックしたのか、そのところの議論が
抜けていれば、これ以上の対策を立てようがない。構成員の先生の指摘について、当該
医師はどのような行動を取ったのか疑問に思うことは当然であると思う。患者やその家
族からそのような話があるのであれば、ファーストコンタクトを取って指示を出した医
師が次の指示を出せないということがあったのかということの方が重要な観点であると
思う。
20.参考資料の3の調査結果の 29 ページを見ると、容態が変化して迅速な対応が必要になっ
た事例における訪問のうち、医薬品の投与が必要になった回数をそれぞれの訪問看護ス
テーションに聞いており、対応事例のうち速やかに対応できなかった回数はかなりの場
合に0件となっている。自分も経験があるが、急に思っていないような容態の変化があ
って、新しい薬が必要になって医師が持って行くこともある。訪問看護ステーションの
看護師が持って行くことがあるということも承知している。一方で、薬局は 24 時間開い
ているところがつながらなかったのは別途検討が必要だと思うが、今、日本全国で 24 時
間の薬剤の提供をすぐできるという体制は現場感としてはなかなか難しいと思っている。
医療のリソースが整っているところはいいが、僻地であったり、離島であったり、そう
いうところがなかなか難しいと思うので、そういうところに限って特例的なものも必要
な状態があるのではないかと推測している。
21.患者の容態の変化があったときにどんな薬剤が本当に必要なのかという点について、す
3
ばにいたいところだが、患宅の介護者も非常に高齢で動くのも苦しく、夜間などは危な
いということを加味して看護師が動いているが、他に対応策はないのか、という声があ
り、こういった状況について標準的な理解の下に解決ができないだろうかということを
考えており、この検討会で課題として意見してきている。
17.今回、特例的な例として、これから論点について議論されると思うが、こういった対応
ができると、薬剤を在宅で提供する側にいる者にとっては、なかなか解決できない場合
にはこういうふうに考えられるのでよいのではないかと思っている。
18.当たり前になっていて表在化しなかったというのは問題であり、やはりそういったこと
は何らかの形で解決しないといけない。例えば訪問看護ステーションの方々に、これは
問題なんだと認識していただくことが大事で、それを認識していただいて、ではどんな
解決策があるのか検討するという方向に持っていくべきであると改めて思う。
19.13-18 の議論の中で、一番重要なところが1つ欠けていると思う。指示をした医師がど
のような行動を次に取ったのか、つまり、薬剤提供が難しいといったときに、それが医
師に伝わっているのか。伝わっていれば次の手を打っているはずで、次の一手を打って
いて、少しタイムラグはあったとしてもそれで解決しているのであればそこで終了なわ
けであるが、それが放置されて、翌日まで延びるようなことであれば、それは指示を出
した医師の問題であると思われるので、実際にそのようなことまであったのかというこ
とが重要である。つまり、患者が「在宅療養を継続する程度の状態の変化」があった際
に指示を出した医師がどのような行動を取ったのか、患者、訪問看護の夜間の看護師が
どのような形であろうともう一回医師にフィードバックしたのか、そのところの議論が
抜けていれば、これ以上の対策を立てようがない。構成員の先生の指摘について、当該
医師はどのような行動を取ったのか疑問に思うことは当然であると思う。患者やその家
族からそのような話があるのであれば、ファーストコンタクトを取って指示を出した医
師が次の指示を出せないということがあったのかということの方が重要な観点であると
思う。
20.参考資料の3の調査結果の 29 ページを見ると、容態が変化して迅速な対応が必要になっ
た事例における訪問のうち、医薬品の投与が必要になった回数をそれぞれの訪問看護ス
テーションに聞いており、対応事例のうち速やかに対応できなかった回数はかなりの場
合に0件となっている。自分も経験があるが、急に思っていないような容態の変化があ
って、新しい薬が必要になって医師が持って行くこともある。訪問看護ステーションの
看護師が持って行くことがあるということも承知している。一方で、薬局は 24 時間開い
ているところがつながらなかったのは別途検討が必要だと思うが、今、日本全国で 24 時
間の薬剤の提供をすぐできるという体制は現場感としてはなかなか難しいと思っている。
医療のリソースが整っているところはいいが、僻地であったり、離島であったり、そう
いうところがなかなか難しいと思うので、そういうところに限って特例的なものも必要
な状態があるのではないかと推測している。
21.患者の容態の変化があったときにどんな薬剤が本当に必要なのかという点について、す
3