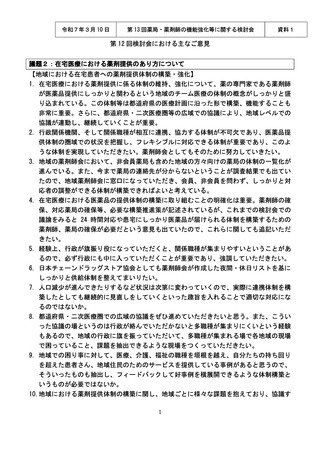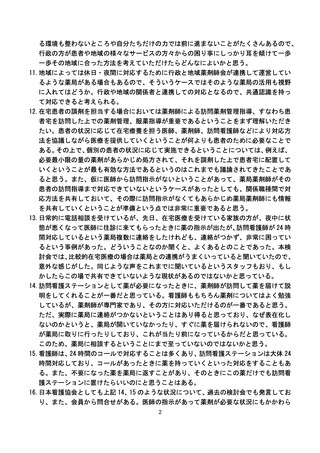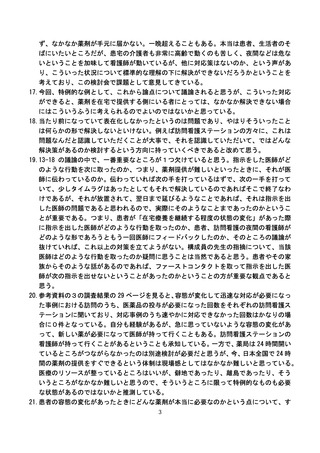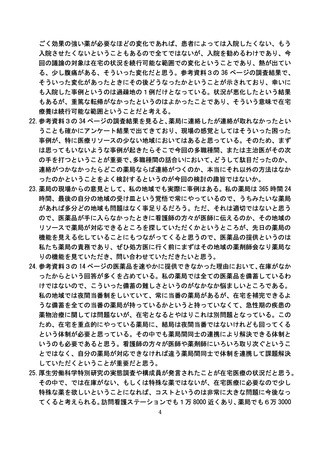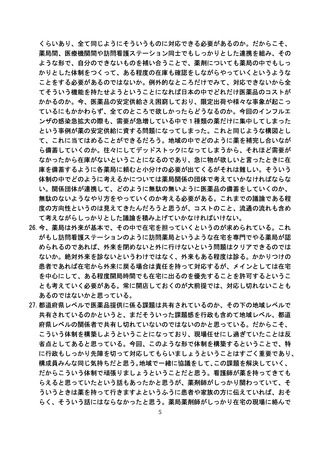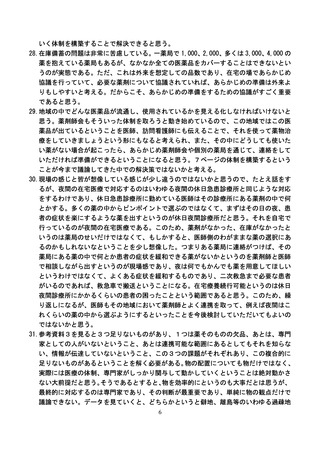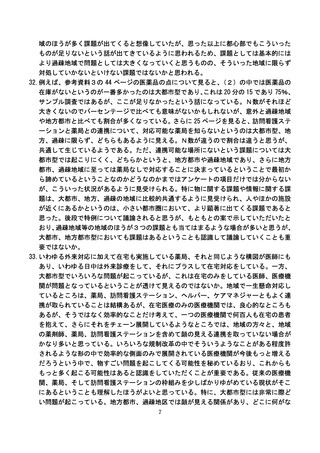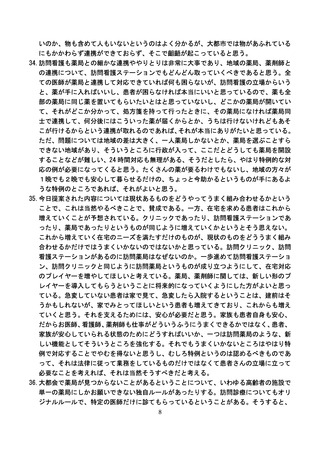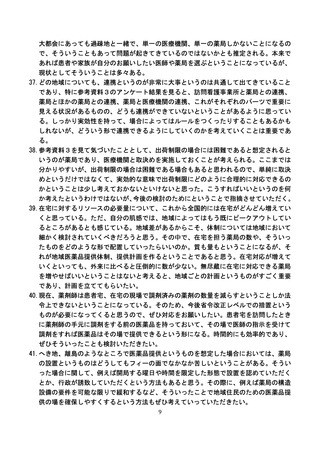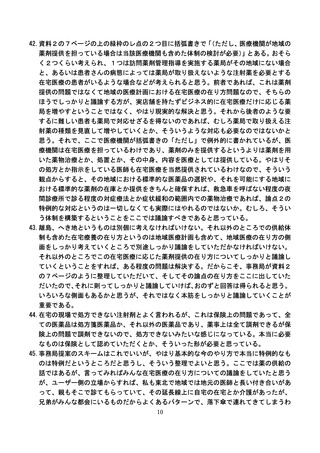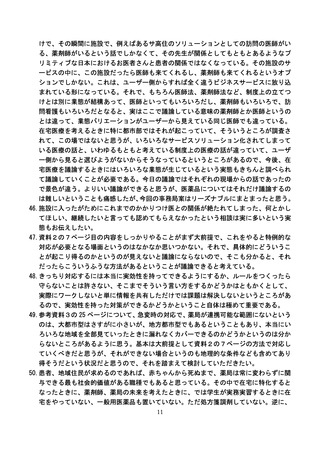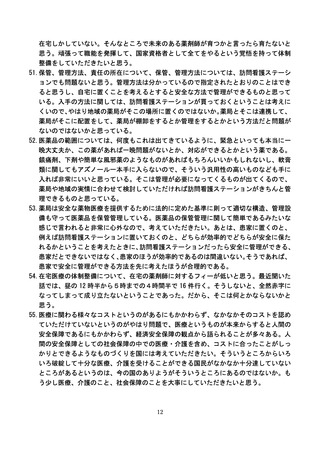よむ、つかう、まなぶ。
資料1_第12回検討会の主なご意見 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
域のほうが多く課題が出てくると想像していたが、思った以上に都心部でもこういった
ものが足りないという話が出てきているように思われるため、課題としては基本的には
より過疎地域で問題としては大きくなっていくと思うものの、そういった地域に限らず
対処していかないといけない課題ではないかと思われる。
32.例えば、参考資料3の 44 ページの医薬品の点について見ると、(2)の中では医薬品の
在庫がないというのが一番多かったのは大都市型であり、これは 20 分の 15 であり 75%、
サンプル調査ではあるが、ここが足りなかったという話になっている。N数がそれほど
大きくないのでパーセンテージで比べても意味がないかもしれないが、意外と過疎地域
や地方都市と比べても割合が多くなっている。さらに 25 ページを見ると、訪問看護ステ
ーションと薬局との連携について、対応可能な薬局を知らないというのは大都市型、地
方、過疎に限らず、どちらもあるように見える。N数が違うので割合は違うと思うが、
共通して生じているようである。ただ、連携可能な場所にないという課題については大
都市型では起こりにくく、どちらかというと、地方都市や過疎地域であり、さらに地方
都市、過疎地域に至っては薬局なしで対応することに決まっているということで最初か
ら諦めているということなのかどうなのかまではアンケートの項目だけでは分からない
が、こういった状況があるように見受けられる。特に物に関する課題や情報に関する課
題は、大都市、地方、過疎の地域に比較的共通するように見受けられ、人やほかの施設
が近くにあるかというのは、小さい都市圏において、より顕著に出てくる課題であると
思った。後段で特例について議論されると思うが、もともとの案で示していただいたと
おり、過疎地域等の地域のほうが3つの課題とも当てはまるような場合が多いと思うが、
大都市、地方都市型においても課題はあるということも認識して議論していくことも重
要ではないか。
33.いわゆる外来対応に加えて在宅も実施している薬局、それと同じような構図が医師にも
あり、いわゆる日中は外来診療をして、それにプラスして在宅対応をしている。一方、
大都市型でいろいろな問題が起こっているが、これは在宅のみをしている医師、医療機
関が問題となっているということが透けて見えるのではないか。地域で一生懸命対応し
ているところは、薬局、訪問看護ステーション、ヘルパー、ケアマネジャーともよく連
携が取られていることは結構あるが、在宅医療のみの医療機関では、良心的なところも
あるが、そうではなく効率的なことだけ考えて、一つの医療機関で何百人も在宅の患者
を抱えて、さらにそれをチェーン展開しているようなところでは、地域の方々と、地域
の薬剤師、薬局、訪問看護ステーションを含めて顔の見える連携を取っていない場合が
かなり多いと思っている。いろいろな規制改革の中でそういうようなことがある程度許
されるような形の中で効率的な側面のみで展開されている医療機関が今後もっと増える
だろうという中で、物すごい問題を起こしてくる可能性を秘めているおり、これからも
もっと多く起こる可能性はあると認識をしていただくことが重要である。従来の医療機
関、薬局、そして訪問看護ステーションの枠組みを少しばかりゆがめている現状がそこ
にあるということも理解したほうがよいと思っている。特に、大都市型には非常に際ど
い問題が起こっている。地方都市、過疎地区では顔が見える関係があり、どこに何がな
7
ものが足りないという話が出てきているように思われるため、課題としては基本的には
より過疎地域で問題としては大きくなっていくと思うものの、そういった地域に限らず
対処していかないといけない課題ではないかと思われる。
32.例えば、参考資料3の 44 ページの医薬品の点について見ると、(2)の中では医薬品の
在庫がないというのが一番多かったのは大都市型であり、これは 20 分の 15 であり 75%、
サンプル調査ではあるが、ここが足りなかったという話になっている。N数がそれほど
大きくないのでパーセンテージで比べても意味がないかもしれないが、意外と過疎地域
や地方都市と比べても割合が多くなっている。さらに 25 ページを見ると、訪問看護ステ
ーションと薬局との連携について、対応可能な薬局を知らないというのは大都市型、地
方、過疎に限らず、どちらもあるように見える。N数が違うので割合は違うと思うが、
共通して生じているようである。ただ、連携可能な場所にないという課題については大
都市型では起こりにくく、どちらかというと、地方都市や過疎地域であり、さらに地方
都市、過疎地域に至っては薬局なしで対応することに決まっているということで最初か
ら諦めているということなのかどうなのかまではアンケートの項目だけでは分からない
が、こういった状況があるように見受けられる。特に物に関する課題や情報に関する課
題は、大都市、地方、過疎の地域に比較的共通するように見受けられ、人やほかの施設
が近くにあるかというのは、小さい都市圏において、より顕著に出てくる課題であると
思った。後段で特例について議論されると思うが、もともとの案で示していただいたと
おり、過疎地域等の地域のほうが3つの課題とも当てはまるような場合が多いと思うが、
大都市、地方都市型においても課題はあるということも認識して議論していくことも重
要ではないか。
33.いわゆる外来対応に加えて在宅も実施している薬局、それと同じような構図が医師にも
あり、いわゆる日中は外来診療をして、それにプラスして在宅対応をしている。一方、
大都市型でいろいろな問題が起こっているが、これは在宅のみをしている医師、医療機
関が問題となっているということが透けて見えるのではないか。地域で一生懸命対応し
ているところは、薬局、訪問看護ステーション、ヘルパー、ケアマネジャーともよく連
携が取られていることは結構あるが、在宅医療のみの医療機関では、良心的なところも
あるが、そうではなく効率的なことだけ考えて、一つの医療機関で何百人も在宅の患者
を抱えて、さらにそれをチェーン展開しているようなところでは、地域の方々と、地域
の薬剤師、薬局、訪問看護ステーションを含めて顔の見える連携を取っていない場合が
かなり多いと思っている。いろいろな規制改革の中でそういうようなことがある程度許
されるような形の中で効率的な側面のみで展開されている医療機関が今後もっと増える
だろうという中で、物すごい問題を起こしてくる可能性を秘めているおり、これからも
もっと多く起こる可能性はあると認識をしていただくことが重要である。従来の医療機
関、薬局、そして訪問看護ステーションの枠組みを少しばかりゆがめている現状がそこ
にあるということも理解したほうがよいと思っている。特に、大都市型には非常に際ど
い問題が起こっている。地方都市、過疎地区では顔が見える関係があり、どこに何がな
7