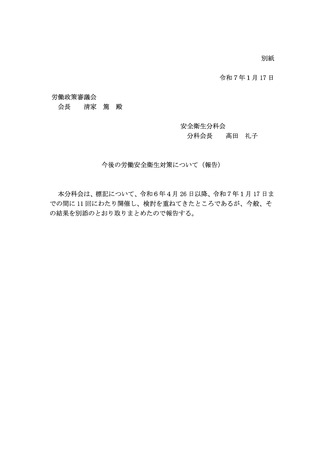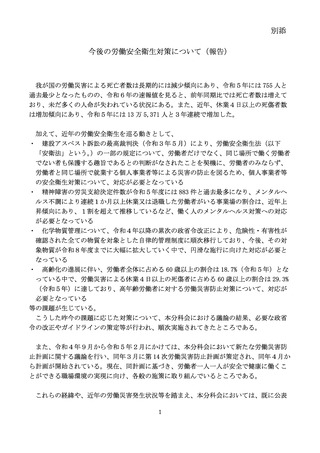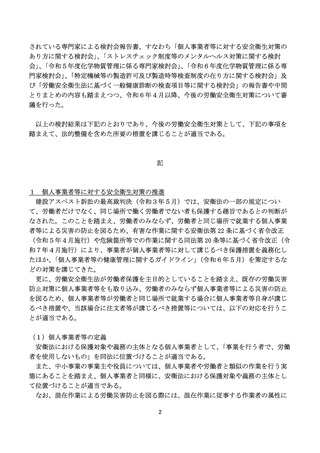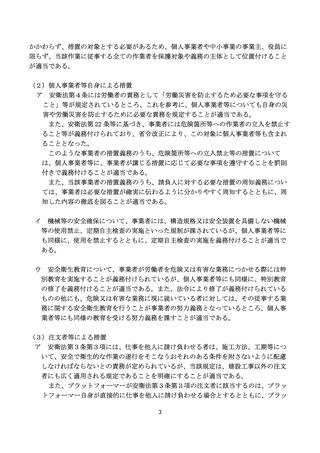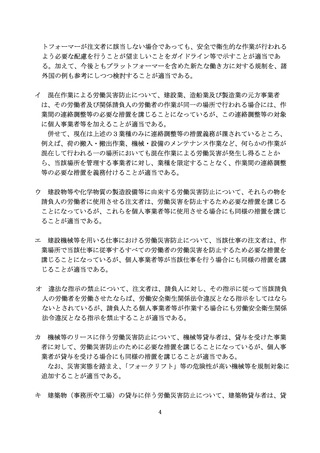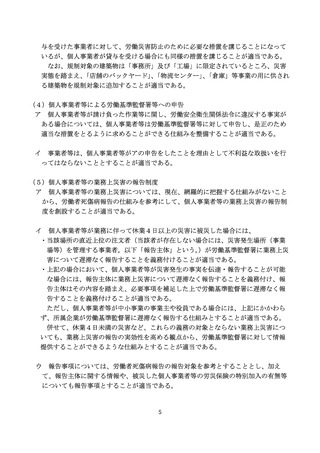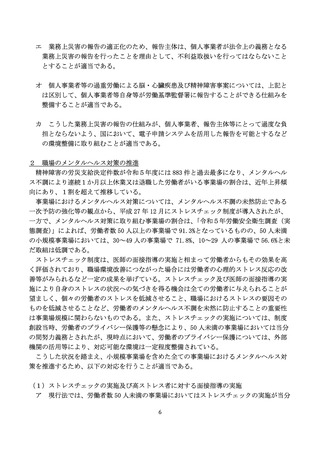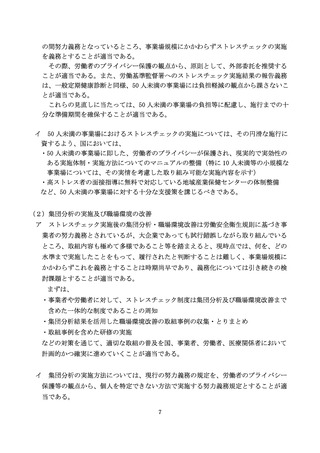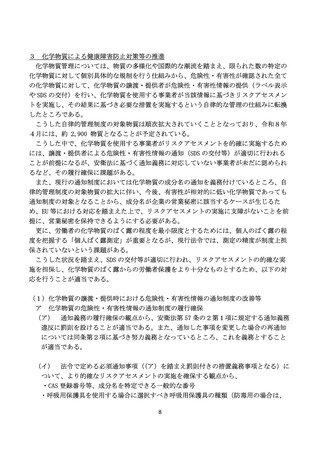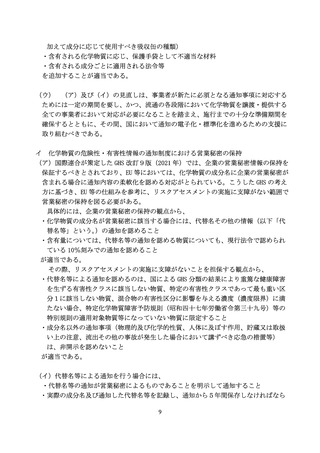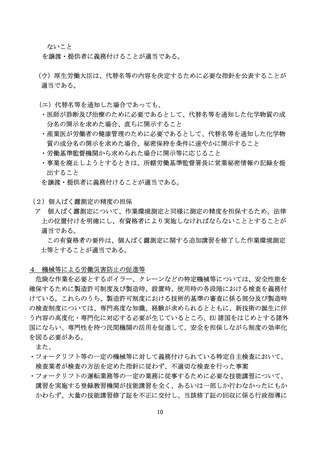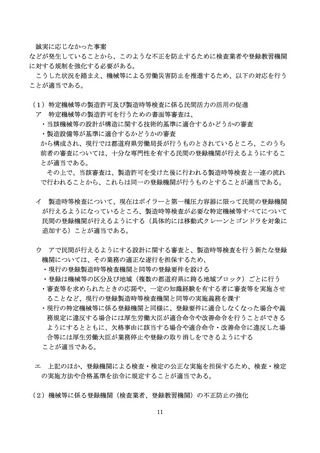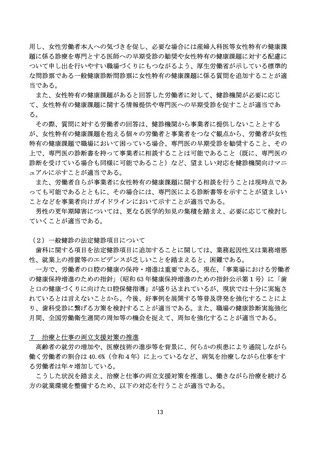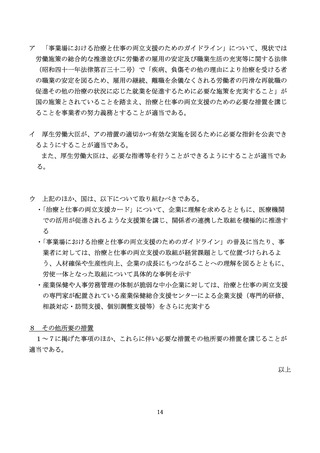よむ、つかう、まなぶ。
今後の労働安全衛生対策について(建議) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html |
| 出典情報 | 今後の労働安全衛生対策について(建議)(1/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
化学物質管理については、物質の多様化や国際的な潮流を踏まえ、限られた数の特定の
化学物質に対 して個別具体的な規制を行う仕組みから、危険性・有害性が確認された全て
の化学物質に対して、化学物質の譲渡・提供者が危険性・有害性情報の提供 (ラベル表示
や SDS の交付) を行い、化学物質を使用する事業者が当該情報に基づきリスクアセスメン
トを実施し、その結果に基づき必要な措置を実施するという自律的な管理の仕組みに転換
したところである。
こうした自律的管理制度の対象物質は順次拡大されていくこととなっており、令和8年
4月には、約 2,900 物質となることが予定されている。
こうした中で、化学物質を使用する事業者がリスクアセスメントを的確に実施するため
には、議渡・提供者による危険性・有害性情報の通知 (SDS の交付等) が適切に行われる
ことが前提になるが、安衛法に基づく通知義務に対応していない事業者が未だに認められ
るなど、その履行確保に課題がある。
また、現行の通知制度においては化学物質の成分名の通知を義務付けているところ、自
律的管理制度の対象物質の拡大に伴い、今後、有害性が相対的に低い化学物質であっても
通知制度の対象となることから、成分名が企業の営業秘密に該当するケースが生じるた
め、EBU 等における対応を路まえた上で、リスクアセスメントの実施に支隊がないことを前
提に、営業秘密を保持できるようにする必要がある。
更に、労働者の化学物質のばく赴の程度を最小限度とするためには、個人のばく外の程
度を把握する「個人ばく赴測定」が重要となるが、現行法令では、測定の精度が制度上担
保されていないという課題がある。
こうした状況を踏まえ、SDS の交付等が適切に行われ、リスクアセスメントの的確な実
施を担保し、化学物質のばく露からの労働者保護をより十分なものとするため、以下の対
応を行うことが適当である。
(1 ) 化学物質の譲渡・提供時における危険性・有害性情報の通知制度の改善等
ア 化学物質の危険性・有害性情報の通知制度の履行確保
(ア) 通知義務の履行確保の観点から、安衛法第 57 条の2第 1 項に規定する通知義務
違反に六則を設けることが適当である。また、通知 した事項を変更 した場合の再通知
については同条第 2 項に基づき努力義務となっているところ、これを義務とすること
が適当である。
(イ) 法令で定める必須通知事項 ((ア) を踏まえ罰則付きの措置義務事項となる) に
ついて、より的確なりリスクアセスメントの実施を確保する観点から、
・CAS 韻録番号等、成分名を特定できる一般的な番号
・呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類 (防毒用の場合は、
8
化学物質管理については、物質の多様化や国際的な潮流を踏まえ、限られた数の特定の
化学物質に対 して個別具体的な規制を行う仕組みから、危険性・有害性が確認された全て
の化学物質に対して、化学物質の譲渡・提供者が危険性・有害性情報の提供 (ラベル表示
や SDS の交付) を行い、化学物質を使用する事業者が当該情報に基づきリスクアセスメン
トを実施し、その結果に基づき必要な措置を実施するという自律的な管理の仕組みに転換
したところである。
こうした自律的管理制度の対象物質は順次拡大されていくこととなっており、令和8年
4月には、約 2,900 物質となることが予定されている。
こうした中で、化学物質を使用する事業者がリスクアセスメントを的確に実施するため
には、議渡・提供者による危険性・有害性情報の通知 (SDS の交付等) が適切に行われる
ことが前提になるが、安衛法に基づく通知義務に対応していない事業者が未だに認められ
るなど、その履行確保に課題がある。
また、現行の通知制度においては化学物質の成分名の通知を義務付けているところ、自
律的管理制度の対象物質の拡大に伴い、今後、有害性が相対的に低い化学物質であっても
通知制度の対象となることから、成分名が企業の営業秘密に該当するケースが生じるた
め、EBU 等における対応を路まえた上で、リスクアセスメントの実施に支隊がないことを前
提に、営業秘密を保持できるようにする必要がある。
更に、労働者の化学物質のばく赴の程度を最小限度とするためには、個人のばく外の程
度を把握する「個人ばく赴測定」が重要となるが、現行法令では、測定の精度が制度上担
保されていないという課題がある。
こうした状況を踏まえ、SDS の交付等が適切に行われ、リスクアセスメントの的確な実
施を担保し、化学物質のばく露からの労働者保護をより十分なものとするため、以下の対
応を行うことが適当である。
(1 ) 化学物質の譲渡・提供時における危険性・有害性情報の通知制度の改善等
ア 化学物質の危険性・有害性情報の通知制度の履行確保
(ア) 通知義務の履行確保の観点から、安衛法第 57 条の2第 1 項に規定する通知義務
違反に六則を設けることが適当である。また、通知 した事項を変更 した場合の再通知
については同条第 2 項に基づき努力義務となっているところ、これを義務とすること
が適当である。
(イ) 法令で定める必須通知事項 ((ア) を踏まえ罰則付きの措置義務事項となる) に
ついて、より的確なりリスクアセスメントの実施を確保する観点から、
・CAS 韻録番号等、成分名を特定できる一般的な番号
・呼吸用保護具を使用する場合に選択すべき呼吸用保護具の種類 (防毒用の場合は、
8