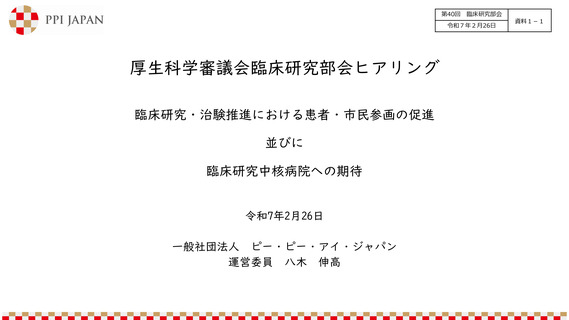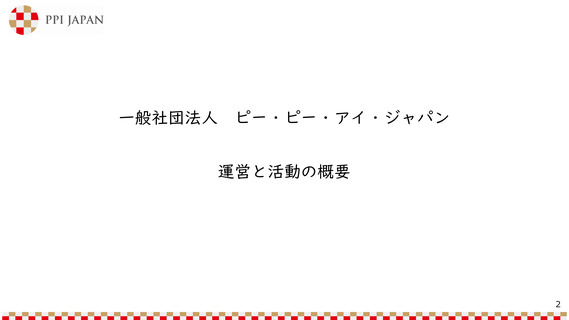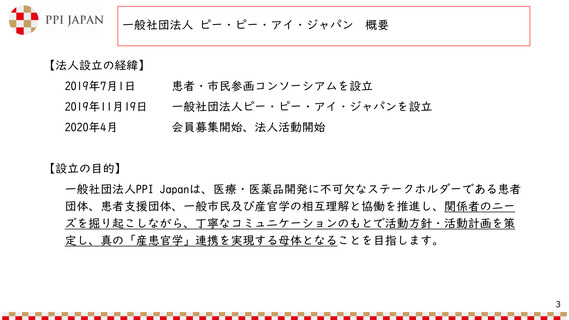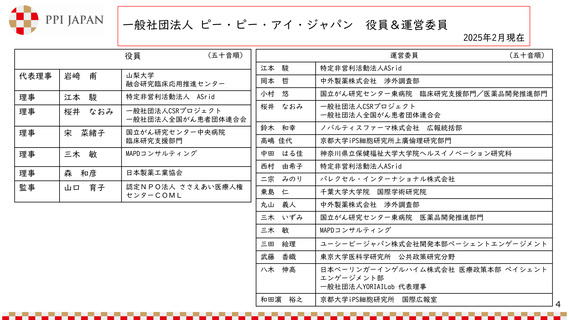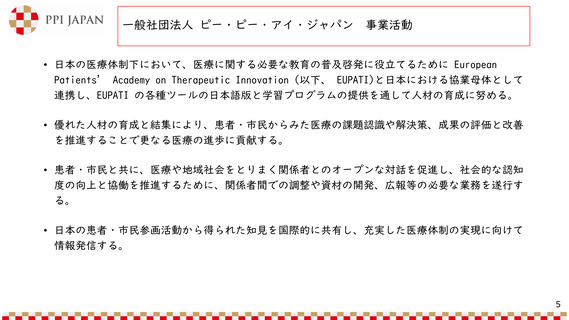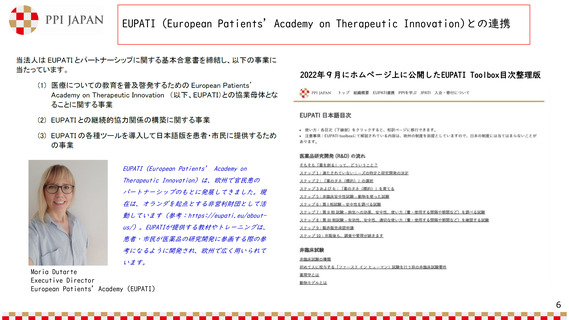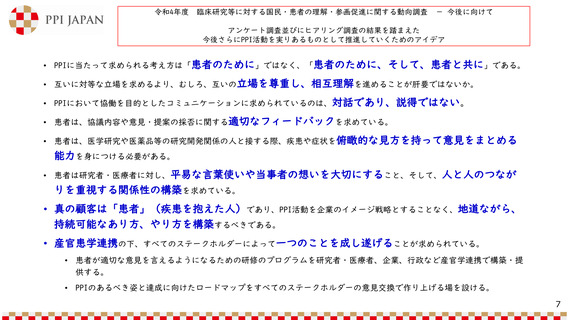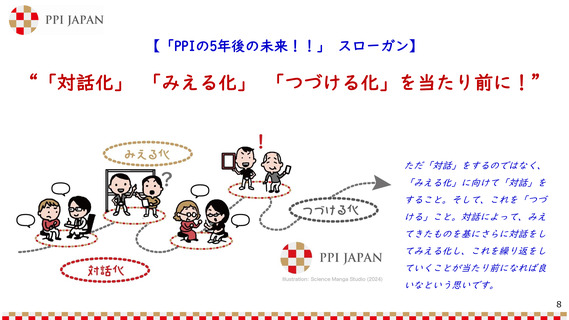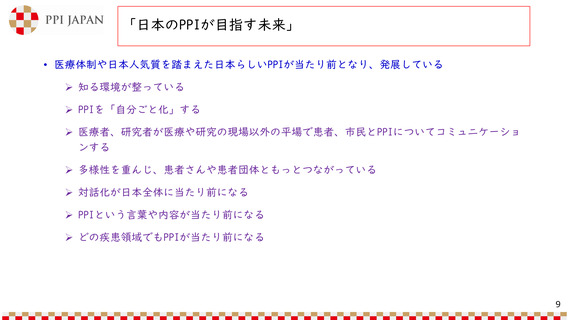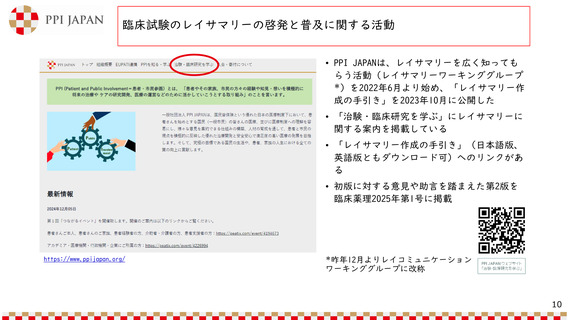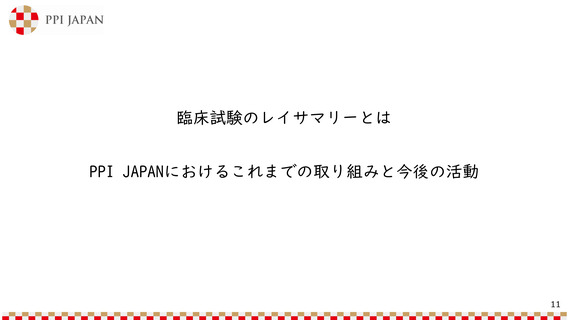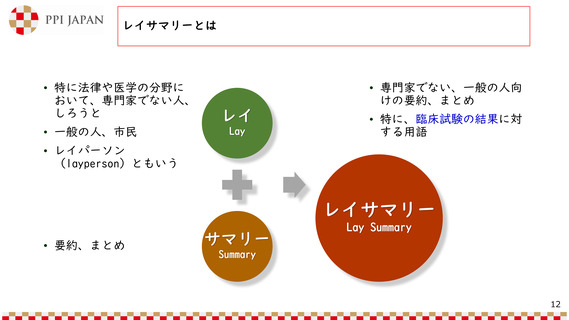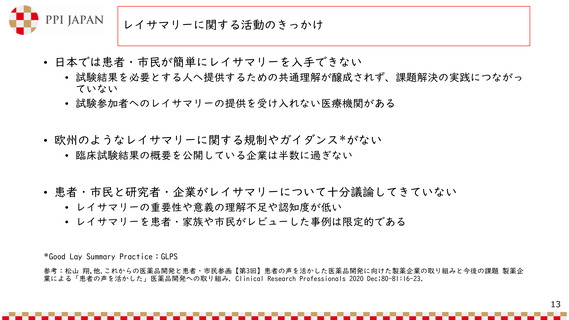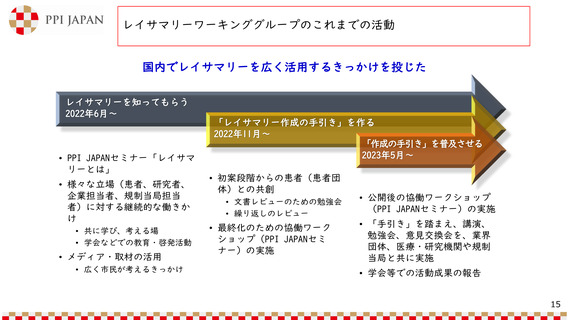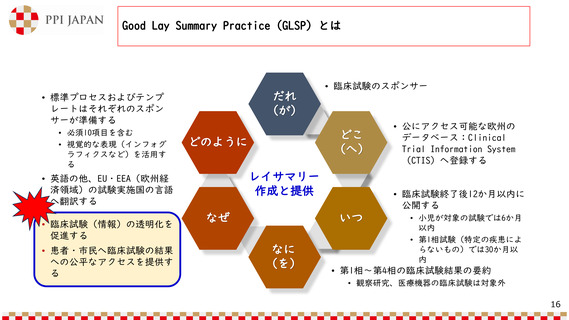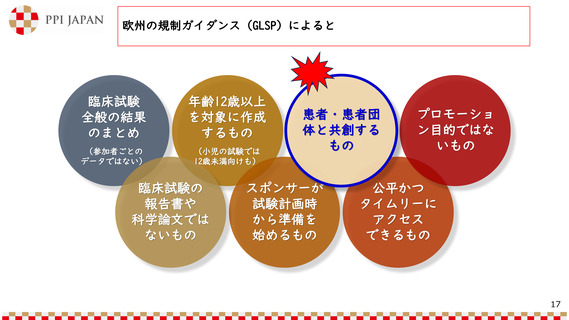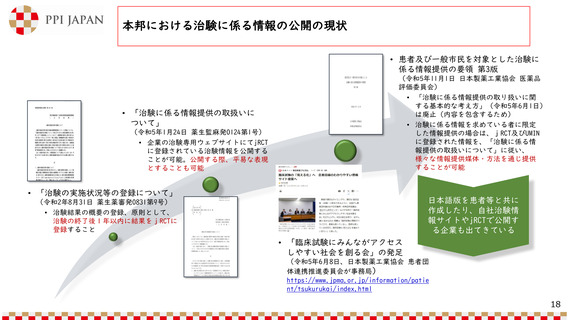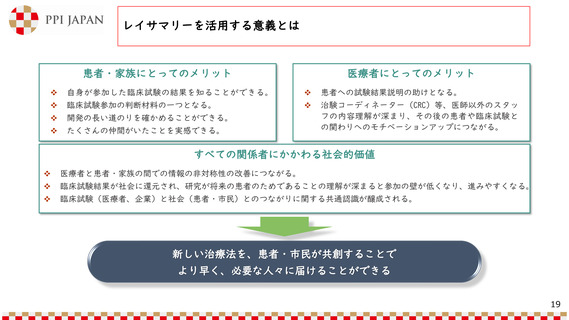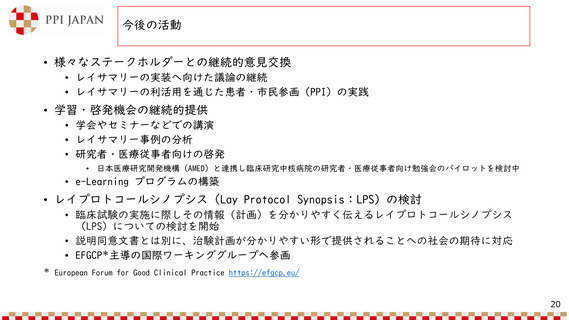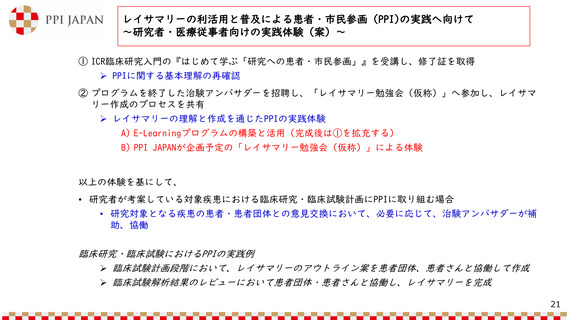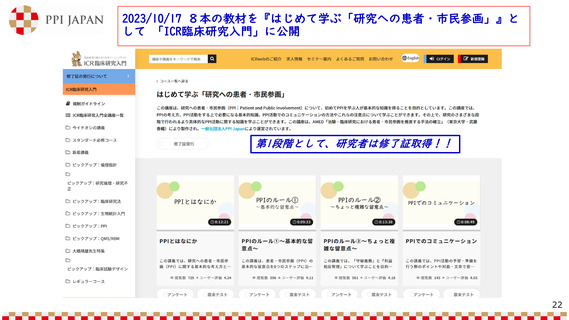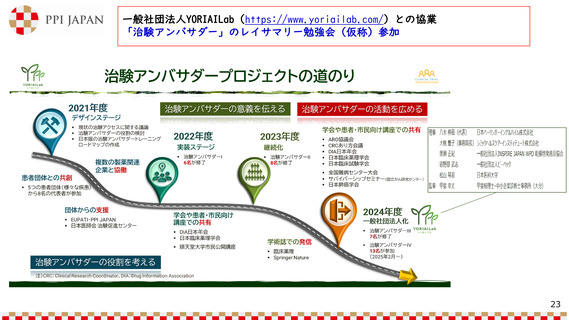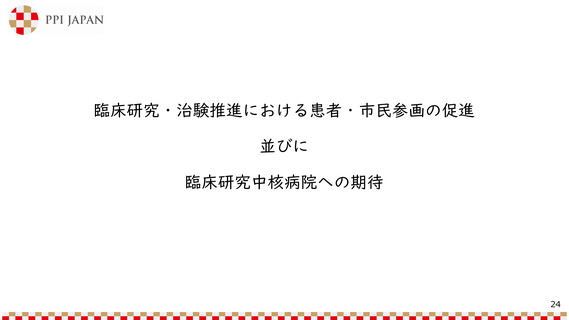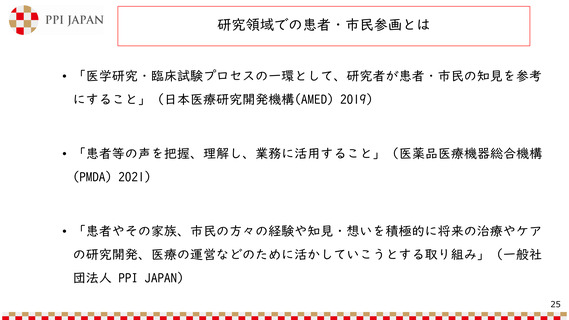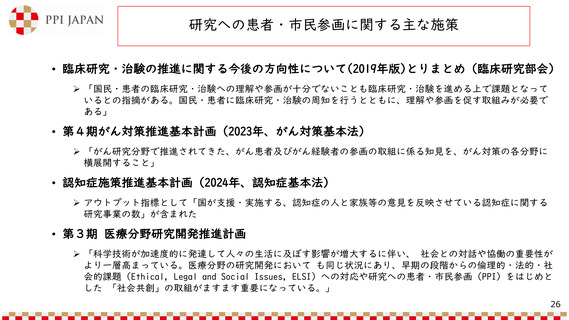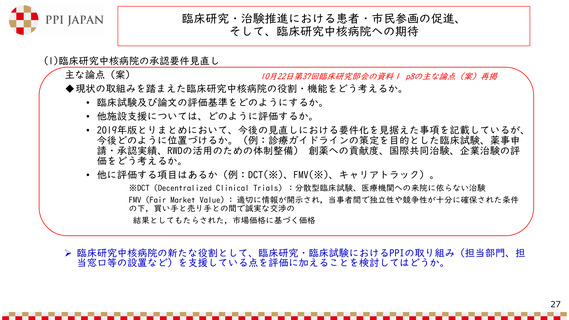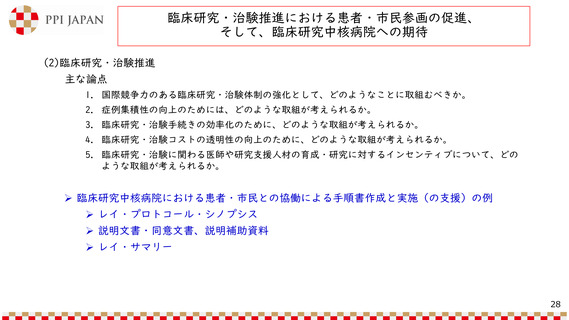よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1:一般社団法人ピー・ピー・アイ・ジャパン 八木参考人 提出資料 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52767.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第40回 2/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度
臨床研究等に対する国民・患者の理解・参画促進に関する動向調査
- 今後に向けて
アンケート調査並びにヒアリング調査の結果を踏まえた
今後さらにPPI活動を実りあるものとして推進していくためのアイデア
• PPIに当たって求められる考え方は「患者のために」ではなく、「患者のために、そして、患者と共に」である。
• 互いに対等な立場を求めるより、むしろ、互いの立場を尊重し、相互理解を進めることが肝要ではないか。
• PPIにおいて協働を目的としたコミュニケーションに求められているのは、対話であり、説得ではない。
• 患者は、協議内容や意見・提案の採否に関する適切なフィードバックを求めている。
• 患者は、医学研究や医薬品等の研究開発関係の人と接する際、疾患や症状を俯瞰的な見方を持って意見をまとめる
能力を⾝につける必要がある。
• 患者は研究者・医療者に対し、平易な⾔葉使いや当事者の想いを⼤切にすること、そして、人と人のつなが
りを重視する関係性の構築を求めている。
• 真の顧客は「患者」(疾患を抱えた人)であり、PPI活動を企業のイメージ戦略とすることなく、地道ながら、
持続可能なあり方、やり方を構築するべきである。
• 産官患学連携の下、すべてのステークホルダーによって一つのことを成し遂げることが求められている。
• 患者が適切な意見を言えるようになるための研修のプログラムを研究者・医療者、企業、行政など産官学連携で構築・提
供する。
• PPIのあるべき姿と達成に向けたロードマップをすべてのステークホルダーの意見交換で作り上げる場を設ける。
7
臨床研究等に対する国民・患者の理解・参画促進に関する動向調査
- 今後に向けて
アンケート調査並びにヒアリング調査の結果を踏まえた
今後さらにPPI活動を実りあるものとして推進していくためのアイデア
• PPIに当たって求められる考え方は「患者のために」ではなく、「患者のために、そして、患者と共に」である。
• 互いに対等な立場を求めるより、むしろ、互いの立場を尊重し、相互理解を進めることが肝要ではないか。
• PPIにおいて協働を目的としたコミュニケーションに求められているのは、対話であり、説得ではない。
• 患者は、協議内容や意見・提案の採否に関する適切なフィードバックを求めている。
• 患者は、医学研究や医薬品等の研究開発関係の人と接する際、疾患や症状を俯瞰的な見方を持って意見をまとめる
能力を⾝につける必要がある。
• 患者は研究者・医療者に対し、平易な⾔葉使いや当事者の想いを⼤切にすること、そして、人と人のつなが
りを重視する関係性の構築を求めている。
• 真の顧客は「患者」(疾患を抱えた人)であり、PPI活動を企業のイメージ戦略とすることなく、地道ながら、
持続可能なあり方、やり方を構築するべきである。
• 産官患学連携の下、すべてのステークホルダーによって一つのことを成し遂げることが求められている。
• 患者が適切な意見を言えるようになるための研修のプログラムを研究者・医療者、企業、行政など産官学連携で構築・提
供する。
• PPIのあるべき姿と達成に向けたロードマップをすべてのステークホルダーの意見交換で作り上げる場を設ける。
7