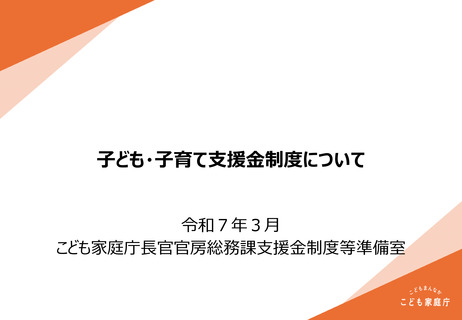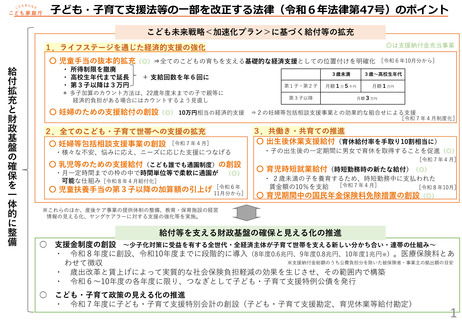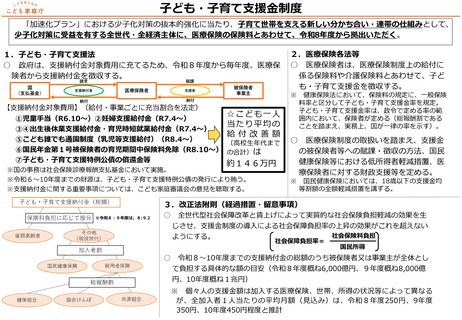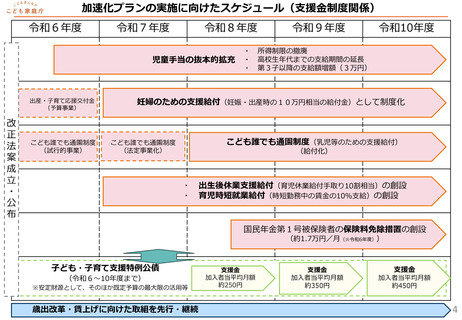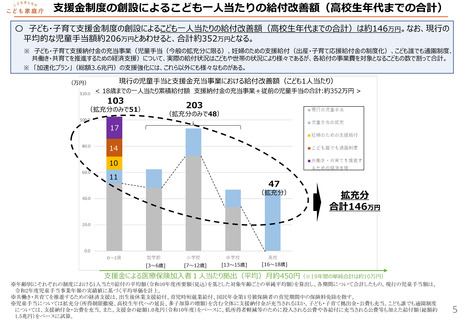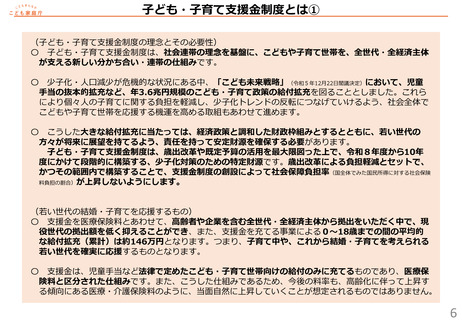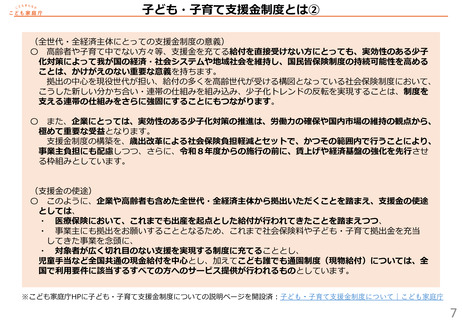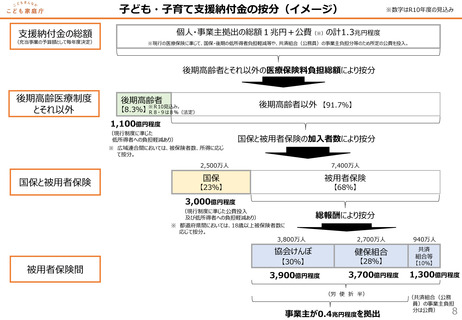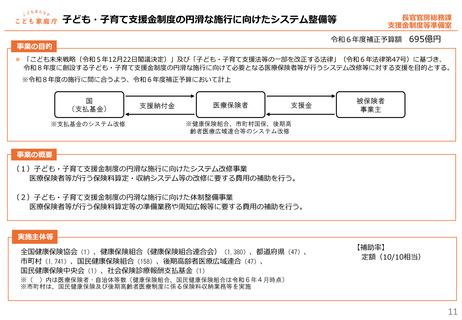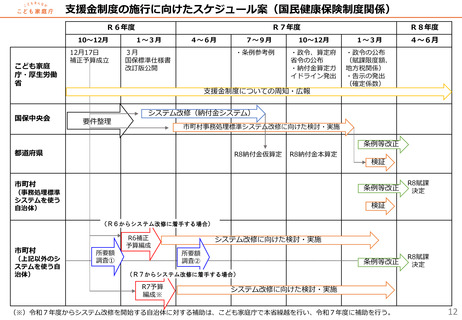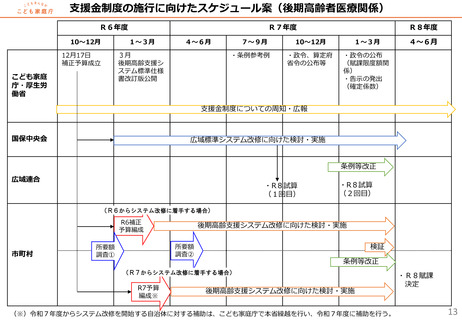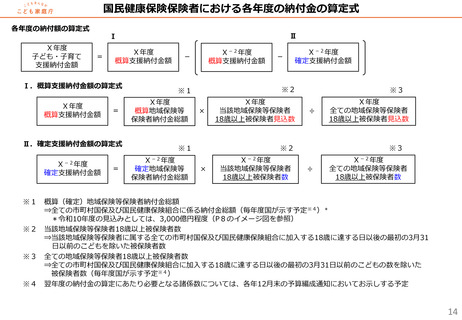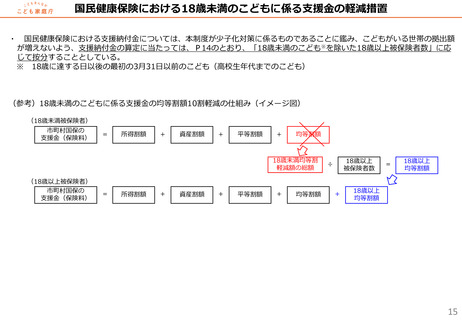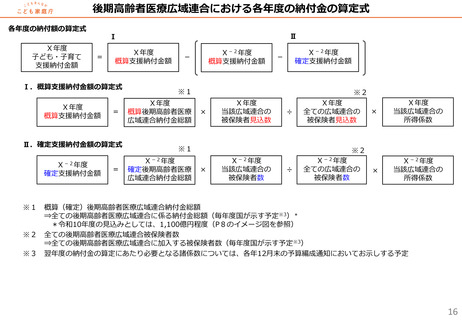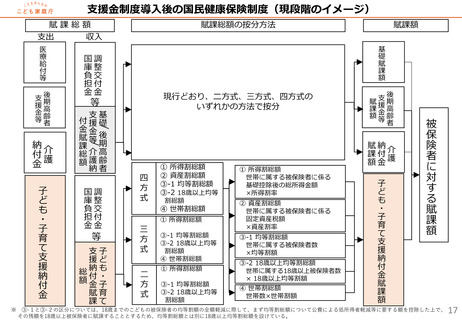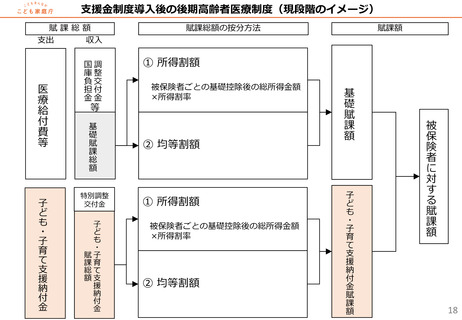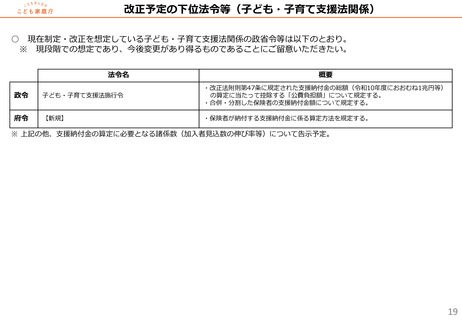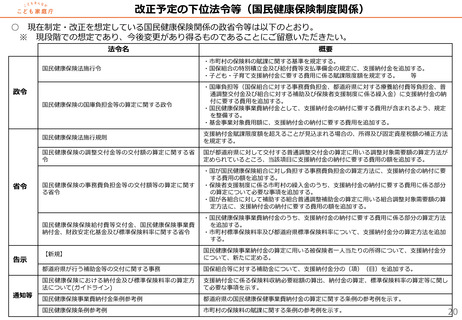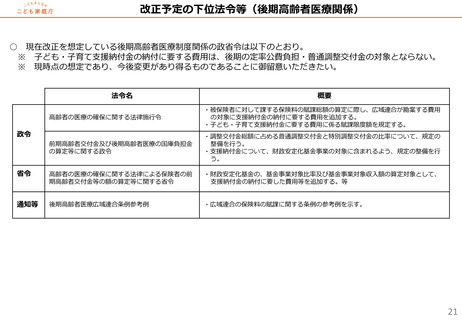よむ、つかう、まなぶ。
こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室説明資料[2.2MB] (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
| 出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
子ども・子育て支援金制度とは②
(全世代・全経済主体にとっての支援金制度の意義)
〇 高齢者や子育て中でない方々等、支援金を充てる給付を直接受けない方にとっても、実効性のある少子
化対策によって我が国の経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高める
ことは、かけがえのない重要な意義を持ちます。
拠出の中心を現役世代が担い、給付の多くを高齢世代が受ける構図となっている社会保険制度において、
こうした新しい分かち合い・連帯の仕組みを組み込み、少子化トレンドの反転を実現することは、制度を
支える連帯の仕組みをさらに強固にすることにもつながります。
〇
また、企業にとっては、実効性のある少子化対策の推進は、労働力の確保や国内市場の維持の観点から、
極めて重要な受益となります。
支援金制度の構築を、歳出改革による社会保険負担軽減とセットで、かつその範囲内で行うことにより、
事業主負担にも配慮しつつ、さらに、令和8年度からの施行の前に、賃上げや経済基盤の強化を先行させ
る枠組みとしています。
(支援金の使途)
〇 このように、企業や高齢者も含めた全世代・全経済主体から拠出いただくことを踏まえ、支援金の使途
としては、
・ 医療保険において、これまでも出産を起点とした給付が行われてきたことを踏まえつつ、
・ 事業主にも拠出をお願いすることとなるため、これまで社会保険料や子ども・子育て拠出金を充当
してきた事業を念頭に、
・ 対象者が広く切れ目のない支援を実現する制度に充てることとし、
児童手当など全国共通の現金給付を中心とし、加えてこども誰でも通園制度(現物給付)については、全
国で利用要件に該当するすべての方へのサービス提供が行われるものとしています。
※こども家庭庁HPに子ども・子育て支援金制度についての説明ページを開設済:子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁
7
(全世代・全経済主体にとっての支援金制度の意義)
〇 高齢者や子育て中でない方々等、支援金を充てる給付を直接受けない方にとっても、実効性のある少子
化対策によって我が国の経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高める
ことは、かけがえのない重要な意義を持ちます。
拠出の中心を現役世代が担い、給付の多くを高齢世代が受ける構図となっている社会保険制度において、
こうした新しい分かち合い・連帯の仕組みを組み込み、少子化トレンドの反転を実現することは、制度を
支える連帯の仕組みをさらに強固にすることにもつながります。
〇
また、企業にとっては、実効性のある少子化対策の推進は、労働力の確保や国内市場の維持の観点から、
極めて重要な受益となります。
支援金制度の構築を、歳出改革による社会保険負担軽減とセットで、かつその範囲内で行うことにより、
事業主負担にも配慮しつつ、さらに、令和8年度からの施行の前に、賃上げや経済基盤の強化を先行させ
る枠組みとしています。
(支援金の使途)
〇 このように、企業や高齢者も含めた全世代・全経済主体から拠出いただくことを踏まえ、支援金の使途
としては、
・ 医療保険において、これまでも出産を起点とした給付が行われてきたことを踏まえつつ、
・ 事業主にも拠出をお願いすることとなるため、これまで社会保険料や子ども・子育て拠出金を充当
してきた事業を念頭に、
・ 対象者が広く切れ目のない支援を実現する制度に充てることとし、
児童手当など全国共通の現金給付を中心とし、加えてこども誰でも通園制度(現物給付)については、全
国で利用要件に該当するすべての方へのサービス提供が行われるものとしています。
※こども家庭庁HPに子ども・子育て支援金制度についての説明ページを開設済:子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁
7