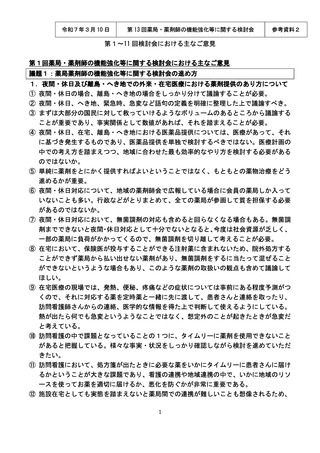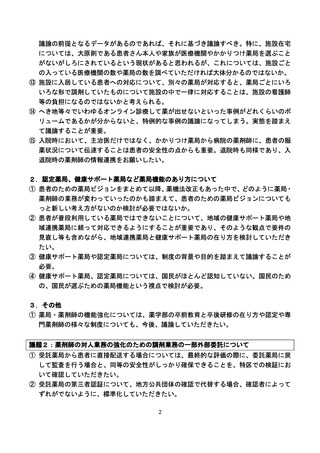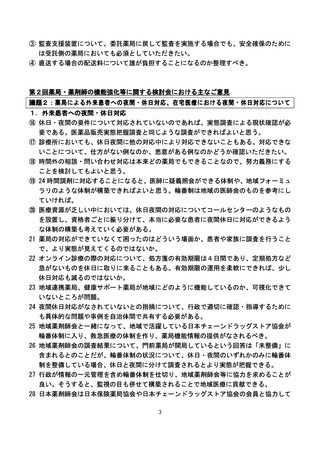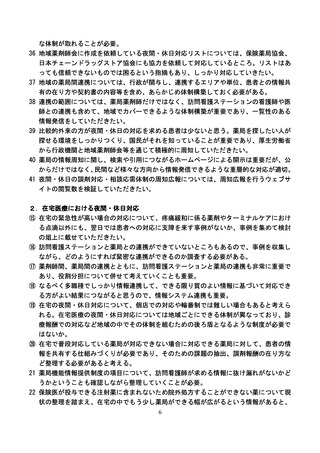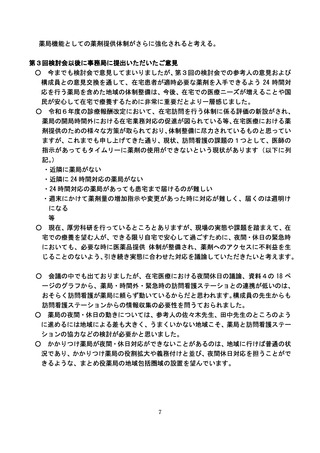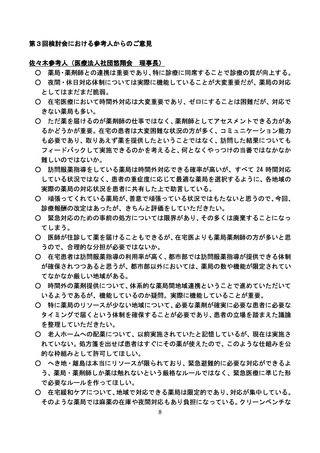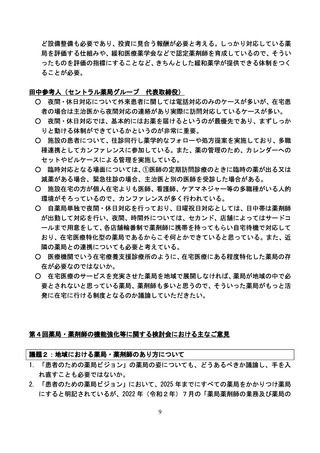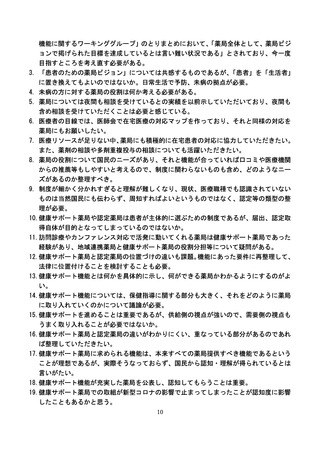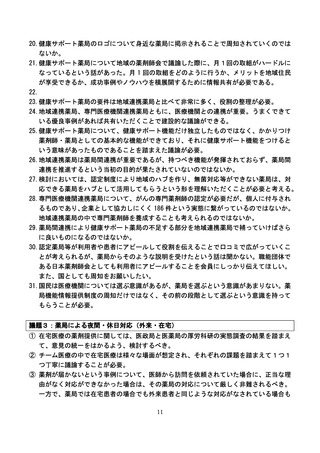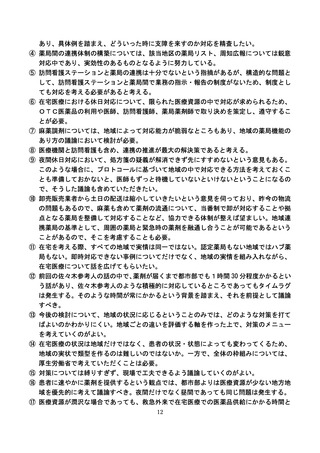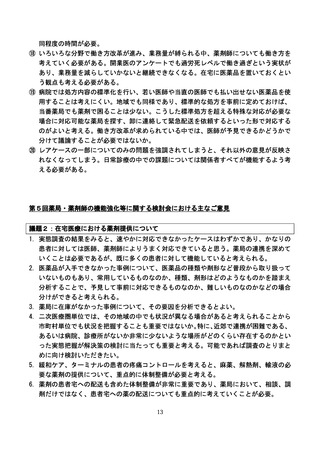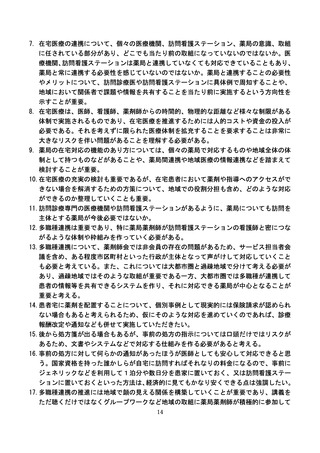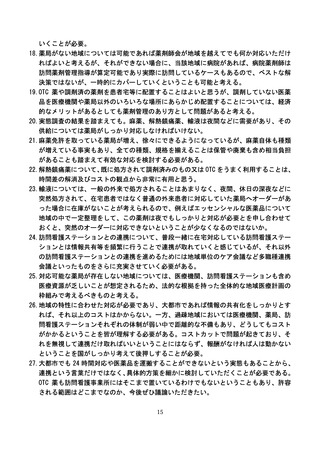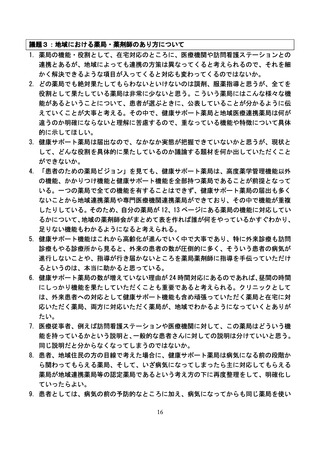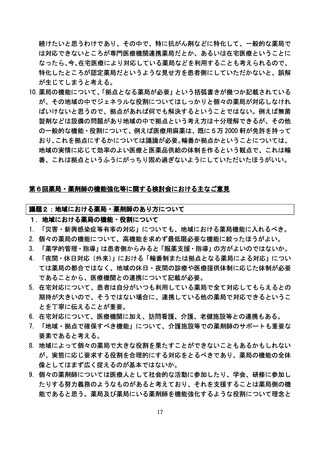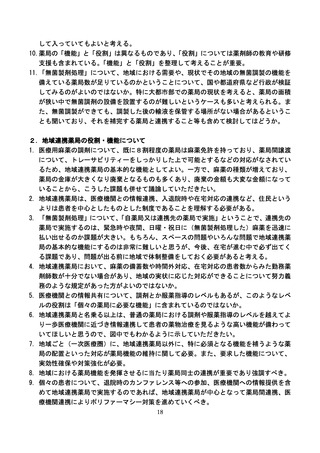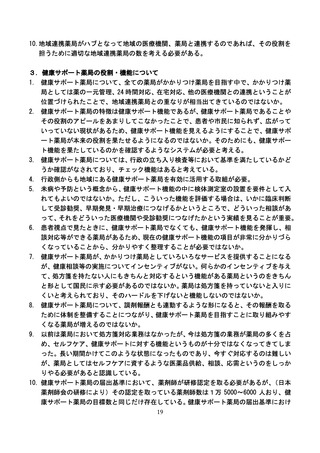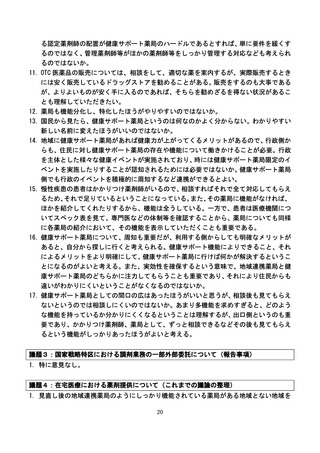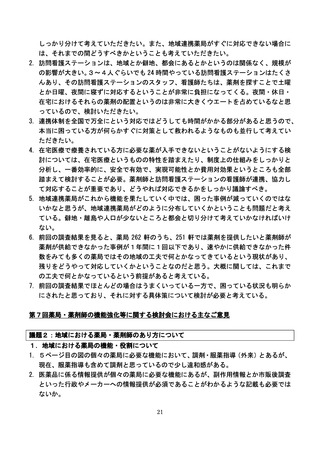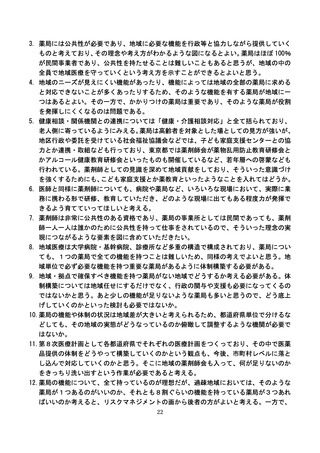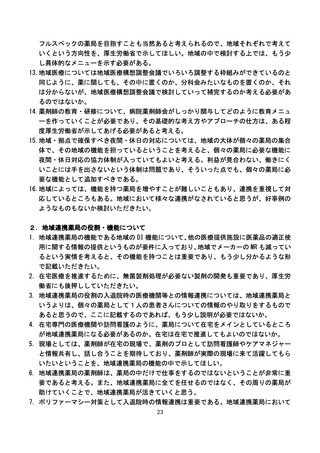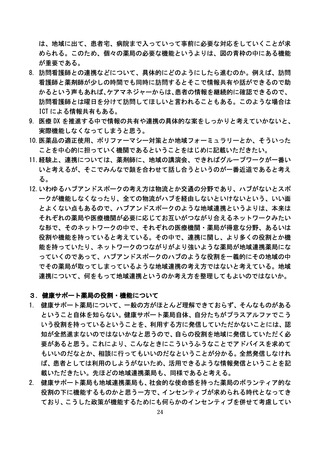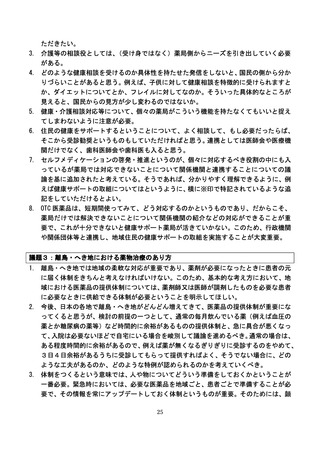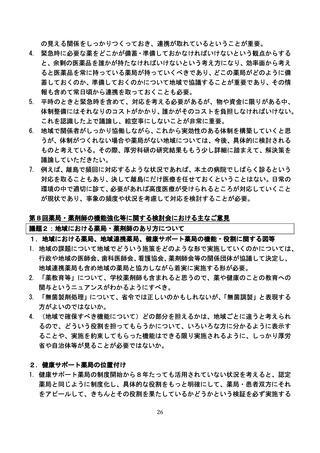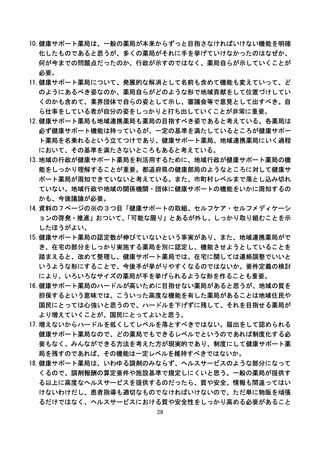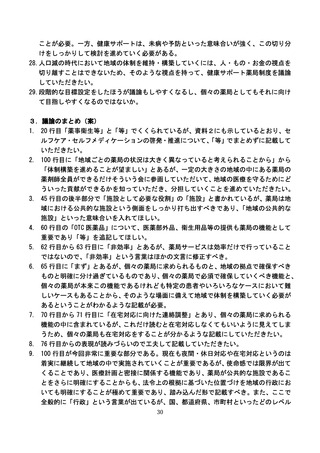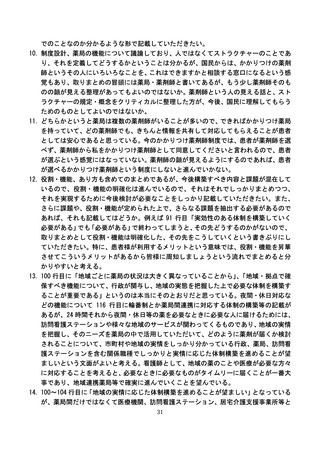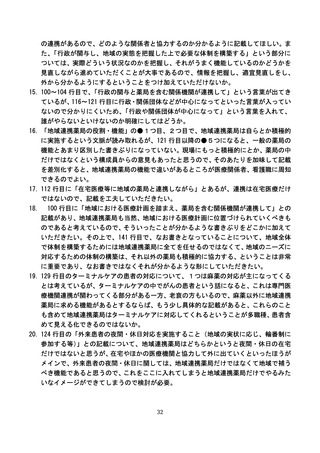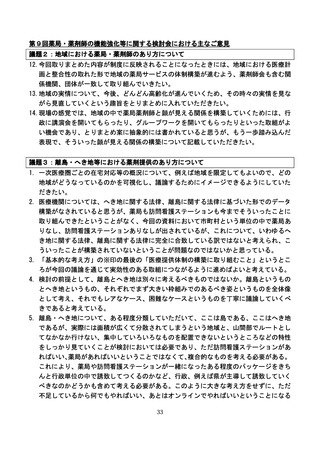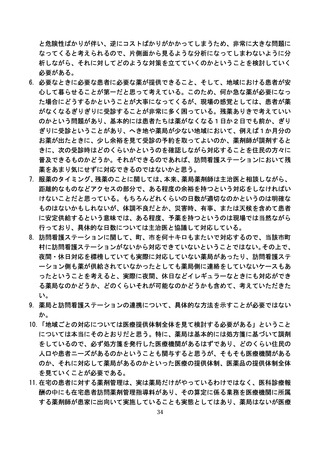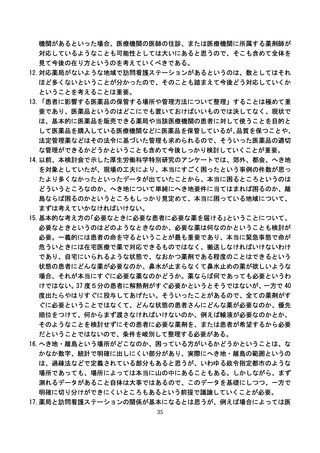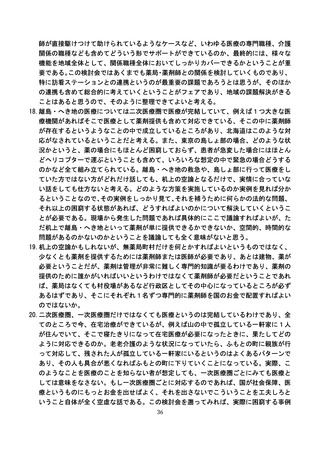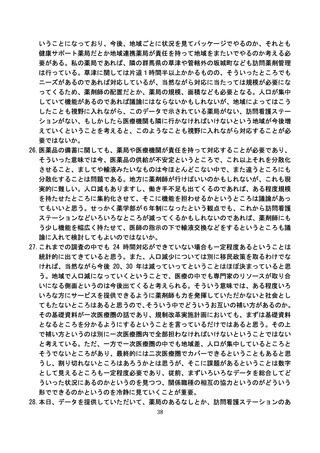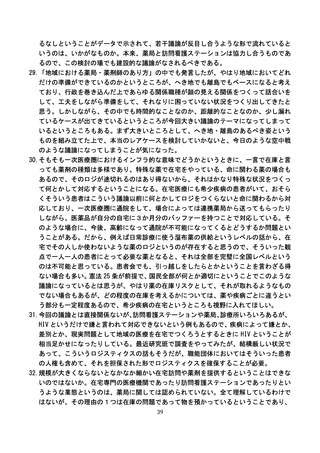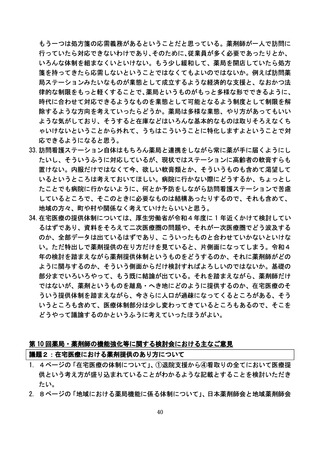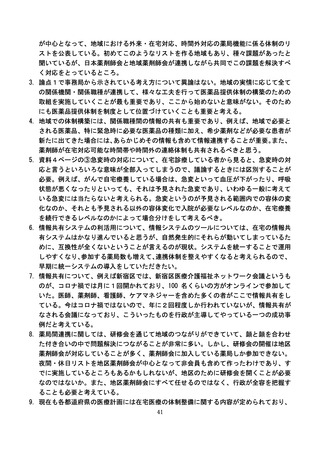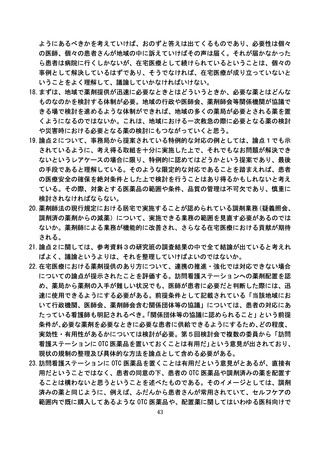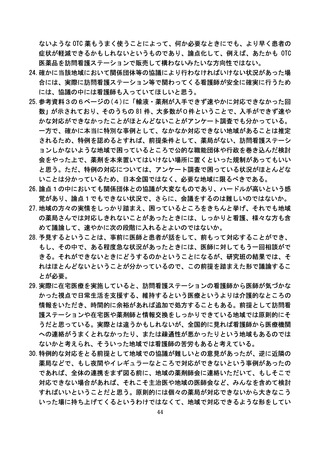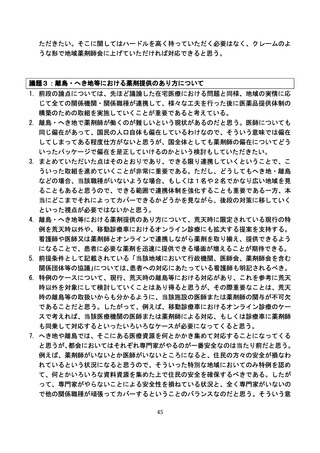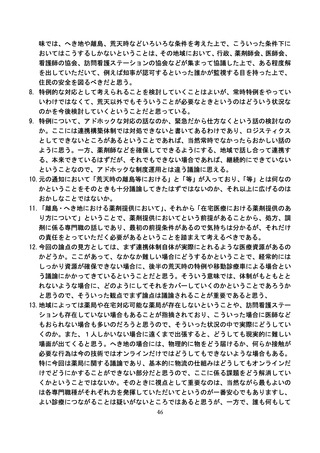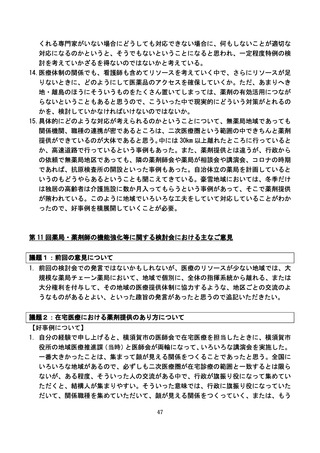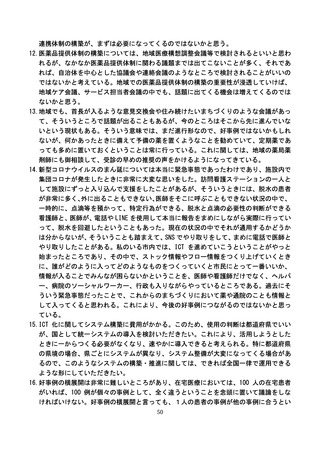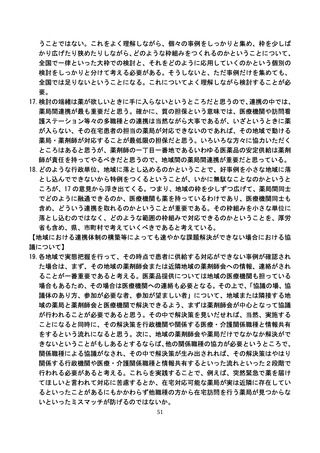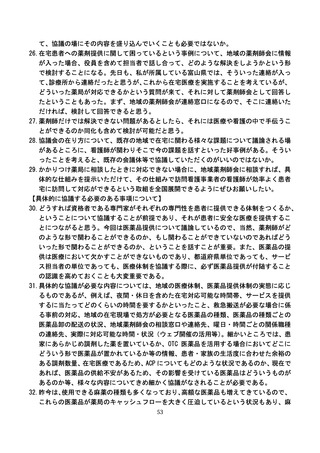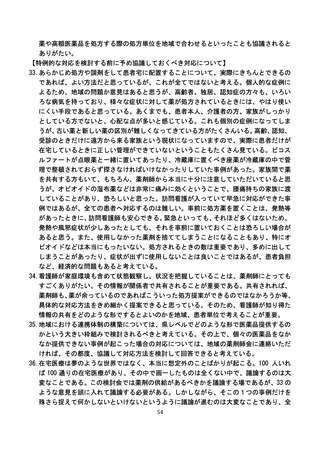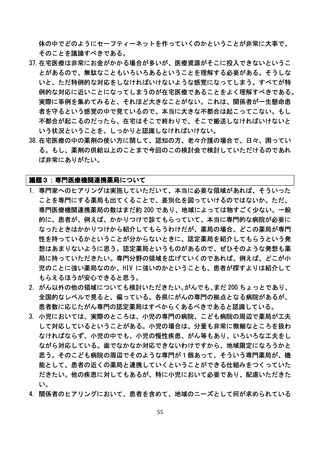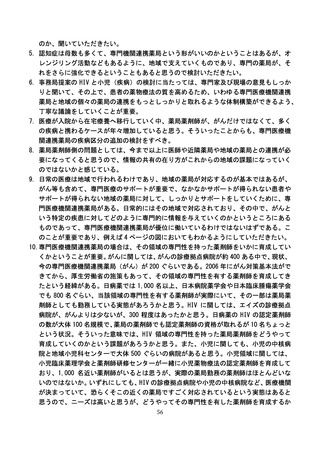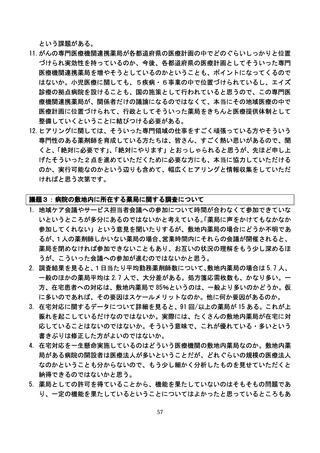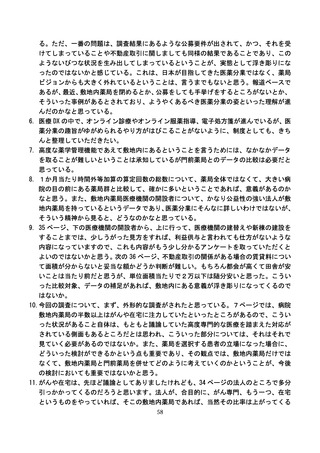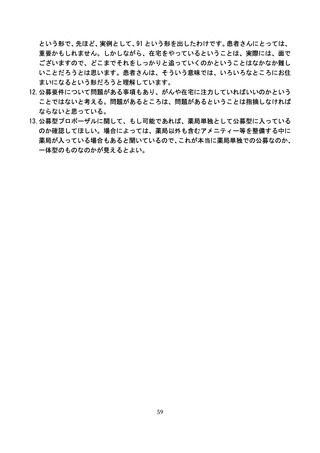よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_第1~11回検討会の主な意見 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
が中心となって、地域における外来・在宅対応、時間外対応の薬局機能に係る体制のリ
ストを公表している。初めてこのようなリストを作る地域もあり、種々課題があったと
聞いているが、日本薬剤師会と地域薬剤師会が連携しながら共同でこの課題を解決すべ
く対応をとっているところ。
3. 論点1で事務局から示されている考え方について異論はない。地域の実情に応じて全て
の関係機関・関係職種が連携して、様々な工夫を行って医薬品提供体制の構築のための
取組を実施していくことが最も重要であり、ここから始めないと意味がない。そのため
にも医薬品提供体制を制度として位置づけていくことも重要と考える。
4. 地域での体制構築には、関係職種間の情報の共有も重要であり、例えば、地域で必要と
される医薬品、特に緊急時に必要な医薬品の種類に加え、希少薬剤などが必要な患者が
新たに出てきた場合には、あらかじめその情報も含めて情報連携することが重要。また、
薬剤師が在宅対応可能な時間帯や時間外の連絡体制も共有されるべきと思う。
5. 資料4ページの③急変時の対応について、在宅診療している者から見ると、急変時の対
応と言うといろいろな意味が全部入ってしまうので、議論するときには区別することが
必要。例えば、がんで自宅療養している場合は、急変といって血圧が下がったり、呼吸
状態が悪くなったりといっても、それは予見された急変であり、いわゆる一般に考えて
いる急変には当たらないと考えられる。急変というのが予見される範囲内での容体の変
化なのか、それとも予見される以外の容体変化で入院が必要なレベルなのか、在宅療養
を続行できるレベルなのかによって場合分けをして考えるべき。
6. 情報共有システムの利活用について、情報システムのツールについては、在宅の情報共
有システムはかなり進んでいると思うが、自然発生的にそれらが動いてしまっているた
めに、互換性が全くないということが言えるのが現状。システムを統一することで運用
しやすくなり、参加する薬局数も増えて、連携体制を整えやすくなると考えられるので、
早期に統一システムの導入をしていただきたい。
7. 情報共有について、例えば新宿区では、新宿区医療介護福祉ネットワーク会議というも
のが、コロナ禍では月に1回開かれており、100 名くらいの方がオンラインで参加して
いた。医師、薬剤師、看護師、ケアマネジャーを含めた多くの者がここで情報共有をし
ている。今はコロナ禍ではないので、年に2回程度しか行われていないが、情報共有が
なされる会議になっており、こういったものを行政が主導してやっている一つの成功事
例だと考えている。
8. 薬局間連携に関しては、研修会を通じて地域のつながりができていて、顔と顔を合わせ
た付き合いの中で問題解決につながることが非常に多い。しかし、研修会の開催は地区
薬剤師会が対応していることが多く、薬剤師会に加入している薬局しか参加できない。
夜間・休日リストを地区薬剤師会が中心となって非会員も含めて作ったわけであり、す
でに実施しているところもあるかもしれないが、地区のために研修会を開くことが必要
なのではないか。また、地区薬剤師会にすべて任せるのではなく、行政が全容を把握す
ることも必要と考えている。
9. 現在も各都道府県の医療計画には在宅医療の体制整備に関する内容が定められており、
41
ストを公表している。初めてこのようなリストを作る地域もあり、種々課題があったと
聞いているが、日本薬剤師会と地域薬剤師会が連携しながら共同でこの課題を解決すべ
く対応をとっているところ。
3. 論点1で事務局から示されている考え方について異論はない。地域の実情に応じて全て
の関係機関・関係職種が連携して、様々な工夫を行って医薬品提供体制の構築のための
取組を実施していくことが最も重要であり、ここから始めないと意味がない。そのため
にも医薬品提供体制を制度として位置づけていくことも重要と考える。
4. 地域での体制構築には、関係職種間の情報の共有も重要であり、例えば、地域で必要と
される医薬品、特に緊急時に必要な医薬品の種類に加え、希少薬剤などが必要な患者が
新たに出てきた場合には、あらかじめその情報も含めて情報連携することが重要。また、
薬剤師が在宅対応可能な時間帯や時間外の連絡体制も共有されるべきと思う。
5. 資料4ページの③急変時の対応について、在宅診療している者から見ると、急変時の対
応と言うといろいろな意味が全部入ってしまうので、議論するときには区別することが
必要。例えば、がんで自宅療養している場合は、急変といって血圧が下がったり、呼吸
状態が悪くなったりといっても、それは予見された急変であり、いわゆる一般に考えて
いる急変には当たらないと考えられる。急変というのが予見される範囲内での容体の変
化なのか、それとも予見される以外の容体変化で入院が必要なレベルなのか、在宅療養
を続行できるレベルなのかによって場合分けをして考えるべき。
6. 情報共有システムの利活用について、情報システムのツールについては、在宅の情報共
有システムはかなり進んでいると思うが、自然発生的にそれらが動いてしまっているた
めに、互換性が全くないということが言えるのが現状。システムを統一することで運用
しやすくなり、参加する薬局数も増えて、連携体制を整えやすくなると考えられるので、
早期に統一システムの導入をしていただきたい。
7. 情報共有について、例えば新宿区では、新宿区医療介護福祉ネットワーク会議というも
のが、コロナ禍では月に1回開かれており、100 名くらいの方がオンラインで参加して
いた。医師、薬剤師、看護師、ケアマネジャーを含めた多くの者がここで情報共有をし
ている。今はコロナ禍ではないので、年に2回程度しか行われていないが、情報共有が
なされる会議になっており、こういったものを行政が主導してやっている一つの成功事
例だと考えている。
8. 薬局間連携に関しては、研修会を通じて地域のつながりができていて、顔と顔を合わせ
た付き合いの中で問題解決につながることが非常に多い。しかし、研修会の開催は地区
薬剤師会が対応していることが多く、薬剤師会に加入している薬局しか参加できない。
夜間・休日リストを地区薬剤師会が中心となって非会員も含めて作ったわけであり、す
でに実施しているところもあるかもしれないが、地区のために研修会を開くことが必要
なのではないか。また、地区薬剤師会にすべて任せるのではなく、行政が全容を把握す
ることも必要と考えている。
9. 現在も各都道府県の医療計画には在宅医療の体制整備に関する内容が定められており、
41