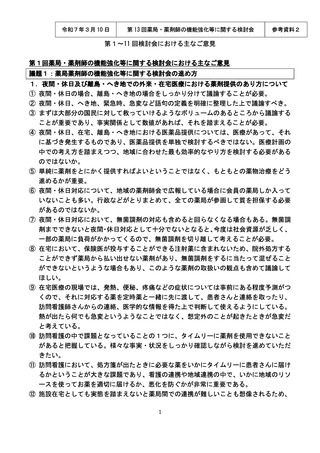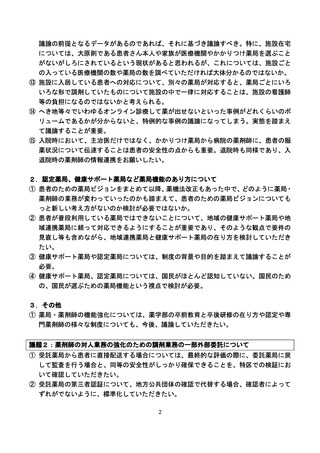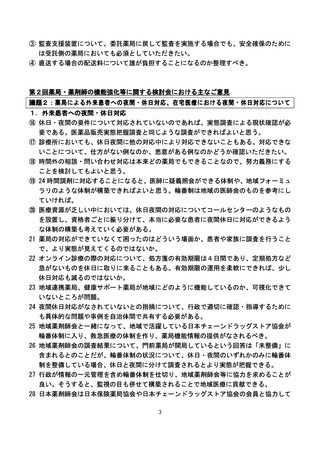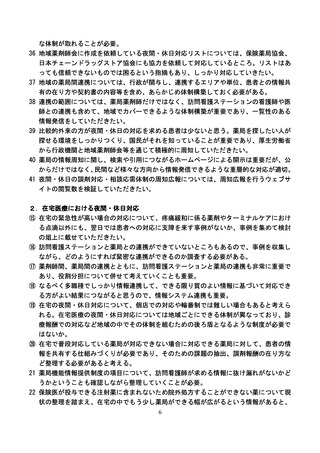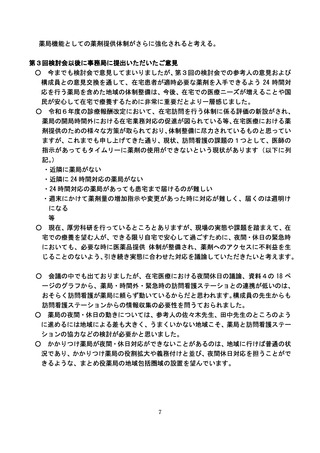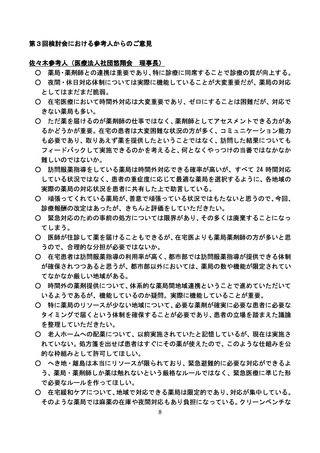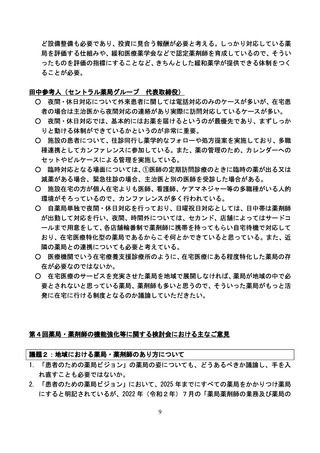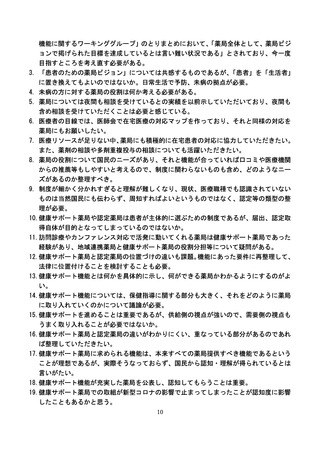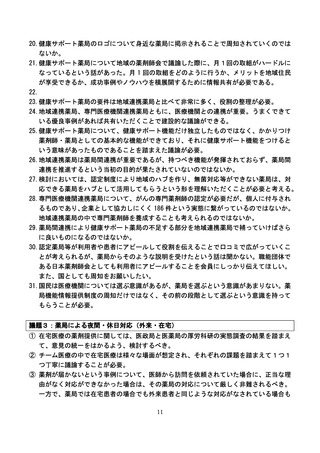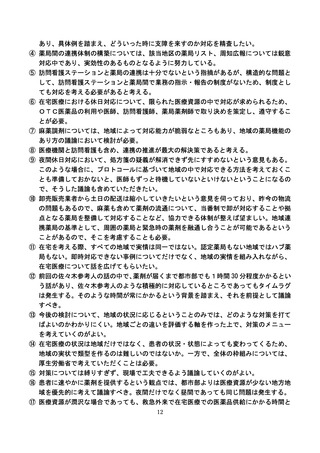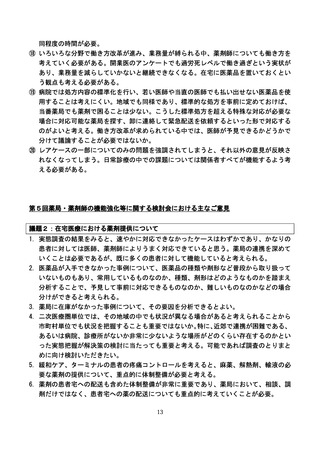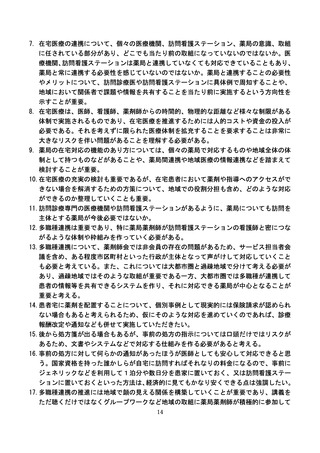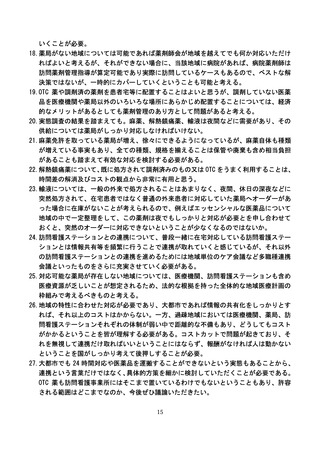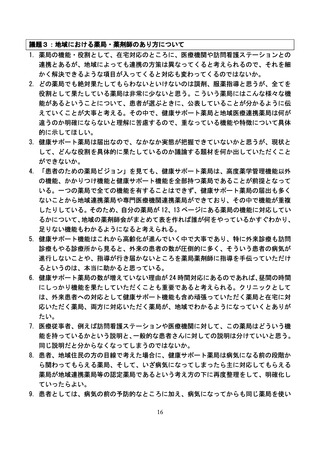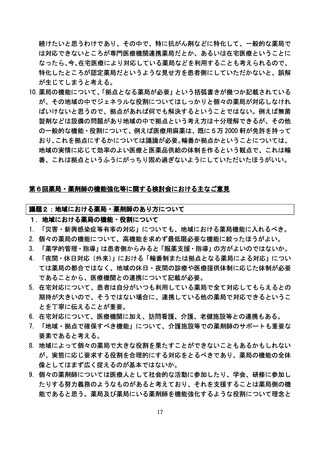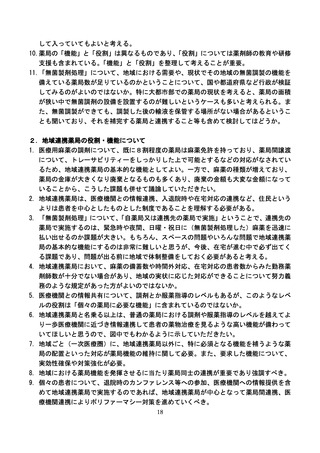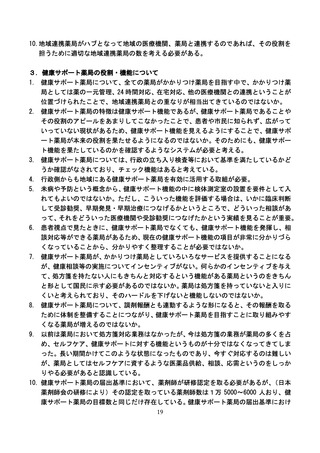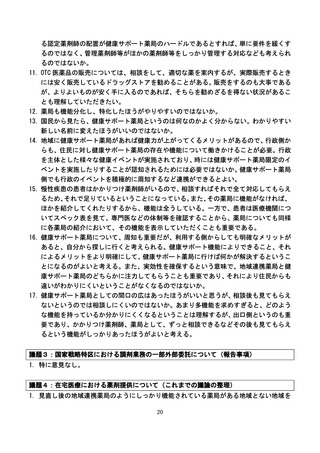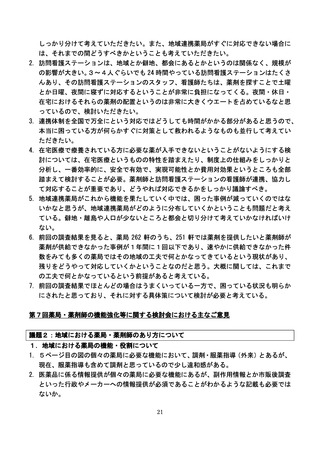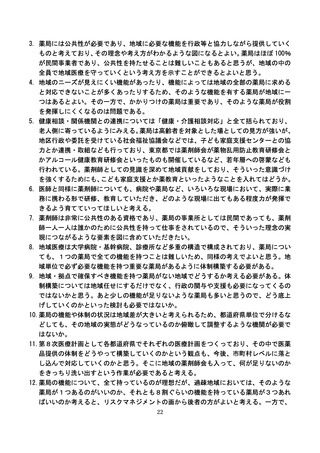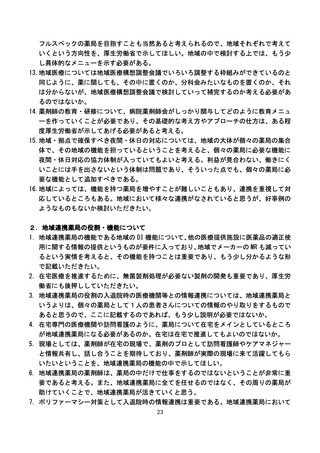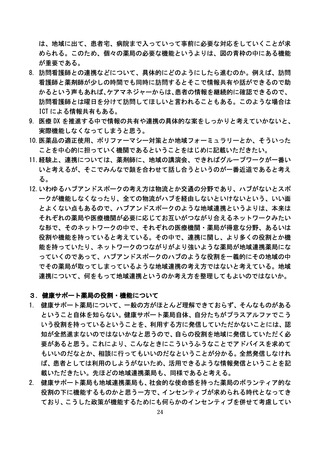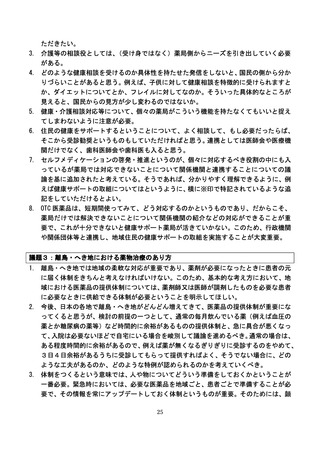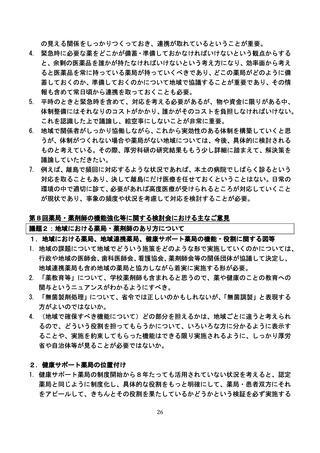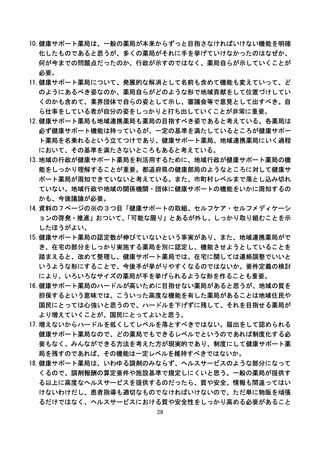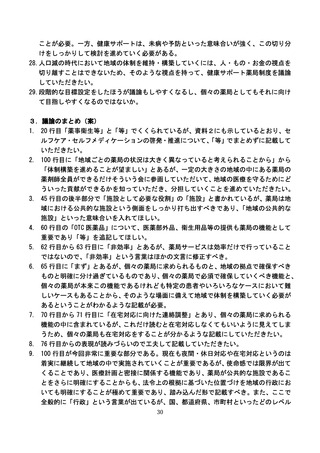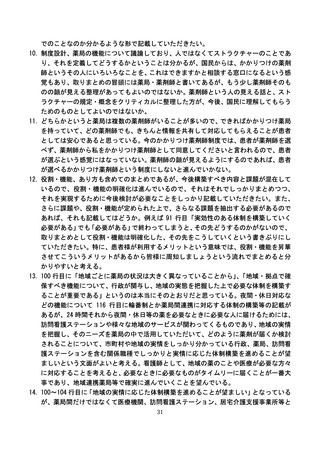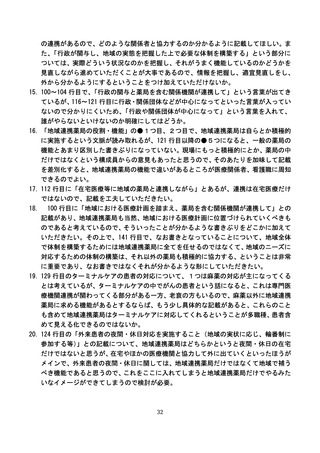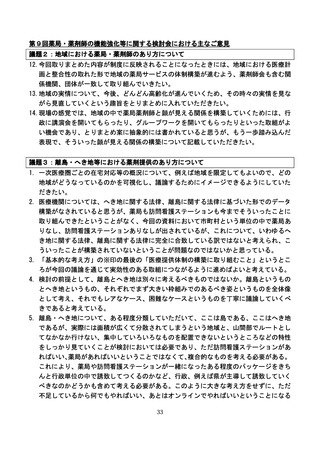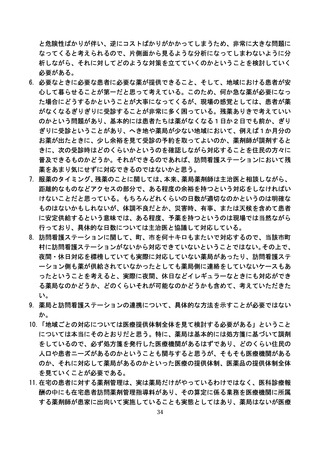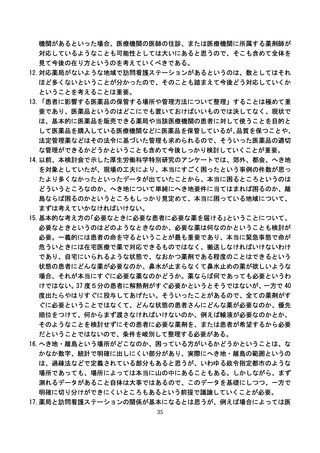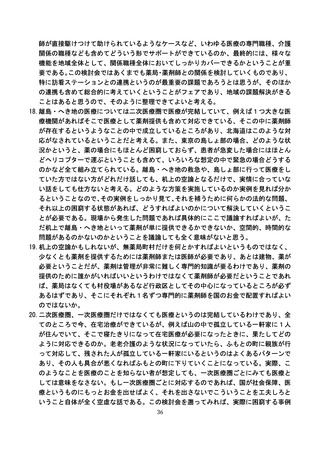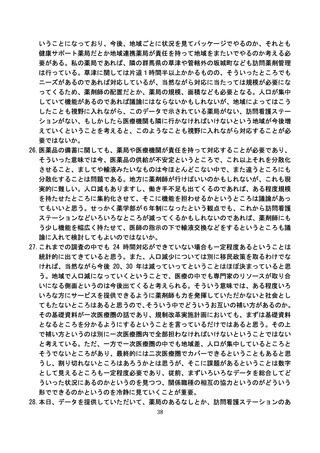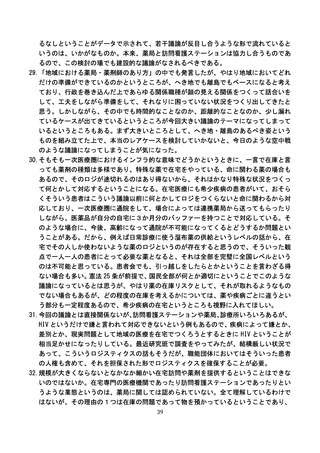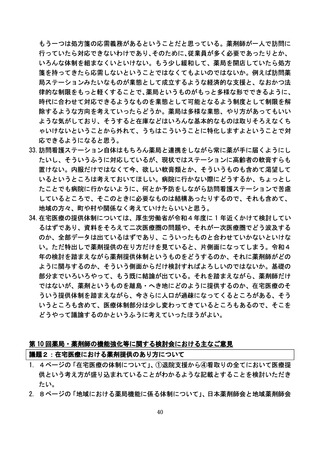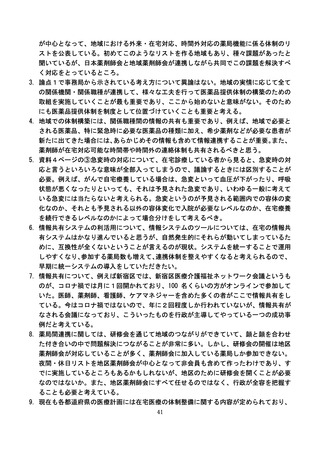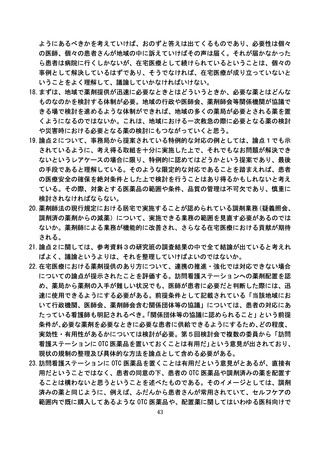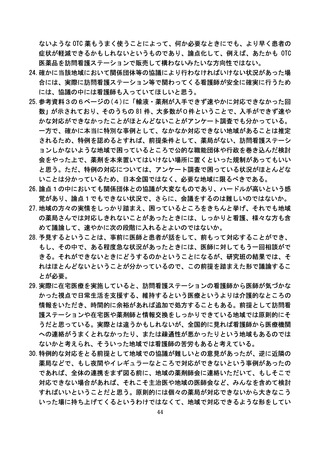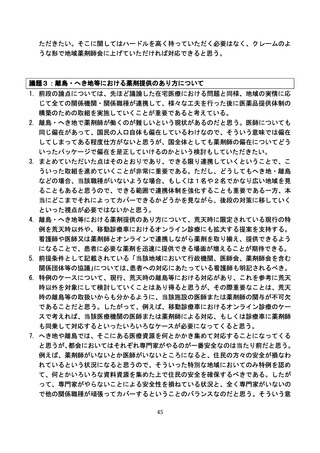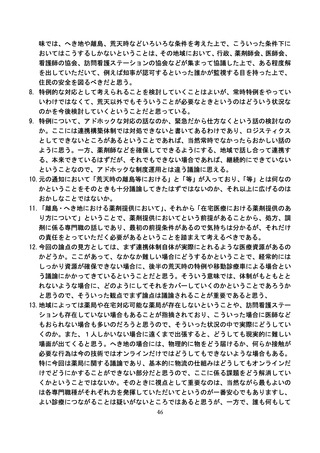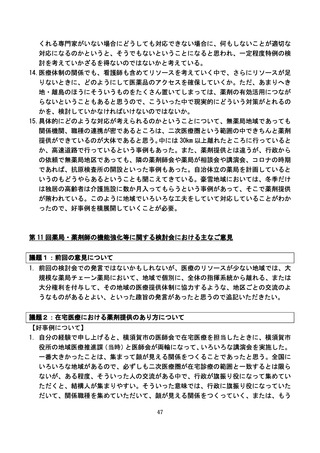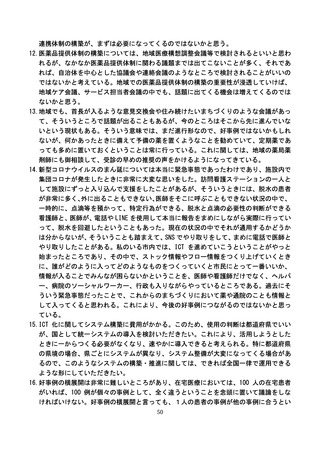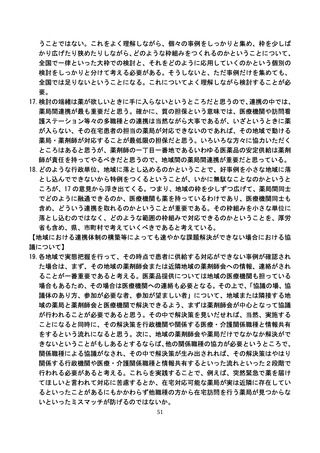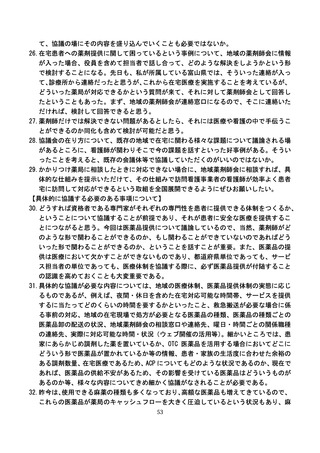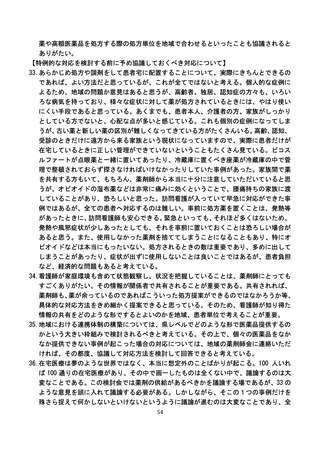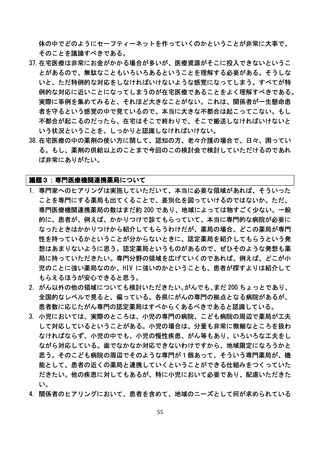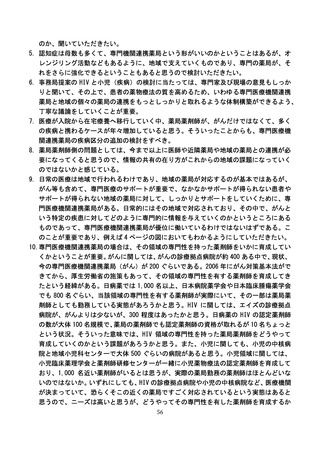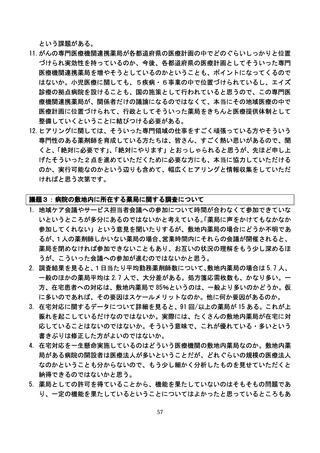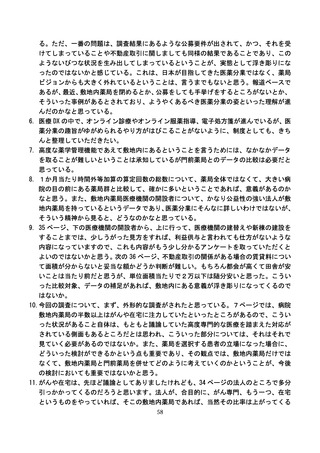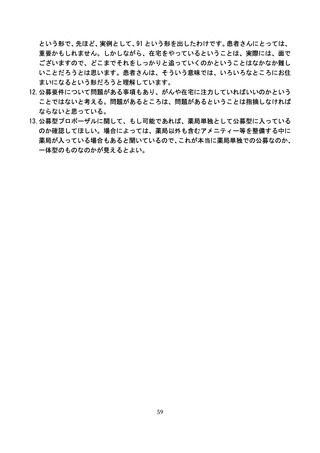よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_第1~11回検討会の主な意見 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
のか、聞いていただきたい。
5. 認知症は母数も多くて、専門機関連携薬局という形がいいのかということはあるが、オ
レンジリング活動などもあるように、地域で支えていくものであり、専門の薬局が、そ
れをさらに強化できるということもあると思うので検討いただきたい。
6. 事務局提案の HIV と小児(疾病)の検討に当たっては、専門家及び現場の意見もしっか
りと聞いて、その上で、患者の薬物療法の質を高めるため、いわゆる専門医療機関連携
薬局と地域の個々の薬局の連携をもっとしっかりと取れるような体制構築ができるよう、
丁寧な議論をしていくことが重要。
7. 医療が入院から在宅療養へ移行していく中、薬局薬剤師が、がんだけではなくて、多く
の疾病と携わるケースが年々増加していると思う。そういったことからも、専門医療機
関連携薬局の疾病区分の追加の検討をすべき。
8. 薬局薬剤師側の問題としては、今まで以上に医師や近隣薬局や地域の薬局との連携が必
要になってくると思うので、情報の共有の在り方がこれからの地域の課題になっていく
のではないかと感じている。
9. 日常の医療は地域で行われるわけであり、地域の薬局が対応するのが基本ではあるが、
がん等も含めて、専門医療のサポートが重要で、なかなかサポートが得られない患者や
サポートが得られない地域の薬局に対して、しっかりとサポートをしていくために、専
門医療機関連携薬局がある。日常的にはその地域で対応されており、その中で、がんと
いう特定の疾患に対してどのように専門的に情報を与えていくのかというところにある
ものであって、専門医療機関連携薬局が優位に働いているわけではないはずである。こ
のことが重要であり、例えば 4 ページの図においてもわかるようにしていただきたい。
10.専門医療機関連携薬局の場合は、その領域の専門性を持った薬剤師をいかに育成してい
くかということが重要。がんに関しては、がんの診療拠点病院が約 400 ある中で、現状、
今の専門医療機関連携薬局(がん)が 200 ぐらいである。2006 年にがん対策基本法がで
きてから、厚生労働省の施策もあって、その領域の専門性を有する薬剤師を育成してき
たという経緯がある。日病薬では 1,000 名以上、日本病院薬学会や日本臨床腫瘍薬学会
でも 800 名ぐらい、当該領域の専門性を有する薬剤師が実際にいて、その一部は薬局薬
剤師としても勤務している実態があろうかと思う。HIV に関しては、エイズの診療拠点
病院が、がんよりは少ないが、300 程度はあったかと思う。日病薬の HIV の認定薬剤師
の数が大体 100 名規模で、薬局の薬剤師でも認定薬剤師の資格が取れるが 10 名ちょっと
という状況。そういった意味では、HIV 領域の専門性を持った薬局薬剤師をどうやって
育成していくのかという課題があろうかと思う。また、小児に関しても、小児の中核病
院と地域小児科センターで大体 500 ぐらいの病院があると思う。小児領域に関しては、
小児臨床薬理学会と薬剤師研修センターが一緒に小児薬物療法の認定薬剤師を育成して
おり、1,000 名近い薬剤師がいるとは思うが、実際の薬局勤務の薬剤師はほとんどいな
いのではないか。いずれにしても、HIV の診療拠点病院や小児の中核病院など、医療機関
が決まっていて、恐らくそこの近くの薬局ですごく対応されているという実態はあると
思うので、ニーズは高いと思うが、どうやってその専門性を有した薬剤師を育成するか
56
5. 認知症は母数も多くて、専門機関連携薬局という形がいいのかということはあるが、オ
レンジリング活動などもあるように、地域で支えていくものであり、専門の薬局が、そ
れをさらに強化できるということもあると思うので検討いただきたい。
6. 事務局提案の HIV と小児(疾病)の検討に当たっては、専門家及び現場の意見もしっか
りと聞いて、その上で、患者の薬物療法の質を高めるため、いわゆる専門医療機関連携
薬局と地域の個々の薬局の連携をもっとしっかりと取れるような体制構築ができるよう、
丁寧な議論をしていくことが重要。
7. 医療が入院から在宅療養へ移行していく中、薬局薬剤師が、がんだけではなくて、多く
の疾病と携わるケースが年々増加していると思う。そういったことからも、専門医療機
関連携薬局の疾病区分の追加の検討をすべき。
8. 薬局薬剤師側の問題としては、今まで以上に医師や近隣薬局や地域の薬局との連携が必
要になってくると思うので、情報の共有の在り方がこれからの地域の課題になっていく
のではないかと感じている。
9. 日常の医療は地域で行われるわけであり、地域の薬局が対応するのが基本ではあるが、
がん等も含めて、専門医療のサポートが重要で、なかなかサポートが得られない患者や
サポートが得られない地域の薬局に対して、しっかりとサポートをしていくために、専
門医療機関連携薬局がある。日常的にはその地域で対応されており、その中で、がんと
いう特定の疾患に対してどのように専門的に情報を与えていくのかというところにある
ものであって、専門医療機関連携薬局が優位に働いているわけではないはずである。こ
のことが重要であり、例えば 4 ページの図においてもわかるようにしていただきたい。
10.専門医療機関連携薬局の場合は、その領域の専門性を持った薬剤師をいかに育成してい
くかということが重要。がんに関しては、がんの診療拠点病院が約 400 ある中で、現状、
今の専門医療機関連携薬局(がん)が 200 ぐらいである。2006 年にがん対策基本法がで
きてから、厚生労働省の施策もあって、その領域の専門性を有する薬剤師を育成してき
たという経緯がある。日病薬では 1,000 名以上、日本病院薬学会や日本臨床腫瘍薬学会
でも 800 名ぐらい、当該領域の専門性を有する薬剤師が実際にいて、その一部は薬局薬
剤師としても勤務している実態があろうかと思う。HIV に関しては、エイズの診療拠点
病院が、がんよりは少ないが、300 程度はあったかと思う。日病薬の HIV の認定薬剤師
の数が大体 100 名規模で、薬局の薬剤師でも認定薬剤師の資格が取れるが 10 名ちょっと
という状況。そういった意味では、HIV 領域の専門性を持った薬局薬剤師をどうやって
育成していくのかという課題があろうかと思う。また、小児に関しても、小児の中核病
院と地域小児科センターで大体 500 ぐらいの病院があると思う。小児領域に関しては、
小児臨床薬理学会と薬剤師研修センターが一緒に小児薬物療法の認定薬剤師を育成して
おり、1,000 名近い薬剤師がいるとは思うが、実際の薬局勤務の薬剤師はほとんどいな
いのではないか。いずれにしても、HIV の診療拠点病院や小児の中核病院など、医療機関
が決まっていて、恐らくそこの近くの薬局ですごく対応されているという実態はあると
思うので、ニーズは高いと思うが、どうやってその専門性を有した薬剤師を育成するか
56