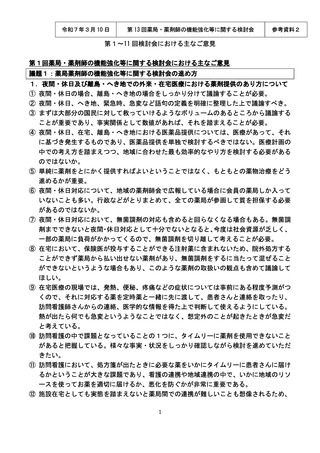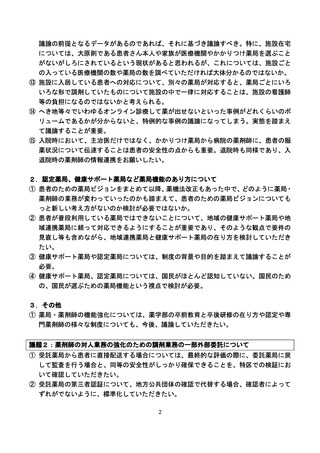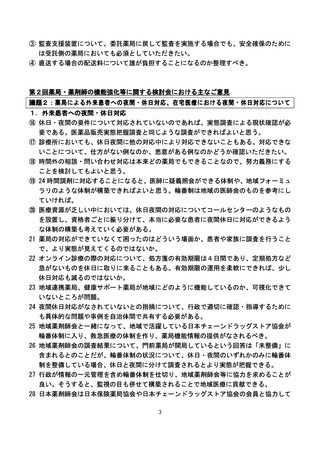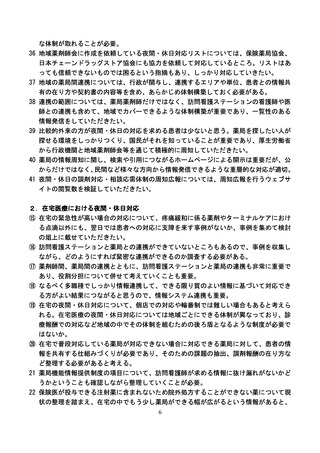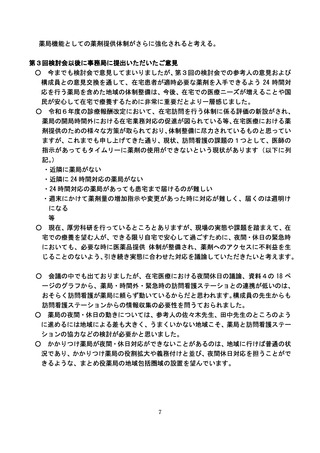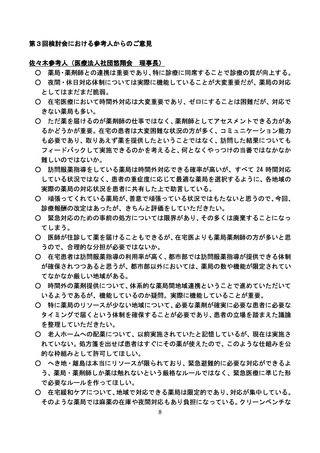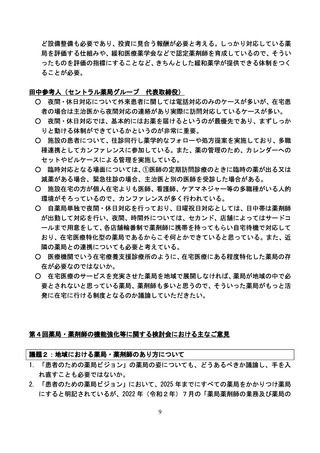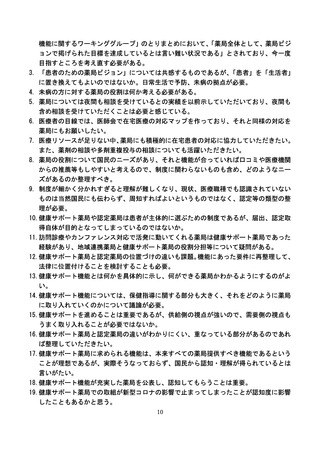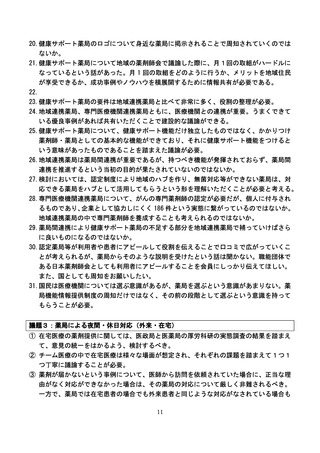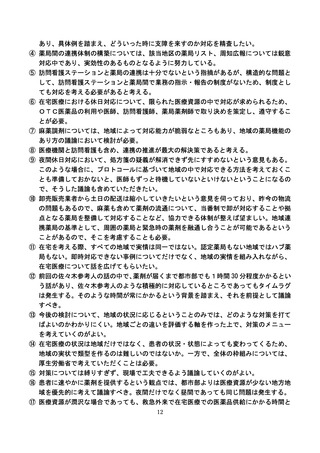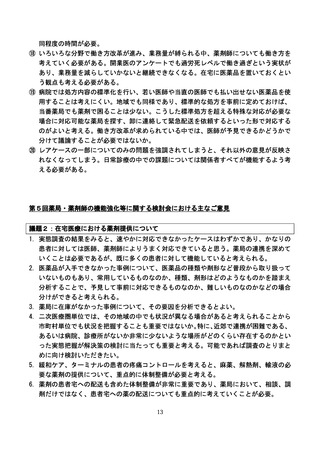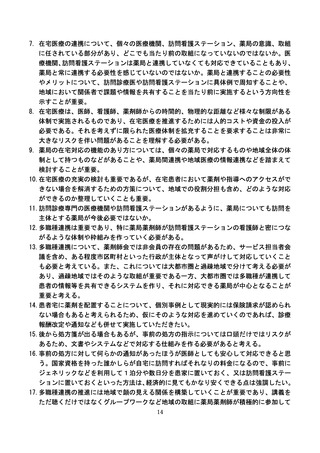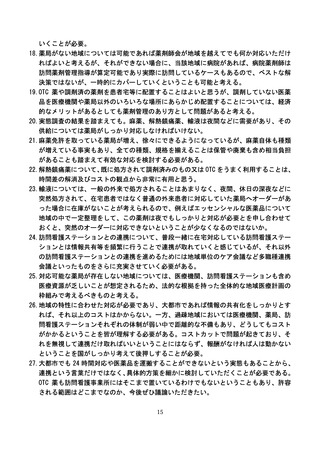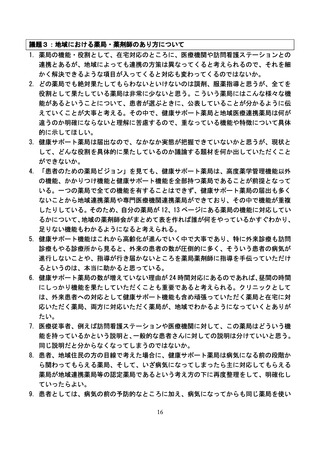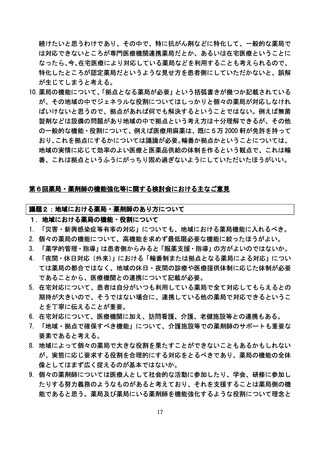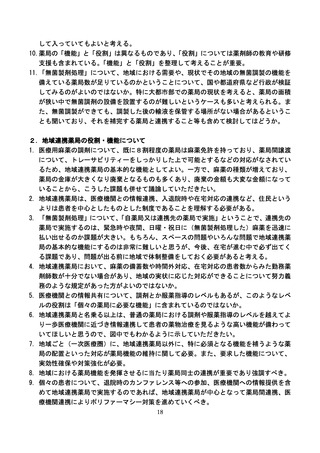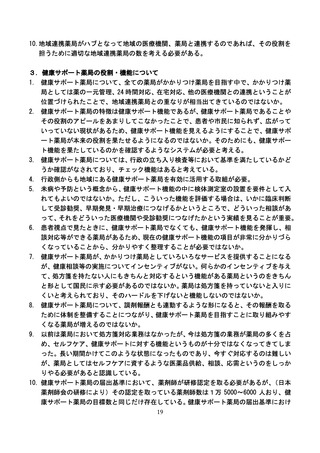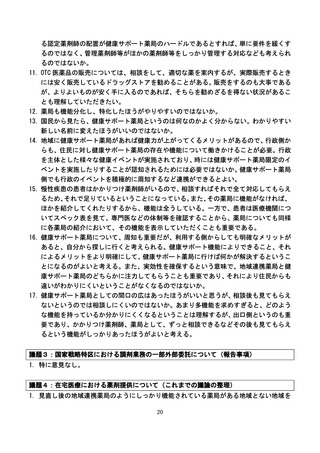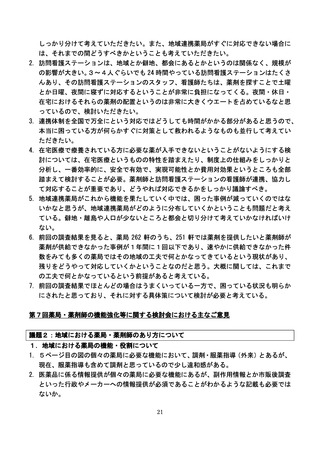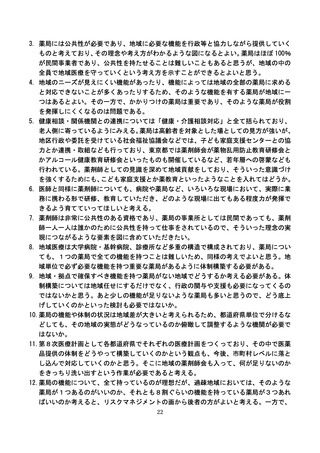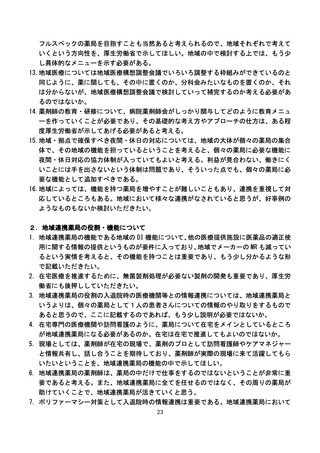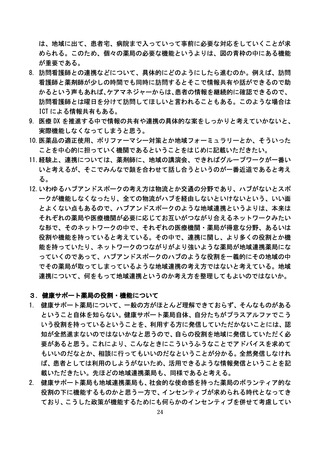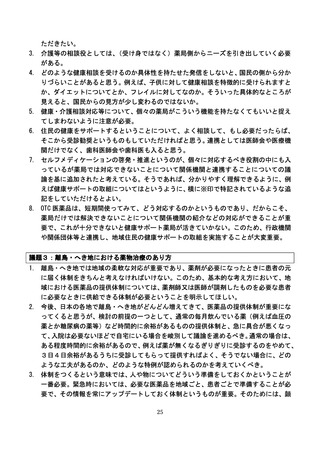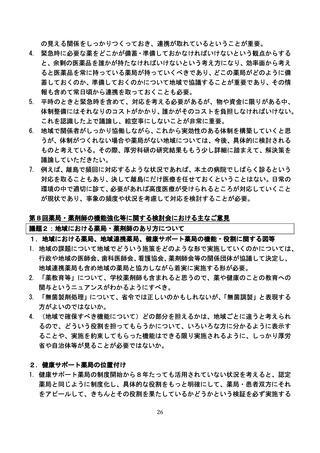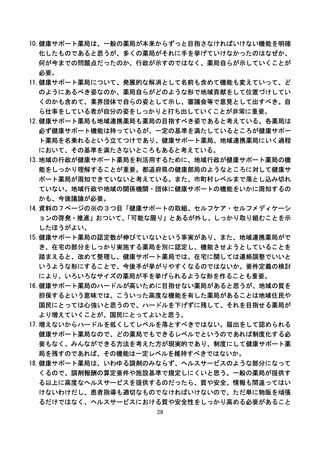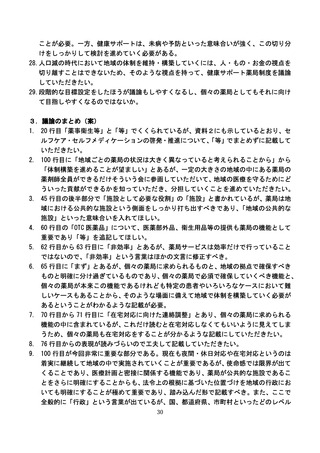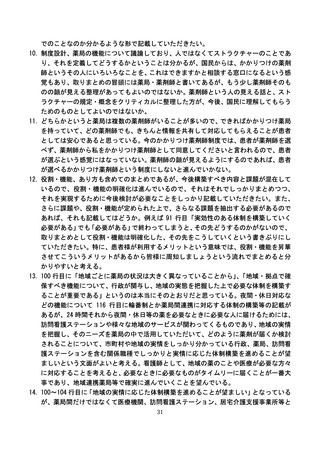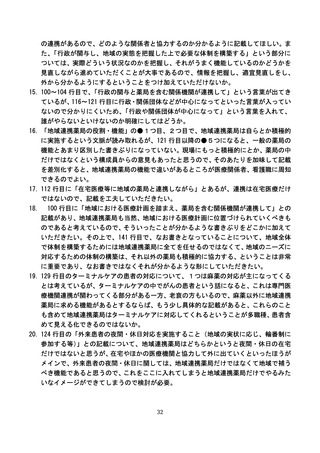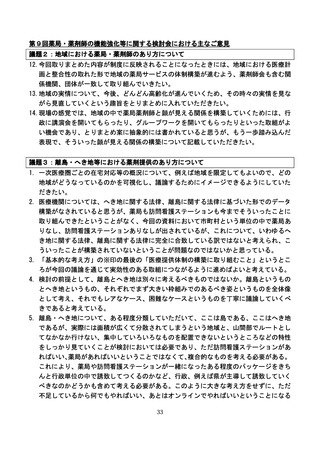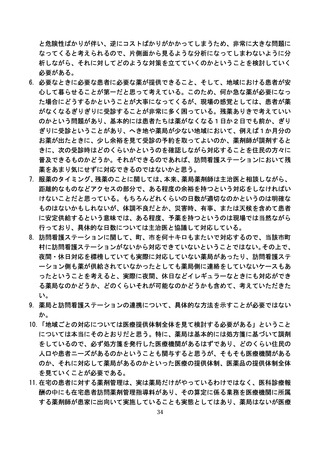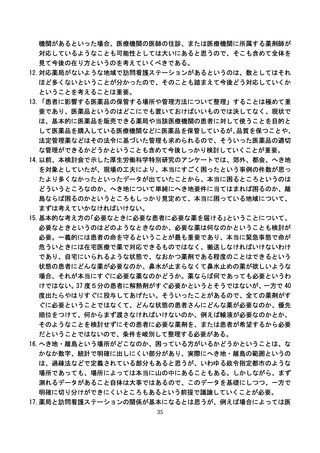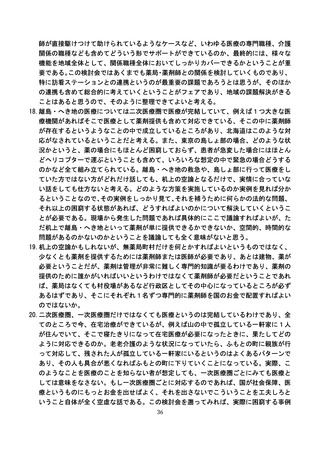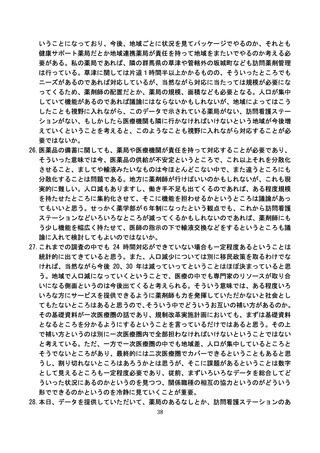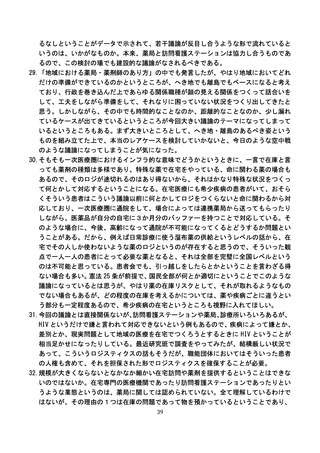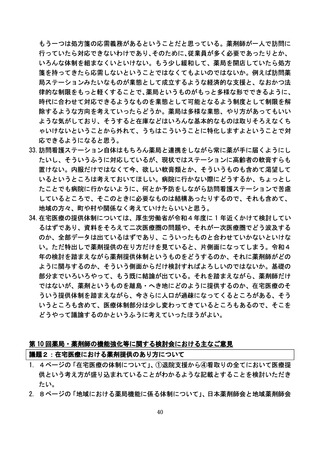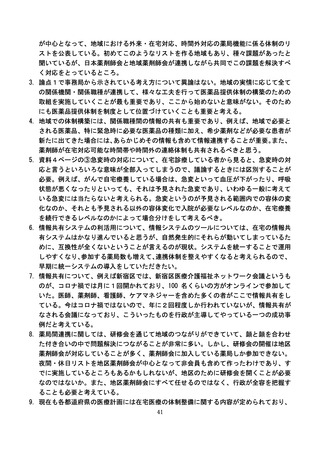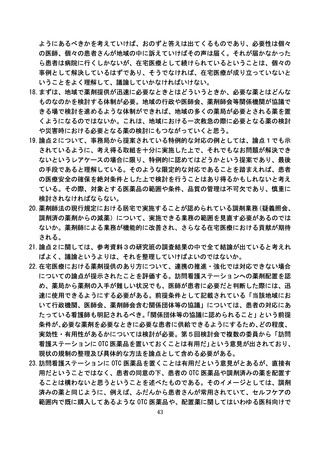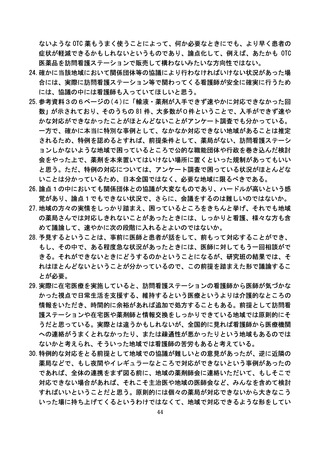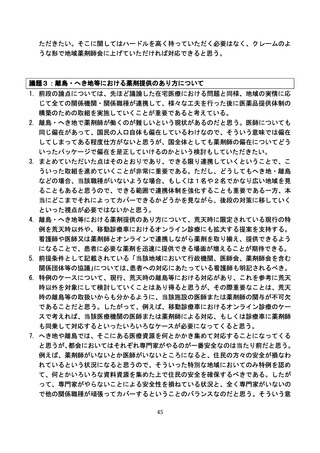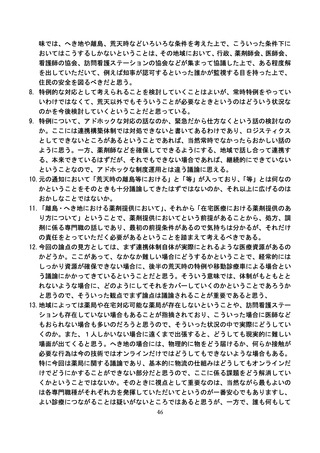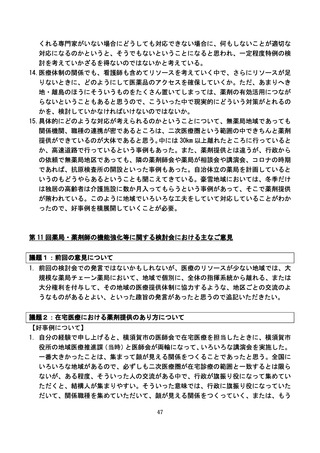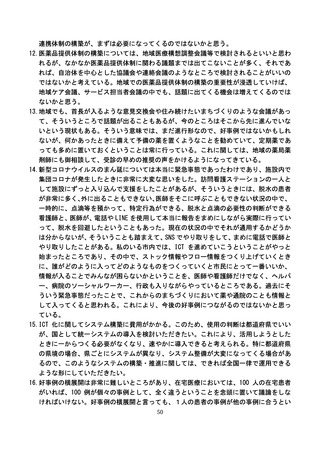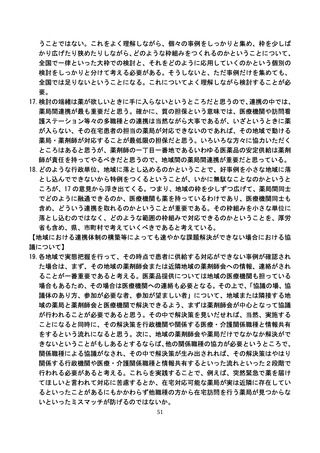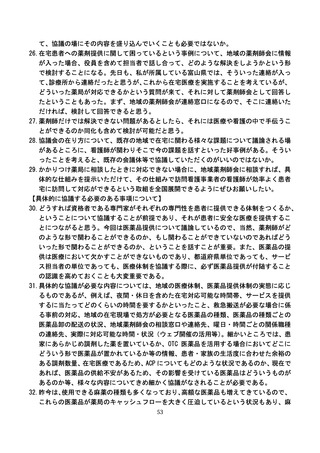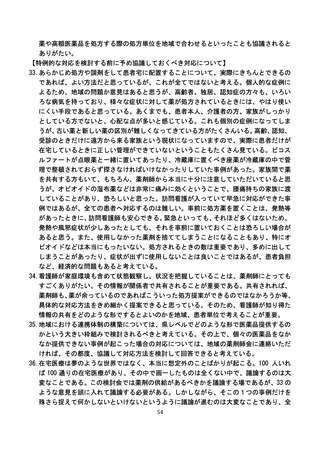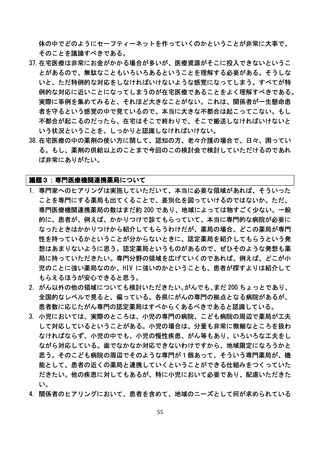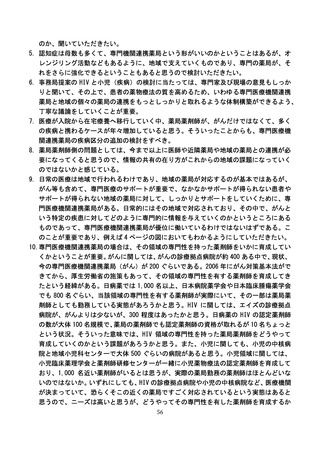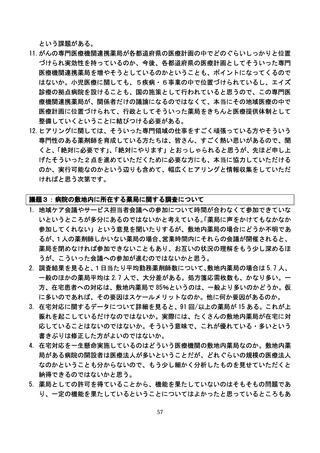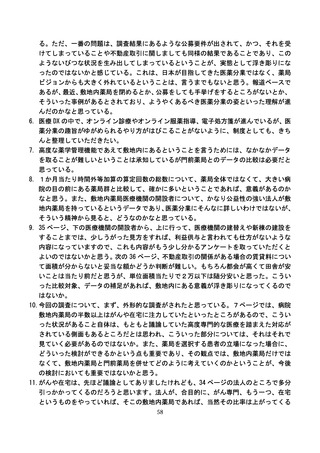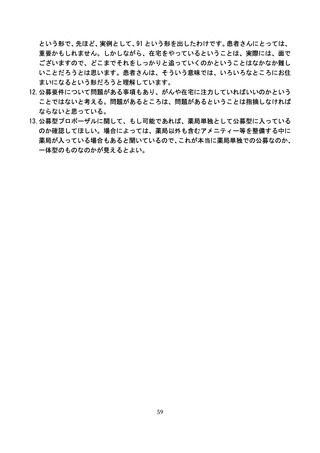よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_第1~11回検討会の主な意見 (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る。ただ、一番の問題は、調査結果にあるような公募要件が出されて、かつ、それを受
けてしまっていることや不動産取引に関しましても同様の結果であることであり、この
ようないびつな状況を生み出してしまっているということが、実態として浮き彫りにな
ったのではないかと感じている。これは、日本が目指してきた医薬分業ではなく、薬局
ビジョンからも大きく外れているということは、言うまでもないと思う。報道ベースで
あるが、最近、敷地内薬局を閉めるとか、公募をしても手挙げをするところがないとか、
そういった事例があるとされており、ようやくあるべき医薬分業の姿といった理解が進
んだのかなと思っている。
6. 医療 DX の中で、オンライン診療やオンライン服薬指導、電子処方箋が進んでいるが、医
薬分業の趣旨がゆがめられるやり方がはびこることがないように、制度としても、きち
んと整理していただきたい。
7. 高度な薬学管理機能であえて敷地内にあるということを言うためには、なかなかデータ
を取ることが難しいということは承知しているが門前薬局とのデータの比較は必要だと
思っている。
8. 1か月当たり時間外等加算の算定回数の総数について、薬局全体ではなくて、大きい病
院の目の前にある薬局群と比較して、確かに多いということであれば、意義があるのか
なと思う。また、敷地内薬局医療機関の開設者について、かなり公益性の強い法人が敷
地内薬局を持っているというデータであり、医薬分業にそんなに詳しいわけではないが、
そういう精神から見ると、どうなのかなと思っている。
9. 35 ページ、下の医療機関の開設者から、上に行って、医療機関の建替えや新棟の建設を
することまでは、少しうがった見方をすれば、利益供与と言われても仕方がないような
内容になっていますので、これも内容がもう少し分かるアンケートを取っていただくと
よいのではないかと思う。次の 36 ページ、不動産取引の関係がある場合の賃貸料につい
て面積が分からないと妥当な額かどうか判断が難しい。もちろん都会が高くて田舎が安
いことは当たり前だと思うが、単位面積当たりで2万以下は随分安いと思った。こうい
った比較対象、データの補足があれば、敷地内にある意義が浮き彫りになってくるので
はないか。
10.今回の調査について、まず、外形的な調査がされたと思っている。7ページでは、病院
敷地内薬局の半数以上はがんや在宅に注力していたといったところがあるので、こうい
った状況があること自体は、もともと議論していた高度専門的な医療を踏まえた対応が
されている側面もあるところだとは思われ、こういった部分については、それはそれで
見ていく必要があるのではないか。また、薬局を選択する患者の立場になった場合に、
どういった検討ができるかという点も重要であり、その観点では、敷地内薬局だけでは
なくて、敷地内薬局と門前薬局を併せてどのように考えていくのかということが、今後
の検討においても重要ではないかと思う。
11.がんや在宅は、先ほど議論としてありましたけれども、34 ページの法人のところで多分
引っかかってくるのだろうと思います。法人が、合目的に、がん専門、もう一つ、在宅
というものをやっていれば、そこの敷地内薬局であれば、当然その比率は上がってくる
58
けてしまっていることや不動産取引に関しましても同様の結果であることであり、この
ようないびつな状況を生み出してしまっているということが、実態として浮き彫りにな
ったのではないかと感じている。これは、日本が目指してきた医薬分業ではなく、薬局
ビジョンからも大きく外れているということは、言うまでもないと思う。報道ベースで
あるが、最近、敷地内薬局を閉めるとか、公募をしても手挙げをするところがないとか、
そういった事例があるとされており、ようやくあるべき医薬分業の姿といった理解が進
んだのかなと思っている。
6. 医療 DX の中で、オンライン診療やオンライン服薬指導、電子処方箋が進んでいるが、医
薬分業の趣旨がゆがめられるやり方がはびこることがないように、制度としても、きち
んと整理していただきたい。
7. 高度な薬学管理機能であえて敷地内にあるということを言うためには、なかなかデータ
を取ることが難しいということは承知しているが門前薬局とのデータの比較は必要だと
思っている。
8. 1か月当たり時間外等加算の算定回数の総数について、薬局全体ではなくて、大きい病
院の目の前にある薬局群と比較して、確かに多いということであれば、意義があるのか
なと思う。また、敷地内薬局医療機関の開設者について、かなり公益性の強い法人が敷
地内薬局を持っているというデータであり、医薬分業にそんなに詳しいわけではないが、
そういう精神から見ると、どうなのかなと思っている。
9. 35 ページ、下の医療機関の開設者から、上に行って、医療機関の建替えや新棟の建設を
することまでは、少しうがった見方をすれば、利益供与と言われても仕方がないような
内容になっていますので、これも内容がもう少し分かるアンケートを取っていただくと
よいのではないかと思う。次の 36 ページ、不動産取引の関係がある場合の賃貸料につい
て面積が分からないと妥当な額かどうか判断が難しい。もちろん都会が高くて田舎が安
いことは当たり前だと思うが、単位面積当たりで2万以下は随分安いと思った。こうい
った比較対象、データの補足があれば、敷地内にある意義が浮き彫りになってくるので
はないか。
10.今回の調査について、まず、外形的な調査がされたと思っている。7ページでは、病院
敷地内薬局の半数以上はがんや在宅に注力していたといったところがあるので、こうい
った状況があること自体は、もともと議論していた高度専門的な医療を踏まえた対応が
されている側面もあるところだとは思われ、こういった部分については、それはそれで
見ていく必要があるのではないか。また、薬局を選択する患者の立場になった場合に、
どういった検討ができるかという点も重要であり、その観点では、敷地内薬局だけでは
なくて、敷地内薬局と門前薬局を併せてどのように考えていくのかということが、今後
の検討においても重要ではないかと思う。
11.がんや在宅は、先ほど議論としてありましたけれども、34 ページの法人のところで多分
引っかかってくるのだろうと思います。法人が、合目的に、がん専門、もう一つ、在宅
というものをやっていれば、そこの敷地内薬局であれば、当然その比率は上がってくる
58