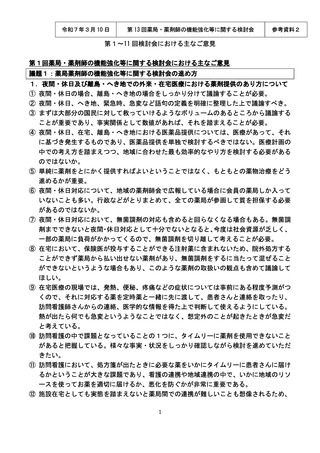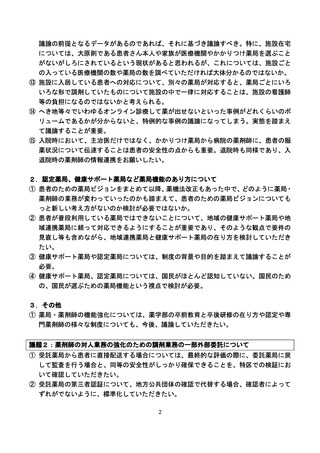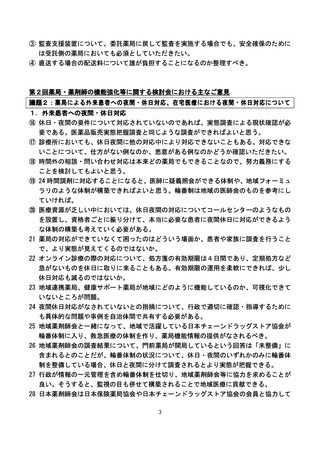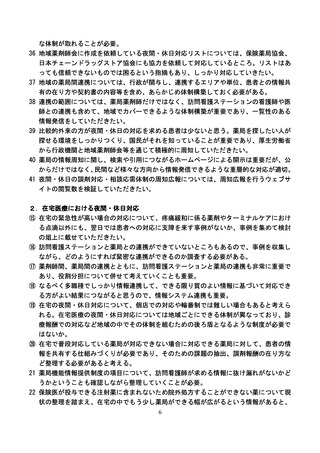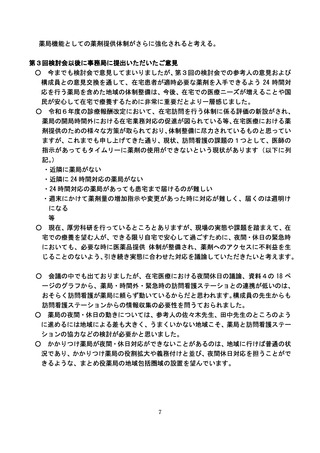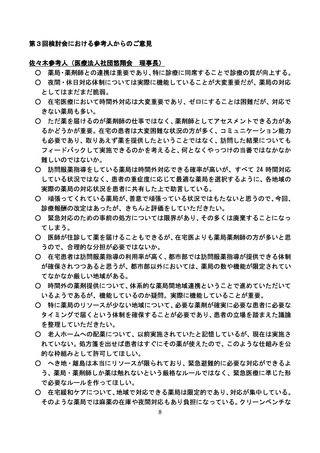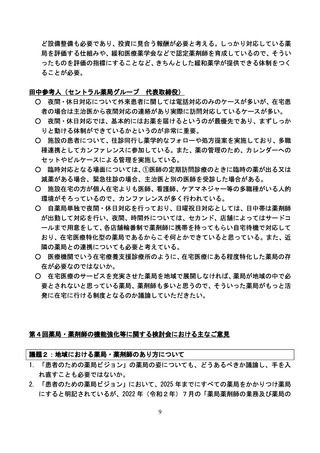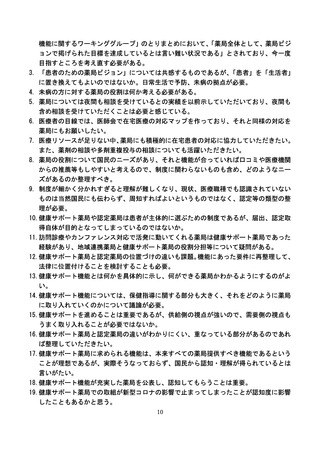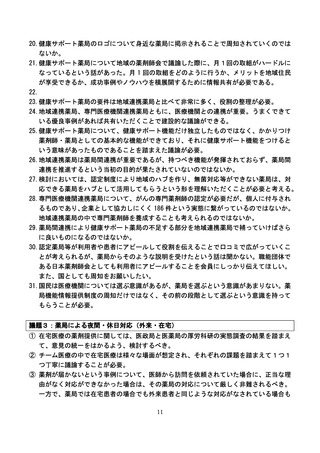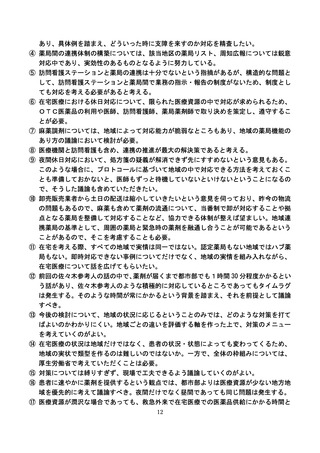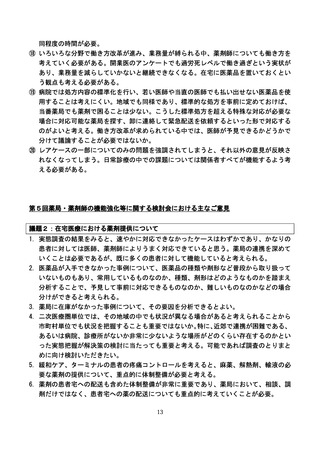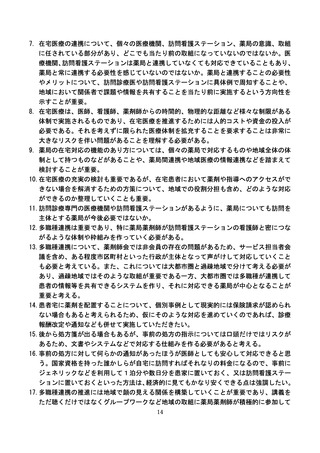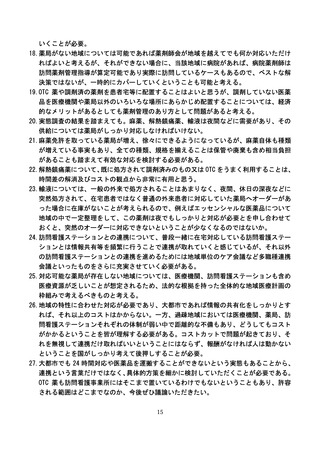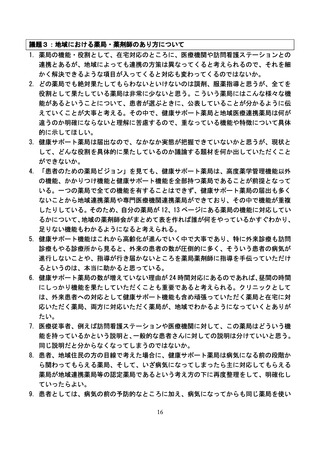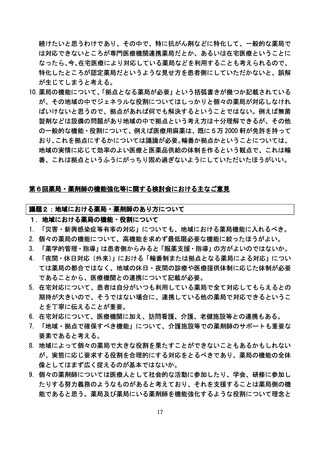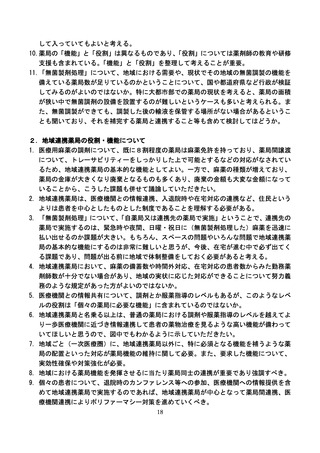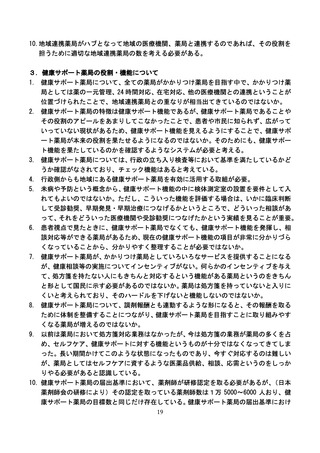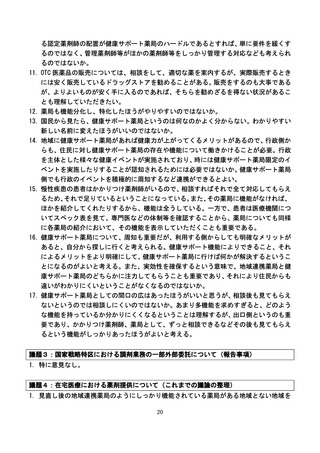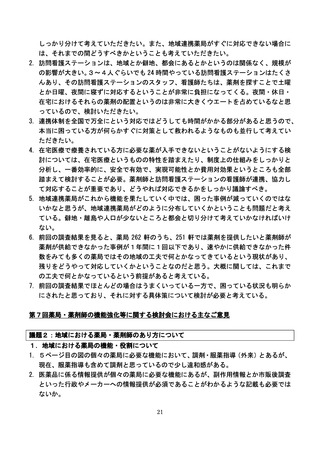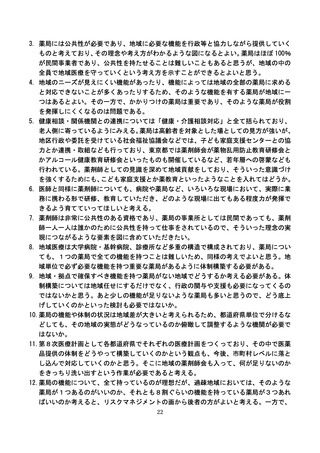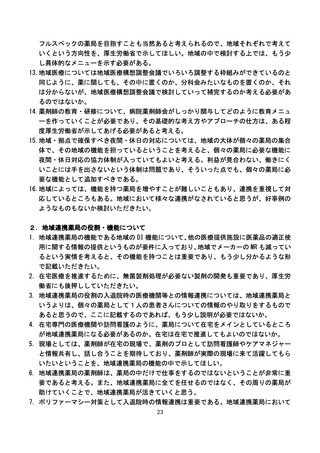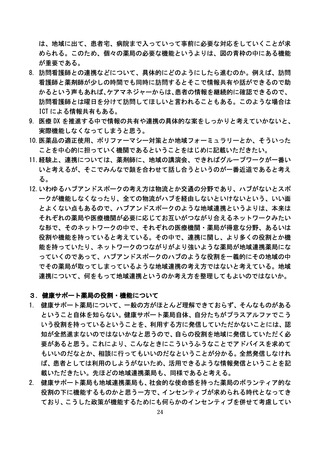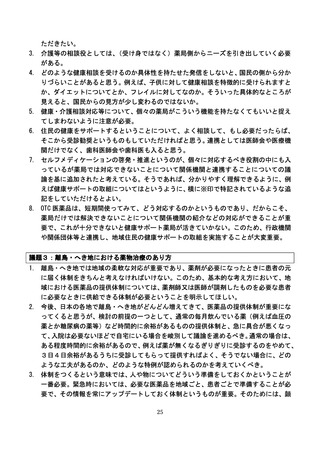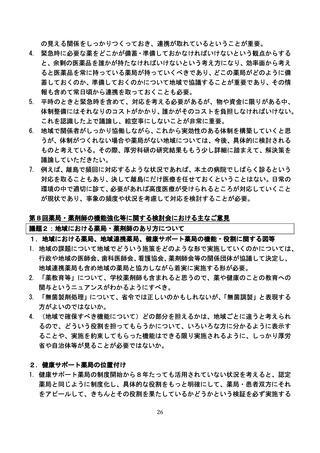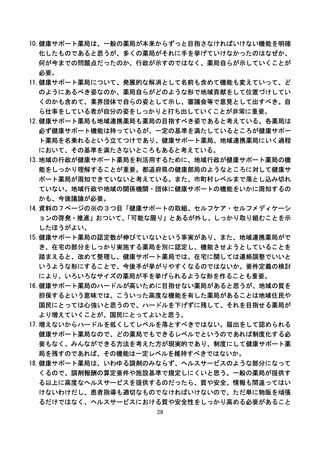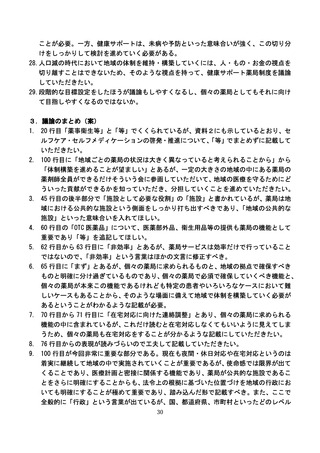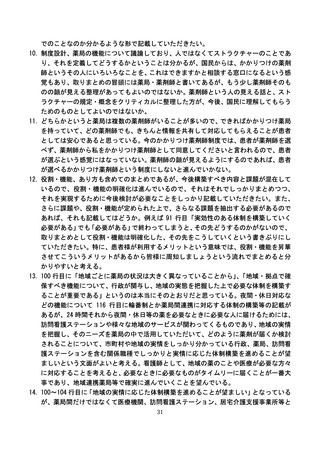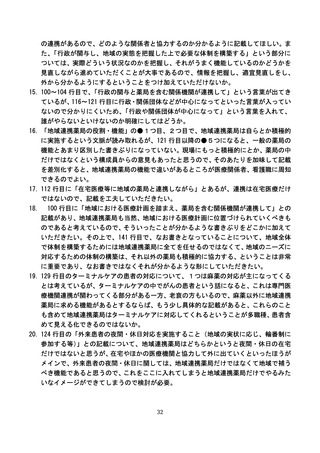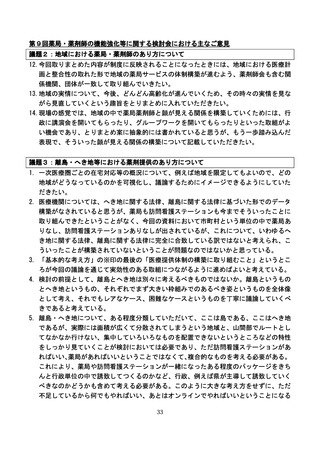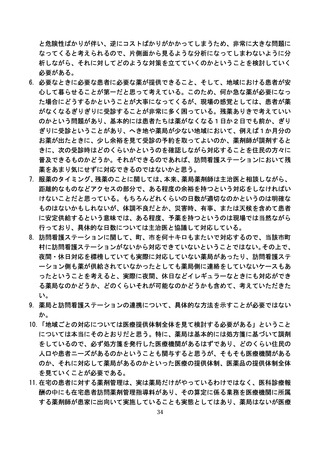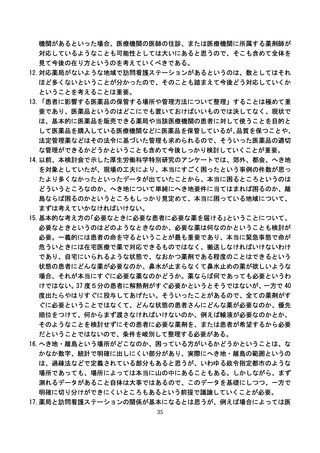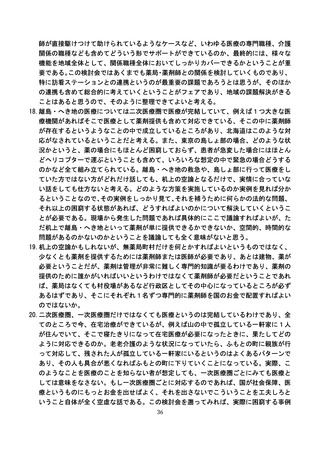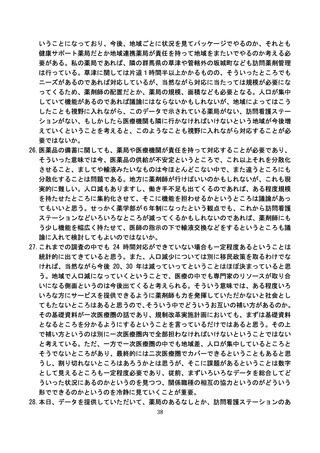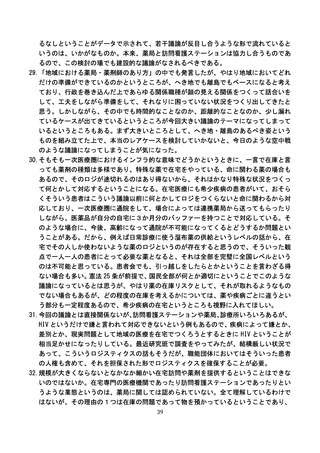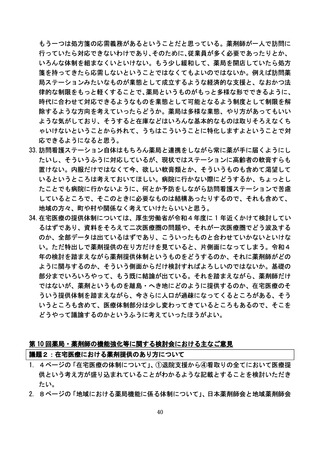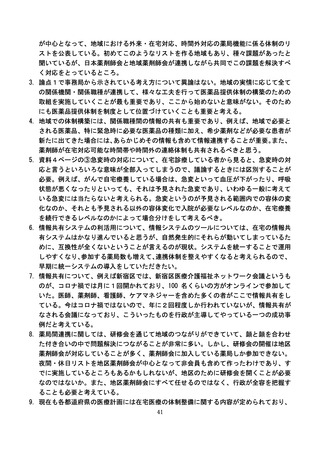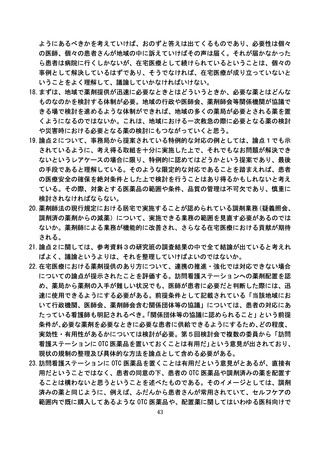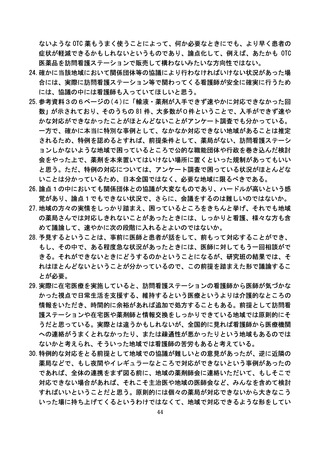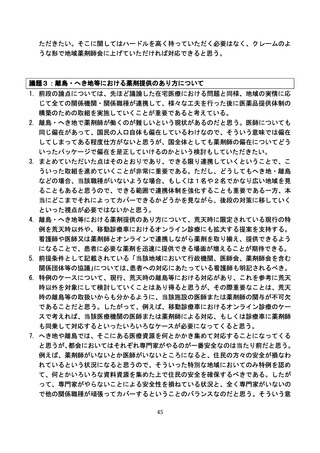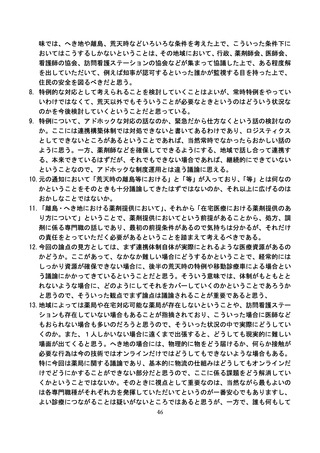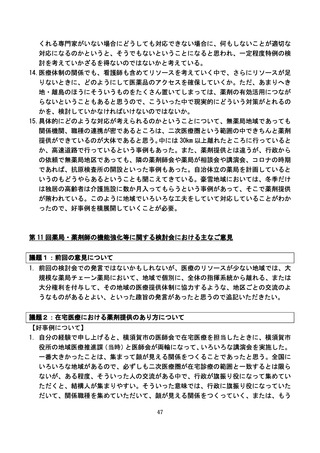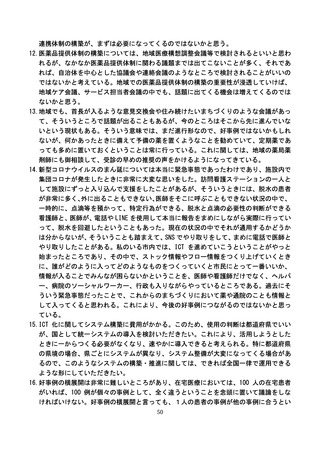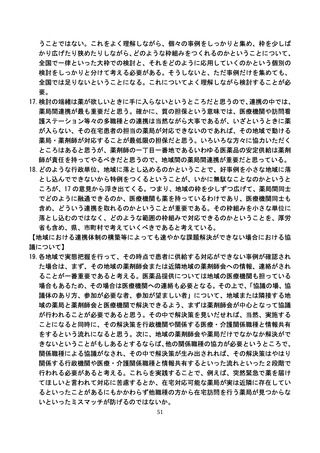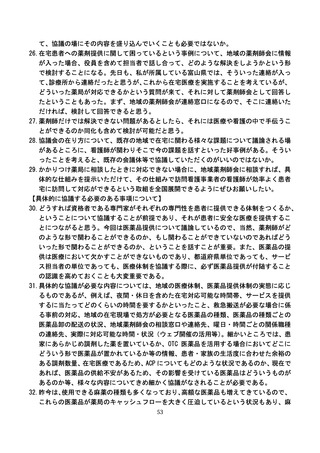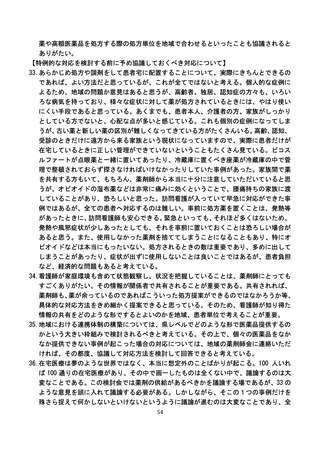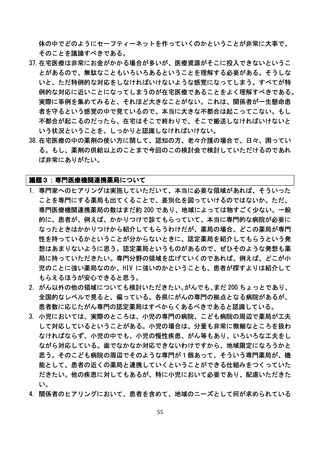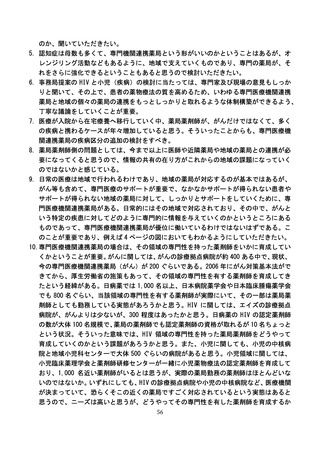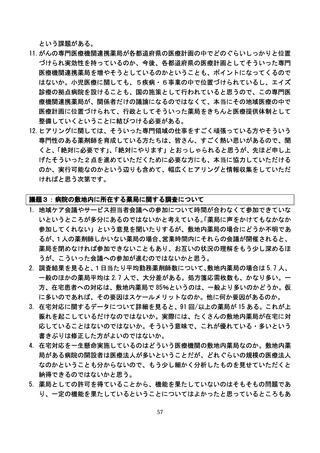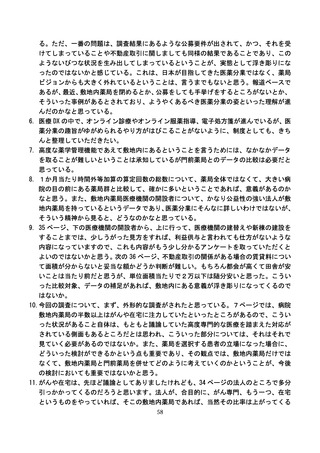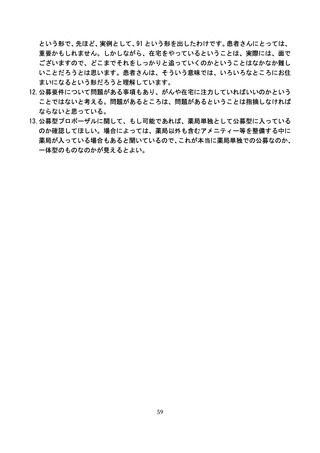よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_第1~11回検討会の主な意見 (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
少し人口が希薄な場所であれば、ウェブ会議システムを使用してグループワークをやる
ことで、顔が見える関係になっていくと思う。
2. 神奈川県医師会で、神奈川県全域に対して、在宅医療トレーニングセンターというもの
を行っている。平成 27 年から地域医療の確保基金を用いて始めたもので、その後、参加
者が非常に多く、うまく回っており、現在は神奈川県にも独自に予算をつけてもらって
いる。ウェブも併用しながら、現場の在宅医療、訪問看護などの実習も行う少ない人数
でやるトレーニングと、講演会形式または Web 会議のブレイクアウトルームも使いなが
ら実施する講演会形式の両立てで実施しており、年間 6,000 人くらいの参加者がおり、
講演会や講習会も 100 回以上やっている。ブレイクアウトルームでも、ファシリテータ
ーを置いて話を促すと、意外と皆さんも盛り上がってくる。ある程度の圏域、ある程度
の広さでつながってきているという実感がある。
3. また、在宅医療トレーニングセンターには、医師会に加え、関係団体、訪問看護事業所、
看護協会、リハビリテーションの方、ホームヘルパーやケアマネジャー、神奈川県も傘
下に入っており、全部で 16~17 ぐらいの関連団体が参加している。そこで運営協議会を
開催し、いろいろな立場で今困っていることなどの課題抽出ができている。まだその課
題解決までにはいっていないが、全体的に医療・介護の関係の課題がどんなことかとい
うことも分かるので、そういう意味では、非常に助かっている。
4. 対応策の1の上のポツが一番重要であり、都道府県等において、医薬品提供について、
医薬品提供計画は医療計画と整合性の取れた形で作成されなければならないと思ってい
る。その際には、日本薬剤師会においても積極的な活動をしたいと考えているが、法的
な措置、盛り込むべき具体的な内容を示すといった、都道府県等が計画を進めるに当た
ってのサポートを厚生労働省にもお願いしたい。また、国が現在示している第8次医療
計画における留意事項及び指針においても、薬局の役割として、医薬品等の供給体制の
確保という記述はあるが、医薬品提供は医療を実施する上で重要なファクターであるこ
とから、もう少し具体的な記載が必要と考えている。現在、困っている地域に速やかに
対応するためにも、都道府県の医療計画もしくは別立ての医薬品提供計画も含めて、き
め細かく医薬品提供についての記述がなされるよう、厚労省の後押しをお願いしたい。
5. 令和6年の元旦に発生した能登半島地震のように、日本は自然災害多発国であるため、
そういった災害時の対応についての医薬品提供の体制や、新型コロナウイルスのパンデ
ミック時のような医薬品の体制などについての視点もぜひ盛り込んでいただきたい。そ
ういったことも含めて、平時の医薬品提供体制の在り方、有事の医薬品提供の在り方を
検討してほしい。
6. 1の 2 つ目のポツについて、好事例として、富山市では、まず、行政が中心となって、
富山市の5つの区域それぞれにおいて、多職種の会議、顔の見える関係をつくることが、
かなり前から行われており、かなり多くの方々が参加している。また、有志で行われて
いる会議、集合して対面でやる会議もあれば、ウェブで実施する会議もあり、医師、薬
剤師、看護師、ケアマネジャーなどいろいろな方々が参加して、地域の課題を解決する
といった事例もあり、こういったことを進めていくことが重要。
48
ことで、顔が見える関係になっていくと思う。
2. 神奈川県医師会で、神奈川県全域に対して、在宅医療トレーニングセンターというもの
を行っている。平成 27 年から地域医療の確保基金を用いて始めたもので、その後、参加
者が非常に多く、うまく回っており、現在は神奈川県にも独自に予算をつけてもらって
いる。ウェブも併用しながら、現場の在宅医療、訪問看護などの実習も行う少ない人数
でやるトレーニングと、講演会形式または Web 会議のブレイクアウトルームも使いなが
ら実施する講演会形式の両立てで実施しており、年間 6,000 人くらいの参加者がおり、
講演会や講習会も 100 回以上やっている。ブレイクアウトルームでも、ファシリテータ
ーを置いて話を促すと、意外と皆さんも盛り上がってくる。ある程度の圏域、ある程度
の広さでつながってきているという実感がある。
3. また、在宅医療トレーニングセンターには、医師会に加え、関係団体、訪問看護事業所、
看護協会、リハビリテーションの方、ホームヘルパーやケアマネジャー、神奈川県も傘
下に入っており、全部で 16~17 ぐらいの関連団体が参加している。そこで運営協議会を
開催し、いろいろな立場で今困っていることなどの課題抽出ができている。まだその課
題解決までにはいっていないが、全体的に医療・介護の関係の課題がどんなことかとい
うことも分かるので、そういう意味では、非常に助かっている。
4. 対応策の1の上のポツが一番重要であり、都道府県等において、医薬品提供について、
医薬品提供計画は医療計画と整合性の取れた形で作成されなければならないと思ってい
る。その際には、日本薬剤師会においても積極的な活動をしたいと考えているが、法的
な措置、盛り込むべき具体的な内容を示すといった、都道府県等が計画を進めるに当た
ってのサポートを厚生労働省にもお願いしたい。また、国が現在示している第8次医療
計画における留意事項及び指針においても、薬局の役割として、医薬品等の供給体制の
確保という記述はあるが、医薬品提供は医療を実施する上で重要なファクターであるこ
とから、もう少し具体的な記載が必要と考えている。現在、困っている地域に速やかに
対応するためにも、都道府県の医療計画もしくは別立ての医薬品提供計画も含めて、き
め細かく医薬品提供についての記述がなされるよう、厚労省の後押しをお願いしたい。
5. 令和6年の元旦に発生した能登半島地震のように、日本は自然災害多発国であるため、
そういった災害時の対応についての医薬品提供の体制や、新型コロナウイルスのパンデ
ミック時のような医薬品の体制などについての視点もぜひ盛り込んでいただきたい。そ
ういったことも含めて、平時の医薬品提供体制の在り方、有事の医薬品提供の在り方を
検討してほしい。
6. 1の 2 つ目のポツについて、好事例として、富山市では、まず、行政が中心となって、
富山市の5つの区域それぞれにおいて、多職種の会議、顔の見える関係をつくることが、
かなり前から行われており、かなり多くの方々が参加している。また、有志で行われて
いる会議、集合して対面でやる会議もあれば、ウェブで実施する会議もあり、医師、薬
剤師、看護師、ケアマネジャーなどいろいろな方々が参加して、地域の課題を解決する
といった事例もあり、こういったことを進めていくことが重要。
48