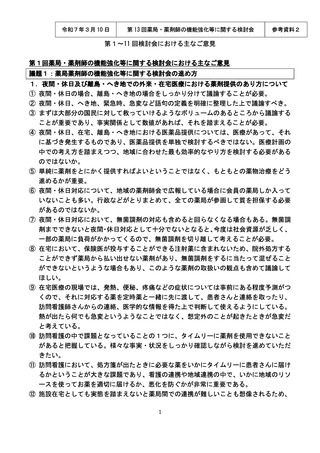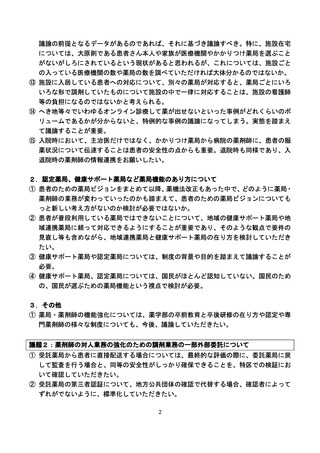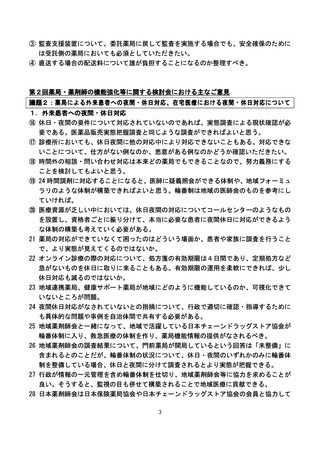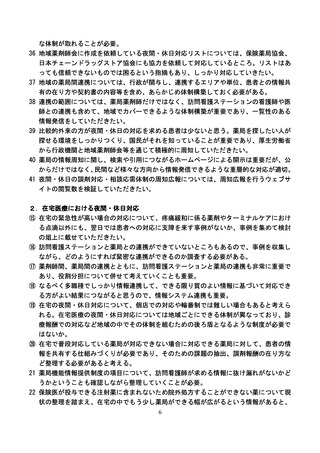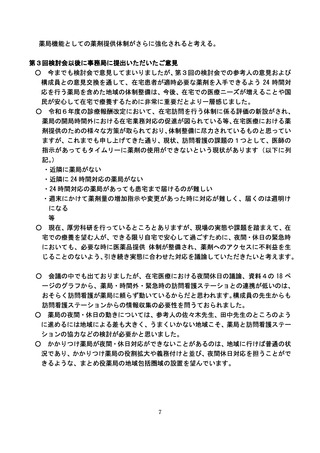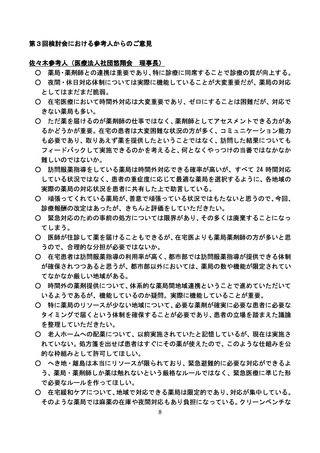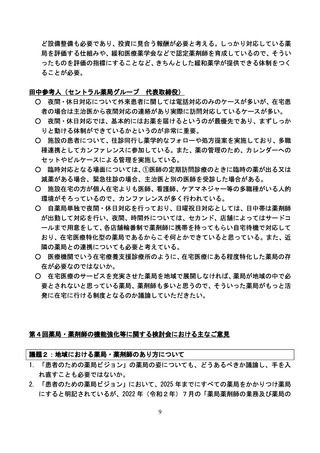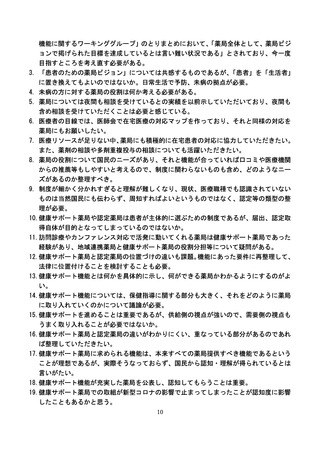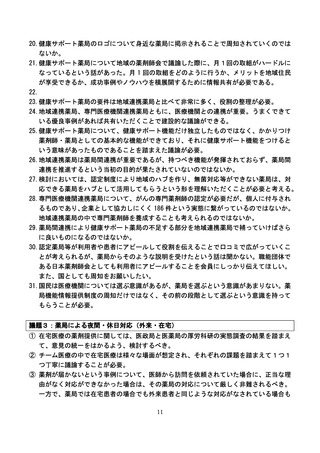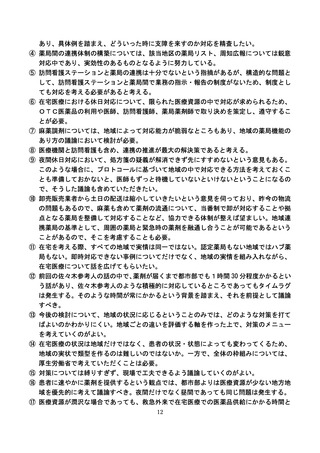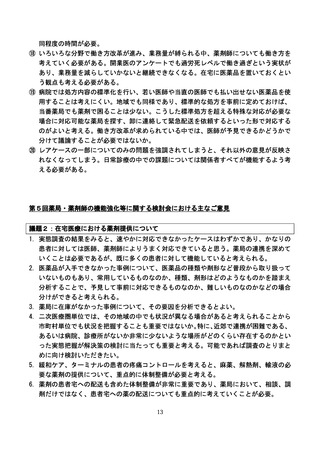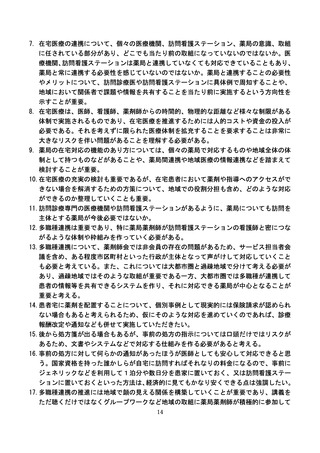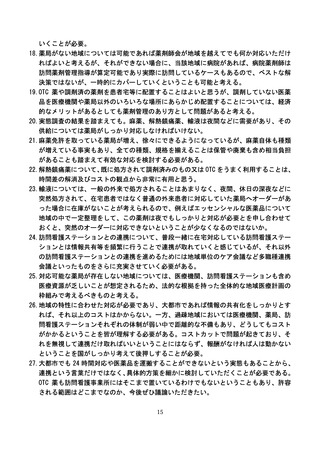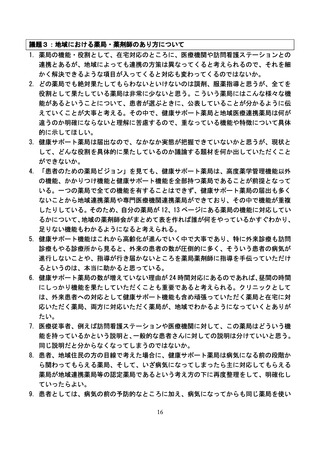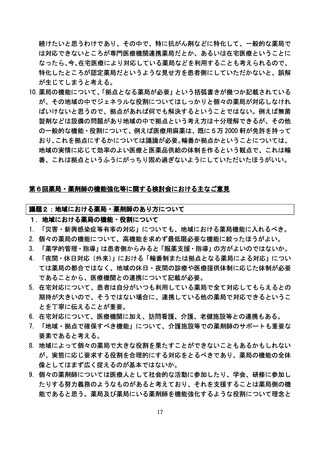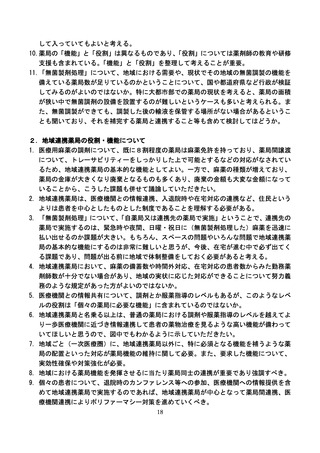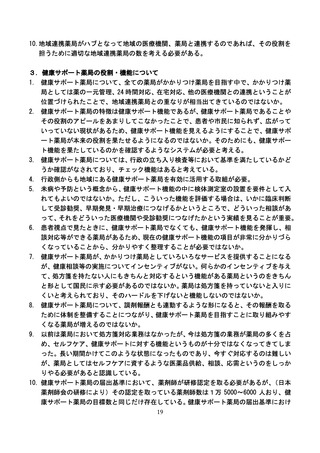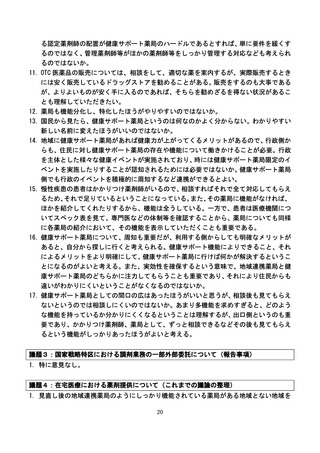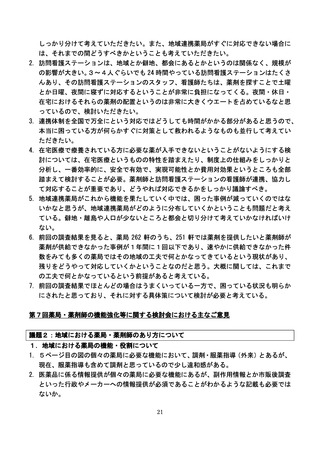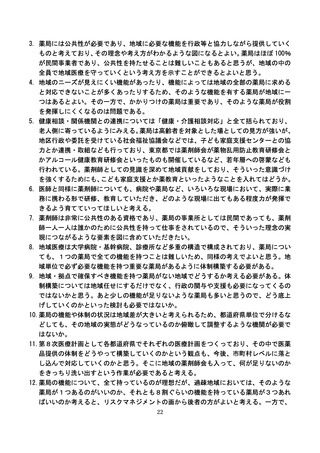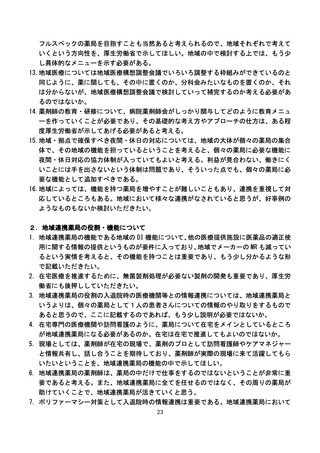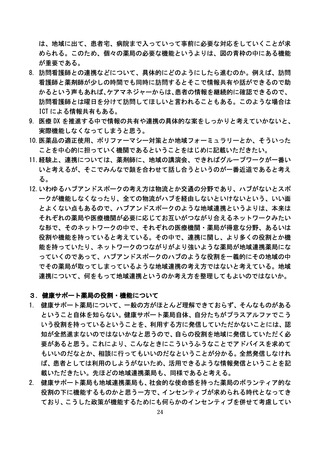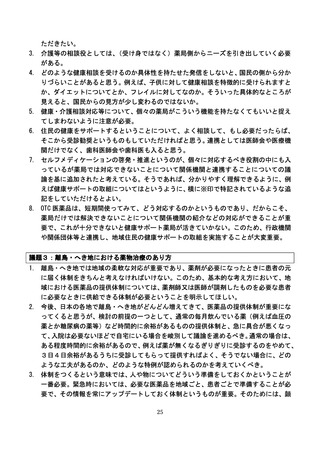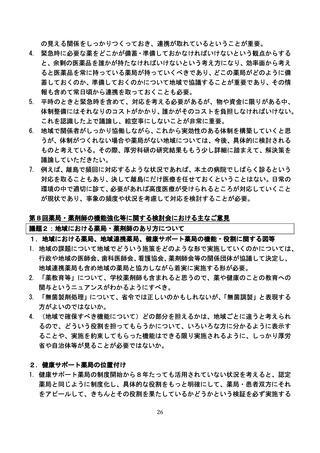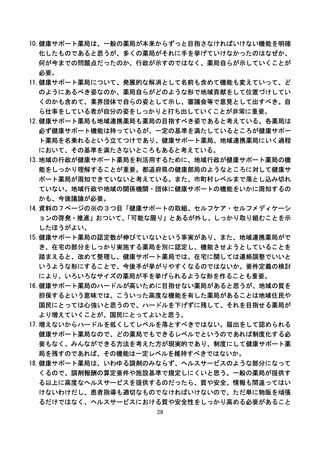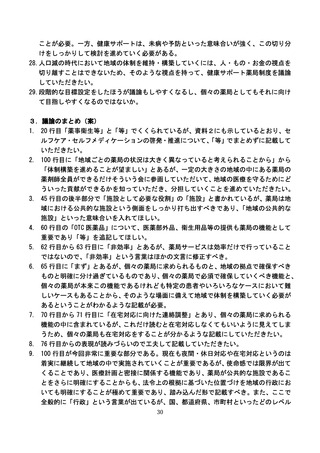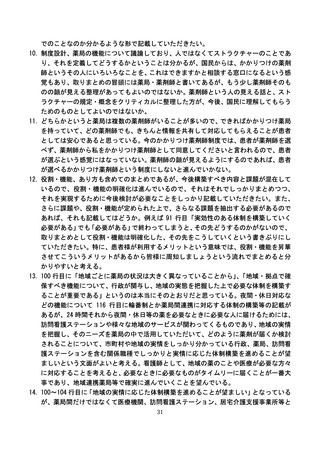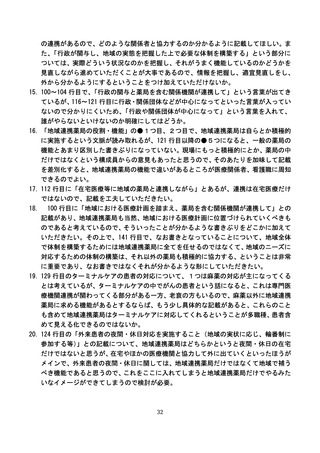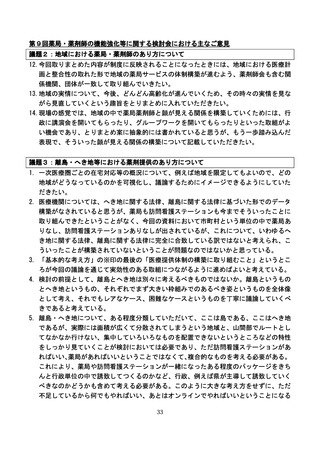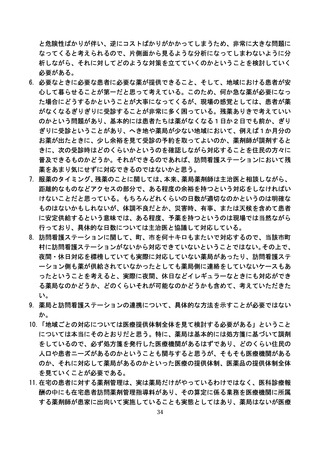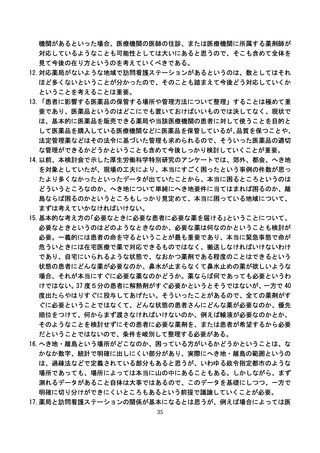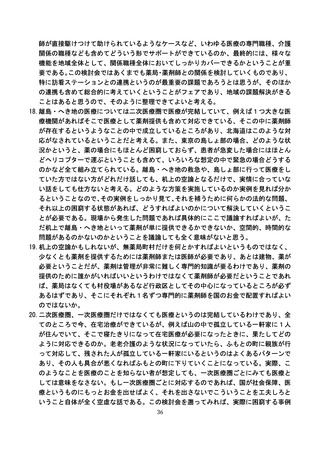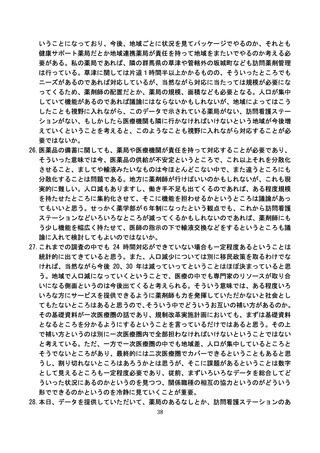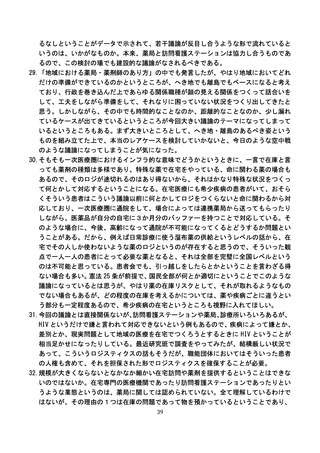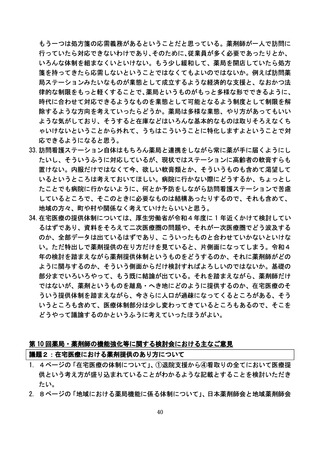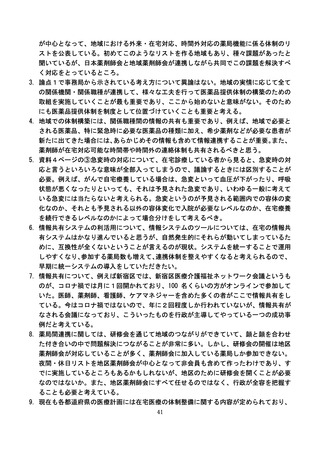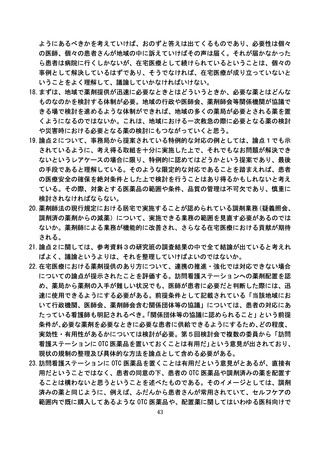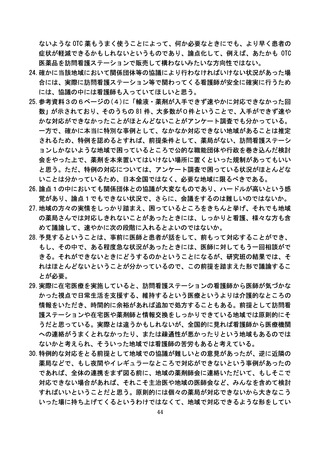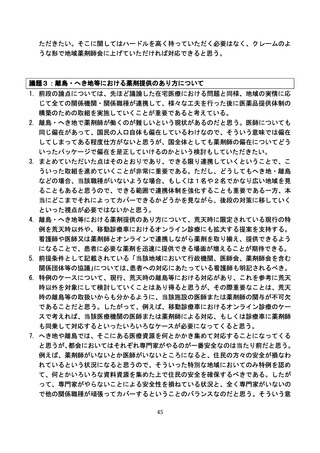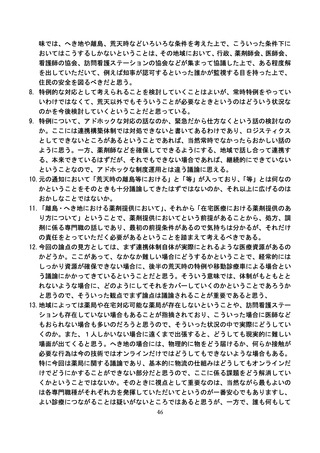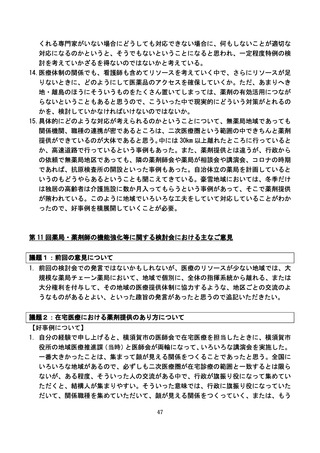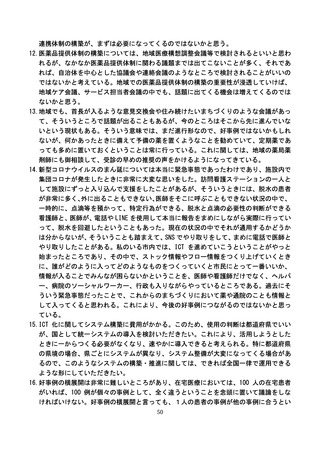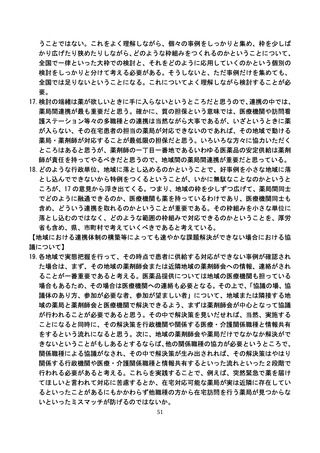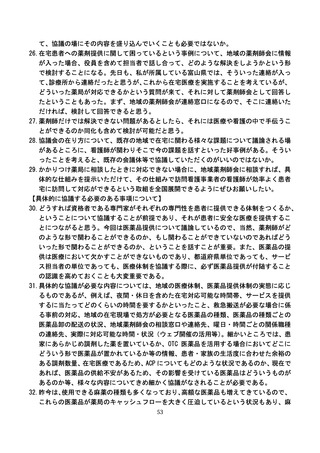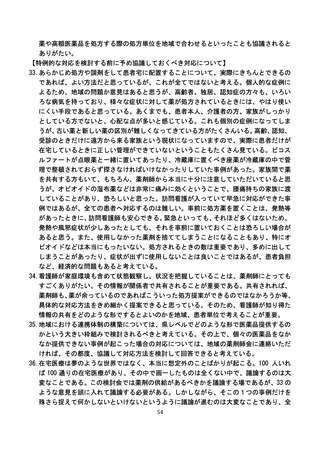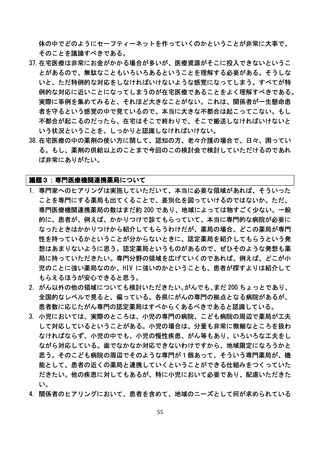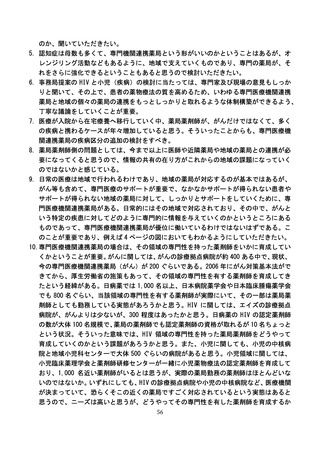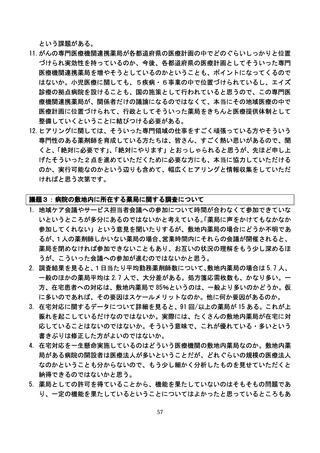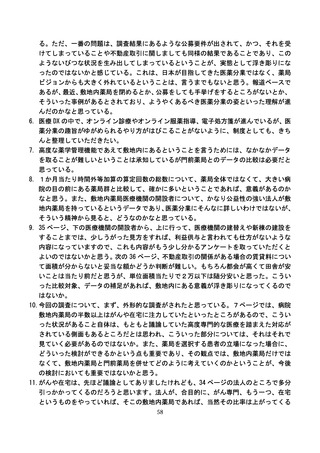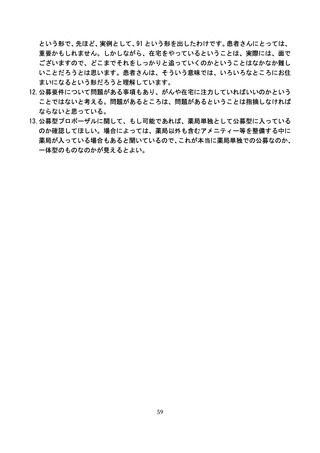よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_第1~11回検討会の主な意見 (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
うことではない。これをよく理解しながら、個々の事例をしっかりと集め、枠を少しば
かり広げたり狭めたりしながら、どのような枠組みをつくれるのかということについて、
全国で一律といった大枠での検討と、それをどのように応用していくのかという個別の
検討をしっかりと分けて考える必要がある。そうしないと、ただ事例だけを集めても、
全国では足りないということになる。これについてよく理解しながら検討することが必
要。
17.検討の端緒は薬が欲しいときに手に入らないというところだと思うので、連携の中では、
薬局間連携が最も重要だと思う。確かに、質の担保という意味では、医療機関や訪問看
護ステーション等々の多職種との連携は当然ながら大事であるが、いざというときに薬
が入らない、その在宅患者の担当の薬局が対応できないのであれば、その地域で動ける
薬局・薬剤師が対応することが最低限の担保だと思う。いろいろな方々に協力いただく
ところはあると思うが、薬剤師の一丁目一番地であるいわゆる医薬品の安定供給は薬剤
師が責任を持ってやるべきだと思うので、地域間の薬局間連携が重要だと思っている。
18.どのような行政単位、地域に落とし込めるのかということで、好事例を小さな地域に落
とし込んでできないから特例をつくるということが、いかに無駄なことなのかというと
ころが、17 の意見から浮き出てくる。つまり、地域の枠を少しずつ広げて、薬局間同士
でどのように融通できるのか、医療機関も薬を持っているわけであり、医療機関同士も
含め、どういう連携を取れるのかということが重要である。その枠組みを小さな単位に
落とし込むのではなく、どのような範囲の枠組みで対応できるのかということを、厚労
省も含め、県、市町村で考えていくべきであると考えている。
【地域における連携体制の構築等によっても速やかな課題解決ができない場合における協
議について】
19.各地域で実態把握を行って、その時点で患者に供給する対応ができない事例が確認され
た場合は、まず、その地域の薬剤師会または近隣地域の薬剤師会への情報、連絡がされ
ることが一番重要であると考える。医薬品提供については地域の医療機関も担っている
場合もあるため、その場合は医療機関への連絡も必要となる。その上で、
「協議の場、協
議体のあり方、参加が必要な者、参加が望ましい者」について、地域または隣接する地
域の薬局と薬剤師会と医療機関で解決できるよう、まずは薬剤師会が中心となって協議
が行われることが必要であると思う。その中で解決策を見いだせれば、当然、実施する
ことになると同時に、その解決策を行政機関や関係する医療・介護関係職種と情報共有
をするという流れになると思う。次に、地域の薬剤師会や薬局だけでなかなか解決がで
きないということがもしあるとするならば、他の関係職種の協力が必要というところで、
関係職種による協議がなされ、その中で解決策が生み出されれば、その解決策はやはり
関係する行政機関や医療・介護関係職種と情報共有するといった流れといった2段階で
行われる必要があると考える。これらを実践することで、例えば、突然緊急で薬を届け
てほしいと言われて対応に苦慮するとか、在宅対応可能な薬局が実は近隣に存在してい
るといったことがあるにもかかわらず他職種の方から在宅訪問を行う薬局が見つからな
いといったミスマッチが防げるのではないか。
51
かり広げたり狭めたりしながら、どのような枠組みをつくれるのかということについて、
全国で一律といった大枠での検討と、それをどのように応用していくのかという個別の
検討をしっかりと分けて考える必要がある。そうしないと、ただ事例だけを集めても、
全国では足りないということになる。これについてよく理解しながら検討することが必
要。
17.検討の端緒は薬が欲しいときに手に入らないというところだと思うので、連携の中では、
薬局間連携が最も重要だと思う。確かに、質の担保という意味では、医療機関や訪問看
護ステーション等々の多職種との連携は当然ながら大事であるが、いざというときに薬
が入らない、その在宅患者の担当の薬局が対応できないのであれば、その地域で動ける
薬局・薬剤師が対応することが最低限の担保だと思う。いろいろな方々に協力いただく
ところはあると思うが、薬剤師の一丁目一番地であるいわゆる医薬品の安定供給は薬剤
師が責任を持ってやるべきだと思うので、地域間の薬局間連携が重要だと思っている。
18.どのような行政単位、地域に落とし込めるのかということで、好事例を小さな地域に落
とし込んでできないから特例をつくるということが、いかに無駄なことなのかというと
ころが、17 の意見から浮き出てくる。つまり、地域の枠を少しずつ広げて、薬局間同士
でどのように融通できるのか、医療機関も薬を持っているわけであり、医療機関同士も
含め、どういう連携を取れるのかということが重要である。その枠組みを小さな単位に
落とし込むのではなく、どのような範囲の枠組みで対応できるのかということを、厚労
省も含め、県、市町村で考えていくべきであると考えている。
【地域における連携体制の構築等によっても速やかな課題解決ができない場合における協
議について】
19.各地域で実態把握を行って、その時点で患者に供給する対応ができない事例が確認され
た場合は、まず、その地域の薬剤師会または近隣地域の薬剤師会への情報、連絡がされ
ることが一番重要であると考える。医薬品提供については地域の医療機関も担っている
場合もあるため、その場合は医療機関への連絡も必要となる。その上で、
「協議の場、協
議体のあり方、参加が必要な者、参加が望ましい者」について、地域または隣接する地
域の薬局と薬剤師会と医療機関で解決できるよう、まずは薬剤師会が中心となって協議
が行われることが必要であると思う。その中で解決策を見いだせれば、当然、実施する
ことになると同時に、その解決策を行政機関や関係する医療・介護関係職種と情報共有
をするという流れになると思う。次に、地域の薬剤師会や薬局だけでなかなか解決がで
きないということがもしあるとするならば、他の関係職種の協力が必要というところで、
関係職種による協議がなされ、その中で解決策が生み出されれば、その解決策はやはり
関係する行政機関や医療・介護関係職種と情報共有するといった流れといった2段階で
行われる必要があると考える。これらを実践することで、例えば、突然緊急で薬を届け
てほしいと言われて対応に苦慮するとか、在宅対応可能な薬局が実は近隣に存在してい
るといったことがあるにもかかわらず他職種の方から在宅訪問を行う薬局が見つからな
いといったミスマッチが防げるのではないか。
51