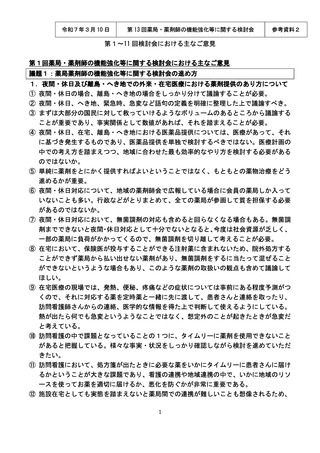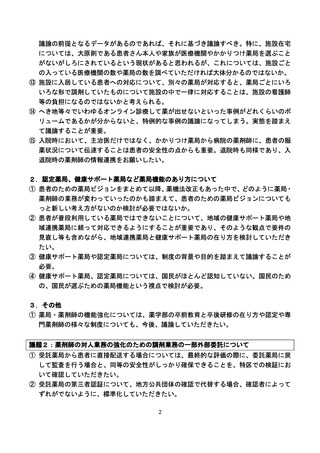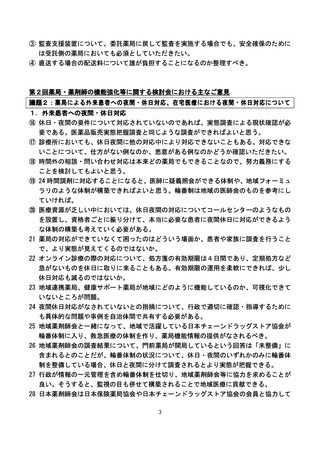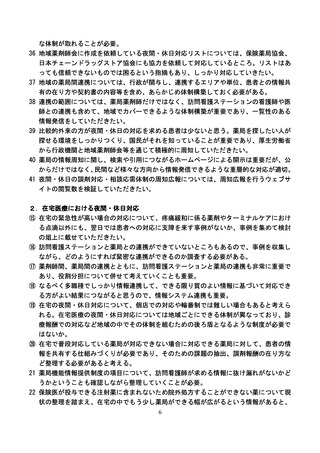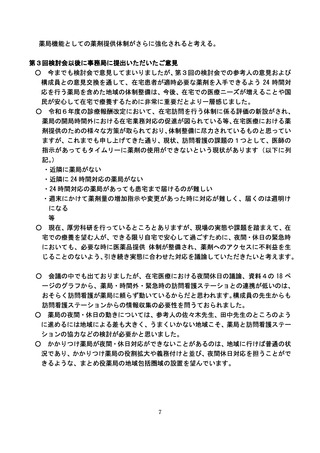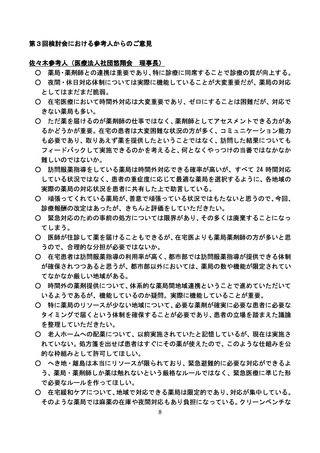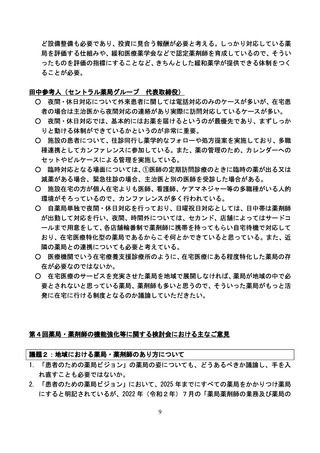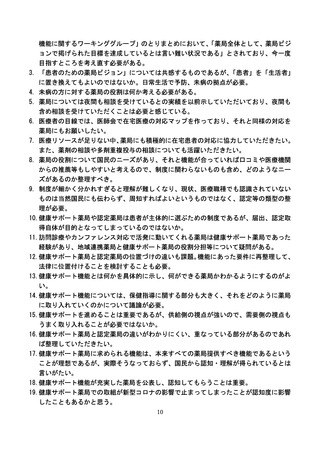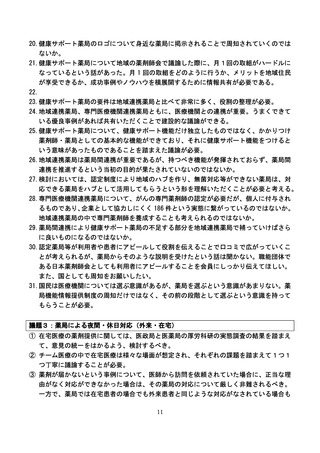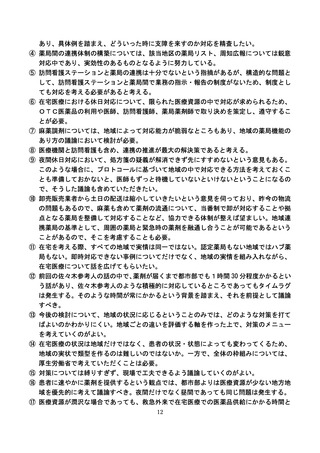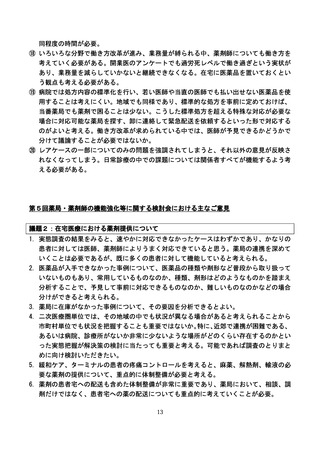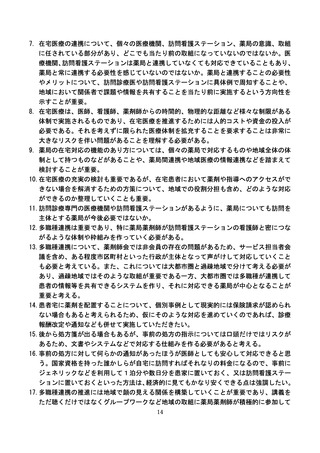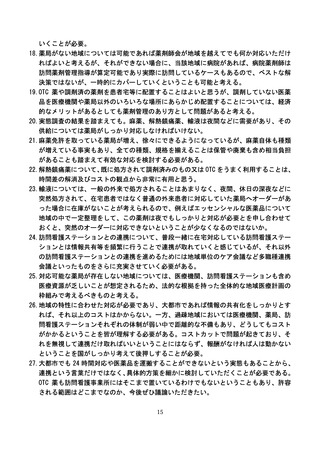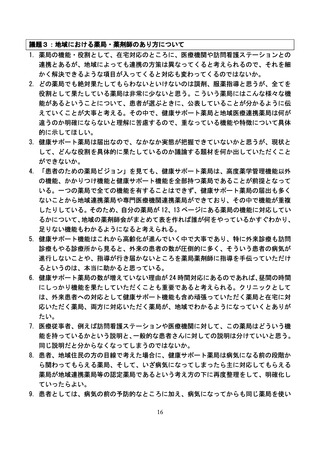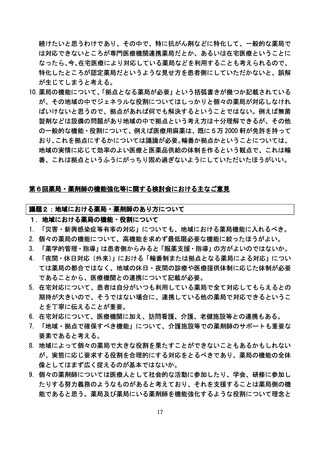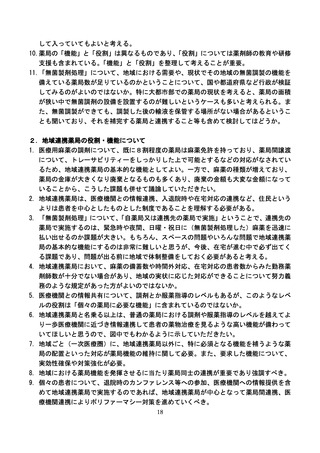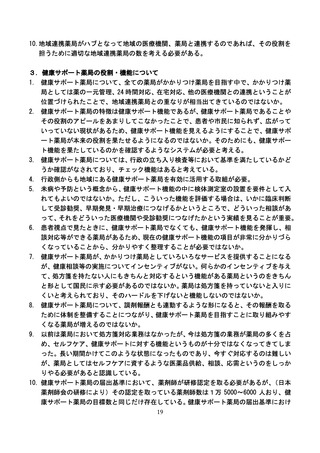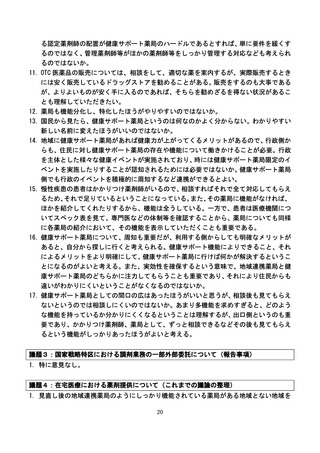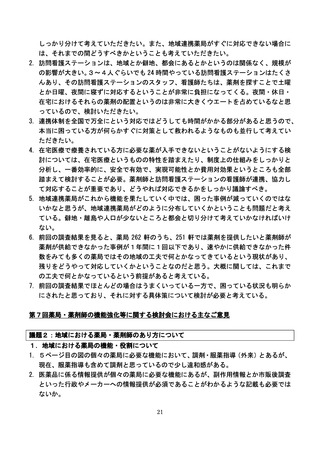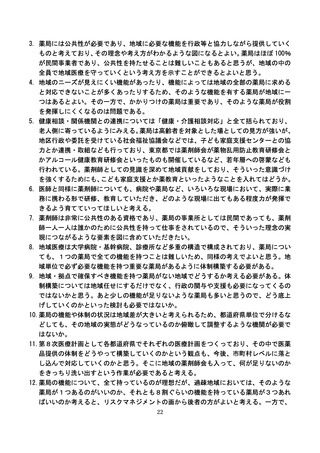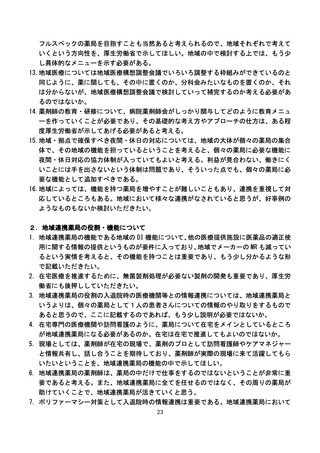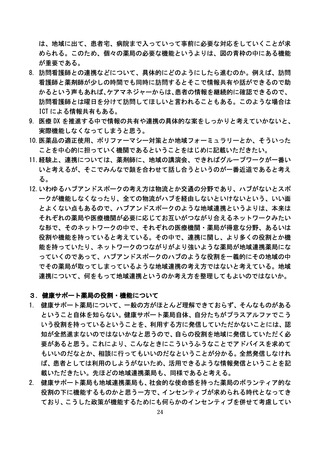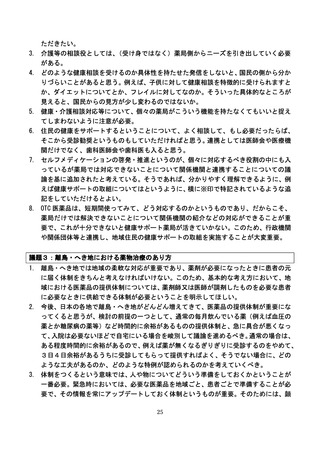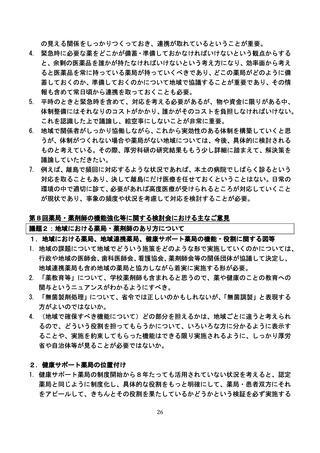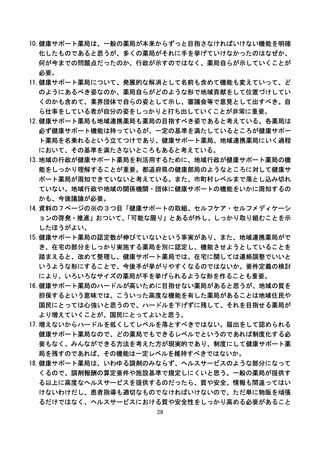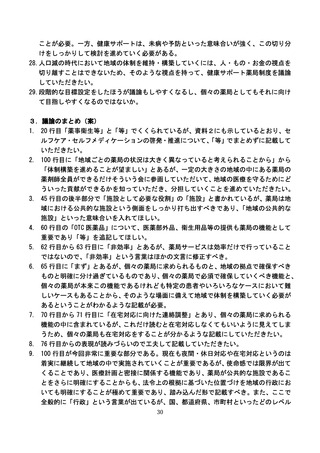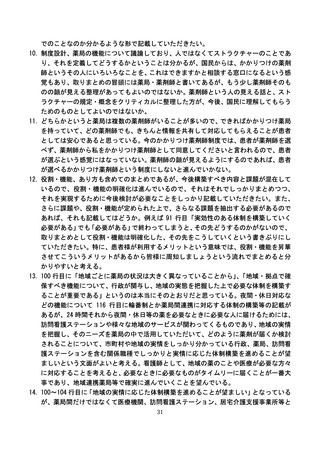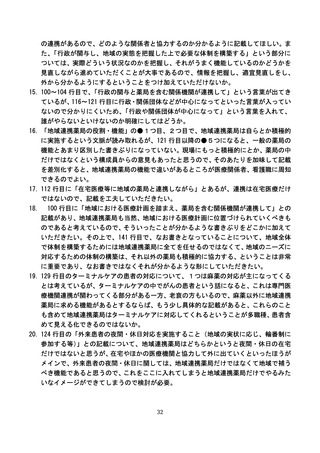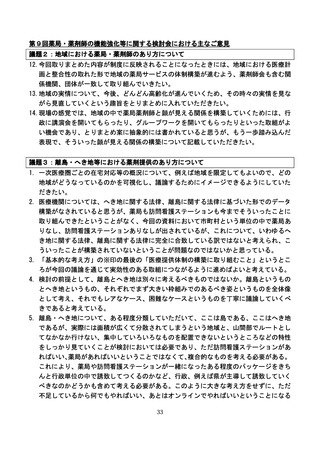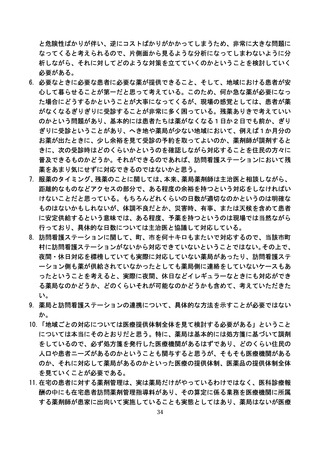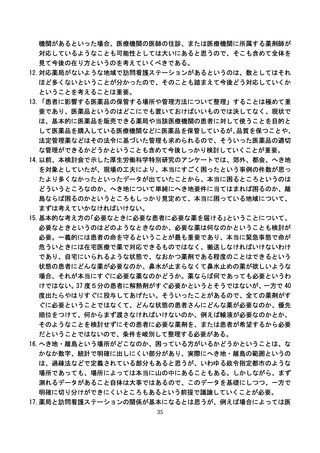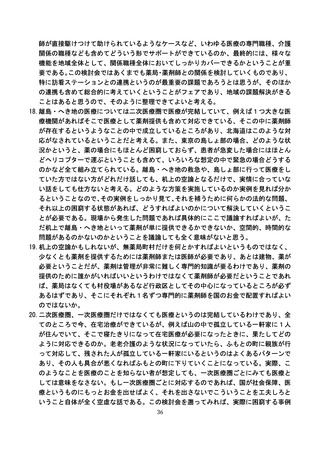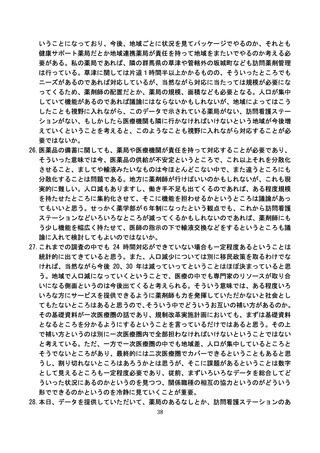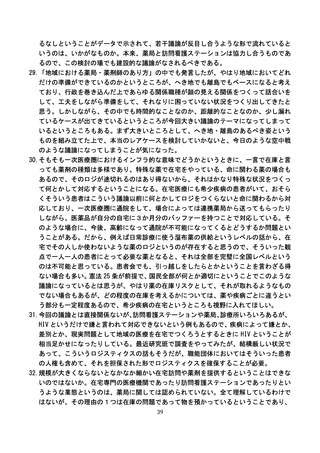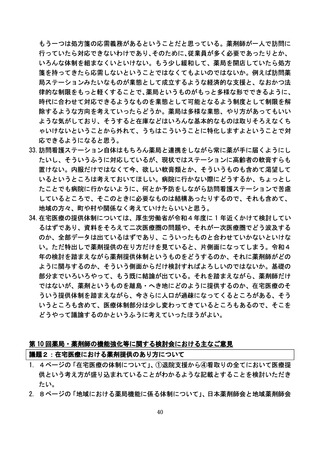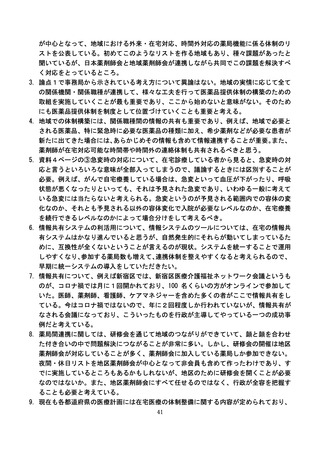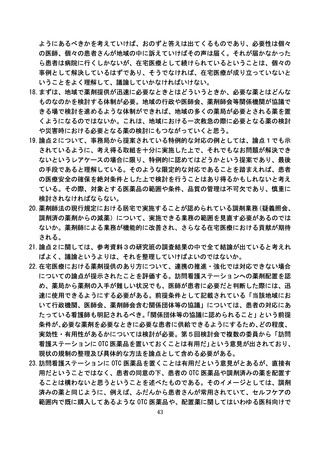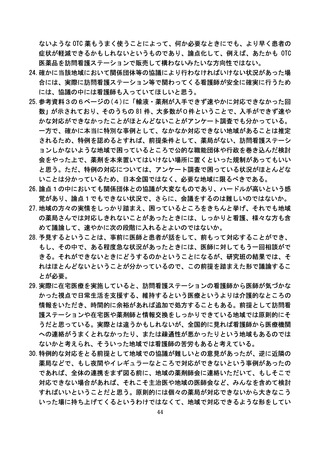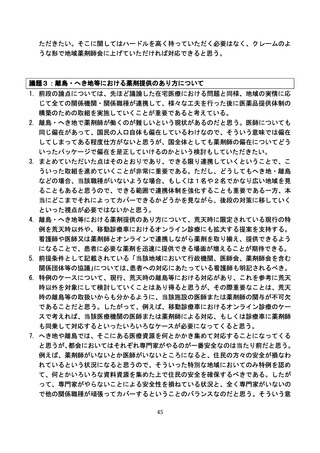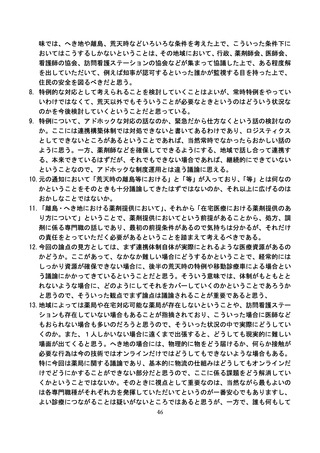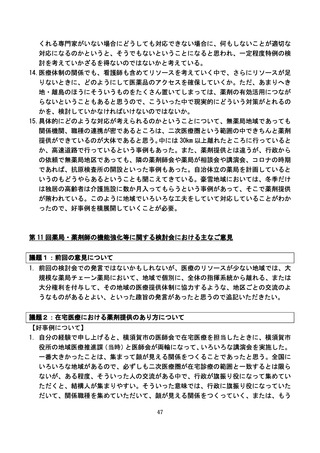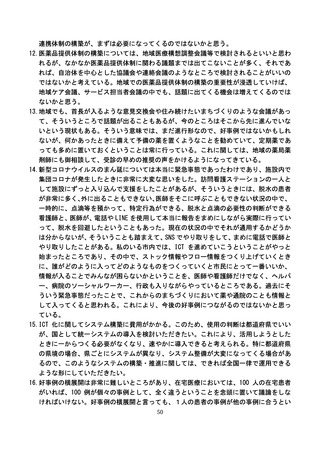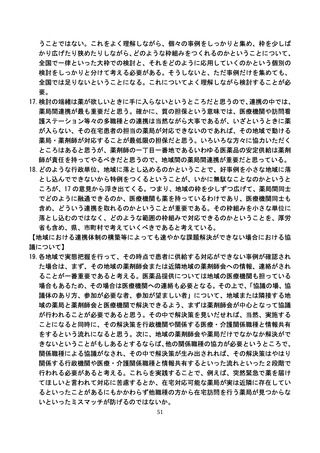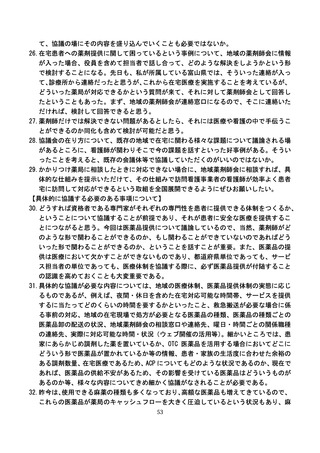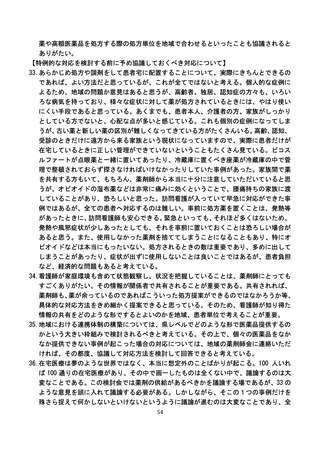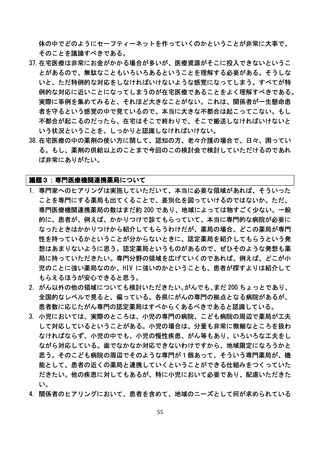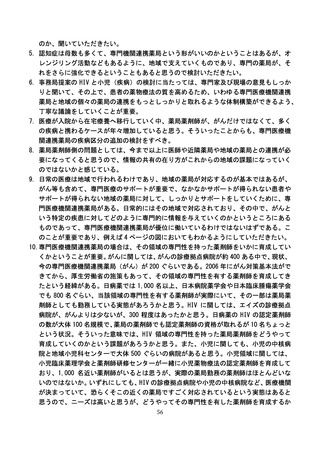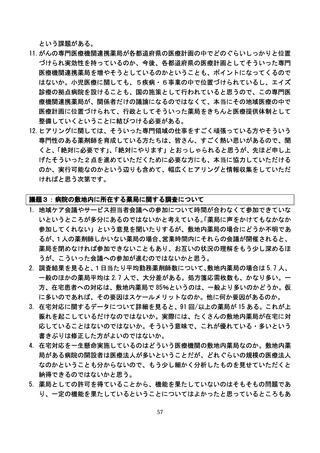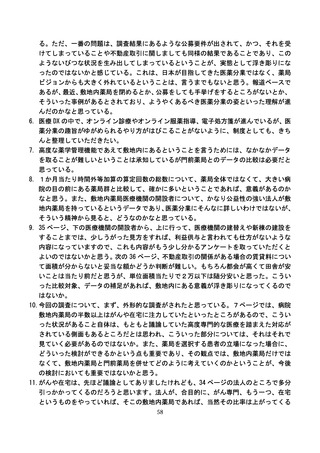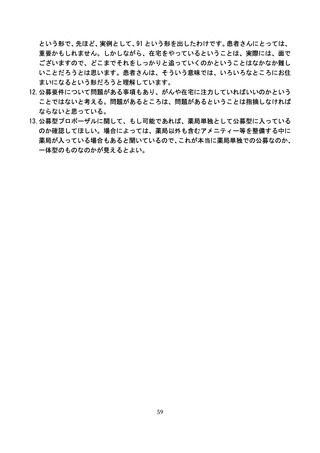よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_第1~11回検討会の主な意見 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
7. 日本保険薬局協会で地域連携の手引を出しており、その後ろに、いわゆる地域医療連携
の事例集ということで、5事例しかないが掲載している。地域の中核の病院がハブとな
りながら、薬剤部も参加して、地域の在宅のクリニックの医師、薬局と連携し、地域の
基幹病院だけではなく行政も関わっているといった多職種連携の事例があった。
8. サービス担当者会議で、患者の個別の案件に関してのみ、医療機関と薬局で調剤した薬
剤の情報共有等がなされているが、現在、医薬品の供給が不安定な状況であり、個別案
件ではなく、地域に広がったら非常に有益なことであり、安定した薬物治療に貢献でき
るのではないかと考えている。
9. 在宅療養において、患者宅訪問の後に、報告書を作成しており、その提出先は、居宅療
養管理指導の算定の要件において、処方医とケアマネジャーとなっているが、訪問看護
ステーションの訪問看護師にも薬局薬剤師が自発的に送ることによって訪問看護師も薬
剤の使用状況や管理の把握・理解が進んで、結果として、患者の在宅医療全体の質のア
ップにつながっているという事例があろうかと思う。
10.薬のことは全て薬剤師で完結させるということだけではなく、例えば、飲み忘れの患者、
飲み過ぎの患者のような事例は多くあるが、このような場合に、多職種が曜日をずらし
て訪問できないかと相談して、何時までに飲めていなかったらその薬は服用を促す、た
だし、何時を過ぎたらスキップするといった、判断を伴わない作業としての指示も必要
になってくると思う。このような機械的な作業となる依頼内容を共有することも必要に
なってくるのではないか。
11.自分が、最近訪問した事例において、年末年始をこれから迎えるに当たって、患者の家
族から、いざという場合に備えて、薬を予備として持っておきたい、次回医師が訪問す
る際にそれをお願いしておきたいという話が出てきた。この患者は要介護5の方で、
「い
ざという場合」は、急な発熱などを意味しているということで、肺炎や尿路感染症など
の感染症を引き起こした際の抗生剤や解熱剤をあらかじめ持っておきたいという希望で
あった。いい機会だったので、あらかじめ薬を備えておきたいと思う理由について伺っ
たところ、命に関わるほどの問題でなかったとしても薬物療法のタイミングは逃したく
ないということで、早く対処することで、その状態の悪化や治療の長期化を防ぎたいと
いうことが一番の希望であり、何かいつもと違うなと感じた場合にはかかりつけの在宅
医に連絡してその医師の指示で速やかな使用開始につなげたいという考えであった。さ
らに、前もって家にあって、日頃から見たり手に触れていて、また、説明を受けておく
と、緊急時により落ち着いて対処ができるのではないかという考えであった。このよう
な患者の家族の意見も含めて、関係する多職種が情報共有をして、評価して、その結果、
どのように対応したかということも含めて、多職種でまた情報共有がされるような体制
の構築をするべきではないかと思う。この患者のケースでは、家族の方がこのような考
えを持っているので、これまで臨時の処方があった場合には薬局が薬を届けに伺ってい
たが、何時だったら今日は家族の手が空いて取りに行ける、何時だったらヘルパーが取
りに行ってくれるということで、必ず連絡を薬局にくれて、そのときに最短で届けられ
るような方法を取ってきたといった経緯もある。医療職だけではなく、介護職も含めた
49
の事例集ということで、5事例しかないが掲載している。地域の中核の病院がハブとな
りながら、薬剤部も参加して、地域の在宅のクリニックの医師、薬局と連携し、地域の
基幹病院だけではなく行政も関わっているといった多職種連携の事例があった。
8. サービス担当者会議で、患者の個別の案件に関してのみ、医療機関と薬局で調剤した薬
剤の情報共有等がなされているが、現在、医薬品の供給が不安定な状況であり、個別案
件ではなく、地域に広がったら非常に有益なことであり、安定した薬物治療に貢献でき
るのではないかと考えている。
9. 在宅療養において、患者宅訪問の後に、報告書を作成しており、その提出先は、居宅療
養管理指導の算定の要件において、処方医とケアマネジャーとなっているが、訪問看護
ステーションの訪問看護師にも薬局薬剤師が自発的に送ることによって訪問看護師も薬
剤の使用状況や管理の把握・理解が進んで、結果として、患者の在宅医療全体の質のア
ップにつながっているという事例があろうかと思う。
10.薬のことは全て薬剤師で完結させるということだけではなく、例えば、飲み忘れの患者、
飲み過ぎの患者のような事例は多くあるが、このような場合に、多職種が曜日をずらし
て訪問できないかと相談して、何時までに飲めていなかったらその薬は服用を促す、た
だし、何時を過ぎたらスキップするといった、判断を伴わない作業としての指示も必要
になってくると思う。このような機械的な作業となる依頼内容を共有することも必要に
なってくるのではないか。
11.自分が、最近訪問した事例において、年末年始をこれから迎えるに当たって、患者の家
族から、いざという場合に備えて、薬を予備として持っておきたい、次回医師が訪問す
る際にそれをお願いしておきたいという話が出てきた。この患者は要介護5の方で、
「い
ざという場合」は、急な発熱などを意味しているということで、肺炎や尿路感染症など
の感染症を引き起こした際の抗生剤や解熱剤をあらかじめ持っておきたいという希望で
あった。いい機会だったので、あらかじめ薬を備えておきたいと思う理由について伺っ
たところ、命に関わるほどの問題でなかったとしても薬物療法のタイミングは逃したく
ないということで、早く対処することで、その状態の悪化や治療の長期化を防ぎたいと
いうことが一番の希望であり、何かいつもと違うなと感じた場合にはかかりつけの在宅
医に連絡してその医師の指示で速やかな使用開始につなげたいという考えであった。さ
らに、前もって家にあって、日頃から見たり手に触れていて、また、説明を受けておく
と、緊急時により落ち着いて対処ができるのではないかという考えであった。このよう
な患者の家族の意見も含めて、関係する多職種が情報共有をして、評価して、その結果、
どのように対応したかということも含めて、多職種でまた情報共有がされるような体制
の構築をするべきではないかと思う。この患者のケースでは、家族の方がこのような考
えを持っているので、これまで臨時の処方があった場合には薬局が薬を届けに伺ってい
たが、何時だったら今日は家族の手が空いて取りに行ける、何時だったらヘルパーが取
りに行ってくれるということで、必ず連絡を薬局にくれて、そのときに最短で届けられ
るような方法を取ってきたといった経緯もある。医療職だけではなく、介護職も含めた
49