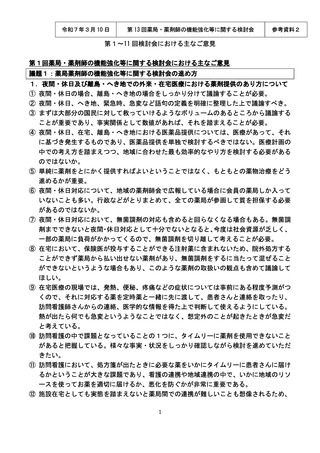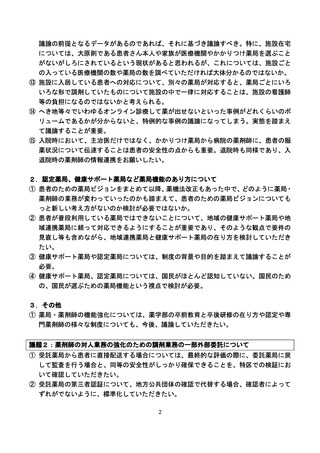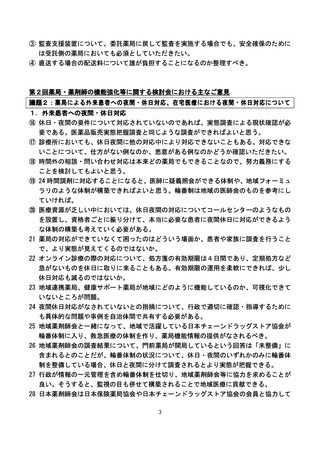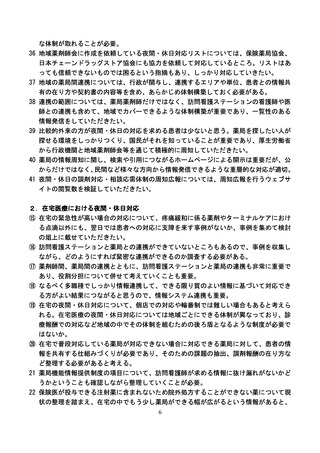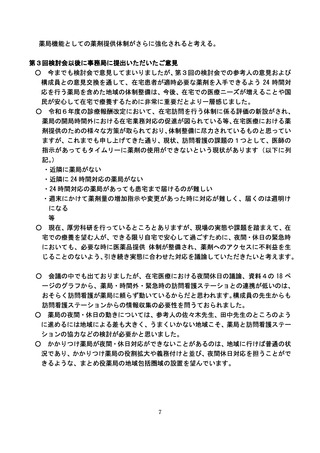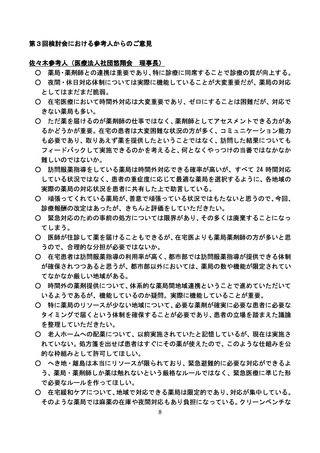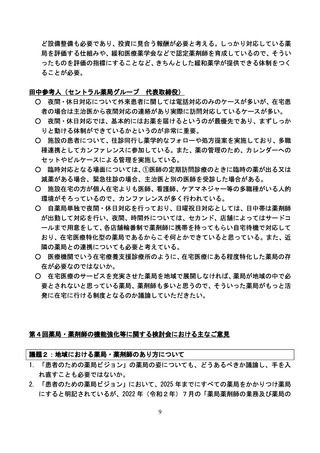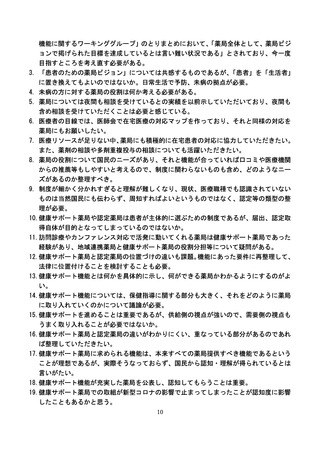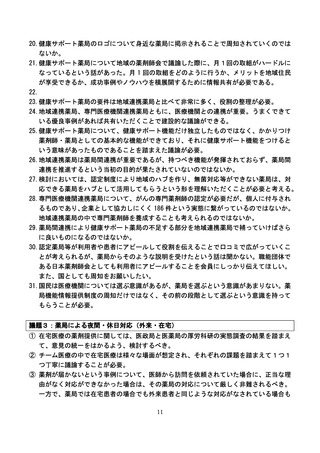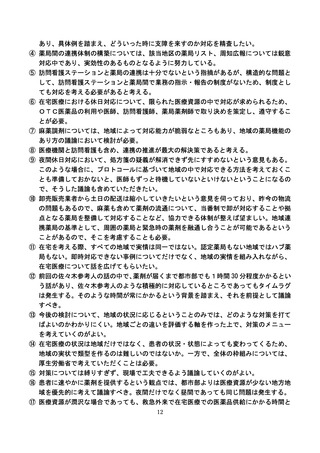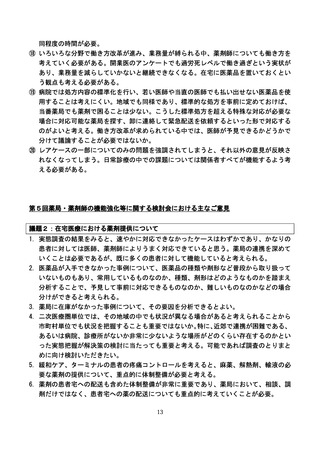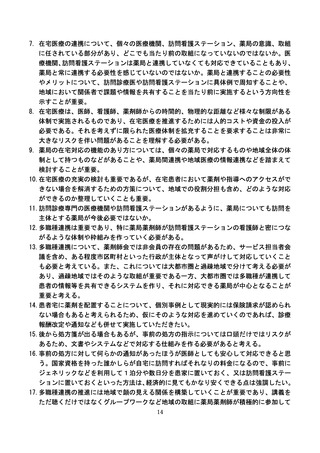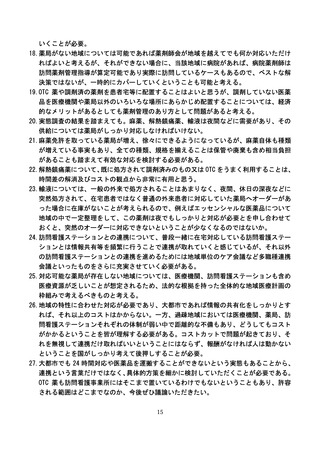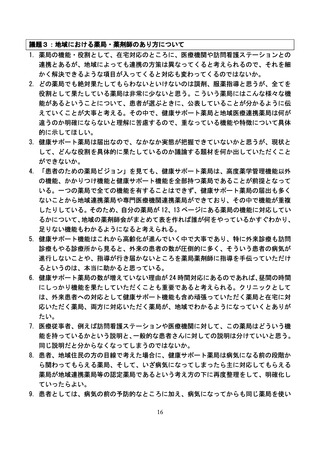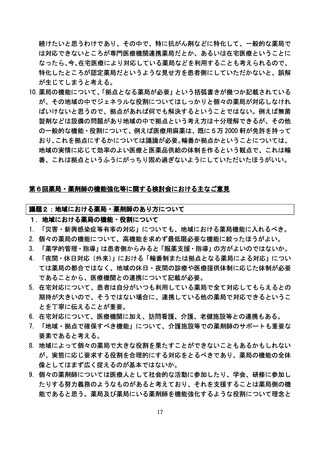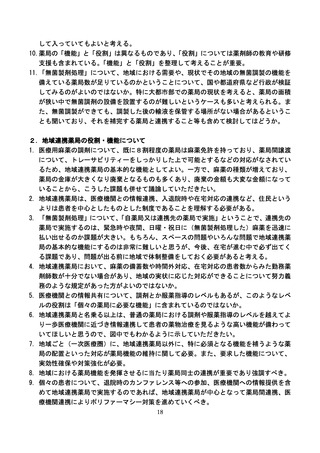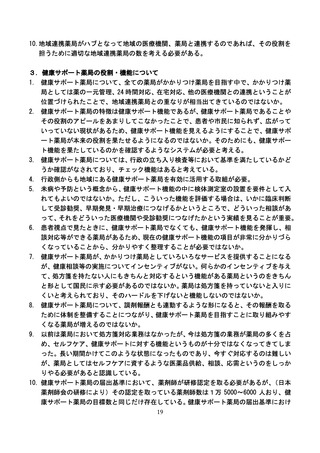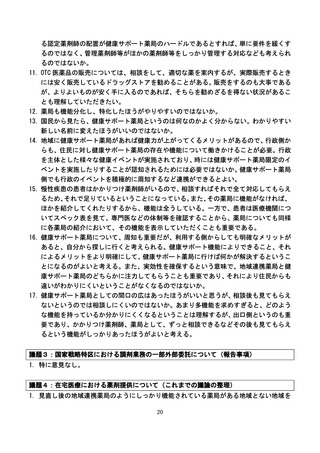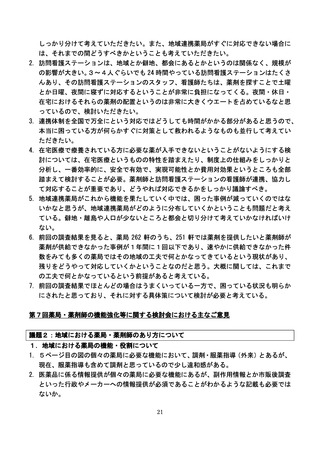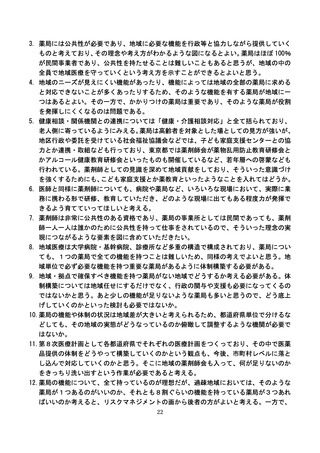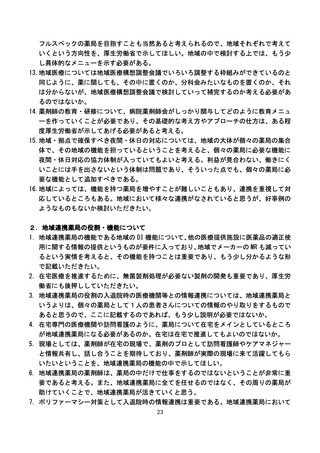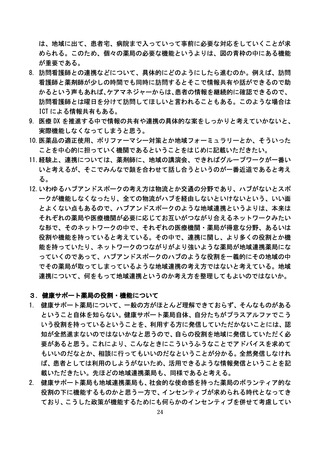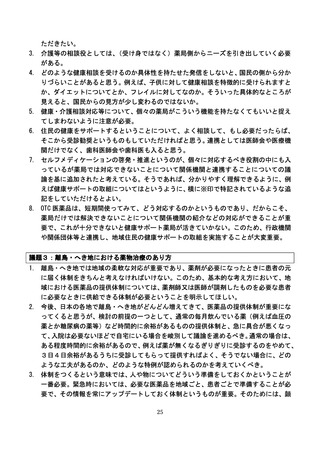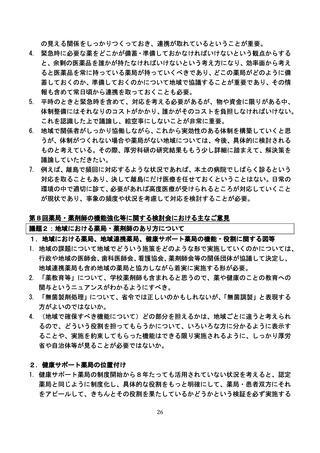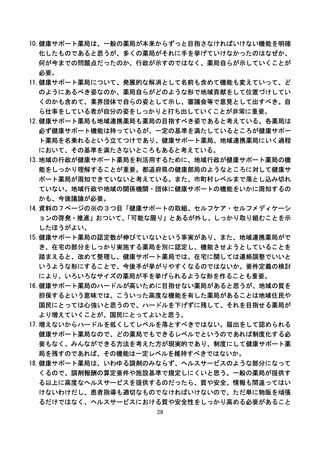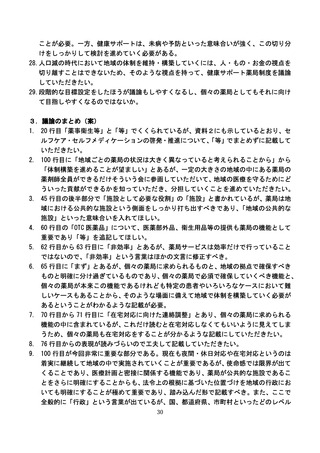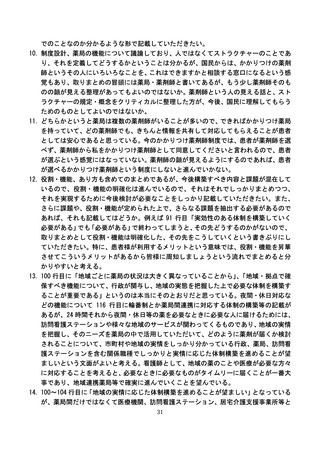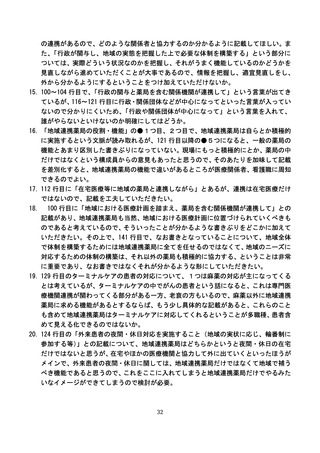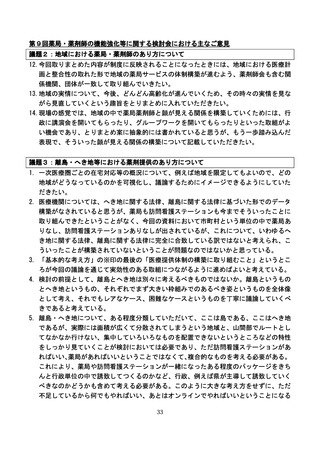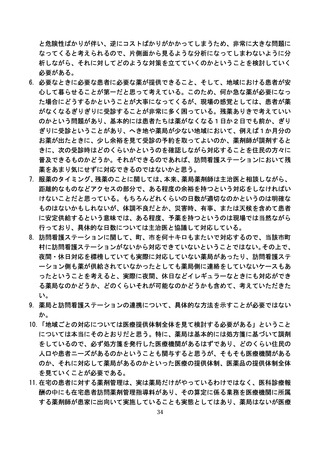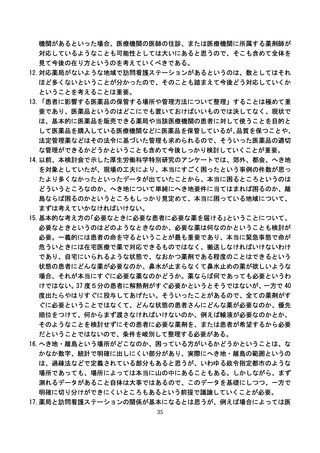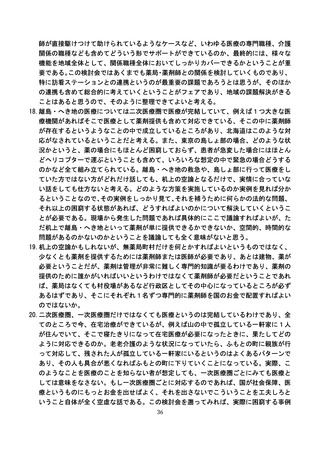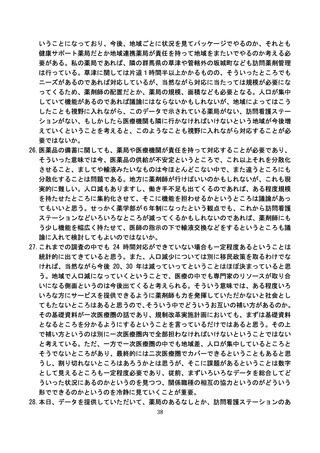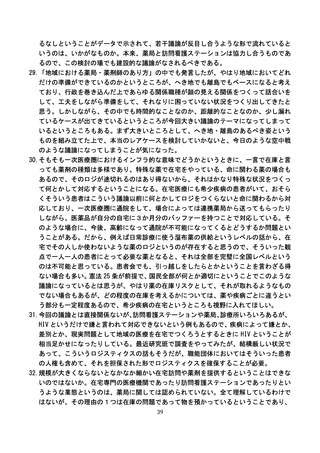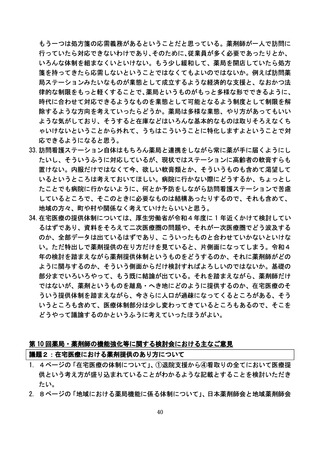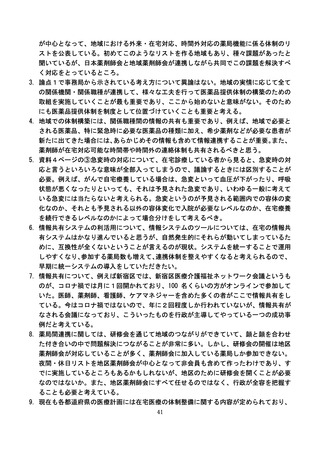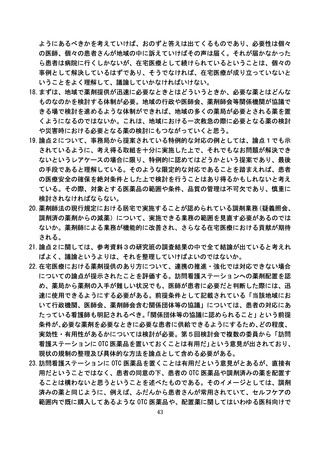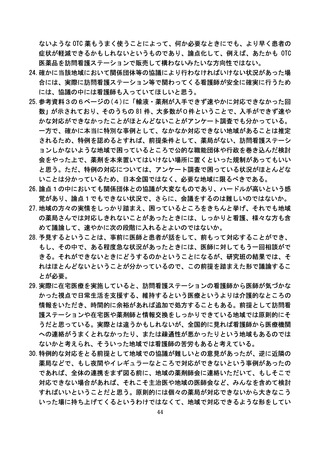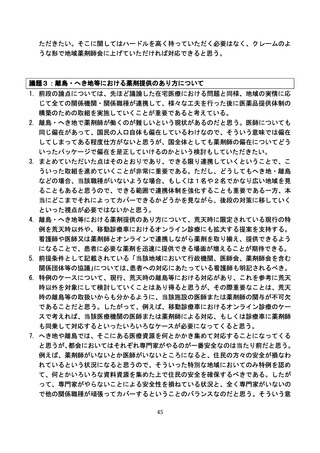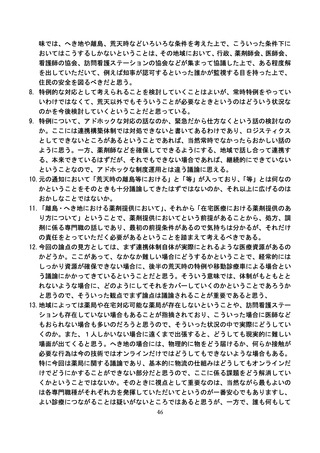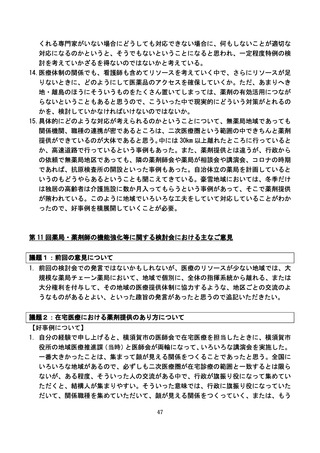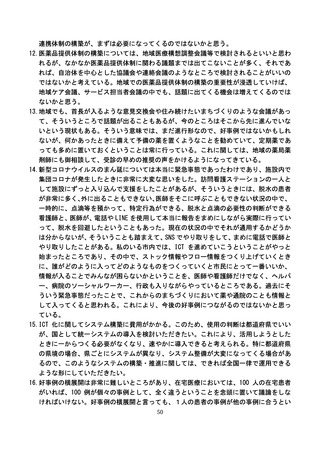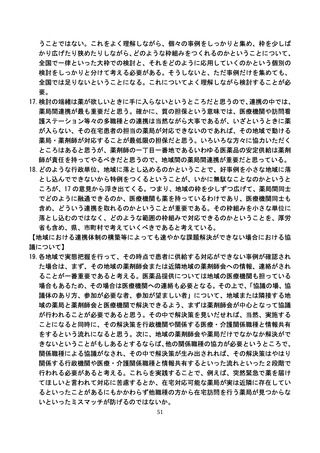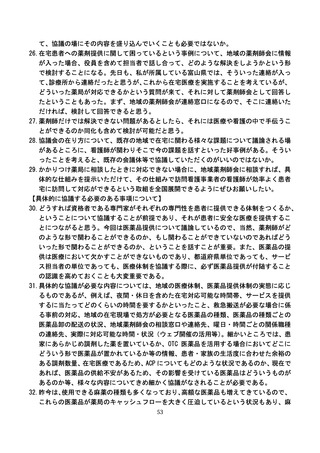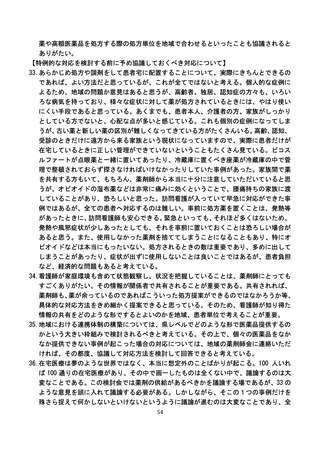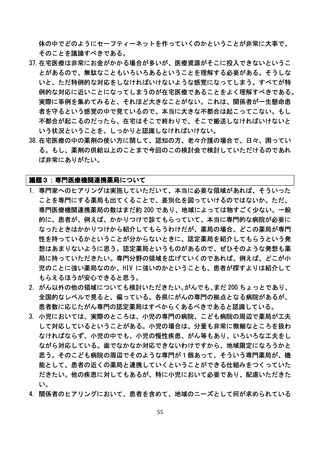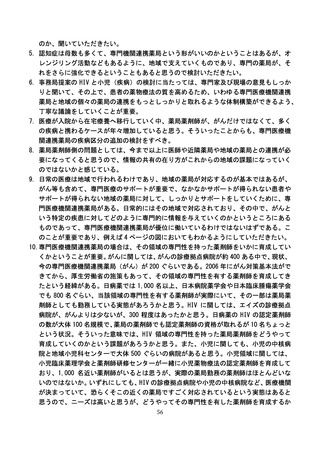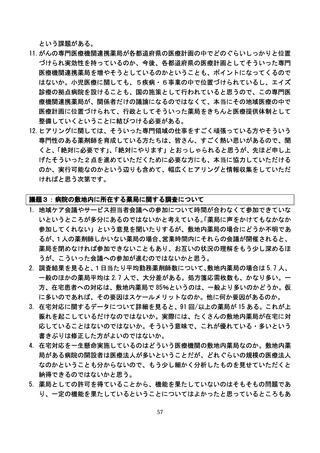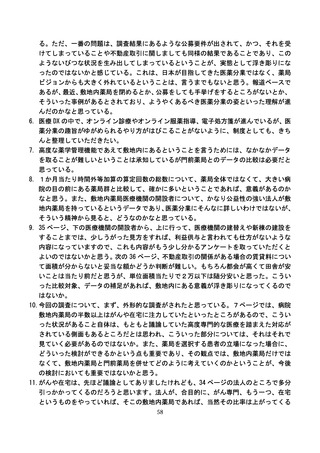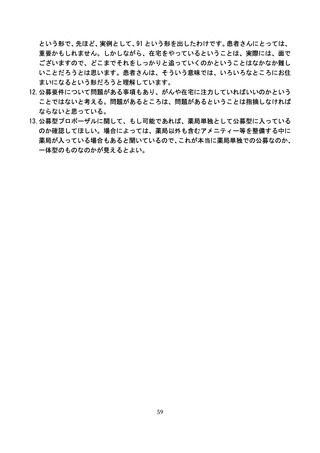よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_第1~11回検討会の主な意見 (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て、協議の場にその内容を盛り込んでいくことも必要ではないか。
26.在宅患者への薬剤提供に関して困っているという事例について、地域の薬剤師会に情報
が入った場合、役員を含めて担当者で話し合って、どのような解決をしようかという形
で検討することになる。先日も、私が所属している富山県では、そういった連絡が入っ
て、診療所から連絡だったと思うが、これから在宅医療を実施することを考えているが、
どういった薬局が対応できるかという質問が来て、それに対して薬剤師会として回答し
たということもあった。まず、地域の薬剤師会が連絡窓口になるので、そこに連絡いた
だければ、検討して回答できると思う。
27.薬剤師だけでは解決できない問題があるとしたら、それには医療や看護の中で手伝うこ
とができるのか同化も含めて検討が可能だと思う。
28.協議会の在り方について、既存の地域で在宅に関わる様々な課題について議論される場
があるところに、看護師が関わりそこで今の課題を話すといった好事例がある。そうい
ったことを考えると、既存の会議体等で協議していただくのがいいのではないか。
29.かかりつけ薬局に相談したときに対応できない場合に、地域薬剤師会に相談すれば、具
体的な仕組みを提示いただけて、その仕組みで訪問看護事業者の看護師が効率よく患者
宅に訪問して対応ができるという取組を全国展開できるようにぜひお願いしたい。
【具体的に協議する必要のある事項について】
30.どうすれば資格者である専門家がそれぞれの専門性を患者に提供できる体制をつくるか、
ということについて協議することが前提であり、それが患者に安全な医療を提供するこ
とにつながると思う。今回は医薬品提供について議論しているので、当然、薬剤師がど
のような形で関わることができるのか、もし関わることができていないのであればどう
いった形で関わることができるのか、ということを話すことが重要。また、医薬品の提
供は医療において欠かすことができないものであり、都道府県単位であっても、サービ
ス担当者の単位であっても、医療体制を協議する際に、必ず医薬品提供が付随すること
の認識を高めておくことも大変重要である。
31.具体的な協議が必要な内容については、地域の医療体制、医薬品提供体制の実態に応じ
るものであるが、例えば、夜間・休日を含めた在宅対応可能な時間帯、サービスを提供
するに当たってどのくらいの時間を要するかといったこと、救急搬送が必要な場合に係
る事前の対応、地域の在宅現場で処方が必要となる医薬品の種類、医薬品の種類ごとの
医薬品卸の配送の状況、地域薬剤師会の相談窓口や連絡先、曜日・時間ごとの関係職種
の連絡先、実際に対応可能な時間・状況(ウェブ開催の活用等)。細かいところでは、患
家にあらかじめ調剤した薬を置いているか、OTC 医薬品を活用する場合においてどこに
どういう形で医薬品が置かれているか等の情報、患者・家族の生活度に合わせた余裕の
ある調剤数量、在宅医療であるため、ACP についてもどのような状況であるのか、現在で
あれば、医薬品の供給不安があるため、その影響を受けている医薬品はどういうものが
あるのか等、様々な内容についてきめ細かく協議がなされることが必要である。
32.昨今は、使用できる麻薬の種類も多くなっており、高額な医薬品も増えてきているので、
これらの医薬品が薬局のキャッシュフローを大きく圧迫しているという状況もあり、麻
53
26.在宅患者への薬剤提供に関して困っているという事例について、地域の薬剤師会に情報
が入った場合、役員を含めて担当者で話し合って、どのような解決をしようかという形
で検討することになる。先日も、私が所属している富山県では、そういった連絡が入っ
て、診療所から連絡だったと思うが、これから在宅医療を実施することを考えているが、
どういった薬局が対応できるかという質問が来て、それに対して薬剤師会として回答し
たということもあった。まず、地域の薬剤師会が連絡窓口になるので、そこに連絡いた
だければ、検討して回答できると思う。
27.薬剤師だけでは解決できない問題があるとしたら、それには医療や看護の中で手伝うこ
とができるのか同化も含めて検討が可能だと思う。
28.協議会の在り方について、既存の地域で在宅に関わる様々な課題について議論される場
があるところに、看護師が関わりそこで今の課題を話すといった好事例がある。そうい
ったことを考えると、既存の会議体等で協議していただくのがいいのではないか。
29.かかりつけ薬局に相談したときに対応できない場合に、地域薬剤師会に相談すれば、具
体的な仕組みを提示いただけて、その仕組みで訪問看護事業者の看護師が効率よく患者
宅に訪問して対応ができるという取組を全国展開できるようにぜひお願いしたい。
【具体的に協議する必要のある事項について】
30.どうすれば資格者である専門家がそれぞれの専門性を患者に提供できる体制をつくるか、
ということについて協議することが前提であり、それが患者に安全な医療を提供するこ
とにつながると思う。今回は医薬品提供について議論しているので、当然、薬剤師がど
のような形で関わることができるのか、もし関わることができていないのであればどう
いった形で関わることができるのか、ということを話すことが重要。また、医薬品の提
供は医療において欠かすことができないものであり、都道府県単位であっても、サービ
ス担当者の単位であっても、医療体制を協議する際に、必ず医薬品提供が付随すること
の認識を高めておくことも大変重要である。
31.具体的な協議が必要な内容については、地域の医療体制、医薬品提供体制の実態に応じ
るものであるが、例えば、夜間・休日を含めた在宅対応可能な時間帯、サービスを提供
するに当たってどのくらいの時間を要するかといったこと、救急搬送が必要な場合に係
る事前の対応、地域の在宅現場で処方が必要となる医薬品の種類、医薬品の種類ごとの
医薬品卸の配送の状況、地域薬剤師会の相談窓口や連絡先、曜日・時間ごとの関係職種
の連絡先、実際に対応可能な時間・状況(ウェブ開催の活用等)。細かいところでは、患
家にあらかじめ調剤した薬を置いているか、OTC 医薬品を活用する場合においてどこに
どういう形で医薬品が置かれているか等の情報、患者・家族の生活度に合わせた余裕の
ある調剤数量、在宅医療であるため、ACP についてもどのような状況であるのか、現在で
あれば、医薬品の供給不安があるため、その影響を受けている医薬品はどういうものが
あるのか等、様々な内容についてきめ細かく協議がなされることが必要である。
32.昨今は、使用できる麻薬の種類も多くなっており、高額な医薬品も増えてきているので、
これらの医薬品が薬局のキャッシュフローを大きく圧迫しているという状況もあり、麻
53