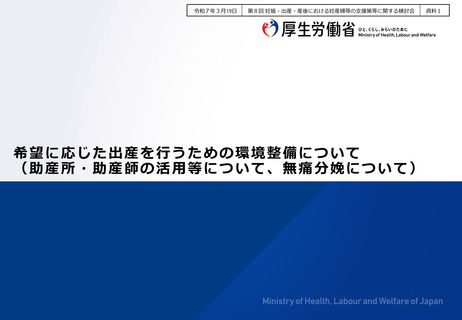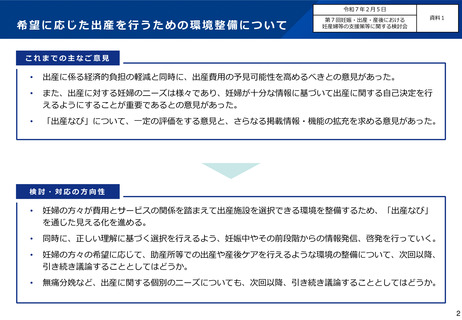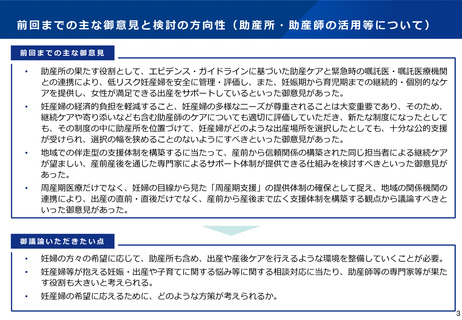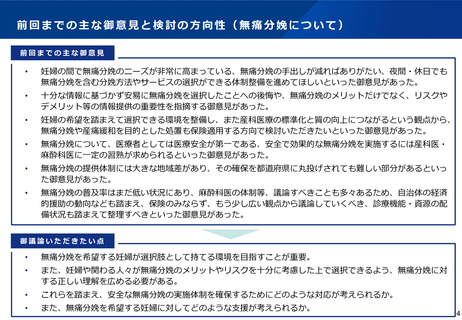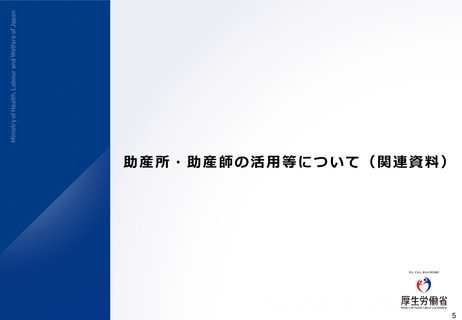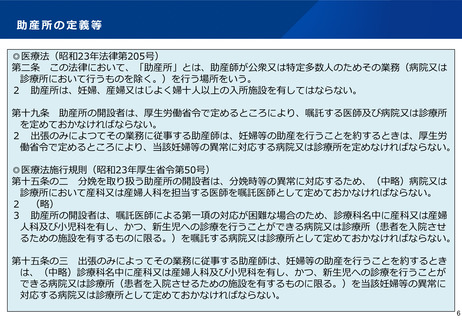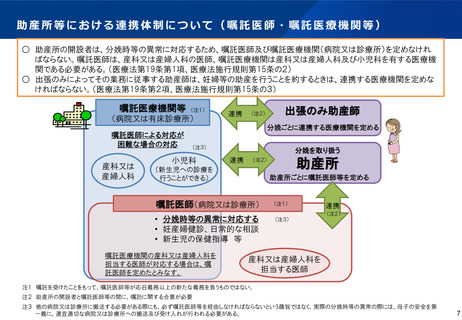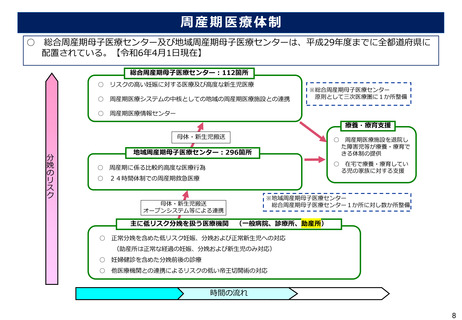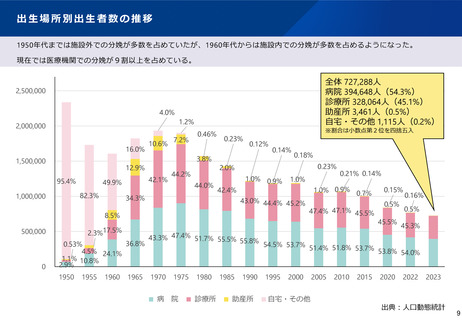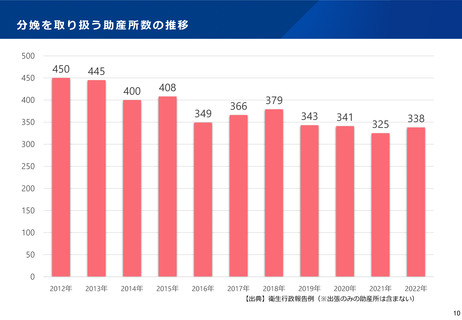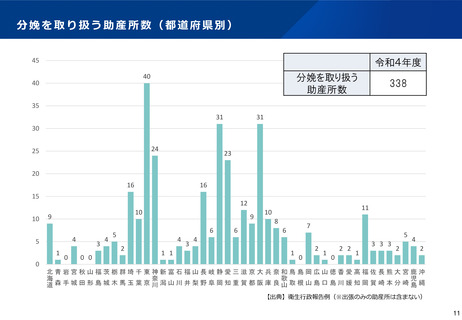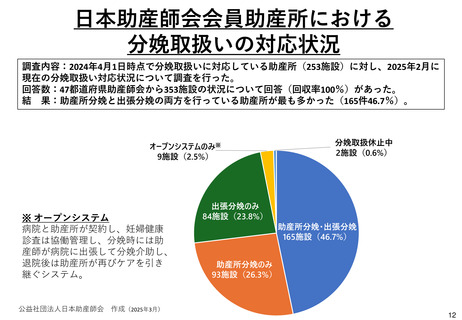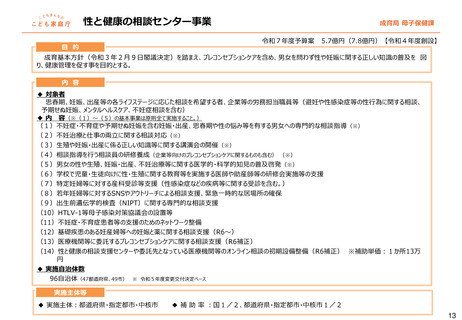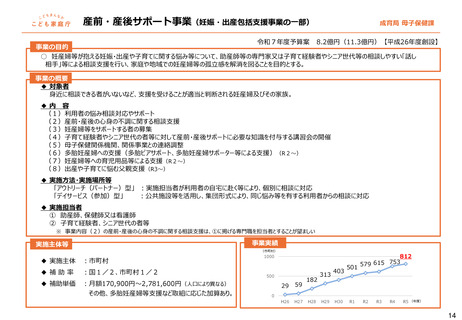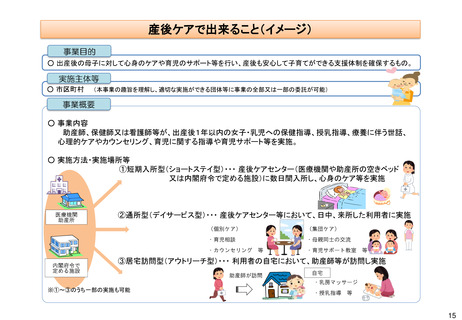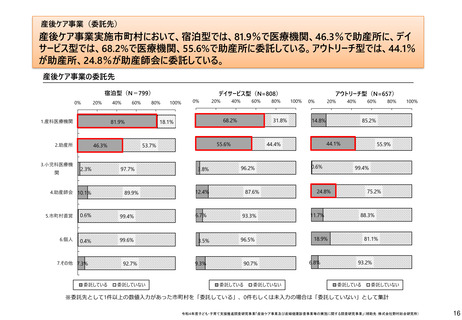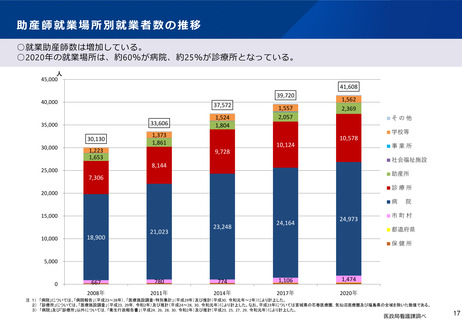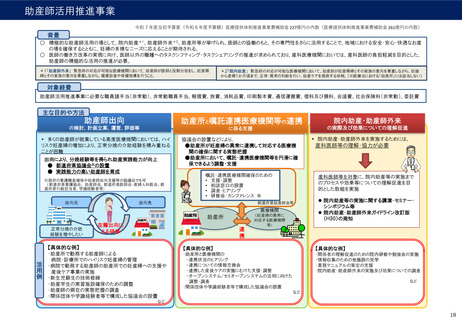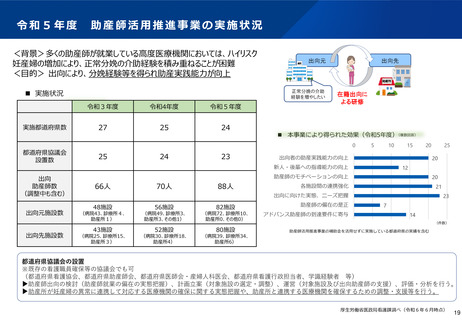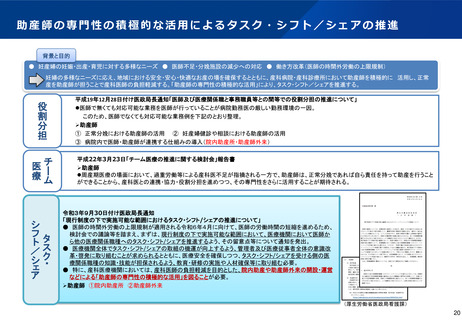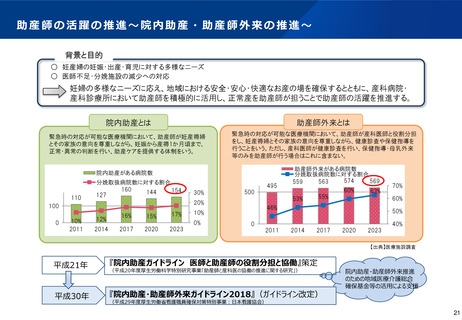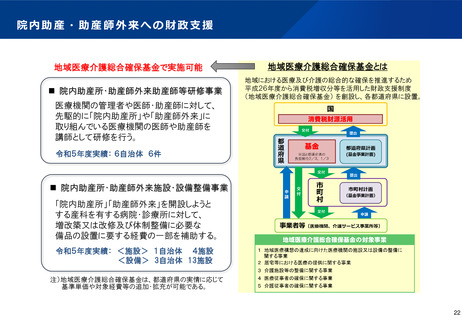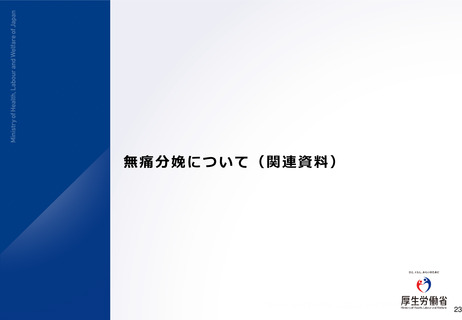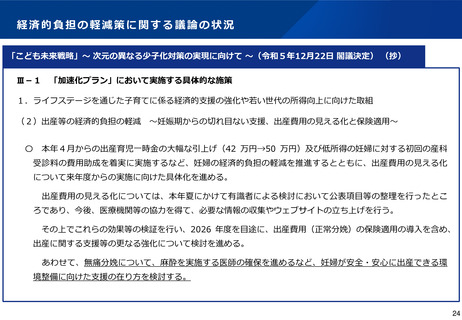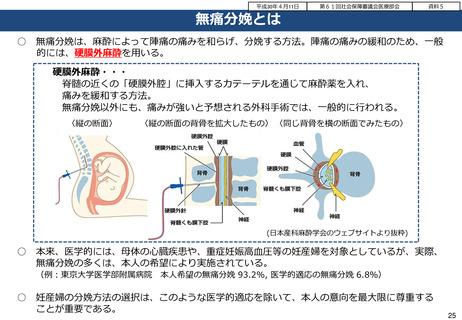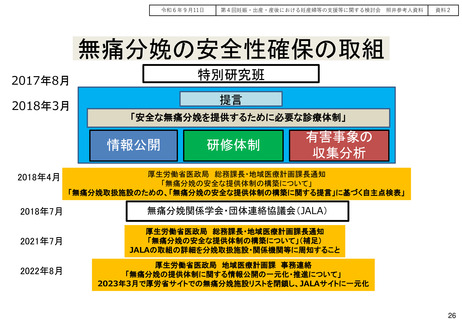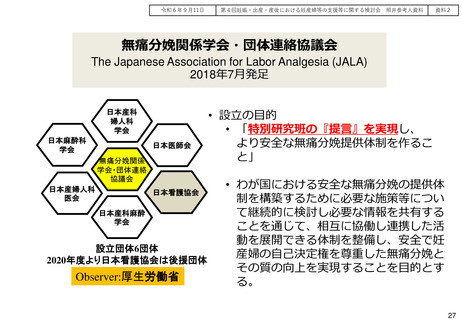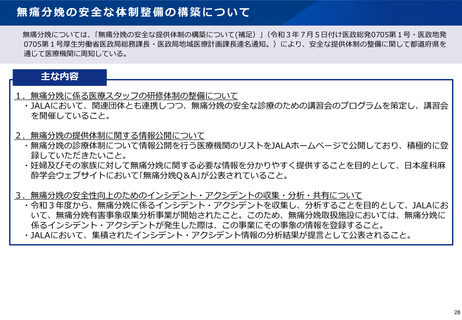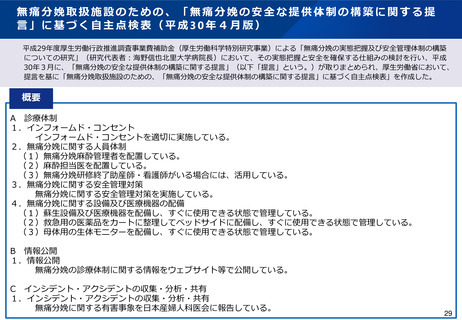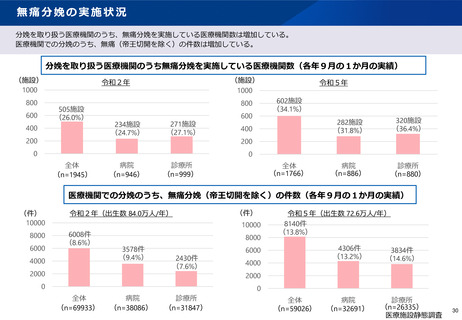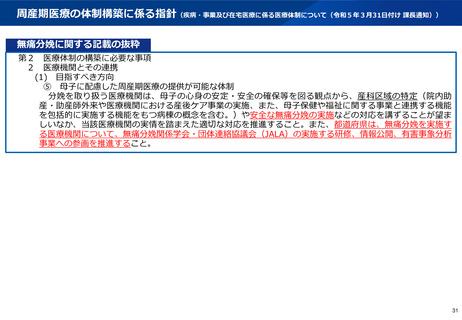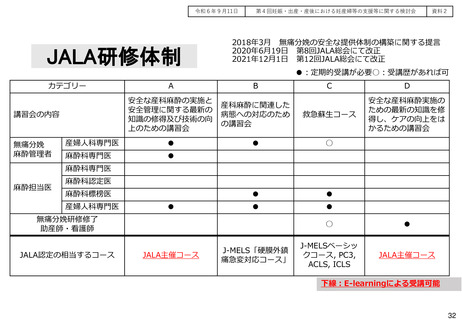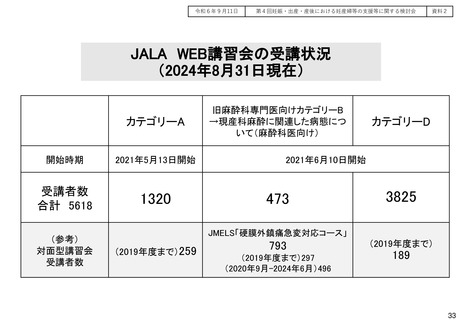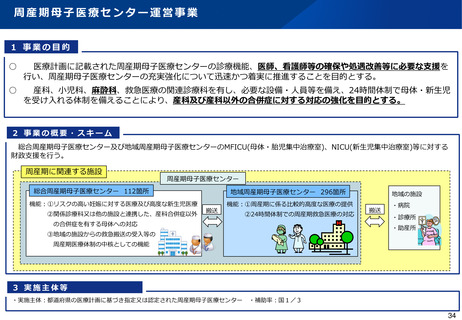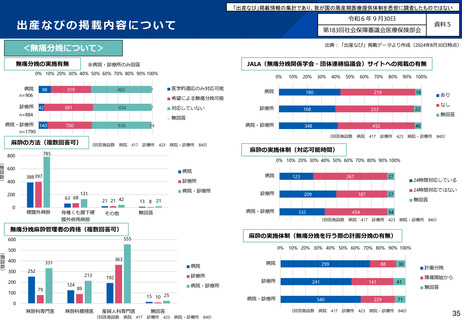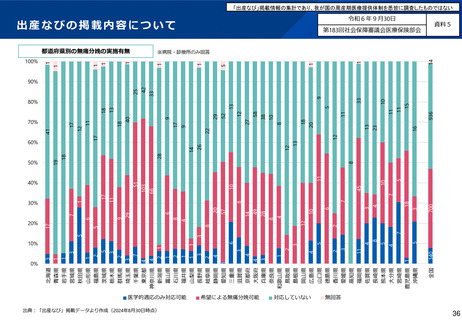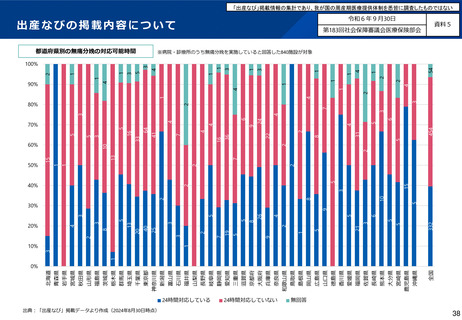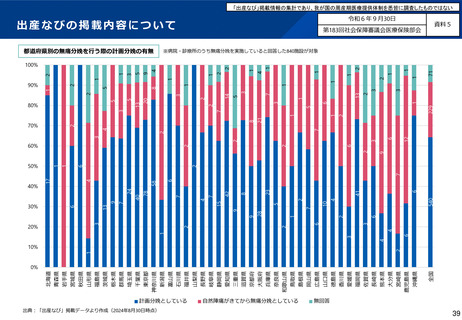よむ、つかう、まなぶ。
資料1 希望に応じた出産を行うための環境整備について(助産所・助産師の活用等について、無痛分娩について) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52966.html |
| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第8回 3/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
助産師の活躍の推進~院内助産・助産師外来の推進~
背景と目的
○ 妊産婦の妊娠・出産・育児に対する多様なニーズ
○ 医師不足・分娩施設の減少への対応
妊婦の多様なニーズに応え、地域における安全・安心・快適なお産の場を確保するとともに、産科病院・
産科診療所において助産師を積極的に活用し、正常産を助産師が担うことで助産師の活躍を推進する。
院内助産とは
助産師外来とは
緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が妊産褥婦
とその家族の意向を尊重しながら、妊娠から産褥1か月頃まで、
正常・異常の判断を行い、助産ケアを提供する体制をいう。
緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が産科医師と役割分担
をし、妊産褥婦とその家族の意向を尊重しながら、健康診査や保健指導を
行うことをいう。ただし、産科医師が健康診査を行い、保健指導・母乳外来
等のみを助産師が行う場合はこれに含まない。
院内助産がある病院数
110
分娩取扱病院数に対する割合
160
154
144
127
10%
2011
12%
2014
16%
15%
17%
2017
2020
2023
55%
53%
63%
70%
60%
46%
10%
0%
60%
500
20%
100
0
495
30%
助産師外来がある病院数
分娩取扱病院数に対する割合
574
569
563
559
50%
0
40%
2011
2014
2017
2020
2023
【出典】医療施設調査
平成21年
『院内助産ガイドライン 医師と助産師の役割分担と協働』策定
平成30年
『院内助産・助産師外来ガイドライン2018』(ガイドライン改定)
(平成20年度厚生労働科学特別研究事業「助産師と産科医の協働の推進に関する研究」)
院内助産・助産師外来推進
のための地域医療介護総合
確保基金等の活用による支援
(平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業:日本看護協会)
21
背景と目的
○ 妊産婦の妊娠・出産・育児に対する多様なニーズ
○ 医師不足・分娩施設の減少への対応
妊婦の多様なニーズに応え、地域における安全・安心・快適なお産の場を確保するとともに、産科病院・
産科診療所において助産師を積極的に活用し、正常産を助産師が担うことで助産師の活躍を推進する。
院内助産とは
助産師外来とは
緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が妊産褥婦
とその家族の意向を尊重しながら、妊娠から産褥1か月頃まで、
正常・異常の判断を行い、助産ケアを提供する体制をいう。
緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が産科医師と役割分担
をし、妊産褥婦とその家族の意向を尊重しながら、健康診査や保健指導を
行うことをいう。ただし、産科医師が健康診査を行い、保健指導・母乳外来
等のみを助産師が行う場合はこれに含まない。
院内助産がある病院数
110
分娩取扱病院数に対する割合
160
154
144
127
10%
2011
12%
2014
16%
15%
17%
2017
2020
2023
55%
53%
63%
70%
60%
46%
10%
0%
60%
500
20%
100
0
495
30%
助産師外来がある病院数
分娩取扱病院数に対する割合
574
569
563
559
50%
0
40%
2011
2014
2017
2020
2023
【出典】医療施設調査
平成21年
『院内助産ガイドライン 医師と助産師の役割分担と協働』策定
平成30年
『院内助産・助産師外来ガイドライン2018』(ガイドライン改定)
(平成20年度厚生労働科学特別研究事業「助産師と産科医の協働の推進に関する研究」)
院内助産・助産師外来推進
のための地域医療介護総合
確保基金等の活用による支援
(平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業:日本看護協会)
21