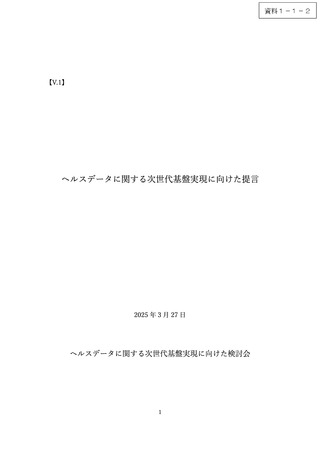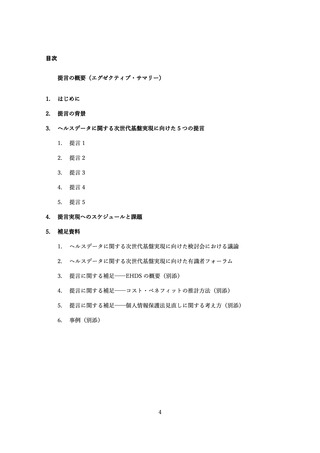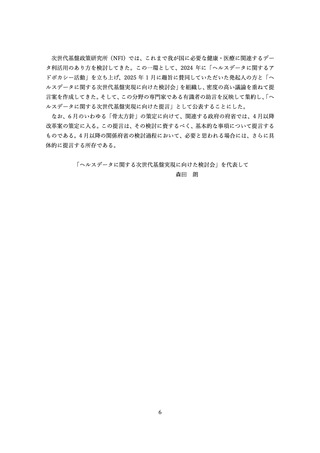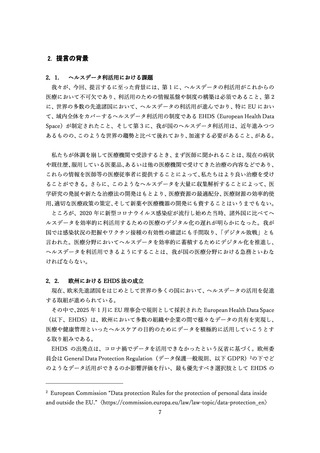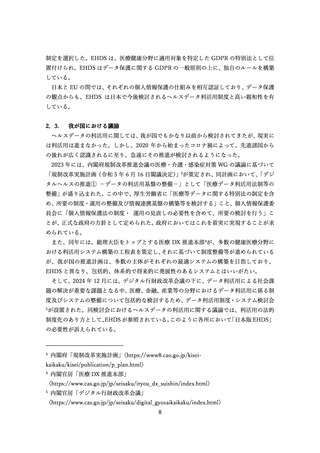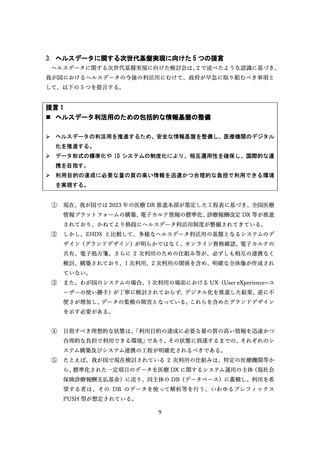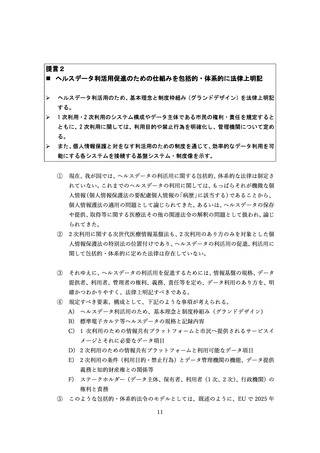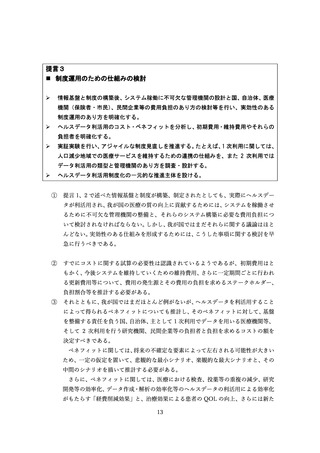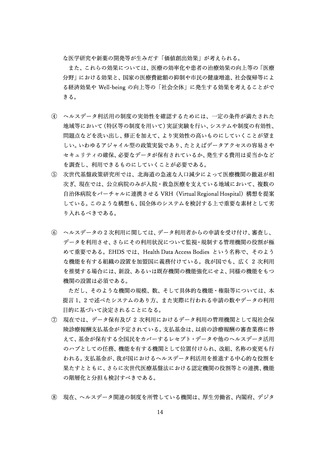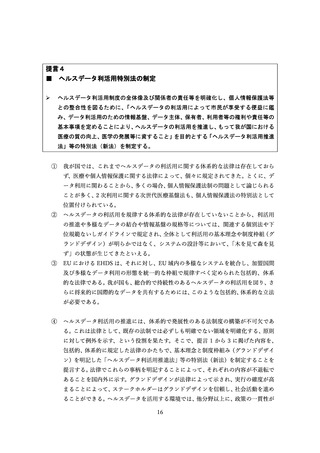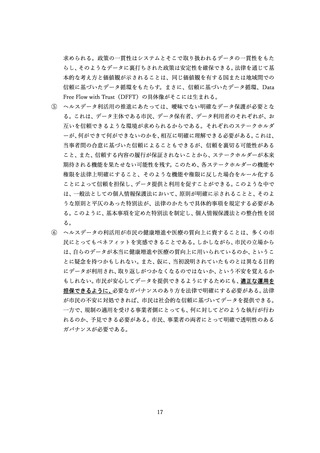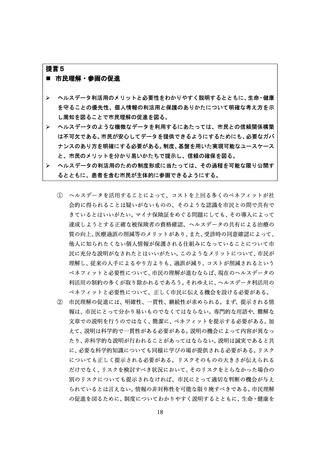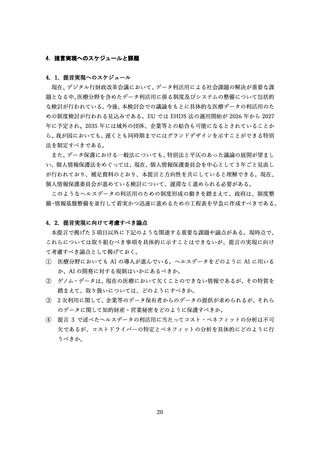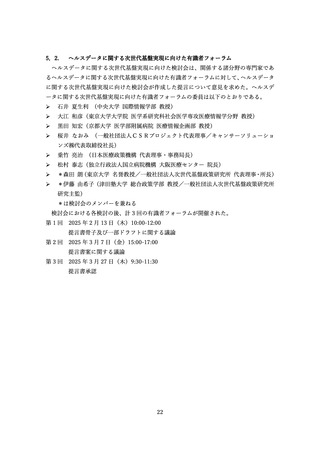よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1-2 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
提言3
◼ 制度運用のための仕組みの検討
➢
情報基盤と制度の構築後、システム稼働に不可欠な管理機関の設計と国、自治体、医療
機関(保険者・市民)、民間企業等の費用負担のあり方の検討等を行い、実効性のある
制度運用のあり方を明確化する。
➢
ヘルスデータ利活用のコスト・ベネフィットを分析し、初期費用・持費費用やそれらの
負担者を明確化する。
➢
実証実験を行い、アジャイルな制度見直しを推進する。たとえば、1 次利用に関しては、
人口減少地域での医療サービスを持費するための連携の仕組みを、また 2 次利用では
データ利活用の類型と管理機関のあり方を調査・設計する。
➢
ヘルスデータ利活用制度化の一元的な推進主体を設ける。
①
提言 1、2 で述べた情報基盤と制度が構築、制定されたとしても、実際にヘルスデー
タが利活用され、我が国の医療の質の向上に貢献するためには、システムを稼働させ
るために不可欠な管理機関の整備と、それらのシステム構築に必要な費用負担につ
いて検討されなければならない。しかし、我が国ではまだそれらに関する議論はほと
んどない。実効性のある仕組みを形成するためには、こうした事項に関する検討を早
急に行うべきである。
②
すでにコストに関する試算の必要性は認識されているようであるが、初期費用はと
もかく、今後システムを維持していくための維持費用、さらに一定期間ごとに行われ
る更新費用等について、費用の発生源とその費用の負担を求めるステークホルダー、
負担割合等を推計する必要がある。
③
それとともに、我が国ではまだほとんど例がないが、ヘルスデータを利活用すること
によって得られるベネフィットについても推計し、そのベネフィットに対して、基盤
を整備する責任を負う国、自治体、主として 1 次利用でデータを用いる医療機関等、
そして 2 次利用を行う研究機関、民間企業等の負担者と負担を求めるコストの額を
決定すべきである。
ベネフィットに関しては、将来の不確定な要素によって左右される可能性が大きい
ため、一定の仮定を置いて、悲観的な最小シナリオ、楽観的な最大シナリオと、その
中間のシナリオを描いて推計する必要がある。
さらに、ベネフィットに関しては、医療における検査、投薬等の重複の減少、研究
開発等の効率化、データ作成・解析の効率化等のヘルスデータの利活用による効率化
がもたらす「経費削減効果」と、治療効果による患者の QOL の向上、さらには新た
13
◼ 制度運用のための仕組みの検討
➢
情報基盤と制度の構築後、システム稼働に不可欠な管理機関の設計と国、自治体、医療
機関(保険者・市民)、民間企業等の費用負担のあり方の検討等を行い、実効性のある
制度運用のあり方を明確化する。
➢
ヘルスデータ利活用のコスト・ベネフィットを分析し、初期費用・持費費用やそれらの
負担者を明確化する。
➢
実証実験を行い、アジャイルな制度見直しを推進する。たとえば、1 次利用に関しては、
人口減少地域での医療サービスを持費するための連携の仕組みを、また 2 次利用では
データ利活用の類型と管理機関のあり方を調査・設計する。
➢
ヘルスデータ利活用制度化の一元的な推進主体を設ける。
①
提言 1、2 で述べた情報基盤と制度が構築、制定されたとしても、実際にヘルスデー
タが利活用され、我が国の医療の質の向上に貢献するためには、システムを稼働させ
るために不可欠な管理機関の整備と、それらのシステム構築に必要な費用負担につ
いて検討されなければならない。しかし、我が国ではまだそれらに関する議論はほと
んどない。実効性のある仕組みを形成するためには、こうした事項に関する検討を早
急に行うべきである。
②
すでにコストに関する試算の必要性は認識されているようであるが、初期費用はと
もかく、今後システムを維持していくための維持費用、さらに一定期間ごとに行われ
る更新費用等について、費用の発生源とその費用の負担を求めるステークホルダー、
負担割合等を推計する必要がある。
③
それとともに、我が国ではまだほとんど例がないが、ヘルスデータを利活用すること
によって得られるベネフィットについても推計し、そのベネフィットに対して、基盤
を整備する責任を負う国、自治体、主として 1 次利用でデータを用いる医療機関等、
そして 2 次利用を行う研究機関、民間企業等の負担者と負担を求めるコストの額を
決定すべきである。
ベネフィットに関しては、将来の不確定な要素によって左右される可能性が大きい
ため、一定の仮定を置いて、悲観的な最小シナリオ、楽観的な最大シナリオと、その
中間のシナリオを描いて推計する必要がある。
さらに、ベネフィットに関しては、医療における検査、投薬等の重複の減少、研究
開発等の効率化、データ作成・解析の効率化等のヘルスデータの利活用による効率化
がもたらす「経費削減効果」と、治療効果による患者の QOL の向上、さらには新た
13