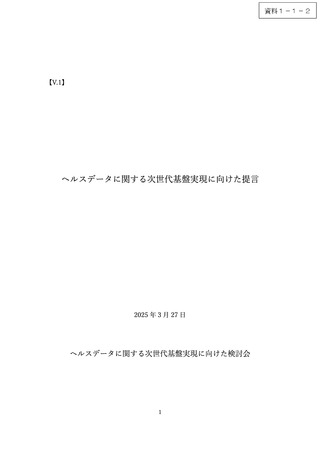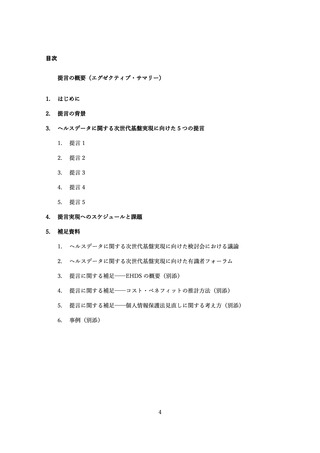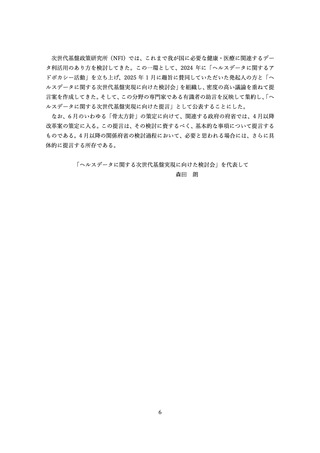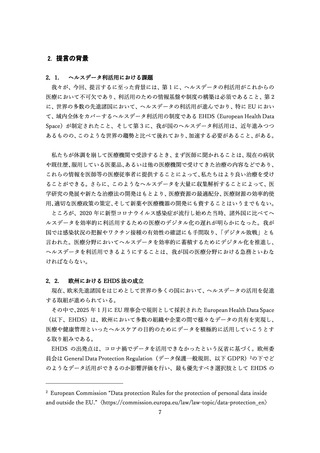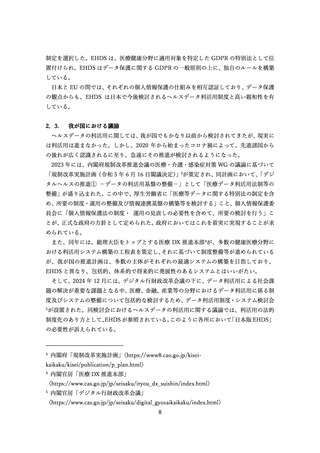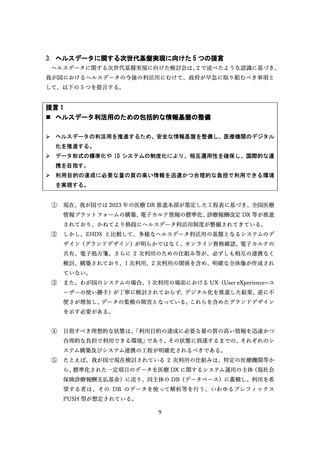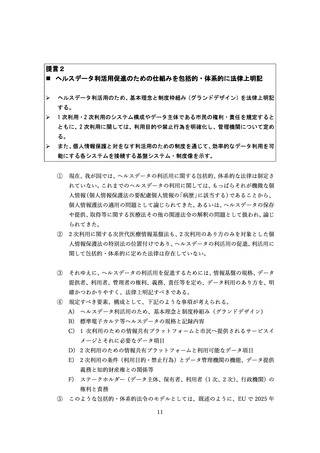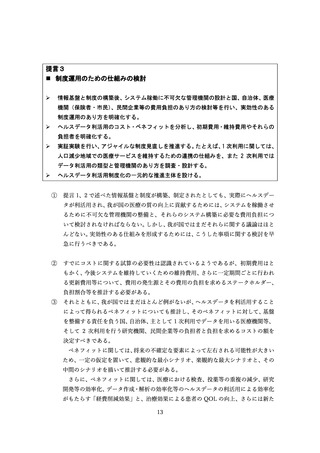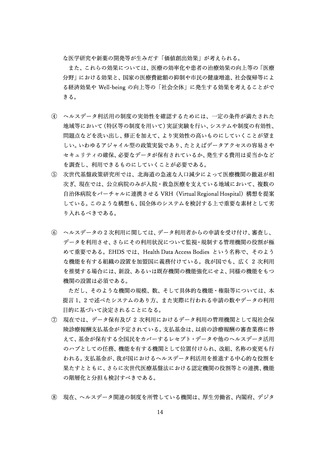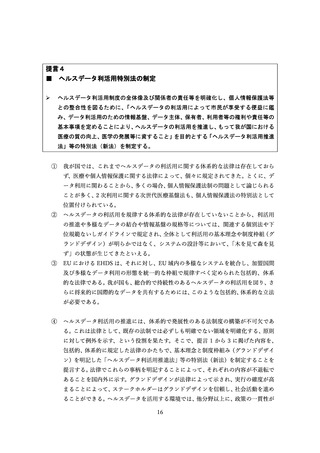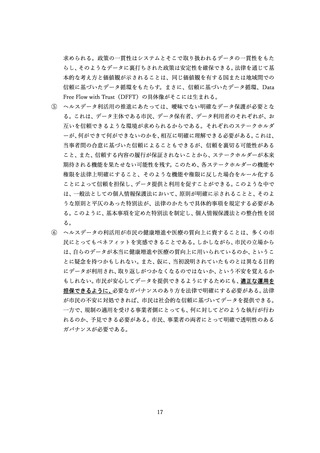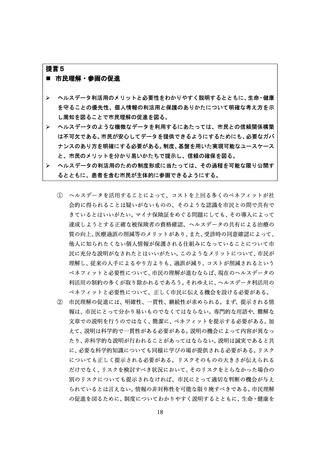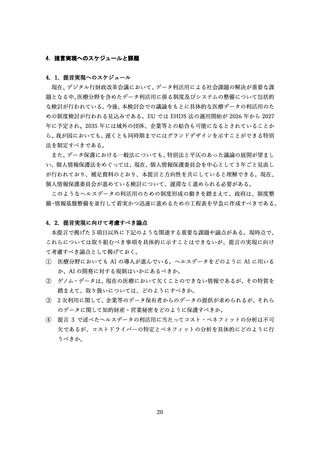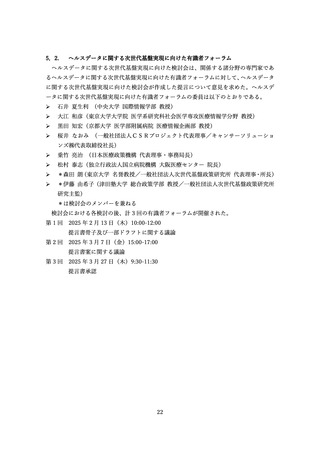よむ、つかう、まなぶ。
資料1-1-2 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
な医学研究や新薬の開発等が生みだす「価値創出効果」が考えられる。
また、これらの効果については、医療の効率化や患者の治療効果の向上等の「医療
分野」における効果と、国家の医療費総額の抑制や市民の健康増進、社会復帰等によ
る経済効果や Well-being の向上等の「社会全体」に発生する効果を考えることがで
きる。
④
ヘルスデータ利活用の制度の実効性を確認するためには、一定の条件が満たされた
地域等において(特区等の制度を用いて)実証実験を行い、システムや制度の有効性、
問題点などを洗い出し、修正を加えて、より実効性の高いものにしていくことが望ま
しい。いわゆるアジャイル型の政策実装であり、たとえばデータアクススの容易さや
スキュリティの確保、必要なデータが保有されているか、発生する費用は妥当かなど
を調査し、利用できるものにしていくことが必要である。
⑤
次世代基盤政策研究所では、北海道の急速な人口減少によって医療機関の撤退が相
次ぎ、現在では、公立病院のみが入院・救急医療を支えている地域において、複数の
自治体病院をバーチャルに連携させる VRH(Virtual Regional Hospital)構想を提案
している。このような構想も、国全体のシステムを検討する上で重要な素材として劣
り入れるべきである。
⑥
ヘルスデータの 2 次利用に関しては、データ利用者からの申請を受け付け、審査し、
データを利用させ、さらにその利用状況について監視・規制する管理機関の役割が極
めて重要である。EHDS では、Health Data Access Bodies という名称で、そのよう
な機能を有する組織の設置を加盟国に義務付けている。我が国でも、広く 2 次利用
を推奨する場合には、新設、あるいは既存機関の機能強化にせよ、同様の機能をもつ
機関の設置は必須である。
ただし、そのような機関の規模、数、そして具体的な機能・権限等については、本
提言 1、2 で述べたシステムのあり方、また実際に行われる申請の数やデータの利用
目的に基づいて決定されることになる。
⑦
現在では、データ保有及び 2 次利用におけるデータ利用の管理機関として現社会保
険診療報酬支払基金が予定されている。支払基金は、以前の診療報酬の審査業務に替
えて、基金が保有する全国民をカバーするレスプト・データや他のヘルスデータ活用
のハブとしての任務、機能を有する機関として位置付けられ、改組、名称の変更も行
われる。支払基金が、我が国におけるヘルスデータ利活用を推進する中心的な役割を
果たすとともに、さらに次世代医療基盤法における認定機関の役割等との連携、機能
の階層化と分担も検討すべきである。
⑧
現在、ヘルスデータ関連の制度を所管している機関は、厚生労働省、内閣府、デジタ
14
また、これらの効果については、医療の効率化や患者の治療効果の向上等の「医療
分野」における効果と、国家の医療費総額の抑制や市民の健康増進、社会復帰等によ
る経済効果や Well-being の向上等の「社会全体」に発生する効果を考えることがで
きる。
④
ヘルスデータ利活用の制度の実効性を確認するためには、一定の条件が満たされた
地域等において(特区等の制度を用いて)実証実験を行い、システムや制度の有効性、
問題点などを洗い出し、修正を加えて、より実効性の高いものにしていくことが望ま
しい。いわゆるアジャイル型の政策実装であり、たとえばデータアクススの容易さや
スキュリティの確保、必要なデータが保有されているか、発生する費用は妥当かなど
を調査し、利用できるものにしていくことが必要である。
⑤
次世代基盤政策研究所では、北海道の急速な人口減少によって医療機関の撤退が相
次ぎ、現在では、公立病院のみが入院・救急医療を支えている地域において、複数の
自治体病院をバーチャルに連携させる VRH(Virtual Regional Hospital)構想を提案
している。このような構想も、国全体のシステムを検討する上で重要な素材として劣
り入れるべきである。
⑥
ヘルスデータの 2 次利用に関しては、データ利用者からの申請を受け付け、審査し、
データを利用させ、さらにその利用状況について監視・規制する管理機関の役割が極
めて重要である。EHDS では、Health Data Access Bodies という名称で、そのよう
な機能を有する組織の設置を加盟国に義務付けている。我が国でも、広く 2 次利用
を推奨する場合には、新設、あるいは既存機関の機能強化にせよ、同様の機能をもつ
機関の設置は必須である。
ただし、そのような機関の規模、数、そして具体的な機能・権限等については、本
提言 1、2 で述べたシステムのあり方、また実際に行われる申請の数やデータの利用
目的に基づいて決定されることになる。
⑦
現在では、データ保有及び 2 次利用におけるデータ利用の管理機関として現社会保
険診療報酬支払基金が予定されている。支払基金は、以前の診療報酬の審査業務に替
えて、基金が保有する全国民をカバーするレスプト・データや他のヘルスデータ活用
のハブとしての任務、機能を有する機関として位置付けられ、改組、名称の変更も行
われる。支払基金が、我が国におけるヘルスデータ利活用を推進する中心的な役割を
果たすとともに、さらに次世代医療基盤法における認定機関の役割等との連携、機能
の階層化と分担も検討すべきである。
⑧
現在、ヘルスデータ関連の制度を所管している機関は、厚生労働省、内閣府、デジタ
14