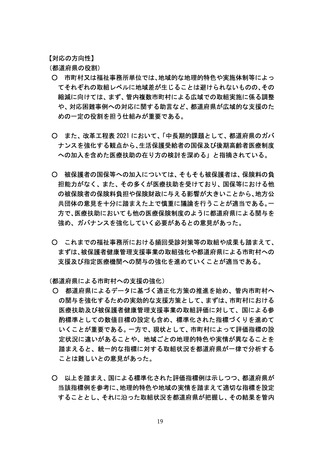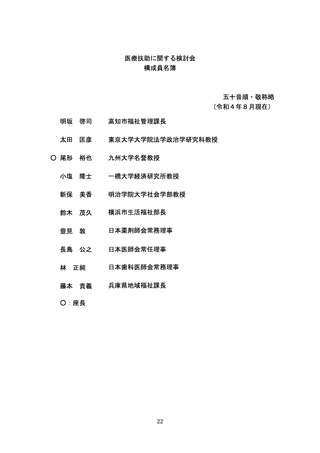よむ、つかう、まなぶ。
医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html |
| 出典情報 | 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ さらに、改革工程表 2021 において、
「生活保護受給者の頻回受診対策に
ついては、本検討会での議論や 2021 年度までの実績等を踏まえ、受診状況
把握対象者の該当要件についての検討を 2022 年度中に行う」旨が示されて
おり、受診回数に係る基準(定義)の見直しについても、検討が求められて
いる。
(重複・多剤投薬の対策)
○ 被保護者に対する重複投薬に着目した現在の取組としては、複数の医療
機関・薬局から同一の向精神薬の投与を受けている者について、主治医等に
確認の上、医療機関と協力して適正受診指導を行っている。
○ また、薬局と連携した薬学的管理・指導の強化に向けて、平成 29 年度か
らは、向精神薬に限らず、処方される薬剤の調剤を行う薬局をできる限り一
か所にする取組を進めるとともに、令和元年度からは、被保護者が医療機関
の受診及び薬局の利用の際に、特定されたお薬手帳を持参することで、併用
禁忌薬の処方防止や重複処方の確認を行うモデル事業を実施している。
○ しかし、調剤費に係るレセプト点検については、通知において、診療内容
と処方薬の整合性の確認は行うこととしているものの、重複投薬等に特化
した確認を必須としておらず、また、上記の薬局と連携した薬学的管理・指
導の強化については、実施箇所数が低調にとどまっている状況である。
○ さらに近年では、一般医療において、高齢者のポリファーマシー(多剤服
用でも特に害をなすもの)に着目した対策が必要とされ、
「高齢者の安全な
薬物療法ガイドライン 2015」においては、5~6種類以上を多剤併用の目
安と考えるのが妥当、との指摘がある。
○ 医療扶助における処方薬剤種類数をみると、65 歳以上の高齢者のうち、
同一月内に 15 種類以上の薬剤の処方を受けている患者の割合は、薬剤が投
与されている高齢者の約 10%存在しており、医療全体と比較してその割合
が高い可能性がある9。
○ 医療保険における保健事業等では、重複・多剤服薬者への訪問指導など、
9
65 歳以上の高齢者のうち 15 種類以上を処方されている患者は、薬剤が投与されている高齢者の5%程度である。な
お、同一条件下での集計ではないため、単純比較はできない。(第3期医療費適正化基本方針の概要,
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000190972.pdf(令和4年8月4日アクセ
ス))
13
「生活保護受給者の頻回受診対策に
ついては、本検討会での議論や 2021 年度までの実績等を踏まえ、受診状況
把握対象者の該当要件についての検討を 2022 年度中に行う」旨が示されて
おり、受診回数に係る基準(定義)の見直しについても、検討が求められて
いる。
(重複・多剤投薬の対策)
○ 被保護者に対する重複投薬に着目した現在の取組としては、複数の医療
機関・薬局から同一の向精神薬の投与を受けている者について、主治医等に
確認の上、医療機関と協力して適正受診指導を行っている。
○ また、薬局と連携した薬学的管理・指導の強化に向けて、平成 29 年度か
らは、向精神薬に限らず、処方される薬剤の調剤を行う薬局をできる限り一
か所にする取組を進めるとともに、令和元年度からは、被保護者が医療機関
の受診及び薬局の利用の際に、特定されたお薬手帳を持参することで、併用
禁忌薬の処方防止や重複処方の確認を行うモデル事業を実施している。
○ しかし、調剤費に係るレセプト点検については、通知において、診療内容
と処方薬の整合性の確認は行うこととしているものの、重複投薬等に特化
した確認を必須としておらず、また、上記の薬局と連携した薬学的管理・指
導の強化については、実施箇所数が低調にとどまっている状況である。
○ さらに近年では、一般医療において、高齢者のポリファーマシー(多剤服
用でも特に害をなすもの)に着目した対策が必要とされ、
「高齢者の安全な
薬物療法ガイドライン 2015」においては、5~6種類以上を多剤併用の目
安と考えるのが妥当、との指摘がある。
○ 医療扶助における処方薬剤種類数をみると、65 歳以上の高齢者のうち、
同一月内に 15 種類以上の薬剤の処方を受けている患者の割合は、薬剤が投
与されている高齢者の約 10%存在しており、医療全体と比較してその割合
が高い可能性がある9。
○ 医療保険における保健事業等では、重複・多剤服薬者への訪問指導など、
9
65 歳以上の高齢者のうち 15 種類以上を処方されている患者は、薬剤が投与されている高齢者の5%程度である。な
お、同一条件下での集計ではないため、単純比較はできない。(第3期医療費適正化基本方針の概要,
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000190972.pdf(令和4年8月4日アクセ
ス))
13