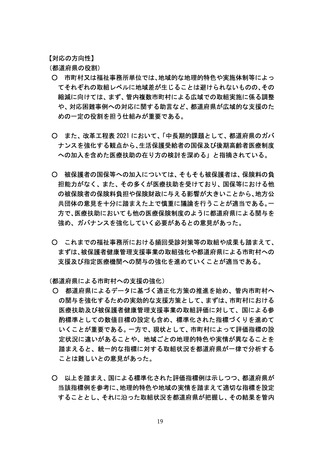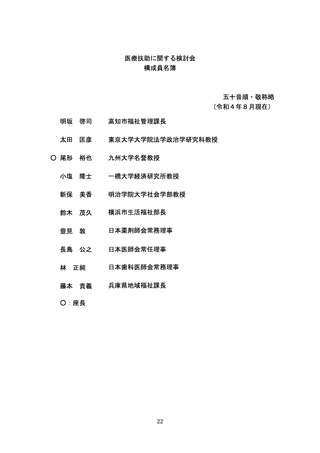よむ、つかう、まなぶ。
医療扶助に関する見直しに向けた整理(令和4年9月6日) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27694.html |
| 出典情報 | 医療扶助に関する検討会(9/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3 各論
(1)被保護者健康管理支援事業
【現状・課題】4
(効果的・効率的な実施体制の構築)
○ 事業が施行されて1年以上が経過し、9割以上の福祉事務所が何らかの
健康管理支援の取組5を実施している。しかし、各福祉事務所における保健医
療専門職の在籍状況は様々であり、また、専門職の在籍の有無によって、各
取組の実施状況や関係部局との連携状況に大きな差がある。
○ 庁内の関係部局との連携状況として、保健部局とは健診結果の活用や健診
受診勧奨等の局面で進みつつある。一方で、事業を効果的かつ効率的に進め
るためには、EBPM の観点から、他の医療保険制度が、保険者機能の一環とし
て行っている健康・医療情報の活用や PDCA サイクルに沿った事業運営を参
考にすべきである。そのため、保健部局に加えて、保険者として保健事業等
を実施する国保部局等との連携も重要となる。現状は、国保部局等と連携し
ている福祉事務所は限られているものの、連携している一部の福祉事務所で
は、データ分析も含めた事業の企画段階から、保健事業等の知見やノウハウ
の活用、情報共有、専門職との相談等によって効果的に実施している取組事
例が確認されている。
(EBPM の観点からの事業の推進)
○ 効果的な事業実施のためには、まず、地域の被保護者の健康状態に関する
調査・分析を行い、地域の健康課題を把握する必要がある。
○ 現在、被保護者の健康課題の現状分析に当たって、8割以上の福祉事務所
では、医療扶助の診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を用いた分
析が行われている。一方で、健診結果の活用は5割程度にとどまっている。
○ また、事業では、社会参加も含めて広く生活全般の環境を改善する視点も
重要となるため、レセプトや健診結果だけではなく、社会生活面の情報も活
用した多角的な分析も重要と考えられる。一部の福祉事務所では、ケースワ
4
本項の現状のデータや取組事例等の記載は、別の注釈がない限り、令和3年度社会福祉推進事業「医療扶助の更なる
ガバナンス強化のため、保健医療施策全般との連携に関する調査研究事業」報告書(https://www.mhlw.go.jp/content
/12200000/000931194.pdf(令和4年8月4日アクセス))において把握されたものである。
5
具体的には、地域の被保護者の健康課題に基づき、
「頻回受診指導」に加え、
「健診受診勧奨」
、「医療機関受診勧
奨」
、「保健指導・生活支援」、
「主治医と連携した保健指導・生活支援(重症化予防)」から1つ以上を選択して実施す
ることとなっている。
6
(1)被保護者健康管理支援事業
【現状・課題】4
(効果的・効率的な実施体制の構築)
○ 事業が施行されて1年以上が経過し、9割以上の福祉事務所が何らかの
健康管理支援の取組5を実施している。しかし、各福祉事務所における保健医
療専門職の在籍状況は様々であり、また、専門職の在籍の有無によって、各
取組の実施状況や関係部局との連携状況に大きな差がある。
○ 庁内の関係部局との連携状況として、保健部局とは健診結果の活用や健診
受診勧奨等の局面で進みつつある。一方で、事業を効果的かつ効率的に進め
るためには、EBPM の観点から、他の医療保険制度が、保険者機能の一環とし
て行っている健康・医療情報の活用や PDCA サイクルに沿った事業運営を参
考にすべきである。そのため、保健部局に加えて、保険者として保健事業等
を実施する国保部局等との連携も重要となる。現状は、国保部局等と連携し
ている福祉事務所は限られているものの、連携している一部の福祉事務所で
は、データ分析も含めた事業の企画段階から、保健事業等の知見やノウハウ
の活用、情報共有、専門職との相談等によって効果的に実施している取組事
例が確認されている。
(EBPM の観点からの事業の推進)
○ 効果的な事業実施のためには、まず、地域の被保護者の健康状態に関する
調査・分析を行い、地域の健康課題を把握する必要がある。
○ 現在、被保護者の健康課題の現状分析に当たって、8割以上の福祉事務所
では、医療扶助の診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を用いた分
析が行われている。一方で、健診結果の活用は5割程度にとどまっている。
○ また、事業では、社会参加も含めて広く生活全般の環境を改善する視点も
重要となるため、レセプトや健診結果だけではなく、社会生活面の情報も活
用した多角的な分析も重要と考えられる。一部の福祉事務所では、ケースワ
4
本項の現状のデータや取組事例等の記載は、別の注釈がない限り、令和3年度社会福祉推進事業「医療扶助の更なる
ガバナンス強化のため、保健医療施策全般との連携に関する調査研究事業」報告書(https://www.mhlw.go.jp/content
/12200000/000931194.pdf(令和4年8月4日アクセス))において把握されたものである。
5
具体的には、地域の被保護者の健康課題に基づき、
「頻回受診指導」に加え、
「健診受診勧奨」
、「医療機関受診勧
奨」
、「保健指導・生活支援」、
「主治医と連携した保健指導・生活支援(重症化予防)」から1つ以上を選択して実施す
ることとなっている。
6