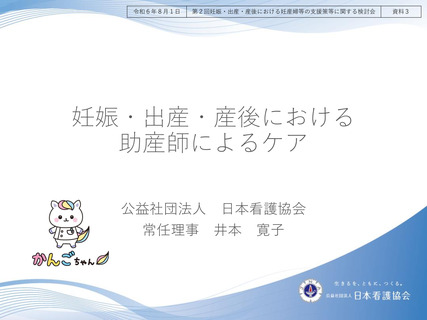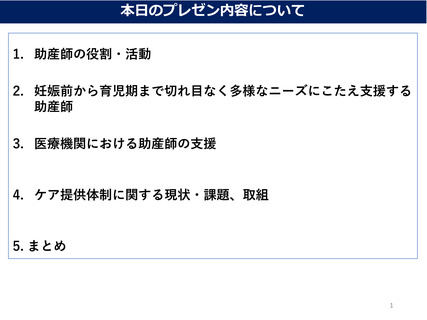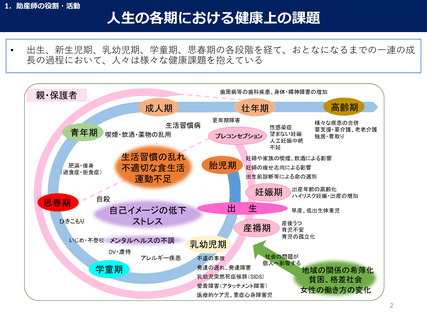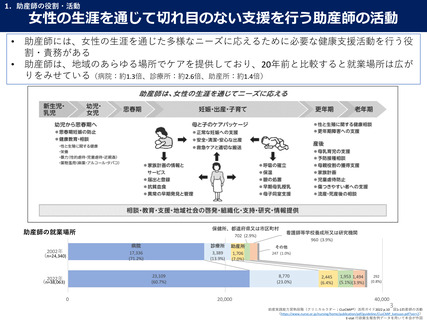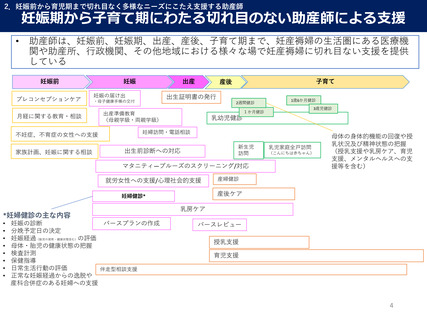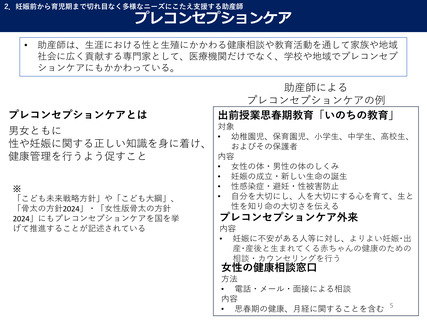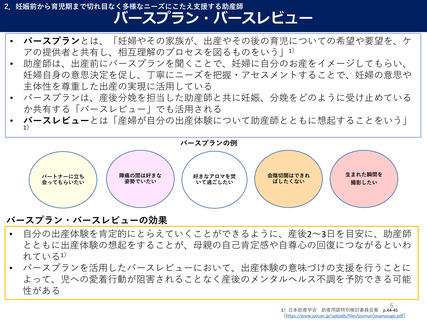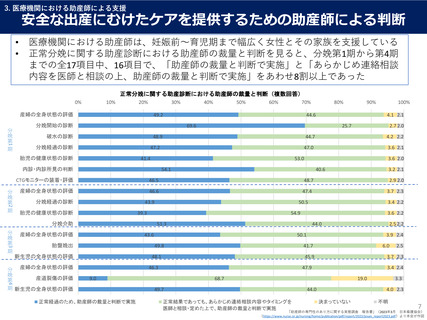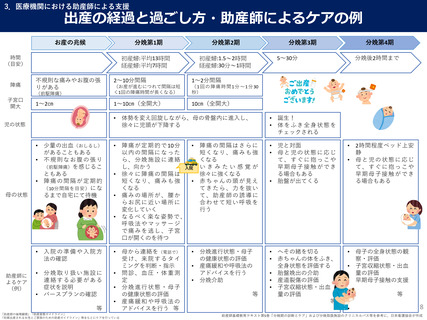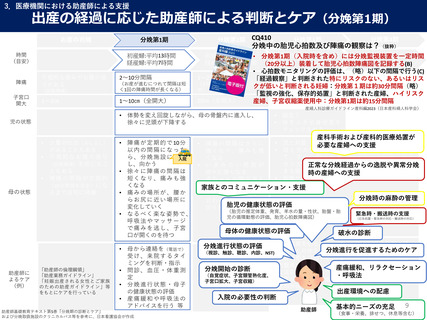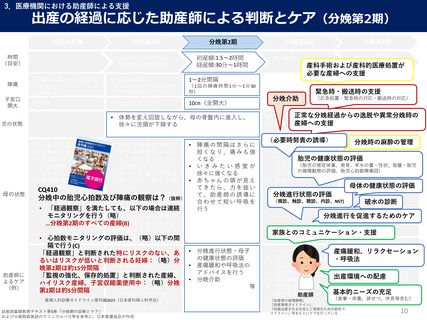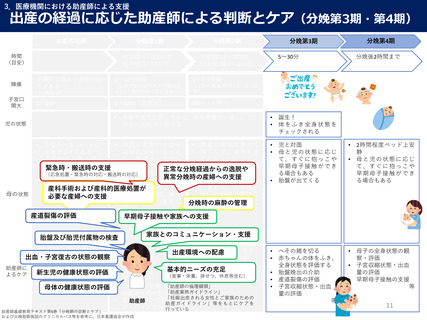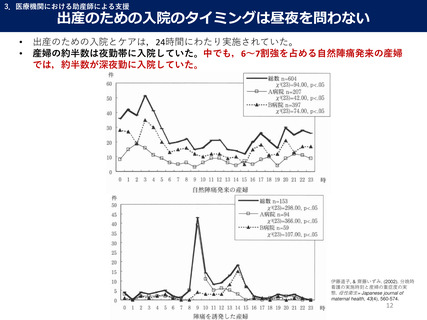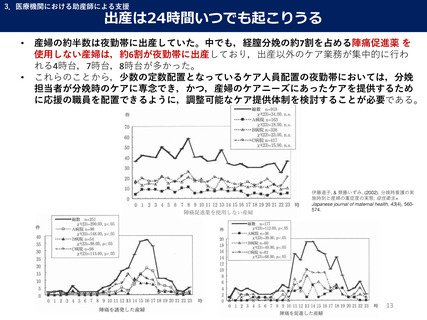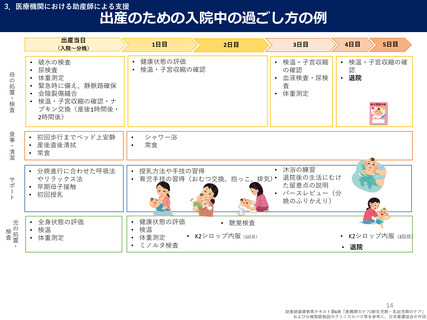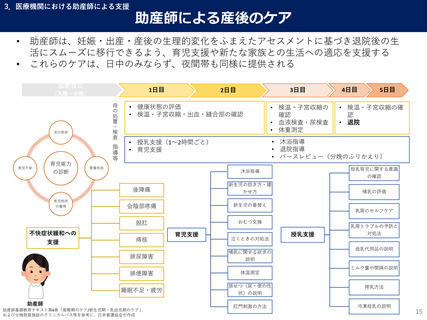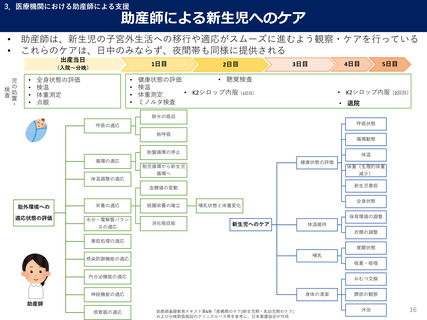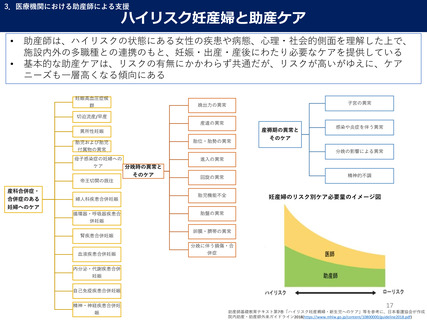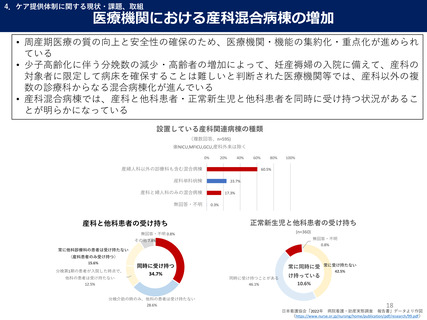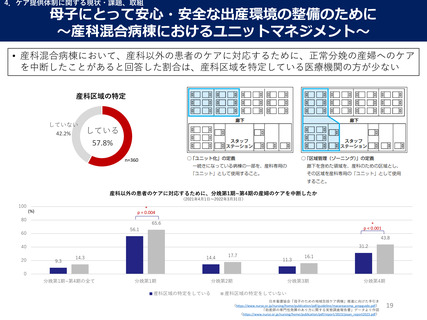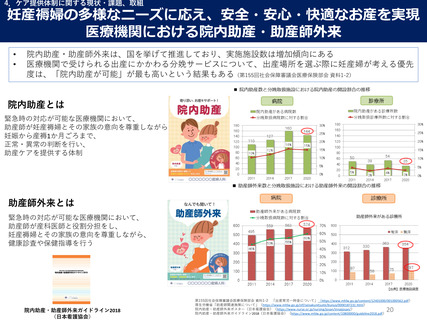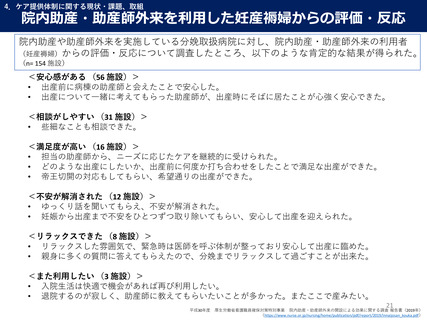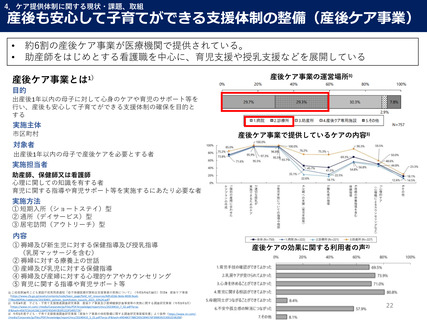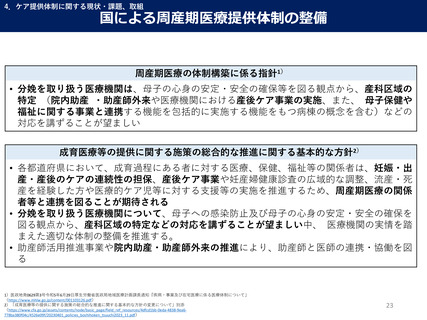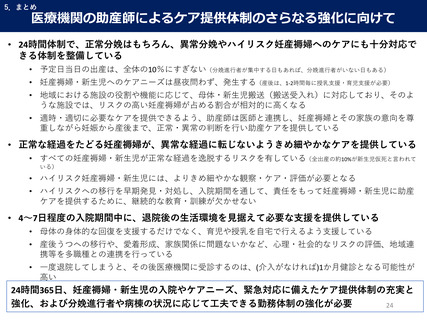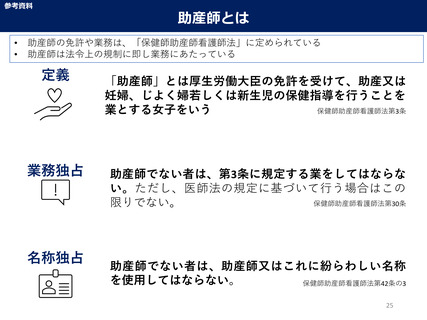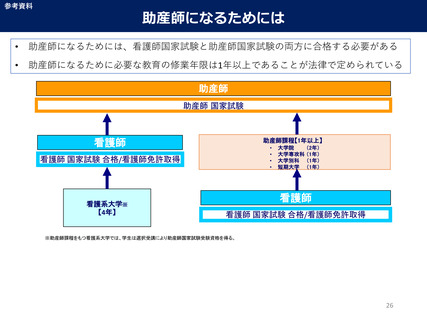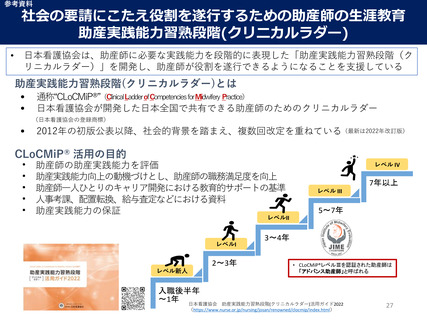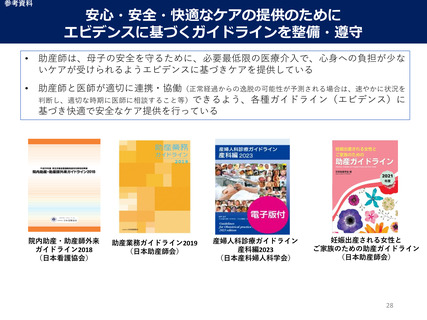よむ、つかう、まなぶ。
資料3 井本構成員提出資料 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41718.html |
| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第2回 8/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3.医療機関における助産師による支援
出産の経過に応じた助産師による判断とケア(分娩第1期)
お産の兆候
分娩第1期
時間
(目安)
陣痛
子宮口
開大
初産婦:平均13時間
経産婦:平均7時間
不規則な痛みやお腹の張
りがある
2~10分間隔
(前駆陣痛)
(お産が進むにつれて間隔は短
く1回の陣痛時間が長くなる)
1~2㎝
1~10㎝(全開大)
分娩第2期 CQ410
分娩第4期
分娩第3期
分娩中の胎児心拍数及び陣痛の観察は?(抜粋)
5~30分
分娩後2時間まで
初産婦:1.5~2時間 • 分娩第1期(入院時を含め)には分娩監視装置を一定時間
経産婦:30分~1時間 (20分以上)装着して胎児心拍数陣痛図を記録する(B)
• 心拍数モニタリングの評価は、(略)以下の間隔で行う(C)
「経過観察」と判断された特にリスクのない、あるいはリス
( 1 回 の 陣 痛 時 間 1 分 ~ 1 分 30
クが低いと判断される妊婦:分娩第1期は約30分間隔(略)
秒)
「監視の強化、保存的処置」と判断された産婦、ハイリスク
10㎝(全開大)
産婦、子宮収縮薬使用中:分娩第1期は約15分間隔
1~2分間隔
産婦人科診療ガイドライン産科編2023(日本産科婦人科学会)
•
児の状態
•
•
•
母の状態
少量の出血(おしるし)
があることもある
不規則なお腹の張り
(前駆陣痛)を感じるこ
ともある
陣痛の間隔が定期的
(10分間隔を目安) にな
るまで自宅に待機
•
•
•
•
•
助産師に
よるケア
(例)
「助産師の倫理綱領」
「助産業務ガイドライン」
「妊娠出産される女性とご家族
のための助産ガイドライン」等
をもとにケアを行っている
•
•
•
体勢を変え回旋しながら、母の骨盤内に進入し、
徐々に児頭が下降する
•
•
誕生!
体をふき全身状態を
チェックされる
産科手術および産科的医療処置が
• 2時間程度ベッド上安
陣 痛 が 定 期 的 で 10 分
• 児と対面
• 陣痛の間隔はさらに
静
必要な産婦への支援
以内の間隔になった
• 母と児の状態に応じ • 母と児の状態に応じ
強くなり、痛みも強
ら 、 分 娩 施 設 に 連入院
絡
て、すぐに抱っこや
くなる
て、すぐに抱っこや
し、向かう
カ ン ガ ル正常な分娩経過からの逸脱や異常分娩
ーケアがで
• いきみたい感覚が
カンガルーケアがで
徐々に陣痛の間隔は
きる場合もある
徐々に強くなる
時の産婦への支援
きる場合もある
短くなり、痛みも強
• 胎盤が出てくる
• 赤ちゃんの頭が見え
くなる
てきたら、力を抜い
家族とのコミュニケーション・支援
痛みの場所が、腰か
て、助産師の誘導に
分娩時の麻酔の管理
らお尻に近い場所に
合わせて短い呼吸に
胎児の健康状態の評価
変化していく
切り替える
(胎児の推定体重、発育、羊水の量・性状、胎盤・胎
緊急時・搬送時の支援
なる べく 楽な 姿勢 で 、
児の循環動態の評価、胎児心拍数陣痛図)
(応急処置・緊急時の対応・搬送時の対応)
呼吸法やマッサージ
で痛みを逃し、子宮
母体の健康状態の評価
破水の診断
口が開くのを待つ
• 母子の全身状態の観
分娩進行状態の評価 • へその緒を切る
母から連絡を (電話で)
分娩進行を促進するためのケア
• (視診、触診、聴診、内診、NST)
分娩進行状態・母子
• 赤ちゃんの体をふき、
察・評価
受け、来院するタイ
の健康状態の評価
全身状態を評価する
• 子宮収縮状態・出血
ミングを判断・指示
• 産痛緩和や呼吸法の
• 胎盤娩出の介助
量の評価
産痛緩和、リラクセーション
分娩開始の診断
問診、血圧・体重測
アドバイスを行う
•
産道裂傷の評価
•
カンガルーケアなど
(自覚症状、子宮頸管熟化度、
・呼吸法
定
• 子宮口拡大、子宮収縮)
分娩介助
• 子宮収縮状態・出血
早期母子接触の支援
分娩進行状態・母子
量の評価
出産環境への配慮
の健康状態の評価
入院の必要性の判断
産痛緩和や呼吸法の
9
アドバイスを行う 等
基本的ニーズの充足
助産師基礎教育テキスト第5巻「分娩期の診断とケア」
および分娩取扱施設のクリニカルパス等を参考に、日本看護協会が作成
助産師
(食事・栄養、排せつ、休息等含む)
出産の経過に応じた助産師による判断とケア(分娩第1期)
お産の兆候
分娩第1期
時間
(目安)
陣痛
子宮口
開大
初産婦:平均13時間
経産婦:平均7時間
不規則な痛みやお腹の張
りがある
2~10分間隔
(前駆陣痛)
(お産が進むにつれて間隔は短
く1回の陣痛時間が長くなる)
1~2㎝
1~10㎝(全開大)
分娩第2期 CQ410
分娩第4期
分娩第3期
分娩中の胎児心拍数及び陣痛の観察は?(抜粋)
5~30分
分娩後2時間まで
初産婦:1.5~2時間 • 分娩第1期(入院時を含め)には分娩監視装置を一定時間
経産婦:30分~1時間 (20分以上)装着して胎児心拍数陣痛図を記録する(B)
• 心拍数モニタリングの評価は、(略)以下の間隔で行う(C)
「経過観察」と判断された特にリスクのない、あるいはリス
( 1 回 の 陣 痛 時 間 1 分 ~ 1 分 30
クが低いと判断される妊婦:分娩第1期は約30分間隔(略)
秒)
「監視の強化、保存的処置」と判断された産婦、ハイリスク
10㎝(全開大)
産婦、子宮収縮薬使用中:分娩第1期は約15分間隔
1~2分間隔
産婦人科診療ガイドライン産科編2023(日本産科婦人科学会)
•
児の状態
•
•
•
母の状態
少量の出血(おしるし)
があることもある
不規則なお腹の張り
(前駆陣痛)を感じるこ
ともある
陣痛の間隔が定期的
(10分間隔を目安) にな
るまで自宅に待機
•
•
•
•
•
助産師に
よるケア
(例)
「助産師の倫理綱領」
「助産業務ガイドライン」
「妊娠出産される女性とご家族
のための助産ガイドライン」等
をもとにケアを行っている
•
•
•
体勢を変え回旋しながら、母の骨盤内に進入し、
徐々に児頭が下降する
•
•
誕生!
体をふき全身状態を
チェックされる
産科手術および産科的医療処置が
• 2時間程度ベッド上安
陣 痛 が 定 期 的 で 10 分
• 児と対面
• 陣痛の間隔はさらに
静
必要な産婦への支援
以内の間隔になった
• 母と児の状態に応じ • 母と児の状態に応じ
強くなり、痛みも強
ら 、 分 娩 施 設 に 連入院
絡
て、すぐに抱っこや
くなる
て、すぐに抱っこや
し、向かう
カ ン ガ ル正常な分娩経過からの逸脱や異常分娩
ーケアがで
• いきみたい感覚が
カンガルーケアがで
徐々に陣痛の間隔は
きる場合もある
徐々に強くなる
時の産婦への支援
きる場合もある
短くなり、痛みも強
• 胎盤が出てくる
• 赤ちゃんの頭が見え
くなる
てきたら、力を抜い
家族とのコミュニケーション・支援
痛みの場所が、腰か
て、助産師の誘導に
分娩時の麻酔の管理
らお尻に近い場所に
合わせて短い呼吸に
胎児の健康状態の評価
変化していく
切り替える
(胎児の推定体重、発育、羊水の量・性状、胎盤・胎
緊急時・搬送時の支援
なる べく 楽な 姿勢 で 、
児の循環動態の評価、胎児心拍数陣痛図)
(応急処置・緊急時の対応・搬送時の対応)
呼吸法やマッサージ
で痛みを逃し、子宮
母体の健康状態の評価
破水の診断
口が開くのを待つ
• 母子の全身状態の観
分娩進行状態の評価 • へその緒を切る
母から連絡を (電話で)
分娩進行を促進するためのケア
• (視診、触診、聴診、内診、NST)
分娩進行状態・母子
• 赤ちゃんの体をふき、
察・評価
受け、来院するタイ
の健康状態の評価
全身状態を評価する
• 子宮収縮状態・出血
ミングを判断・指示
• 産痛緩和や呼吸法の
• 胎盤娩出の介助
量の評価
産痛緩和、リラクセーション
分娩開始の診断
問診、血圧・体重測
アドバイスを行う
•
産道裂傷の評価
•
カンガルーケアなど
(自覚症状、子宮頸管熟化度、
・呼吸法
定
• 子宮口拡大、子宮収縮)
分娩介助
• 子宮収縮状態・出血
早期母子接触の支援
分娩進行状態・母子
量の評価
出産環境への配慮
の健康状態の評価
入院の必要性の判断
産痛緩和や呼吸法の
9
アドバイスを行う 等
基本的ニーズの充足
助産師基礎教育テキスト第5巻「分娩期の診断とケア」
および分娩取扱施設のクリニカルパス等を参考に、日本看護協会が作成
助産師
(食事・栄養、排せつ、休息等含む)