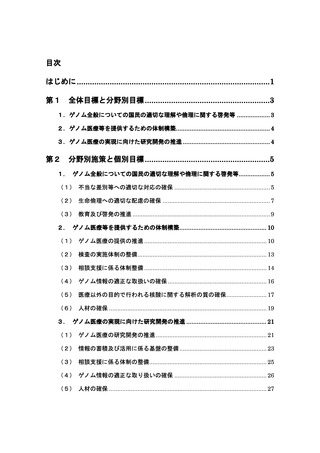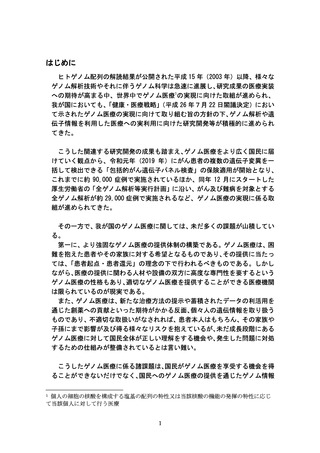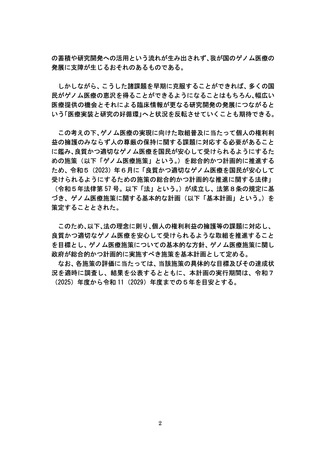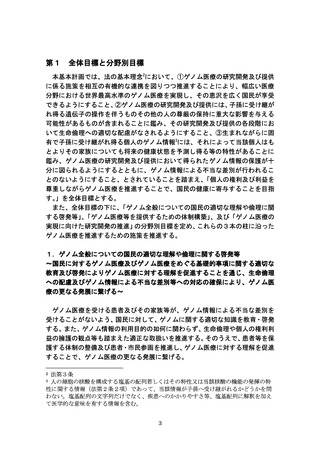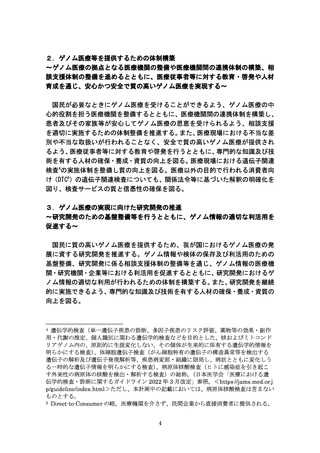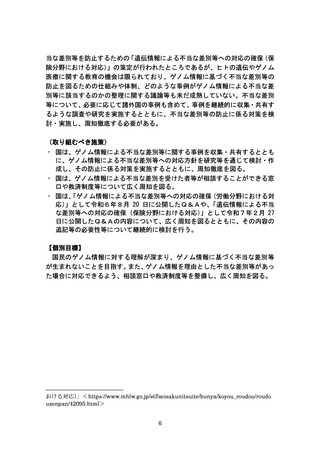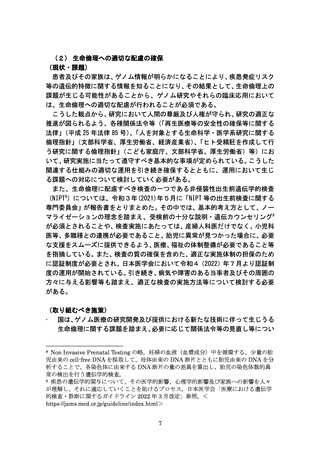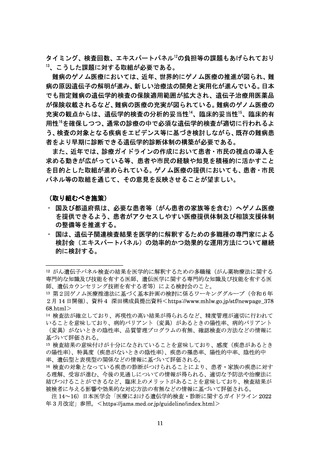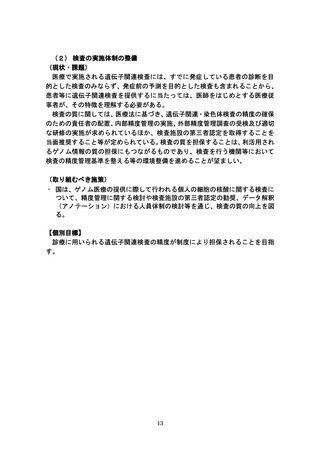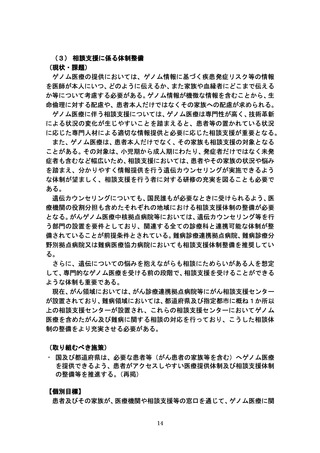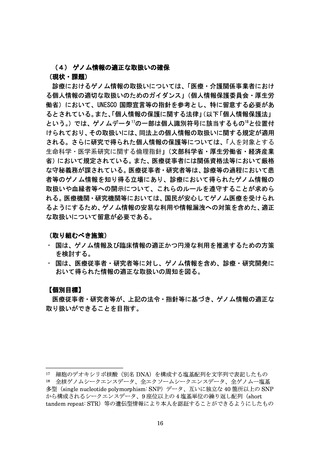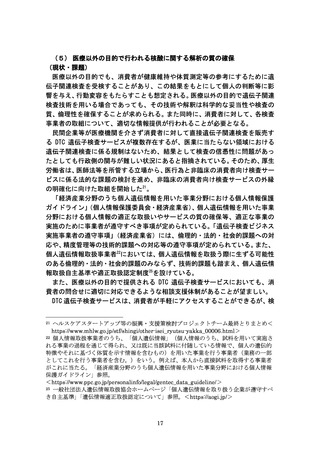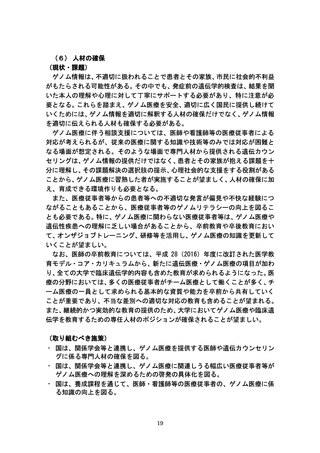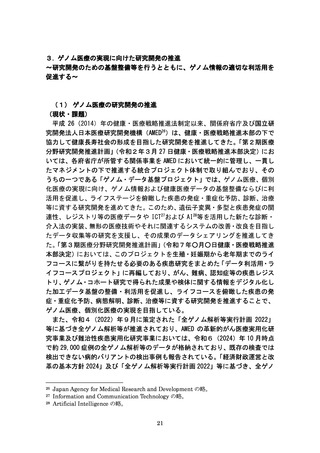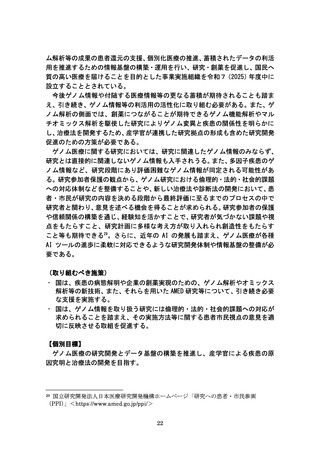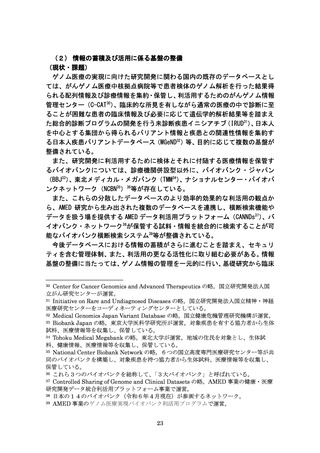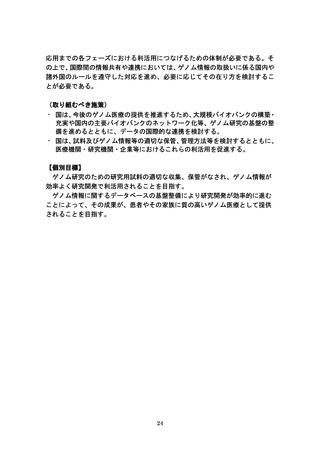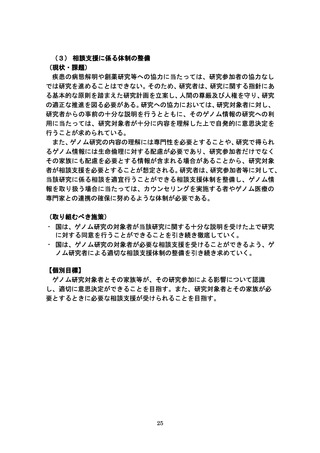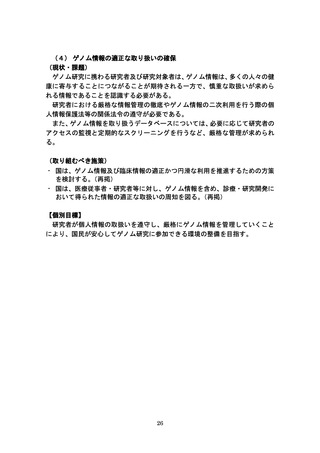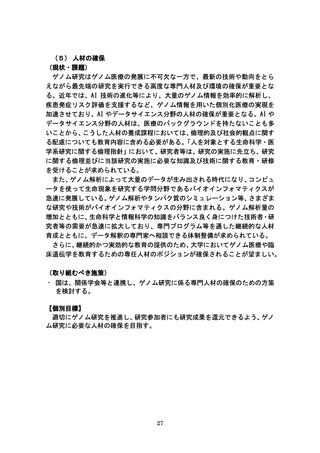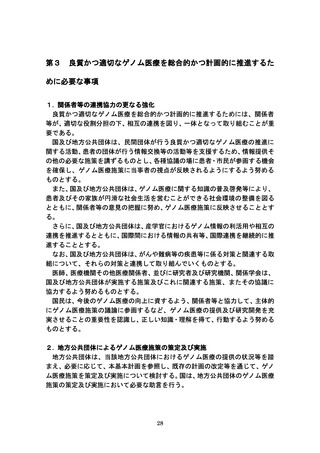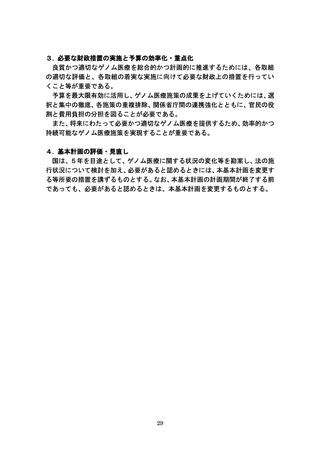よむ、つかう、まなぶ。
資料1 ゲノム医療施策に関する基本的な計画(案) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53142.html |
| 出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第10回 2/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2) 生命倫理への適切な配慮の確保
(現状・課題)
患者及びその家族は、ゲノム情報が明らかになることにより、疾患発症リスク
等の遺伝的特徴に関する情報を知ることになり、その結果として、生命倫理上の
課題が生じる可能性があることから、ゲノム研究やそれらの臨床応用において
は、生命倫理への適切な配慮が行われることが必須である。
こうした観点から、研究において人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な
推進が図られるよう、各種関係法令等(「再生医療等の安全性の確保等に関する
法律」
(平成 25 年法律 85 号)、
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針」
(文部科学省、厚生労働省、経済産業省)、
「ヒト受精胚を作成して行
う研究に関する倫理指針」
(こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省)等)にお
いて、研究実施に当たって遵守すべき基本的な事項が定められている。こうした
関連する仕組みの適切な運用を引き続き確保するとともに、運用において生じ
る課題への対応について検討していく必要がある。
また、生命倫理に配慮すべき検査の一つである非侵襲性出生前遺伝学的検査
(NIPT8)については、令和3年(2021)年5月に「NIPT 等の出生前検査に関する
専門委員会」が報告書をとりまとめた。その中では、基本的考え方として、ノー
マライゼーションの理念を踏まえ、受検前の十分な説明・遺伝カウンセリング9
が必須とされることや、検査実施にあたっては、産婦人科医だけでなく、小児科
医等、多職種との連携が必要であること、胎児に異常が見つかった場合に、必要
な支援をスムーズに提供できるよう、医療、福祉の体制整備が必要であること等
を指摘している。また、検査の質の確保を含めた、適正な実施体制の担保のため
に認証制度が必要とされ、日本医学会において令和4(2022)年7月より認証制
度の運用が開始されている。引き続き、病気や障害のある当事者及びその周囲の
方々に与える影響等も踏まえ、適正な検査の実施方法等について検討する必要
がある。
(取り組むべき施策)
国は、ゲノム医療の研究開発及び提供における新たな技術に伴って生じうる
生命倫理に関する課題を踏まえ、必要に応じて関係法令等の見直し等につい
Non Invasive Prenatal Testing の略。妊婦の血液(血漿成分)中を循環する、少量の胎
児由来の cell-free DNA を採取して、母体由来の DNA 断片とともに胎児由来の DNA を分
析することで、各染色体に由来する DNA 断片の量の差異を算出し、胎児の染色体数的異
常の検出を行う遺伝学的検査。
9 疾患の遺伝学的関与について、その医学的影響、心理学的影響及び家族への影響を人々
が理解し、それに適応していくことを助けるプロセス。日本医学会「医療における遺伝学
的検査・診断に関するガイドライン 2022 年 3 月改定」参照。<
https://jams.med.or.jp/guideline/index.html>
8
7
(現状・課題)
患者及びその家族は、ゲノム情報が明らかになることにより、疾患発症リスク
等の遺伝的特徴に関する情報を知ることになり、その結果として、生命倫理上の
課題が生じる可能性があることから、ゲノム研究やそれらの臨床応用において
は、生命倫理への適切な配慮が行われることが必須である。
こうした観点から、研究において人間の尊厳及び人権が守られ、研究の適正な
推進が図られるよう、各種関係法令等(「再生医療等の安全性の確保等に関する
法律」
(平成 25 年法律 85 号)、
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針」
(文部科学省、厚生労働省、経済産業省)、
「ヒト受精胚を作成して行
う研究に関する倫理指針」
(こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省)等)にお
いて、研究実施に当たって遵守すべき基本的な事項が定められている。こうした
関連する仕組みの適切な運用を引き続き確保するとともに、運用において生じ
る課題への対応について検討していく必要がある。
また、生命倫理に配慮すべき検査の一つである非侵襲性出生前遺伝学的検査
(NIPT8)については、令和3年(2021)年5月に「NIPT 等の出生前検査に関する
専門委員会」が報告書をとりまとめた。その中では、基本的考え方として、ノー
マライゼーションの理念を踏まえ、受検前の十分な説明・遺伝カウンセリング9
が必須とされることや、検査実施にあたっては、産婦人科医だけでなく、小児科
医等、多職種との連携が必要であること、胎児に異常が見つかった場合に、必要
な支援をスムーズに提供できるよう、医療、福祉の体制整備が必要であること等
を指摘している。また、検査の質の確保を含めた、適正な実施体制の担保のため
に認証制度が必要とされ、日本医学会において令和4(2022)年7月より認証制
度の運用が開始されている。引き続き、病気や障害のある当事者及びその周囲の
方々に与える影響等も踏まえ、適正な検査の実施方法等について検討する必要
がある。
(取り組むべき施策)
国は、ゲノム医療の研究開発及び提供における新たな技術に伴って生じうる
生命倫理に関する課題を踏まえ、必要に応じて関係法令等の見直し等につい
Non Invasive Prenatal Testing の略。妊婦の血液(血漿成分)中を循環する、少量の胎
児由来の cell-free DNA を採取して、母体由来の DNA 断片とともに胎児由来の DNA を分
析することで、各染色体に由来する DNA 断片の量の差異を算出し、胎児の染色体数的異
常の検出を行う遺伝学的検査。
9 疾患の遺伝学的関与について、その医学的影響、心理学的影響及び家族への影響を人々
が理解し、それに適応していくことを助けるプロセス。日本医学会「医療における遺伝学
的検査・診断に関するガイドライン 2022 年 3 月改定」参照。<
https://jams.med.or.jp/guideline/index.html>
8
7