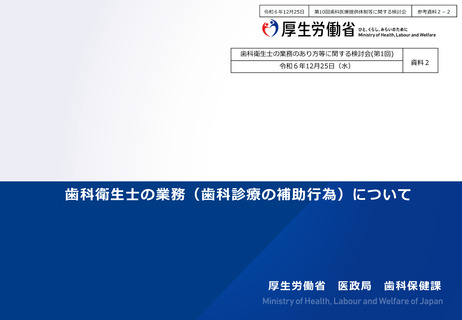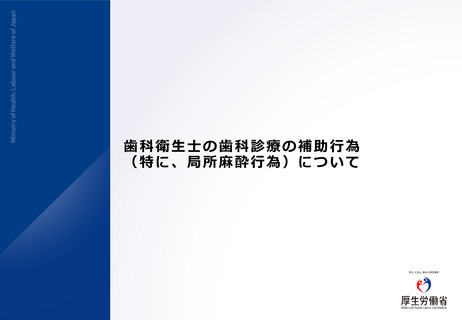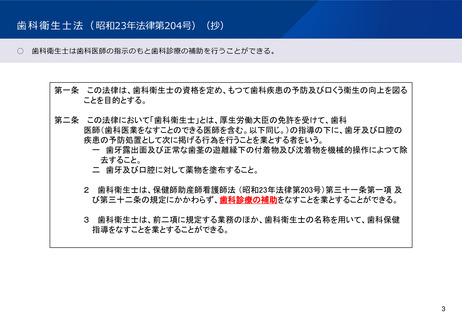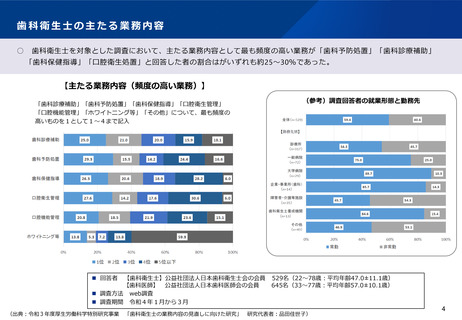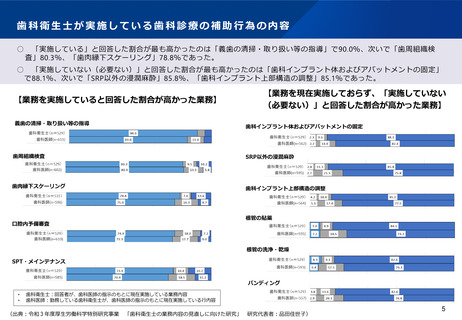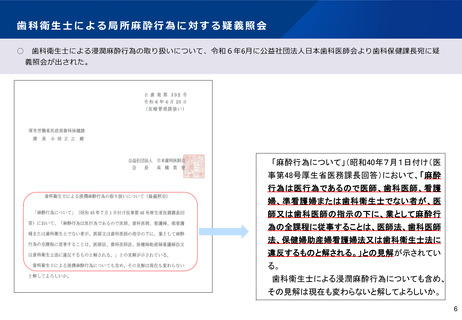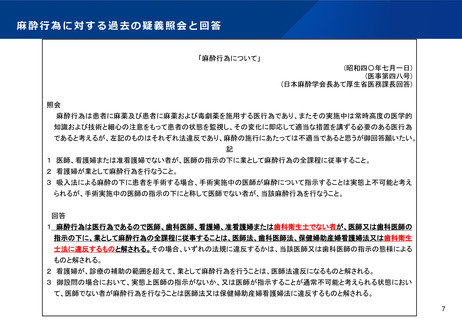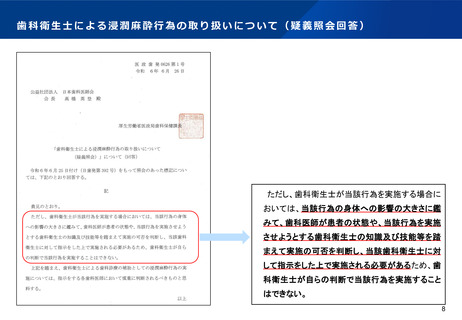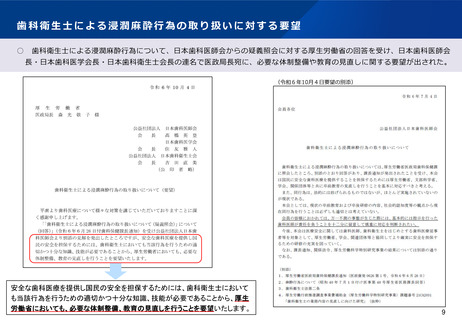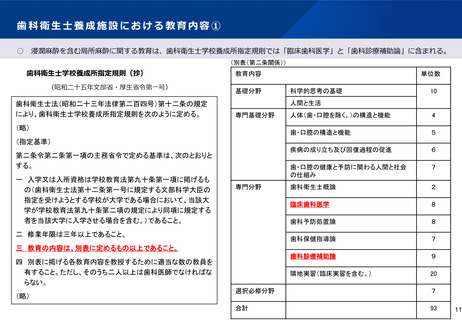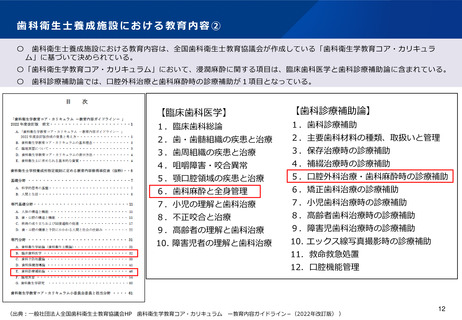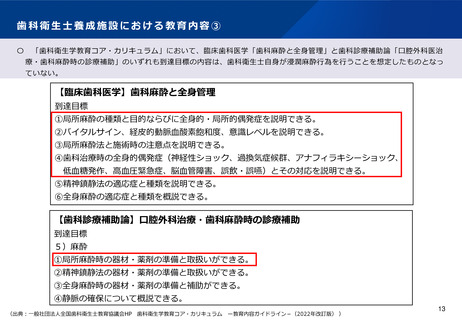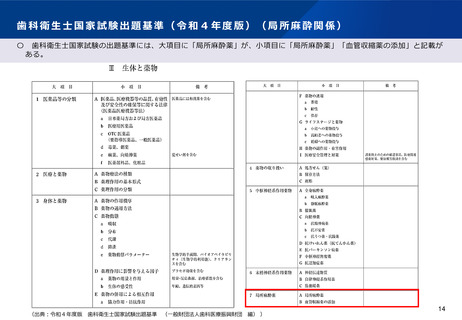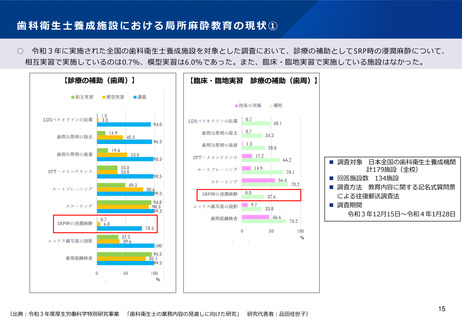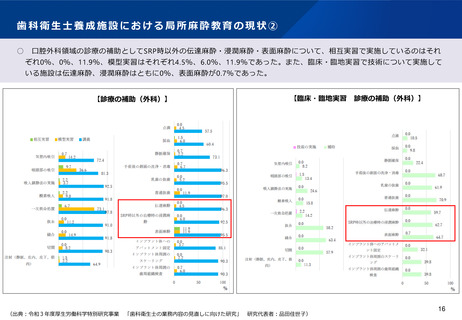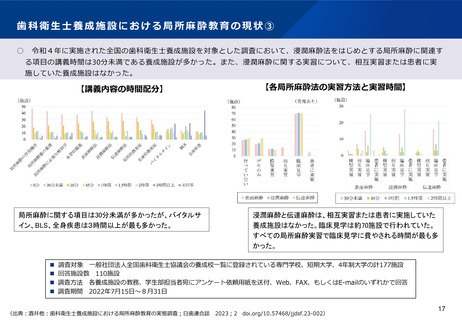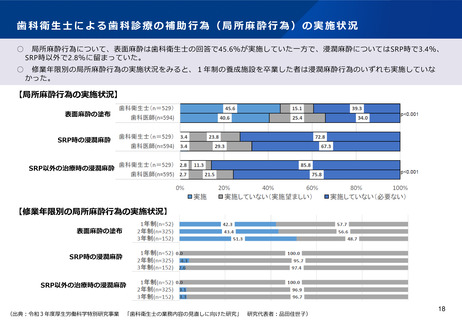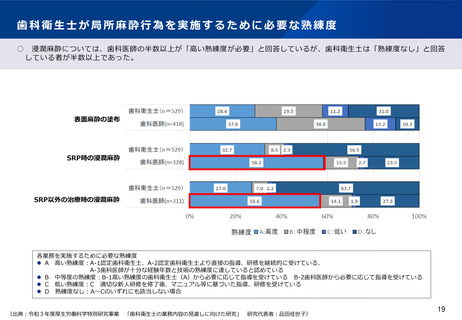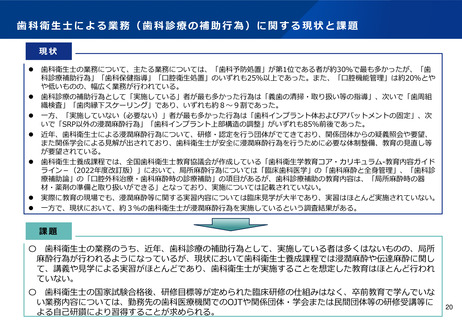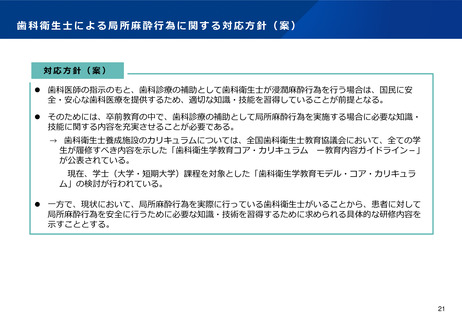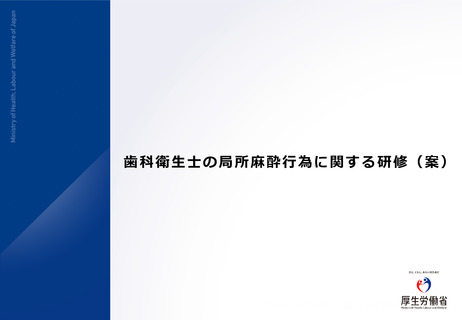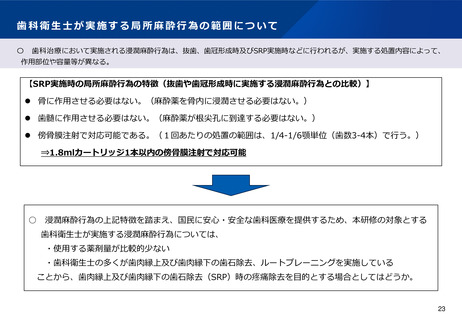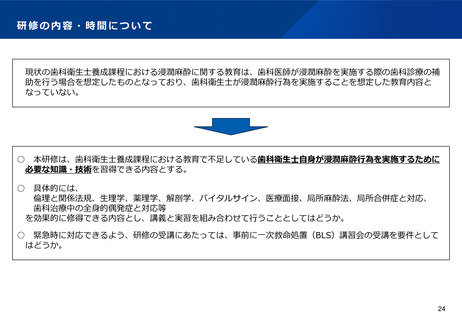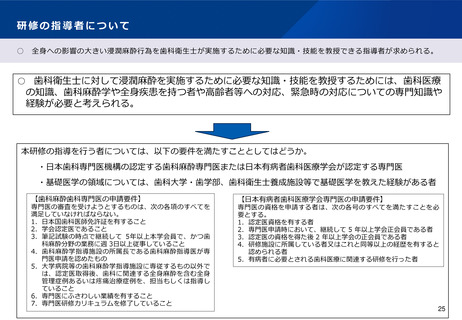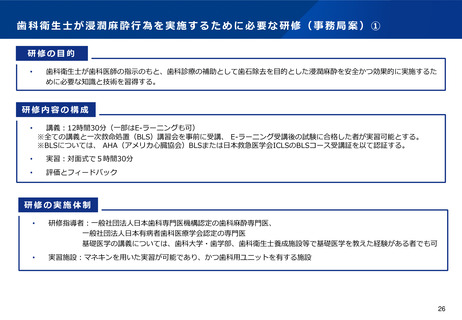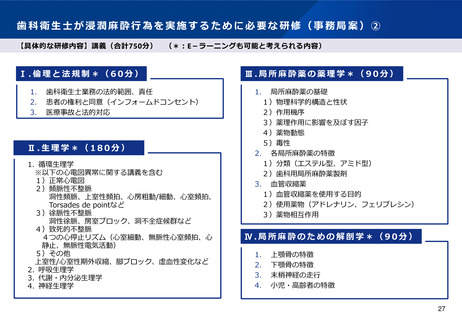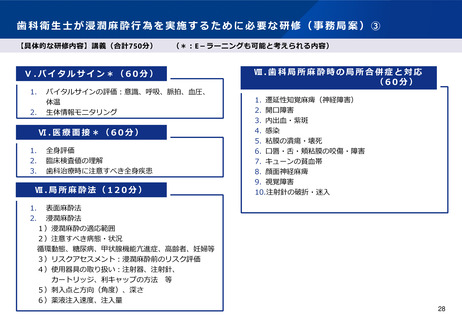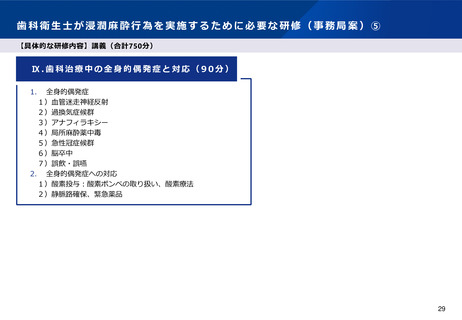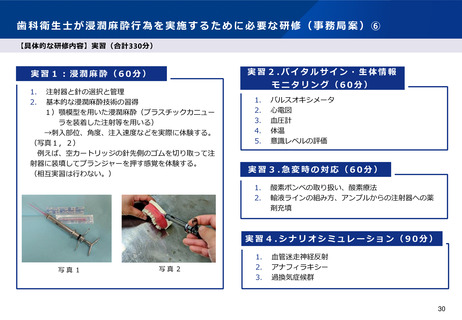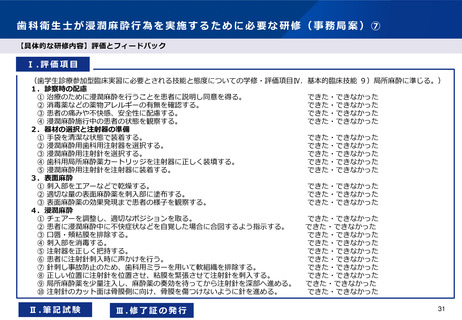よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-2 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料2 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |
| 出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
歯科衛生士が実施する局所麻酔行為の範囲について
〇
歯科治療において実施される浸潤麻酔行為は、抜歯、歯冠形成時及びSRP実施時などに行われるが、実施する処置内容によって、
作用部位や容量等が異なる。
【SRP実施時の局所麻酔行為の特徴(抜歯や歯冠形成時に実施する浸潤麻酔行為との比較)】
⚫ 骨に作用させる必要はない。(麻酔薬を骨内に浸潤させる必要はない。)
⚫ 歯髄に作用させる必要はない。(麻酔薬が根尖孔に到達する必要はない。)
⚫ 傍骨膜注射で対応可能である。(1回あたりの処置の範囲は、1/4-1/6顎単位(歯数3-4本)で行う。)
⇒1.8mlカートリッジ1本以内の傍骨膜注射で対応可能
○ 浸潤麻酔行為の上記特徴を踏まえ、国民に安心・安全な歯科医療を提供するため、本研修の対象とする
歯科衛生士が実施する浸潤麻酔行為については、
・使用する薬剤量が比較的少ない
・歯科衛生士の多くが歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去、ルートプレーニングを実施している
ことから、歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去(SRP)時の疼痛除去を目的とする場合としてはどうか。
23
〇
歯科治療において実施される浸潤麻酔行為は、抜歯、歯冠形成時及びSRP実施時などに行われるが、実施する処置内容によって、
作用部位や容量等が異なる。
【SRP実施時の局所麻酔行為の特徴(抜歯や歯冠形成時に実施する浸潤麻酔行為との比較)】
⚫ 骨に作用させる必要はない。(麻酔薬を骨内に浸潤させる必要はない。)
⚫ 歯髄に作用させる必要はない。(麻酔薬が根尖孔に到達する必要はない。)
⚫ 傍骨膜注射で対応可能である。(1回あたりの処置の範囲は、1/4-1/6顎単位(歯数3-4本)で行う。)
⇒1.8mlカートリッジ1本以内の傍骨膜注射で対応可能
○ 浸潤麻酔行為の上記特徴を踏まえ、国民に安心・安全な歯科医療を提供するため、本研修の対象とする
歯科衛生士が実施する浸潤麻酔行為については、
・使用する薬剤量が比較的少ない
・歯科衛生士の多くが歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去、ルートプレーニングを実施している
ことから、歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去(SRP)時の疼痛除去を目的とする場合としてはどうか。
23