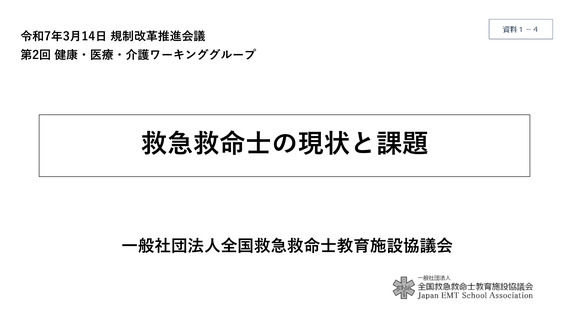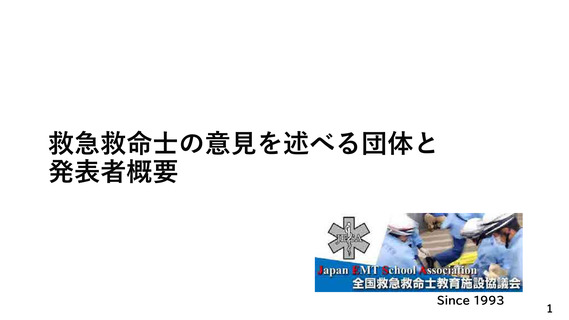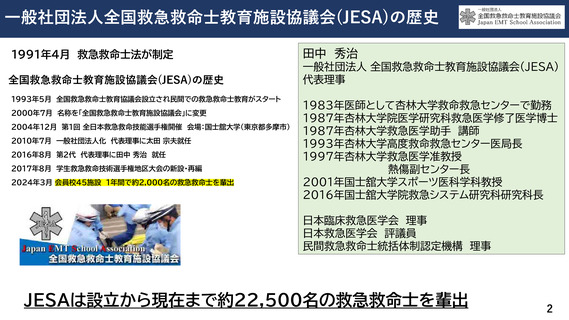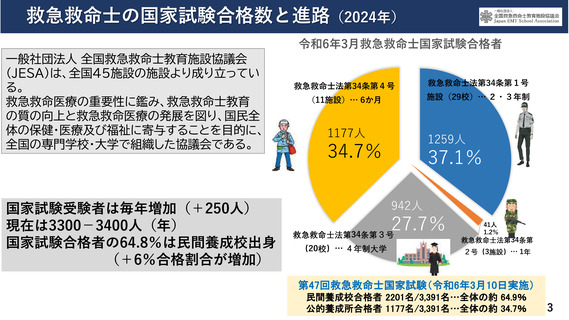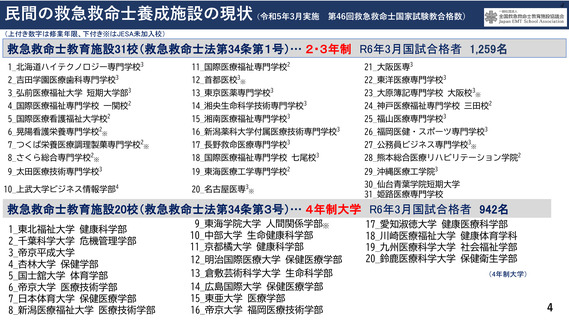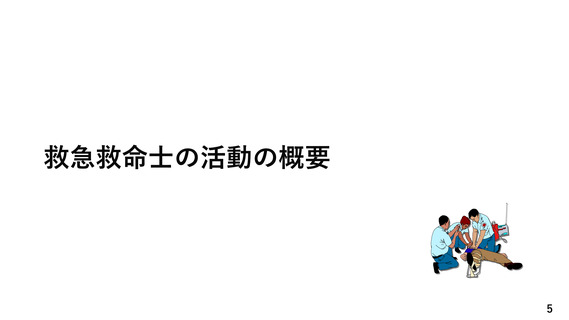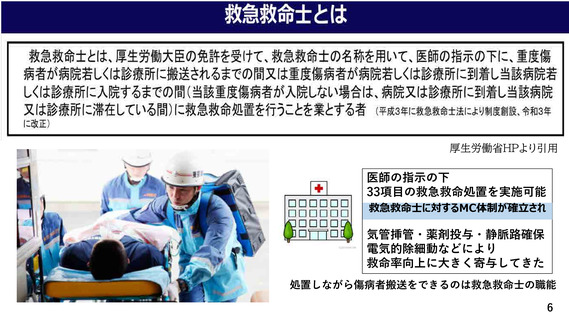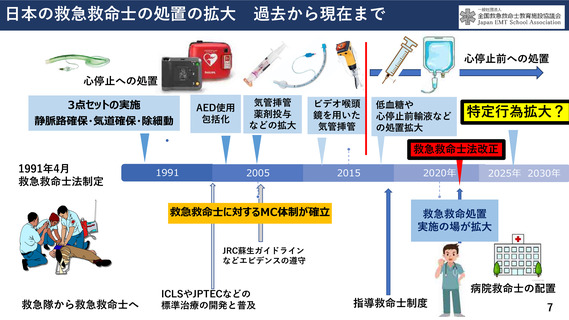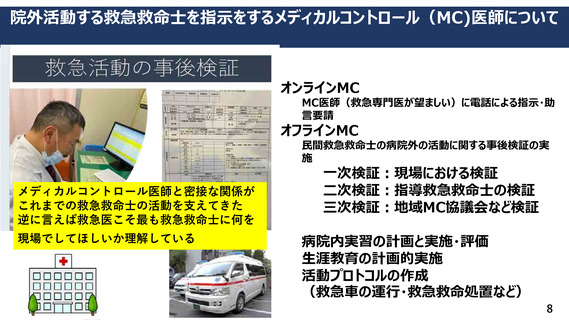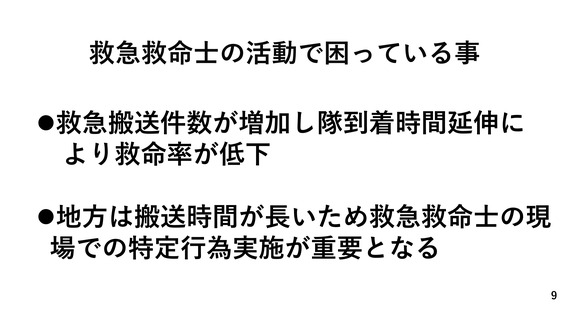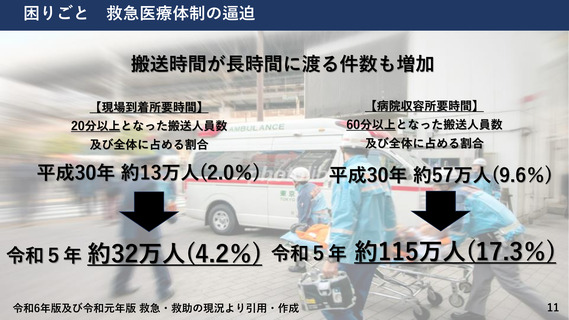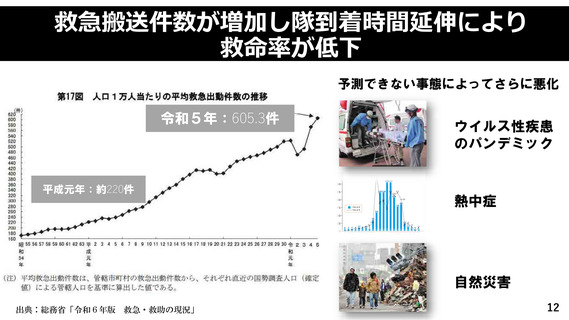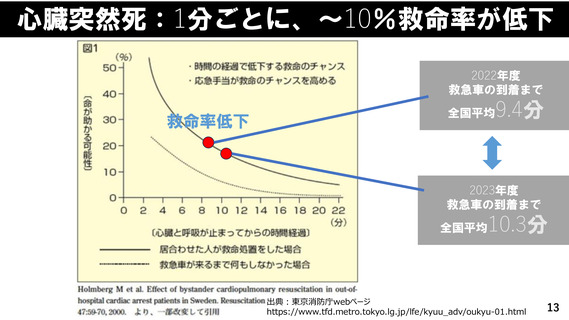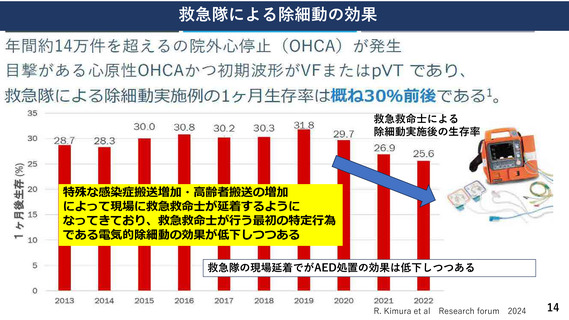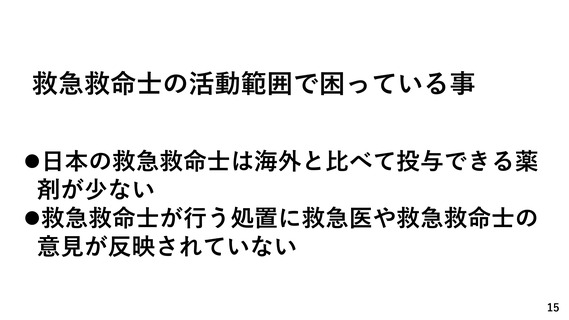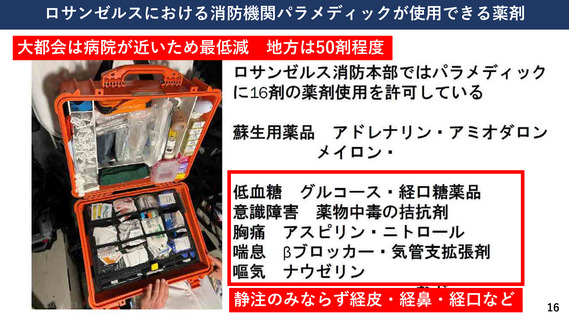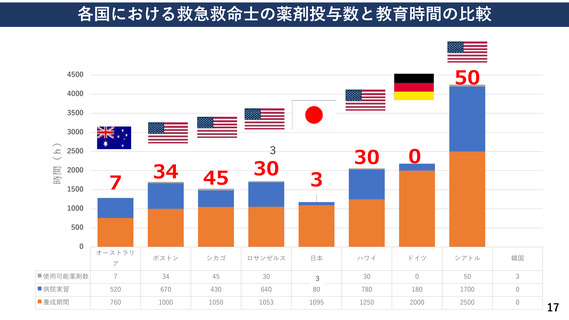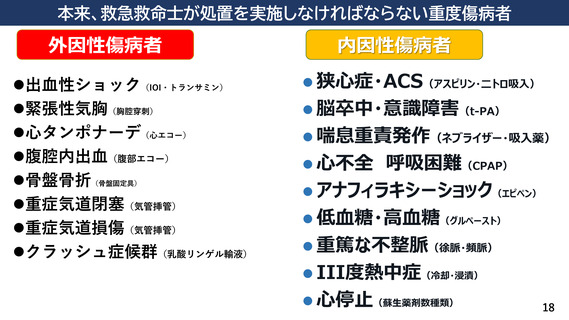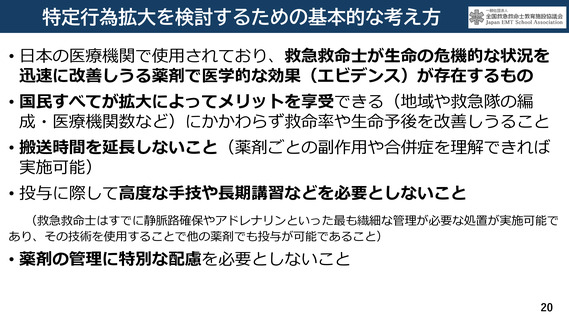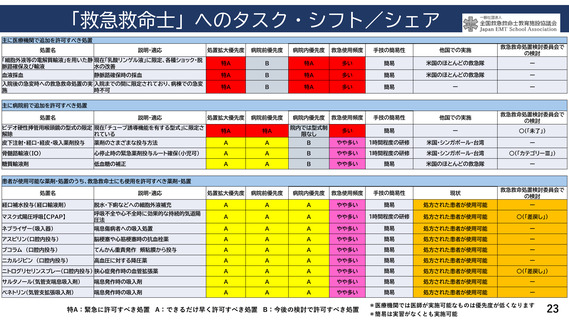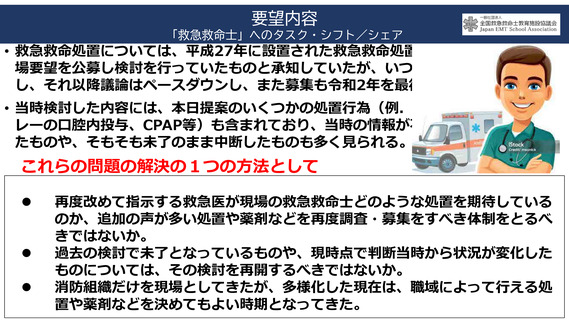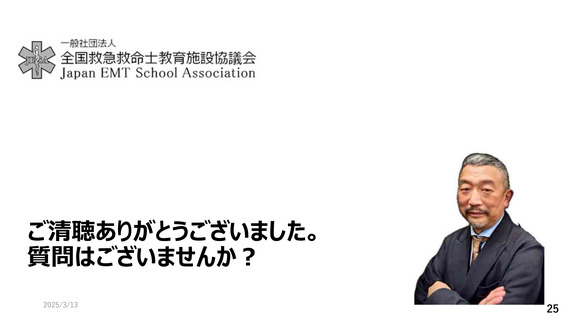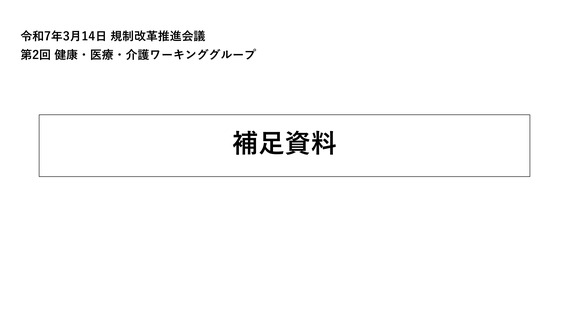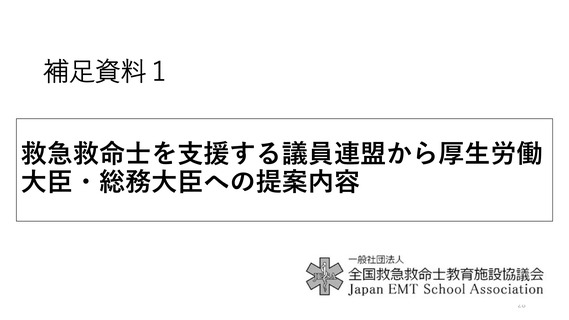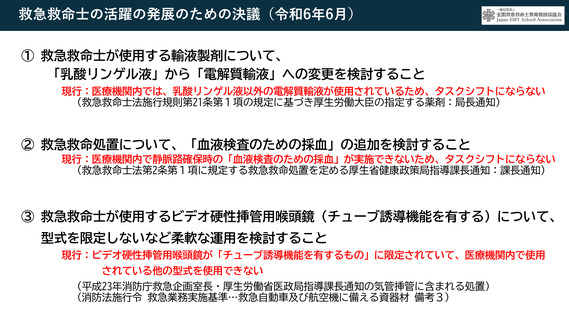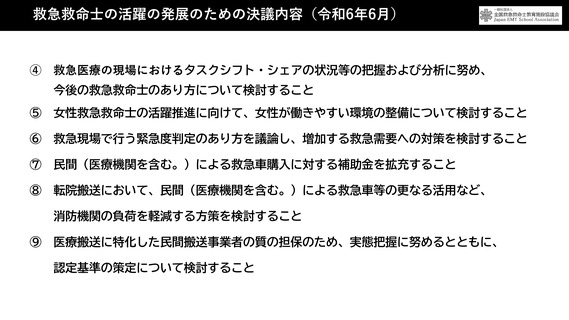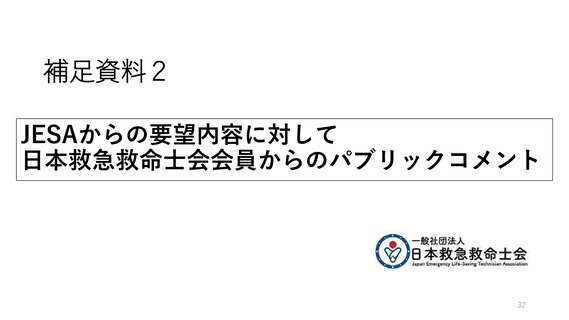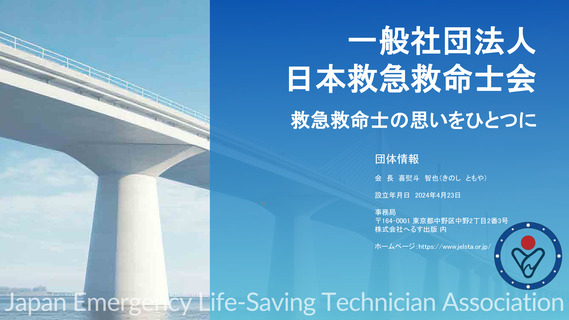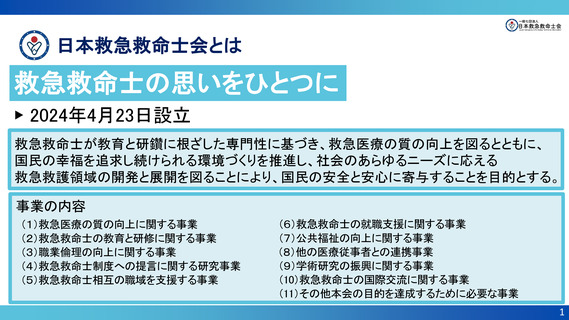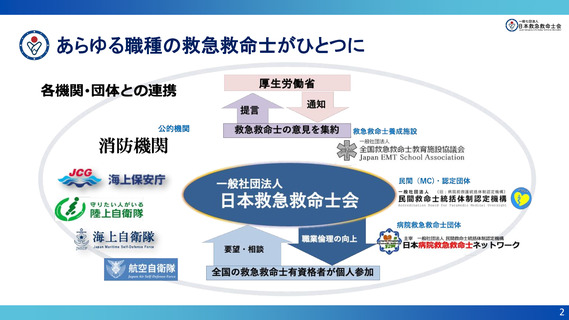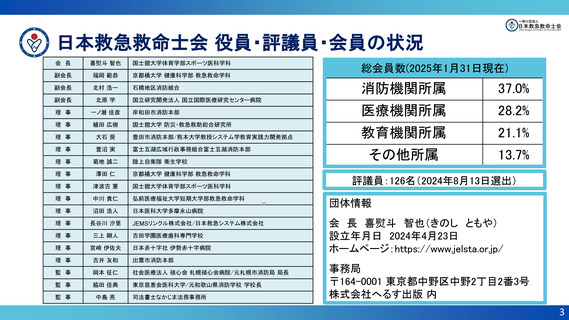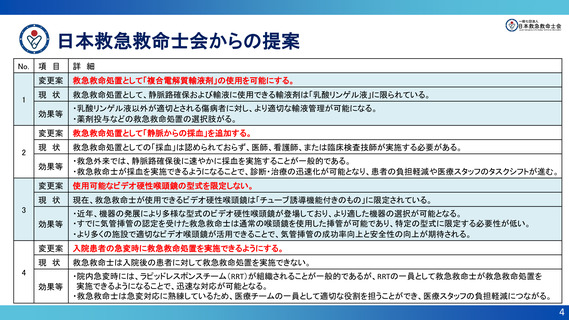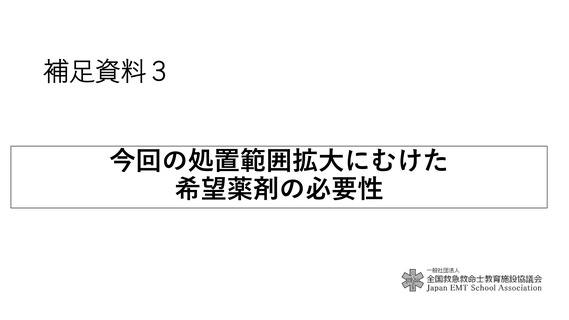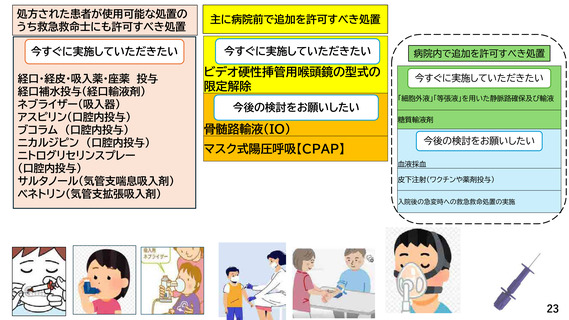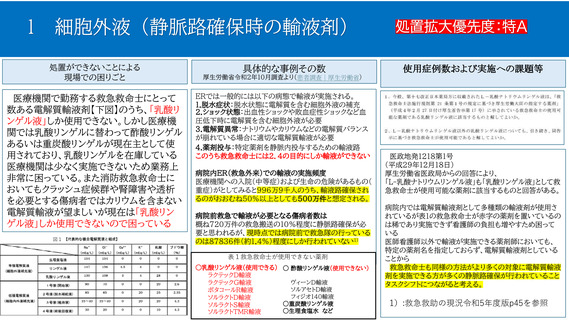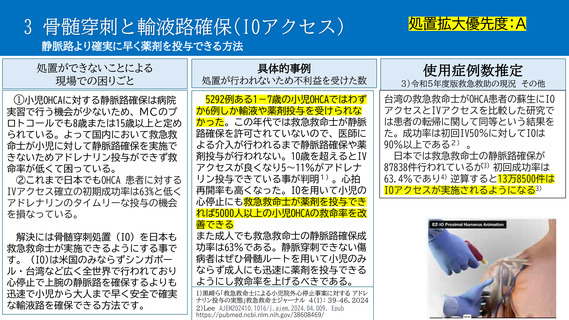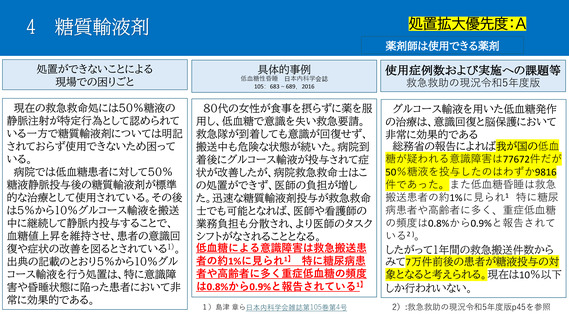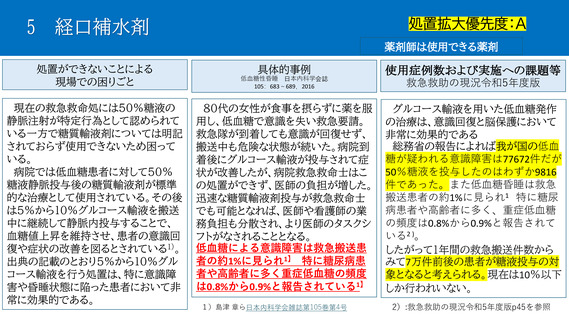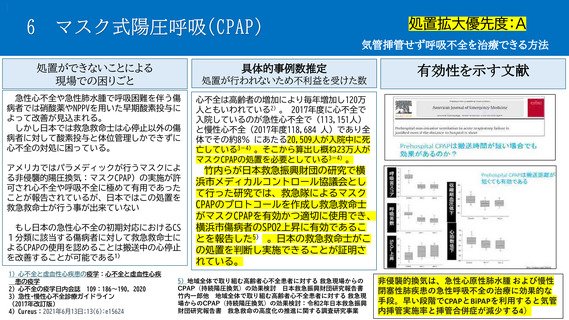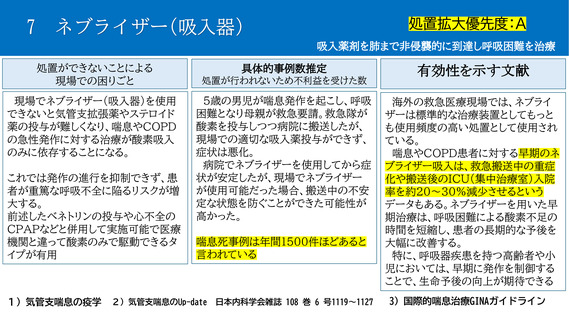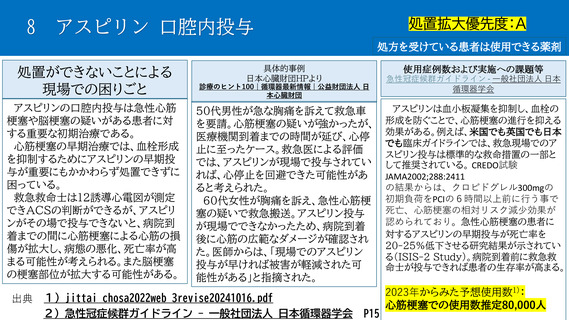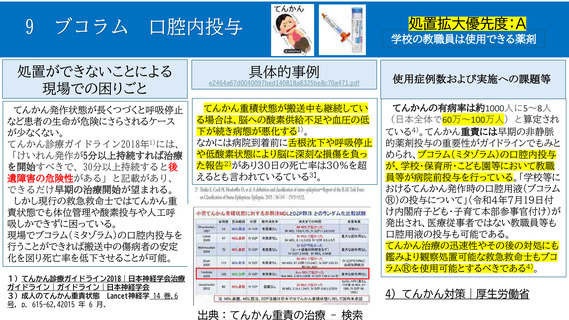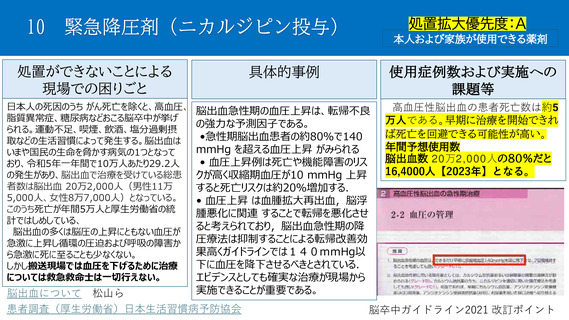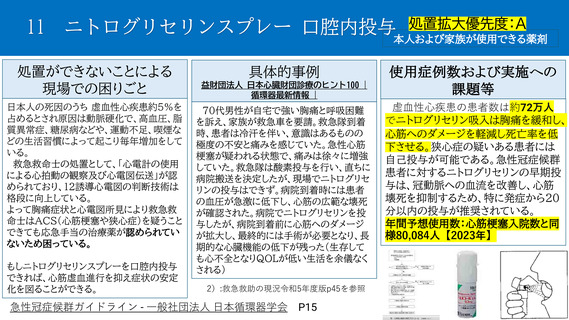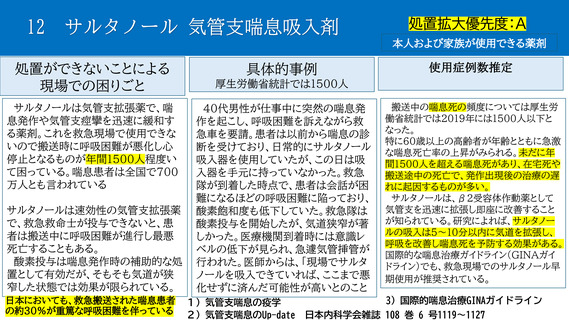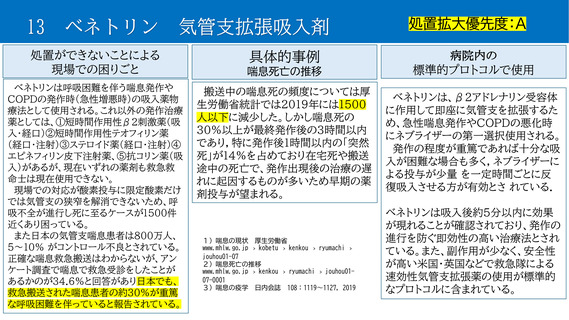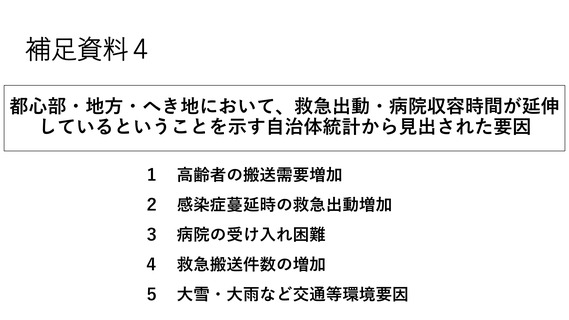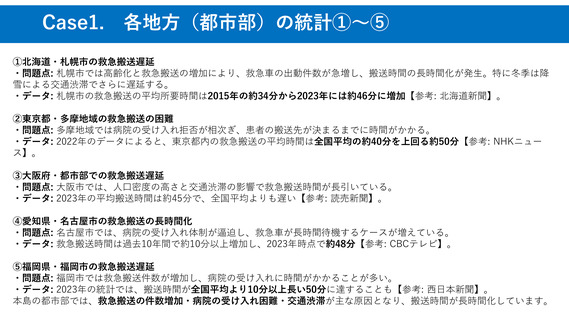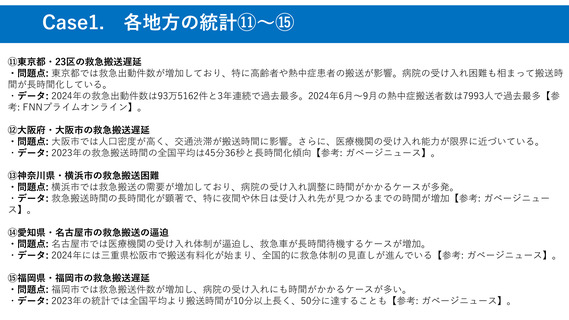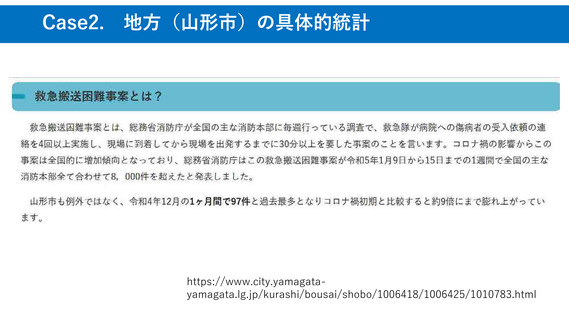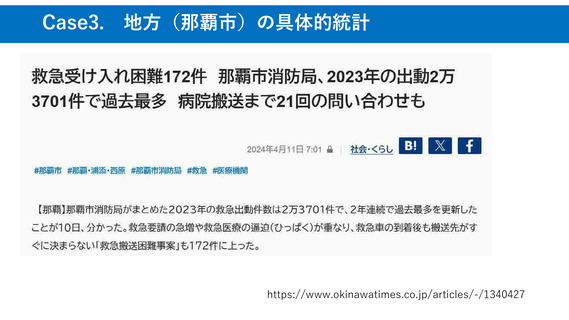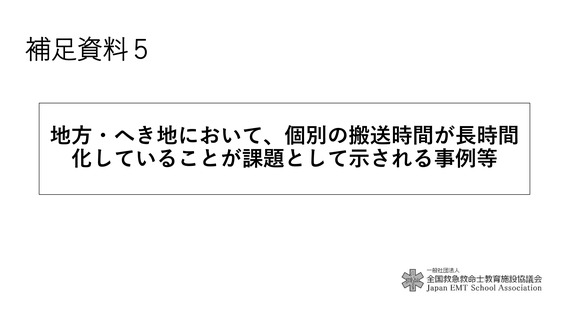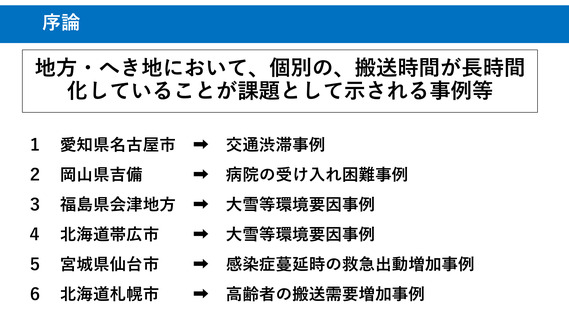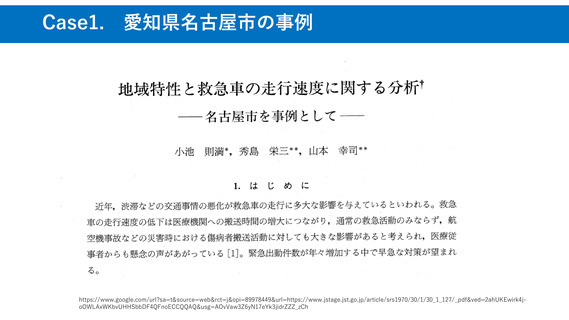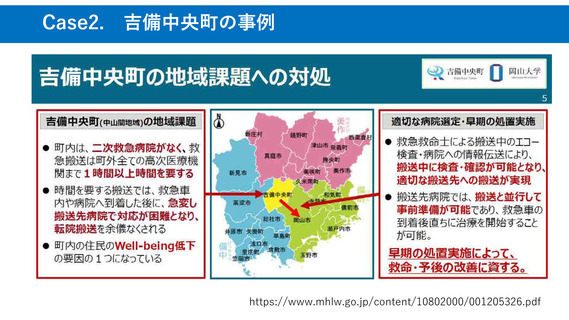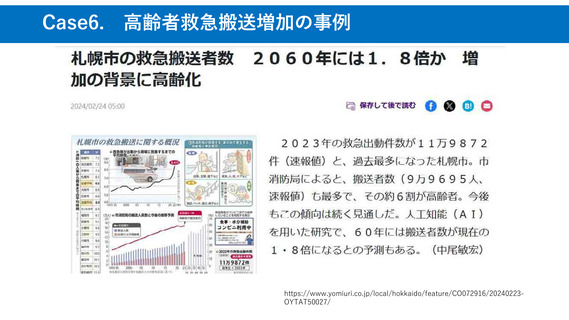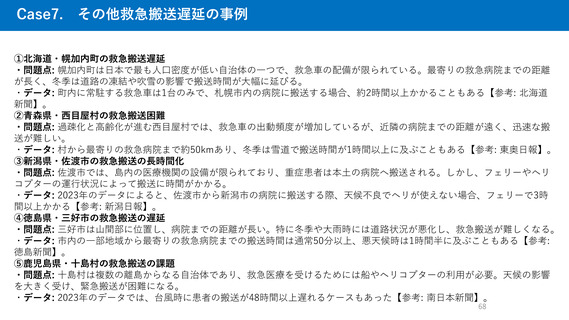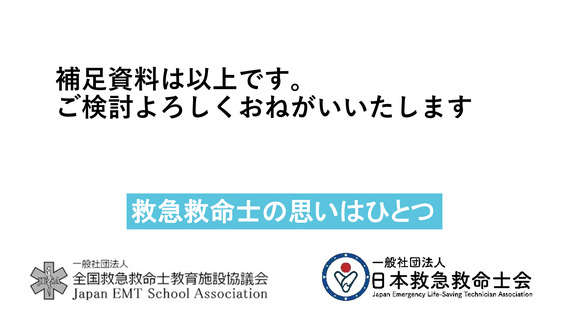よむ、つかう、まなぶ。
資料1ー4 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 御提出資料 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1
細胞外液(静脈路確保時の輸液剤)
処置ができないことによる
現場での困りごと
医療機関で勤務する救急救命士にとって
数ある電解質輸液剤【下図】のうち、「乳酸リ
ンゲル液」しか使用できない。しかし医療機
関では乳酸リンゲルに替わって酢酸リンゲル
あるいは重炭酸リンゲルが現在主として使
用されており、乳酸リンゲルを在庫している
医療機関は少なく実施できないため業務上
非常に困っている。また消防救急救命士に
おいてもクラッシュ症候群や腎障害や透析
を必要とする傷病者ではカリウムを含まない
電解質輸液が望ましいが現在は「乳酸リン
ゲル液」しか使用できないので困っている
図1
具体的な事例その数
処置拡大優先度:特A
使用症例数および実施への課題等
厚生労働省令和2年10月調査より(患者調査|厚生労働省)
ERでは一般的には以下の病態で輸液が実施される。
1.脱水症状:脱水状態に電解質を含む細胞外液の補充
2.ショック状態:出血性ショックや敗血症性ショックなど血
圧低下時に電解質を含む細胞外液が必要
3.電解質異常:ナトリウムやカリウムなどの電解質バランス
が崩れている場合に適切な電解質輸液が必要
4.薬剤投与:特定薬剤を静脈内投与するための輸液路
このうち救急救命士には2.4の目的にしか輸液ができない
病院内ER(救急外来)での輸液の実施頻度
医療機関への入院(中等症)および生命の危険があるもの(
重症)がとしてみると996万9千人のうち、輸液路確保され
るのがおおむね50%以上としても500万件と想定される。
病院前救急で輸液が必要となる傷病者数は
概ね720万件の救急搬送の10%程度に静脈路確保が必
要と思われるが、現時点では病院前で救急隊の行っている
のは87836件(約1.4%)程度にしか行われていない1)
表1救急救命士が使用できない薬剤
○乳酸リンゲル液(使用できる) ○ 酢酸リンゲル液(使用できない)
ラクテックD輸液
ヴィーンD輸液
ラクテックG輸液
ソルアセトD輸液
ポタコールR輸液
フィジオ140輸液
ソルラクトD輸液
○重炭酸リンゲル液
ソルラクトS輸液
○生理食塩水 など
ソルラクトTMR輸液
医政地発1218第1号
(平成29年12月18日)
厚生労働省医政局からの回答により、
「L-乳酸ナトリウムリンゲル液」も「乳酸リンゲル液」として救
急救命士が使用可能な薬剤に該当するものと回答がある。
病院内では電解質輸液剤として多種類の輸液剤が使用さ
れているが表1の救急救命士が赤字の薬剤を置いているの
は稀であり実施できず看護師の負担も増やすため困って
いる
医師看護師以外で輸液が実施できる薬剤師においても、
特定の薬剤名を指定しておらず、電解質輸液剤としている
ことから
救急救命士も同様の方法がより多くの対象に電解質輸液
剤を実施できる方が多くの静脈路確保が行われていること
タスクシフトにつながると考える。
1):救急救助の現況令和5年度版p45を参照
細胞外液(静脈路確保時の輸液剤)
処置ができないことによる
現場での困りごと
医療機関で勤務する救急救命士にとって
数ある電解質輸液剤【下図】のうち、「乳酸リ
ンゲル液」しか使用できない。しかし医療機
関では乳酸リンゲルに替わって酢酸リンゲル
あるいは重炭酸リンゲルが現在主として使
用されており、乳酸リンゲルを在庫している
医療機関は少なく実施できないため業務上
非常に困っている。また消防救急救命士に
おいてもクラッシュ症候群や腎障害や透析
を必要とする傷病者ではカリウムを含まない
電解質輸液が望ましいが現在は「乳酸リン
ゲル液」しか使用できないので困っている
図1
具体的な事例その数
処置拡大優先度:特A
使用症例数および実施への課題等
厚生労働省令和2年10月調査より(患者調査|厚生労働省)
ERでは一般的には以下の病態で輸液が実施される。
1.脱水症状:脱水状態に電解質を含む細胞外液の補充
2.ショック状態:出血性ショックや敗血症性ショックなど血
圧低下時に電解質を含む細胞外液が必要
3.電解質異常:ナトリウムやカリウムなどの電解質バランス
が崩れている場合に適切な電解質輸液が必要
4.薬剤投与:特定薬剤を静脈内投与するための輸液路
このうち救急救命士には2.4の目的にしか輸液ができない
病院内ER(救急外来)での輸液の実施頻度
医療機関への入院(中等症)および生命の危険があるもの(
重症)がとしてみると996万9千人のうち、輸液路確保され
るのがおおむね50%以上としても500万件と想定される。
病院前救急で輸液が必要となる傷病者数は
概ね720万件の救急搬送の10%程度に静脈路確保が必
要と思われるが、現時点では病院前で救急隊の行っている
のは87836件(約1.4%)程度にしか行われていない1)
表1救急救命士が使用できない薬剤
○乳酸リンゲル液(使用できる) ○ 酢酸リンゲル液(使用できない)
ラクテックD輸液
ヴィーンD輸液
ラクテックG輸液
ソルアセトD輸液
ポタコールR輸液
フィジオ140輸液
ソルラクトD輸液
○重炭酸リンゲル液
ソルラクトS輸液
○生理食塩水 など
ソルラクトTMR輸液
医政地発1218第1号
(平成29年12月18日)
厚生労働省医政局からの回答により、
「L-乳酸ナトリウムリンゲル液」も「乳酸リンゲル液」として救
急救命士が使用可能な薬剤に該当するものと回答がある。
病院内では電解質輸液剤として多種類の輸液剤が使用さ
れているが表1の救急救命士が赤字の薬剤を置いているの
は稀であり実施できず看護師の負担も増やすため困って
いる
医師看護師以外で輸液が実施できる薬剤師においても、
特定の薬剤名を指定しておらず、電解質輸液剤としている
ことから
救急救命士も同様の方法がより多くの対象に電解質輸液
剤を実施できる方が多くの静脈路確保が行われていること
タスクシフトにつながると考える。
1):救急救助の現況令和5年度版p45を参照