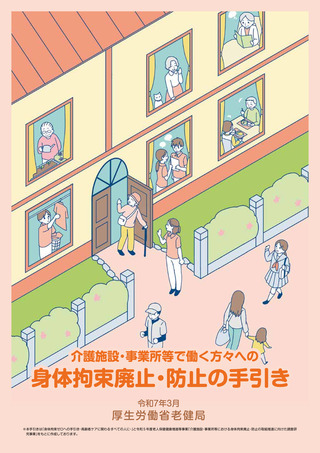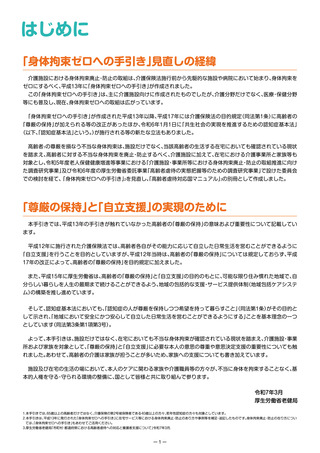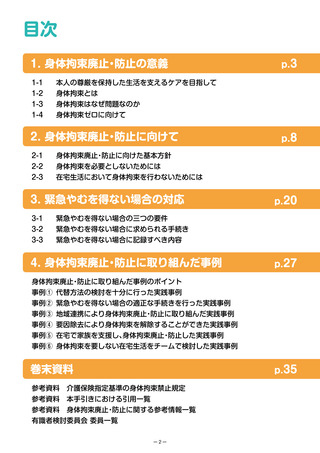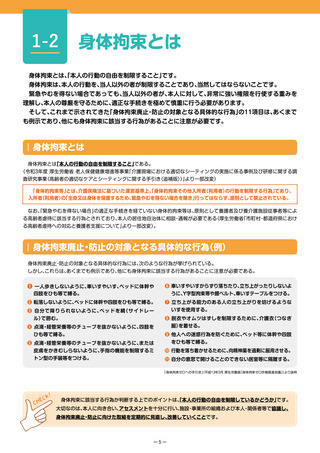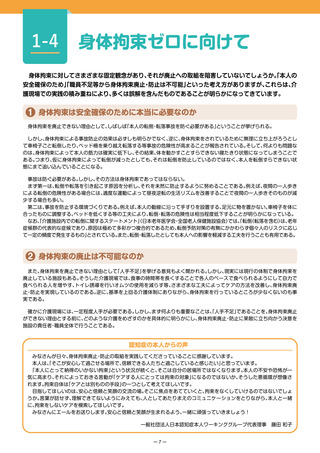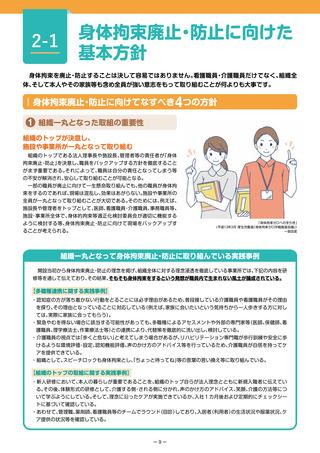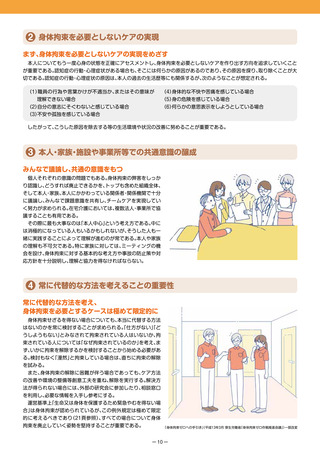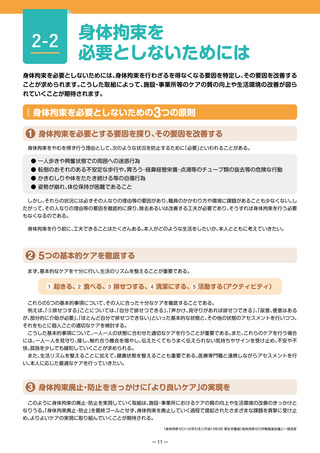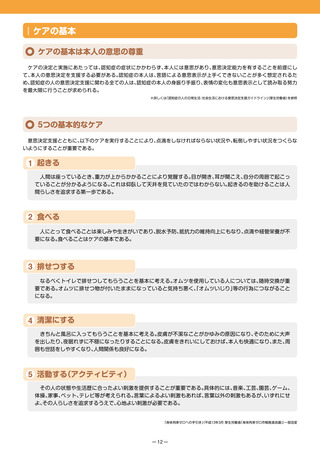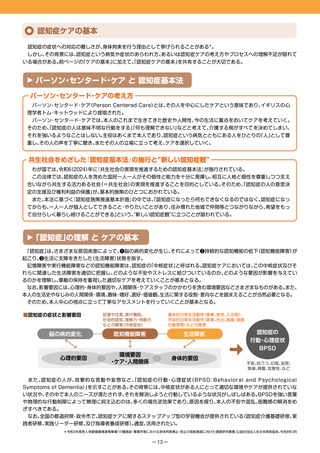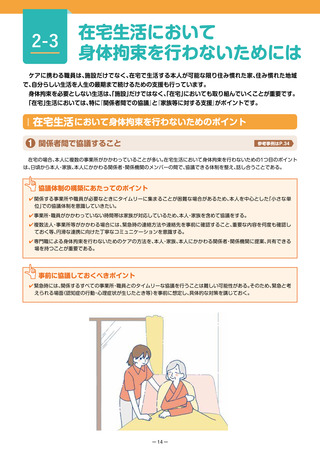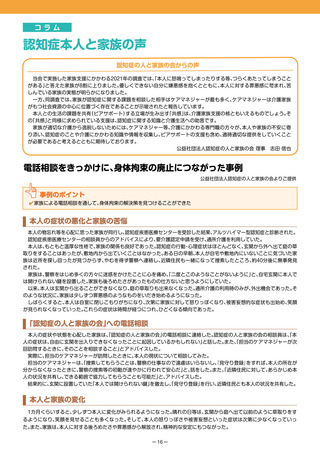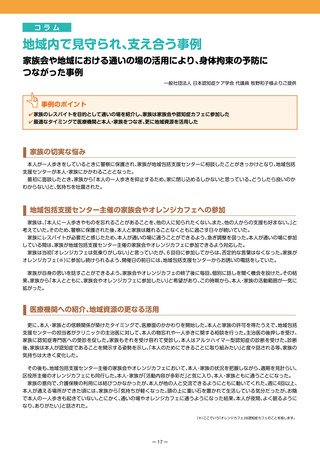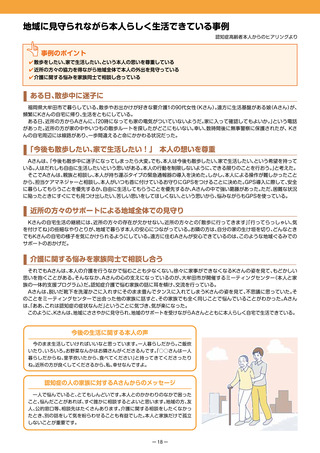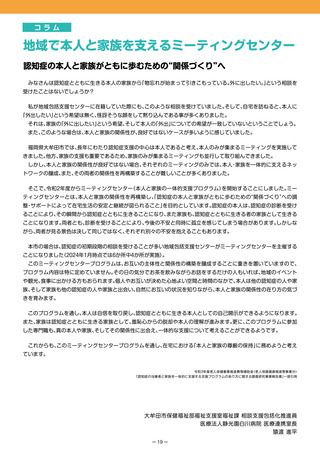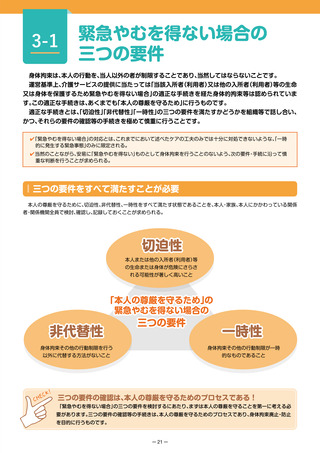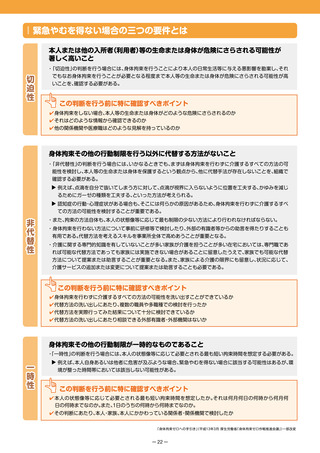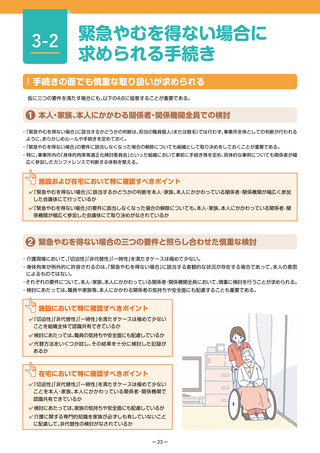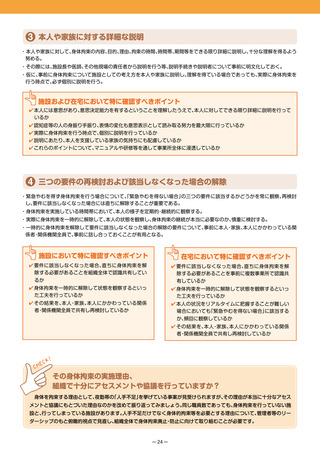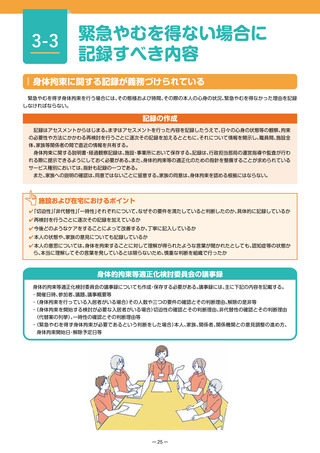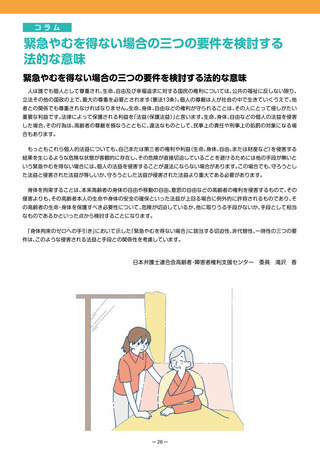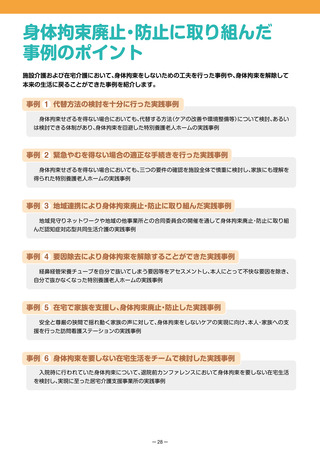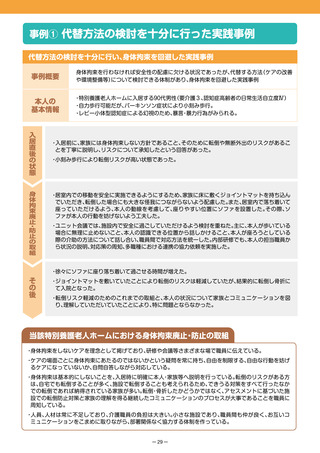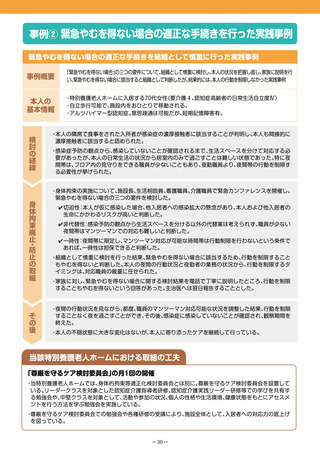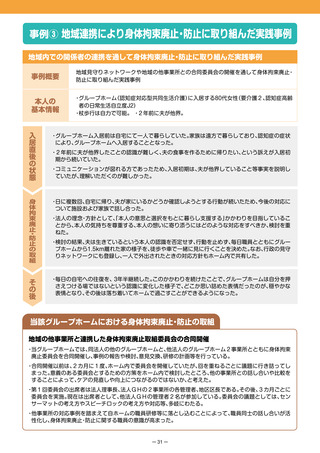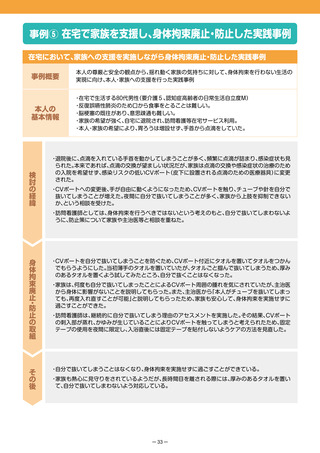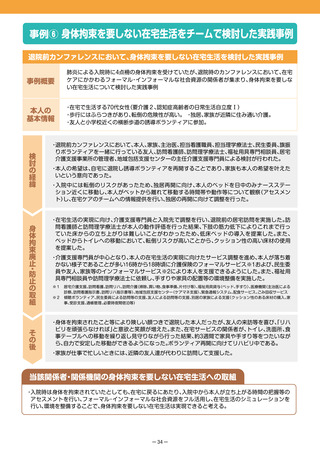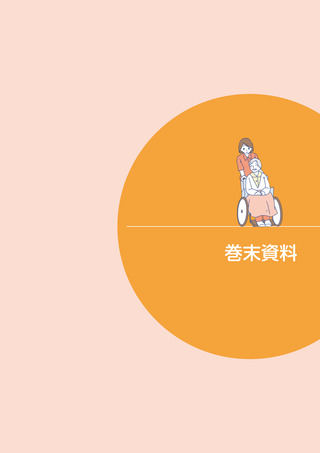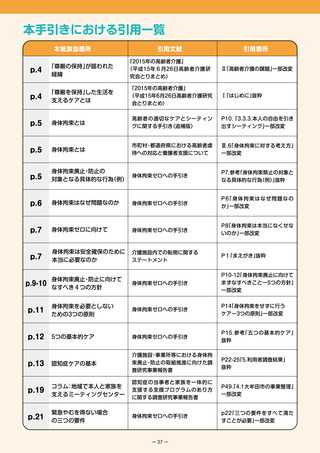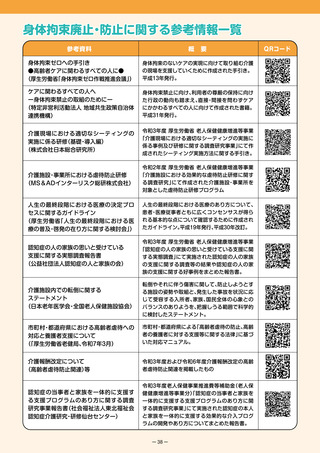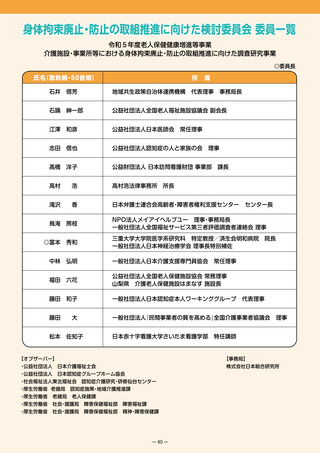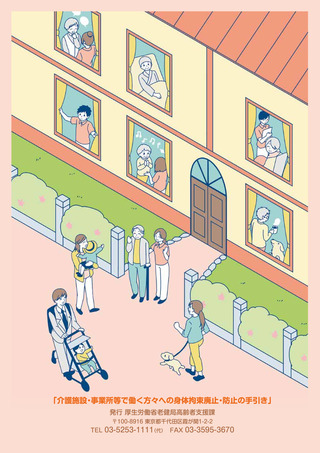よむ、つかう、まなぶ。
介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |
| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
身体拘束廃止・防止に向けた
基本方針
2-1
身体拘束を廃止・防止することは決して容易ではありません。看護職員・介護職員だけでなく、組織全
体、そして本人やその家族等も含め全員が強い意志をもって取り組むことが何よりも大事です。
身体拘束廃止・防止に向けてなすべき4つの方針
1 組織一丸となった取組の重要性
組織のトップが決意し、
施設や事業所が一丸となって取り組む
組織のトップである法人理事長や施設長、管理者等の責任者が「身体
拘束廃止・防止」を決意し、職員をバックアップする方針を徹底すること
がまず重要である。それによって、職員は自分の責任となってしまう等
の不安が解消され、安心して取り組むことが可能となる。
一部の職員が廃止に向けて一生懸命取り組んでも、他の職員が身体拘
束をするのであれば、現場は混乱し、効果はあがらない。施設や事業所の
全員が一丸となって取り組むことが大切である。そのためには、例えば、
施設長や管理者をトップとして、医師、看護職員・介護職員、事務職員等、
施設・事業所全体で、身体的拘束等適正化検討委員会が適切に機能する
ように検討する等、身体拘束廃止・防止に向けて現場をバックアップす
ることが考えられる。
「身体拘束ゼロへの手引き」
(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)
一部改変
組織一丸となって身体拘束廃止・防止に取り組んでいる実践事例
開設当初から身体拘束廃止・防止の理念を掲げ、組織全体に対する理念浸透を徹底している事業所では、下記の内容を研
修等を通して伝えており、その結果、そもそも身体拘束をするという発想が職員内で生まれない風土が醸成されている。
【多職種連携に関する実践事例】
・認知症の方が落ち着かない行動をとることには必ず理由があるため、普段接している介護職員や看護職員がその理由
を探り、その理由となっていることに対応している(例えば、家族に会いたいという気持ちから一人歩きする方に対し
ては、実際に家族に会ってもらう)。
・緊急やむを得ない場合に該当する可能性があっても、多職種によるアセスメントや外部の専門家等(医師、保健師、看
護職員、理学療法士、作業療法士等)との連携により、代替策を徹底的に洗い出し、検討している。
・介護職員の視点では「歩くと危ない」と考えてしまう場合があるが、リハビリテーション専門職が歩行訓練や安全に歩
けるような環境評価・設定、認知機能評価、声のかけ方のアドバイス等を行っているため、介護職員が自信を持ってケ
アを提供できている。
・組織として、スピーチロックも身体拘束とし、
「ちょっと待ってね」等の言葉の言い換え等に取り組んでいる。
【組織のトップの取組に関する実践事例】
・新人研修において、本人の暮らしが重要であることを、組織のトップ自らが法人理念とともに新規入職者に伝えてい
る。その後、体験形式の研修として、介護する側・される側に分かれ、声のかけ方のアドバイス、笑顔、介護の方法等につ
いて学ぶようにしている。そして、理念に沿ったケアが実施できているか、入社1カ月後および定期的にチェックシー
トに基づいて確認している。
・あわせて、管理職、薬剤師、看護職員等のチームでラウンド(回診)しており、入居者(利用者)の生活状況や服薬状況、ケ
ア提供の状況等を確認している。
ー9ー
基本方針
2-1
身体拘束を廃止・防止することは決して容易ではありません。看護職員・介護職員だけでなく、組織全
体、そして本人やその家族等も含め全員が強い意志をもって取り組むことが何よりも大事です。
身体拘束廃止・防止に向けてなすべき4つの方針
1 組織一丸となった取組の重要性
組織のトップが決意し、
施設や事業所が一丸となって取り組む
組織のトップである法人理事長や施設長、管理者等の責任者が「身体
拘束廃止・防止」を決意し、職員をバックアップする方針を徹底すること
がまず重要である。それによって、職員は自分の責任となってしまう等
の不安が解消され、安心して取り組むことが可能となる。
一部の職員が廃止に向けて一生懸命取り組んでも、他の職員が身体拘
束をするのであれば、現場は混乱し、効果はあがらない。施設や事業所の
全員が一丸となって取り組むことが大切である。そのためには、例えば、
施設長や管理者をトップとして、医師、看護職員・介護職員、事務職員等、
施設・事業所全体で、身体的拘束等適正化検討委員会が適切に機能する
ように検討する等、身体拘束廃止・防止に向けて現場をバックアップす
ることが考えられる。
「身体拘束ゼロへの手引き」
(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)
一部改変
組織一丸となって身体拘束廃止・防止に取り組んでいる実践事例
開設当初から身体拘束廃止・防止の理念を掲げ、組織全体に対する理念浸透を徹底している事業所では、下記の内容を研
修等を通して伝えており、その結果、そもそも身体拘束をするという発想が職員内で生まれない風土が醸成されている。
【多職種連携に関する実践事例】
・認知症の方が落ち着かない行動をとることには必ず理由があるため、普段接している介護職員や看護職員がその理由
を探り、その理由となっていることに対応している(例えば、家族に会いたいという気持ちから一人歩きする方に対し
ては、実際に家族に会ってもらう)。
・緊急やむを得ない場合に該当する可能性があっても、多職種によるアセスメントや外部の専門家等(医師、保健師、看
護職員、理学療法士、作業療法士等)との連携により、代替策を徹底的に洗い出し、検討している。
・介護職員の視点では「歩くと危ない」と考えてしまう場合があるが、リハビリテーション専門職が歩行訓練や安全に歩
けるような環境評価・設定、認知機能評価、声のかけ方のアドバイス等を行っているため、介護職員が自信を持ってケ
アを提供できている。
・組織として、スピーチロックも身体拘束とし、
「ちょっと待ってね」等の言葉の言い換え等に取り組んでいる。
【組織のトップの取組に関する実践事例】
・新人研修において、本人の暮らしが重要であることを、組織のトップ自らが法人理念とともに新規入職者に伝えてい
る。その後、体験形式の研修として、介護する側・される側に分かれ、声のかけ方のアドバイス、笑顔、介護の方法等につ
いて学ぶようにしている。そして、理念に沿ったケアが実施できているか、入社1カ月後および定期的にチェックシー
トに基づいて確認している。
・あわせて、管理職、薬剤師、看護職員等のチームでラウンド(回診)しており、入居者(利用者)の生活状況や服薬状況、ケ
ア提供の状況等を確認している。
ー9ー