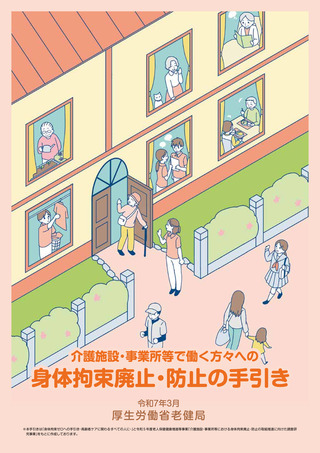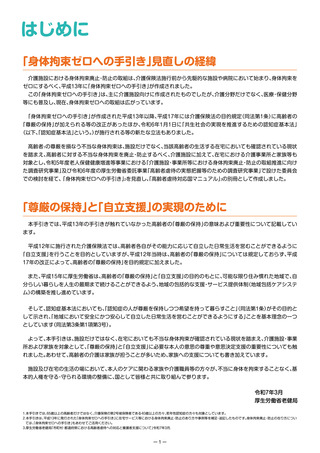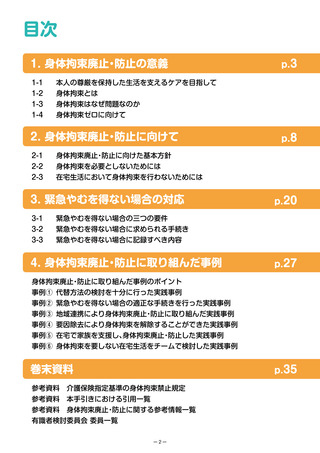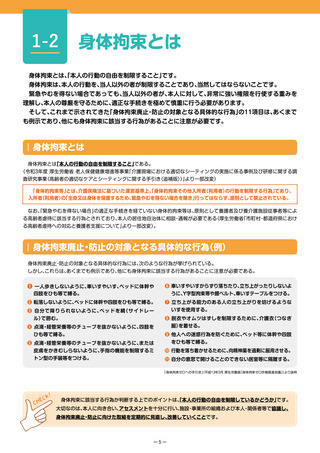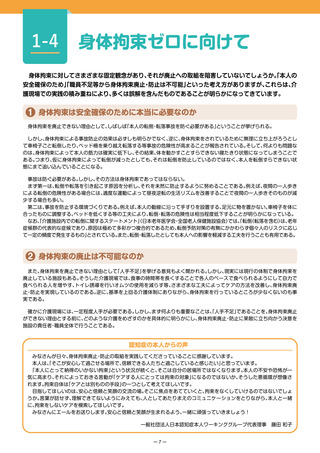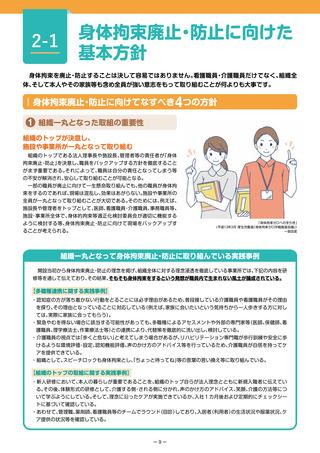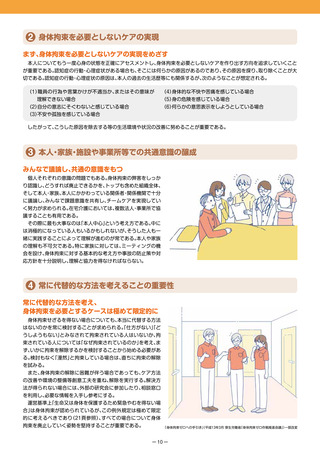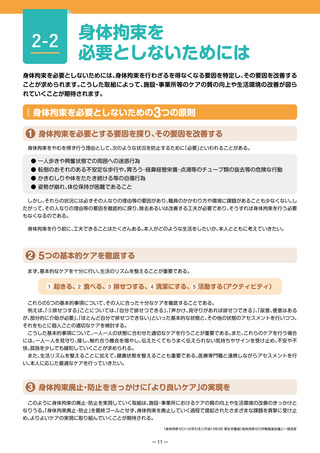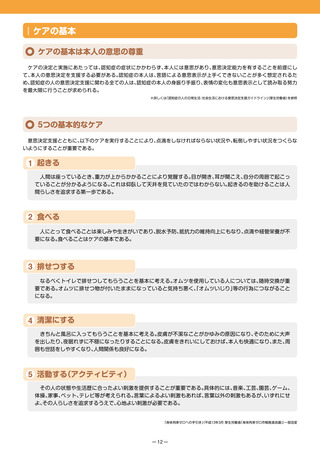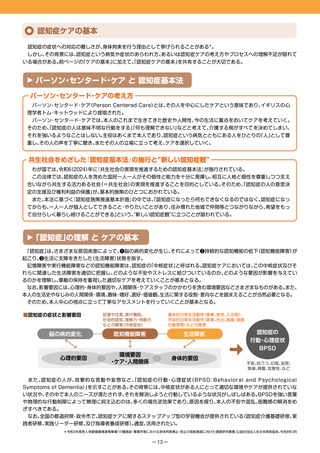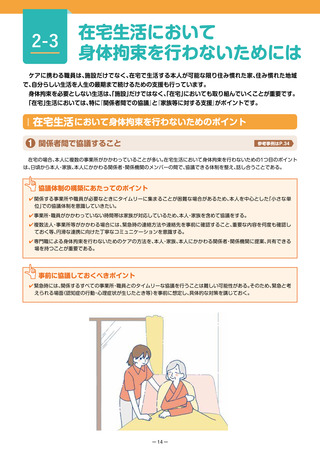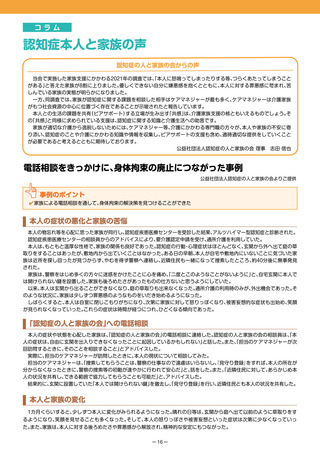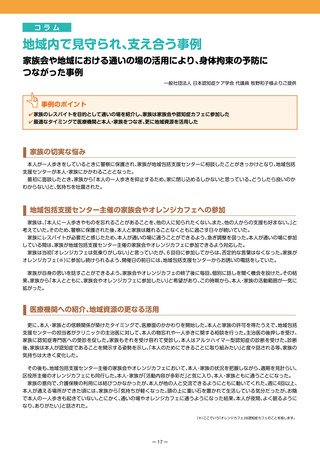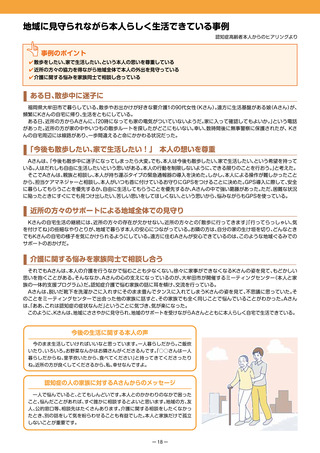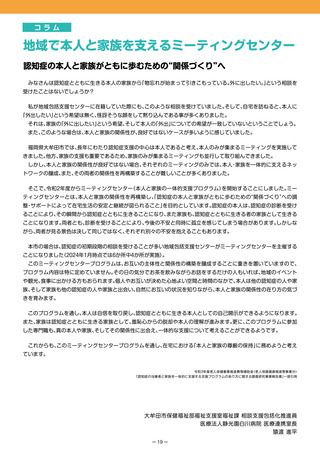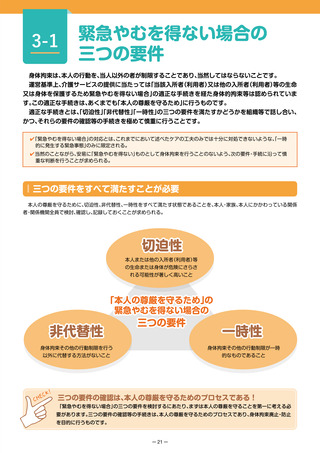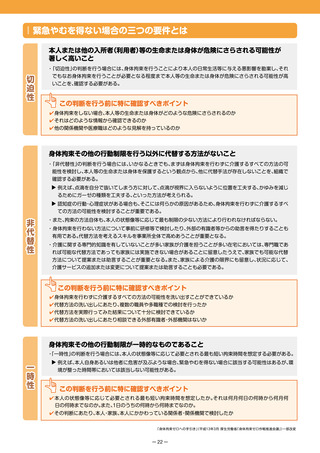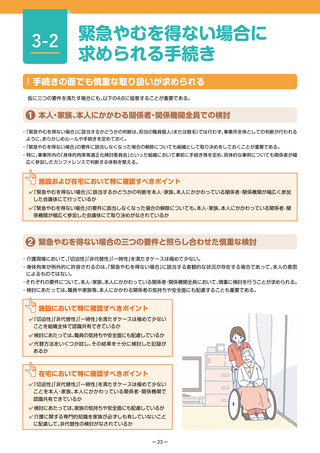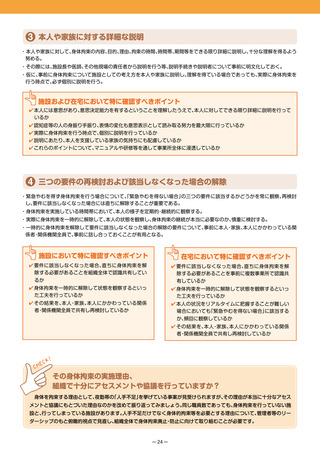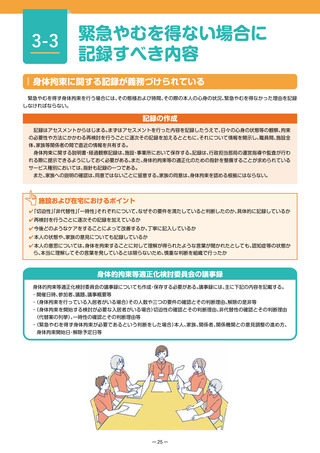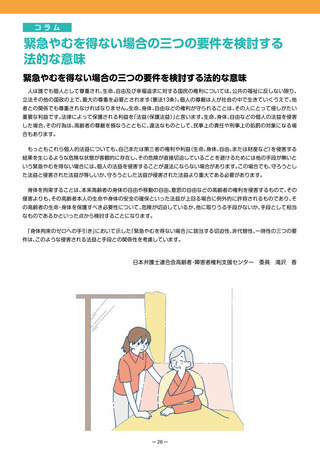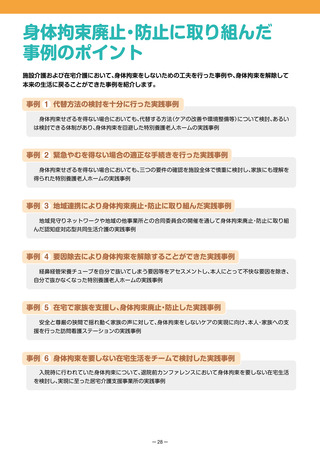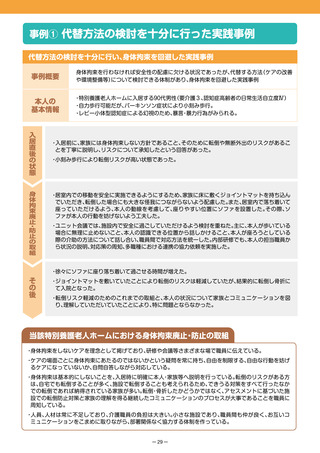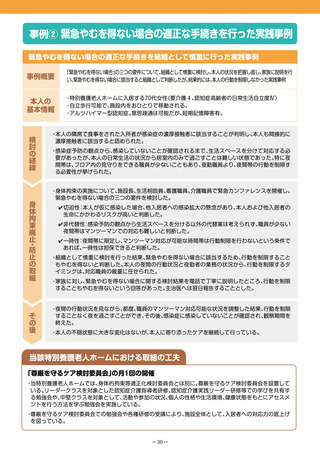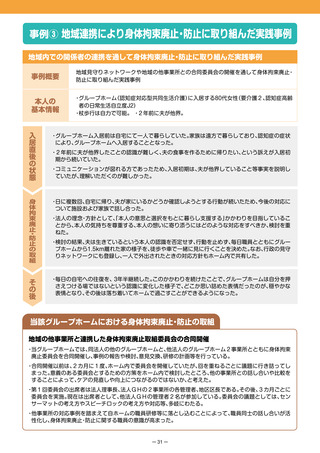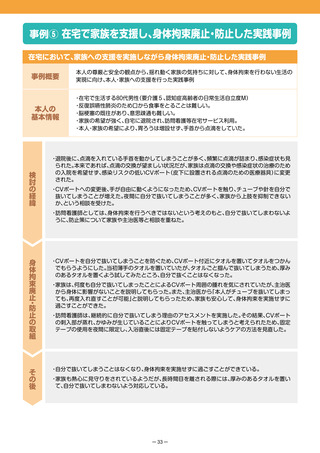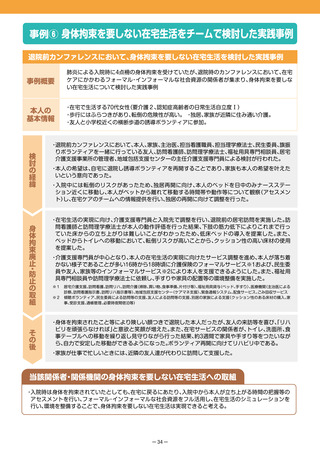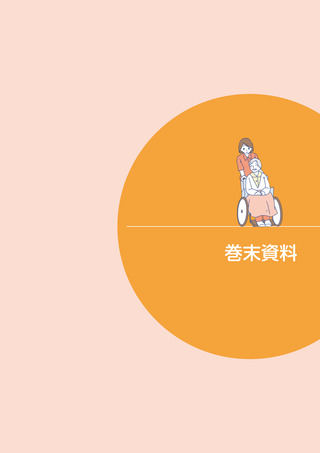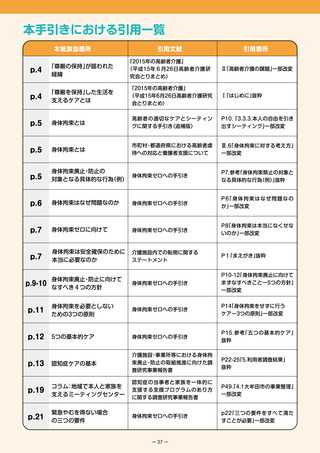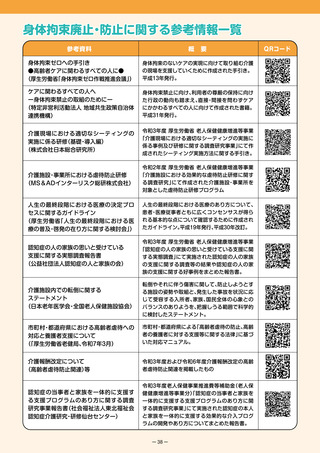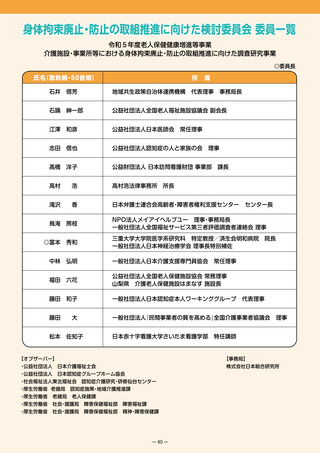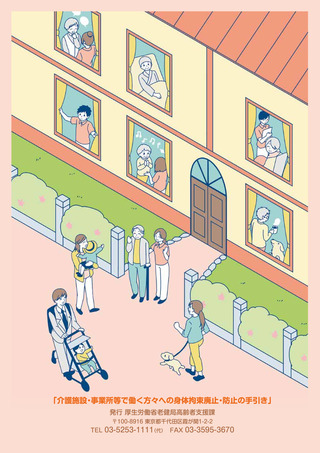よむ、つかう、まなぶ。
介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |
| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 家族等に対する支援を行うこと
参考事例はP.33
在宅生活において身体拘束を行わないための2つ目のポイントは、家族等に対する支援を行うことである。
在宅の場合、施設・事業所等がかかわる時間帯以外は、家族がケアをしていることが多い。身体拘束とは、
「本人の行動の自由を
制限すること」であり、家族が行う制限も身体拘束に該当する。したがって、ケアに携わる職員が、家族等に対する支援を行うこと
も極めて重要である。
家族等に対する支援を行うためには、まずは、家族に対する支援体制を構築していく必要がある。そして、身体拘束廃止・防止や
本人の尊厳や意思について、本人・家族とともに考えていくことが重要となる。
家族と本人の信頼関係は、本人の尊厳や意思の尊重に家族が思いを馳せて本人とコミュニケーションをとることによって構築
される。家族に対する支援体制を整え、本人・家族、本人にかかわる関係者・関係機関での話し合いの場を持つことによって、本人
と家族の信頼関係が醸成され、結果的に身体拘束をしなくても生活できるようになるケースが少なくない。
家族に対する支援体制の構築にあたってのポイント
✔身体拘束を必要としない在宅生活の実現には、施設・事業所等が、本人だけではなく、在宅で本人を支援する家族の意思や
環境を理解する必要がある。
✔身体拘束に関する苦悩について、家族から施設・事業所等に相談しづらい場合がある。日頃から、本人・家族・施設・事業所
等の間で相談できる関係性を築き、本人・家族が安心して生活できる環境を構築していきたい。
✔家族が何か困りごとや悩みを抱えていた場合に、家族に対する情緒的支援を行ったり、相談窓口を紹介したりすることも
有用である。家族が不安に感じていたら、必要に応じて地域にあるピアサポート活動の場(認知症カフェ等)や認知症の人
と家族の会が実施するつどい等を紹介することで、同じ立場の仲間で話すことができ、不安の解消につながることもあ
る。また、役場や社会福祉協議会等が電話相談窓口を設置していることもあるため、確認しておきたい。
認知症の本人や家族等の相談窓口
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助等を行
い、高齢者の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的
な機関として市町村が設置しています。
認知症疾患医療センター
認知症疾患医療センターは、認知症の速やかな鑑別診断や、行動・心理症状(BPSD)と身体合併症に対する急性期医
療、専門医療相談、関係機関との連携、研修会の開催等の役割を担っています。
本人・家族とともに考えていくにあたってのポイント
✔身体拘束が「本人の行動の自由を制限すること」であることや、本人の尊厳や意思尊重の重要性、身体拘束の悪循環(※)等
を家族に丁寧に説明し、
「身体拘束をしないこと」が高齢者の自立促進につながること、あるいは、家族等の本人に対する
理解と信頼関係が深まることで、本人の状態が落ち着き、身体拘束の必要がなくなり、結果的に家族の負担軽減につなが
るケースがあることを意識したい。家族等の生活のためや治療上の必要性により、本人に対する身体拘束が必要と考えて
いる場合もあることから、
「身体拘束の必要性や代替性は、本人・家族、本人にかかわる関係者・関係機関の間で協議をする
必要があること」をお伝えし、家族の生活を守るためにもどのような支援やケアの方法があるか話し合う場をまず持つこ
とを提案していきたい。
▼
例えば、本人とのコミュニケーションにおいては、
「本人の発言を否定せず、本人の心に寄り添って、不安を取り除き、
受け入れる」ことが重要である。このような認知症ケアの技術を家族に伝えていきたい。
✔家族等による身体拘束を防止するには、本人の状態を家族に理解してもらうことが重要である。
▼
例えば、在宅復帰時における尿道カテーテル等の継続の必要性について、主治医、本人・家族、施設・事業所職員等で一
緒に考えてみる等、本人・家族にとって望むべきあり方やそのための工夫をともに考えることが重要となる。
▼
また、認知症の方の場合、家族に「認知症の症状は進行性であり、いきなり進むのではなく、長い経過をたどること」、
「一人
一人の症状や困りごとは異なること」を理解いただき、目の前の本人の声をしっかりと聞いていくことの重要性をお伝え
していきたい。
✔また、本人および家族どちらも、本当に困っていることを言語化することが難しい場合やお互いの前では言いにくい、関
係者には言いにくい等配慮が必要な場合、家族は気づいていないが、他の方々が気づいている場合等、真の困りごと等を
引き出す支援を行い、具体的な対応策につなげられるようにすることも必要である。
※身体拘束の悪循環については、P.6を参照
ー 15 ー
参考事例はP.33
在宅生活において身体拘束を行わないための2つ目のポイントは、家族等に対する支援を行うことである。
在宅の場合、施設・事業所等がかかわる時間帯以外は、家族がケアをしていることが多い。身体拘束とは、
「本人の行動の自由を
制限すること」であり、家族が行う制限も身体拘束に該当する。したがって、ケアに携わる職員が、家族等に対する支援を行うこと
も極めて重要である。
家族等に対する支援を行うためには、まずは、家族に対する支援体制を構築していく必要がある。そして、身体拘束廃止・防止や
本人の尊厳や意思について、本人・家族とともに考えていくことが重要となる。
家族と本人の信頼関係は、本人の尊厳や意思の尊重に家族が思いを馳せて本人とコミュニケーションをとることによって構築
される。家族に対する支援体制を整え、本人・家族、本人にかかわる関係者・関係機関での話し合いの場を持つことによって、本人
と家族の信頼関係が醸成され、結果的に身体拘束をしなくても生活できるようになるケースが少なくない。
家族に対する支援体制の構築にあたってのポイント
✔身体拘束を必要としない在宅生活の実現には、施設・事業所等が、本人だけではなく、在宅で本人を支援する家族の意思や
環境を理解する必要がある。
✔身体拘束に関する苦悩について、家族から施設・事業所等に相談しづらい場合がある。日頃から、本人・家族・施設・事業所
等の間で相談できる関係性を築き、本人・家族が安心して生活できる環境を構築していきたい。
✔家族が何か困りごとや悩みを抱えていた場合に、家族に対する情緒的支援を行ったり、相談窓口を紹介したりすることも
有用である。家族が不安に感じていたら、必要に応じて地域にあるピアサポート活動の場(認知症カフェ等)や認知症の人
と家族の会が実施するつどい等を紹介することで、同じ立場の仲間で話すことができ、不安の解消につながることもあ
る。また、役場や社会福祉協議会等が電話相談窓口を設置していることもあるため、確認しておきたい。
認知症の本人や家族等の相談窓口
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助等を行
い、高齢者の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的
な機関として市町村が設置しています。
認知症疾患医療センター
認知症疾患医療センターは、認知症の速やかな鑑別診断や、行動・心理症状(BPSD)と身体合併症に対する急性期医
療、専門医療相談、関係機関との連携、研修会の開催等の役割を担っています。
本人・家族とともに考えていくにあたってのポイント
✔身体拘束が「本人の行動の自由を制限すること」であることや、本人の尊厳や意思尊重の重要性、身体拘束の悪循環(※)等
を家族に丁寧に説明し、
「身体拘束をしないこと」が高齢者の自立促進につながること、あるいは、家族等の本人に対する
理解と信頼関係が深まることで、本人の状態が落ち着き、身体拘束の必要がなくなり、結果的に家族の負担軽減につなが
るケースがあることを意識したい。家族等の生活のためや治療上の必要性により、本人に対する身体拘束が必要と考えて
いる場合もあることから、
「身体拘束の必要性や代替性は、本人・家族、本人にかかわる関係者・関係機関の間で協議をする
必要があること」をお伝えし、家族の生活を守るためにもどのような支援やケアの方法があるか話し合う場をまず持つこ
とを提案していきたい。
▼
例えば、本人とのコミュニケーションにおいては、
「本人の発言を否定せず、本人の心に寄り添って、不安を取り除き、
受け入れる」ことが重要である。このような認知症ケアの技術を家族に伝えていきたい。
✔家族等による身体拘束を防止するには、本人の状態を家族に理解してもらうことが重要である。
▼
例えば、在宅復帰時における尿道カテーテル等の継続の必要性について、主治医、本人・家族、施設・事業所職員等で一
緒に考えてみる等、本人・家族にとって望むべきあり方やそのための工夫をともに考えることが重要となる。
▼
また、認知症の方の場合、家族に「認知症の症状は進行性であり、いきなり進むのではなく、長い経過をたどること」、
「一人
一人の症状や困りごとは異なること」を理解いただき、目の前の本人の声をしっかりと聞いていくことの重要性をお伝え
していきたい。
✔また、本人および家族どちらも、本当に困っていることを言語化することが難しい場合やお互いの前では言いにくい、関
係者には言いにくい等配慮が必要な場合、家族は気づいていないが、他の方々が気づいている場合等、真の困りごと等を
引き出す支援を行い、具体的な対応策につなげられるようにすることも必要である。
※身体拘束の悪循環については、P.6を参照
ー 15 ー