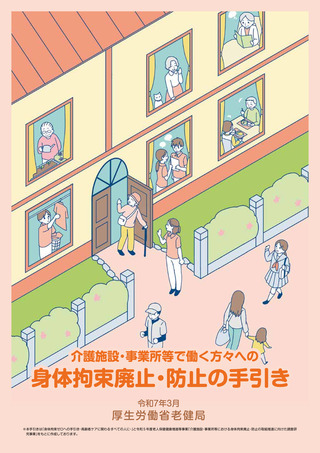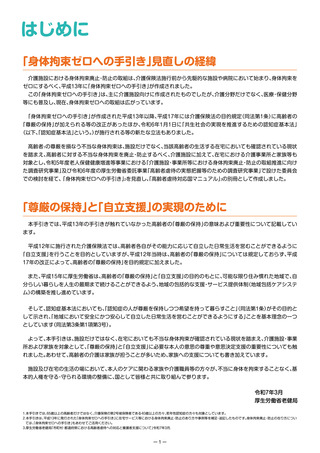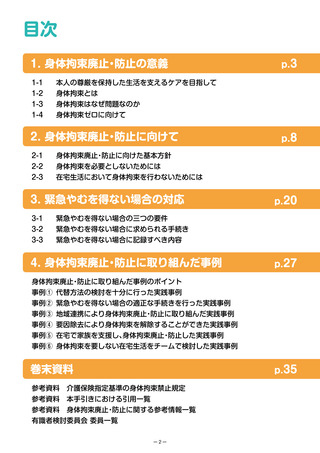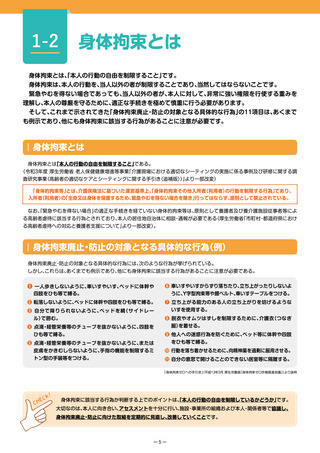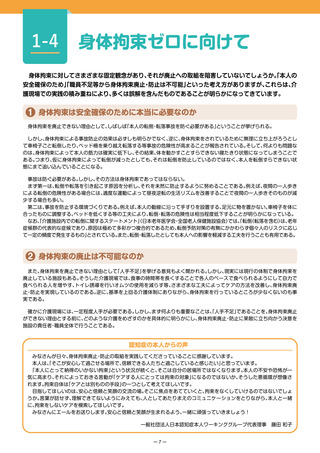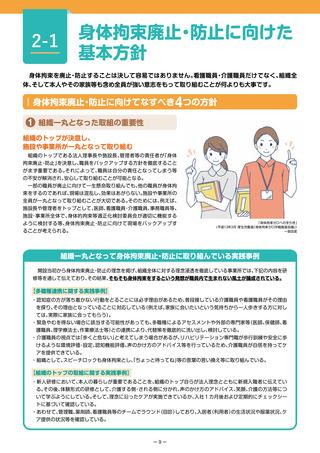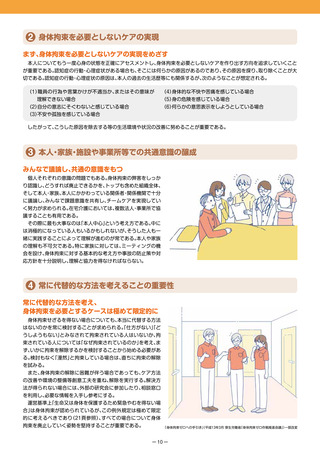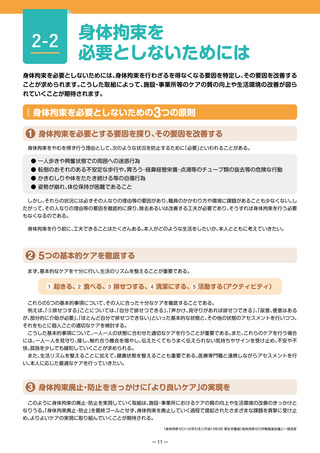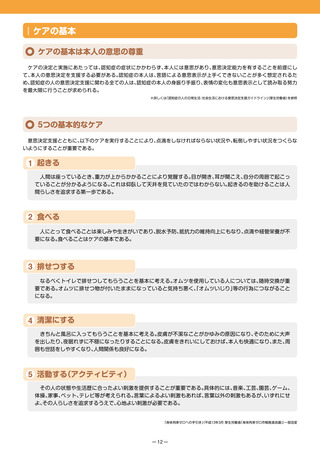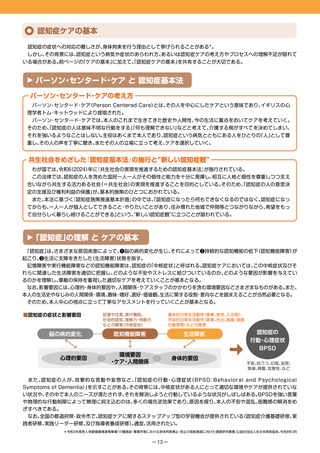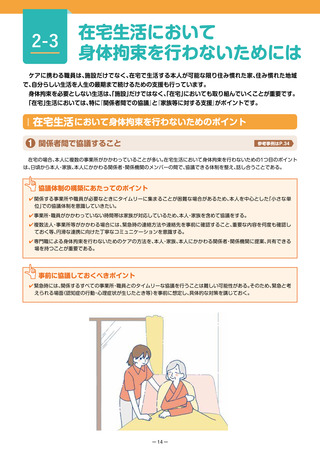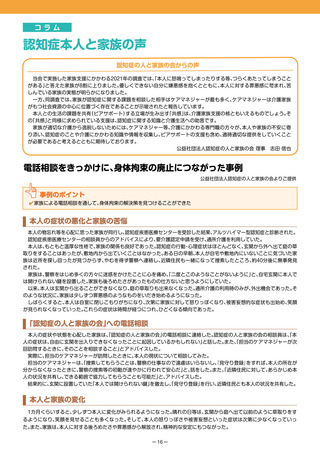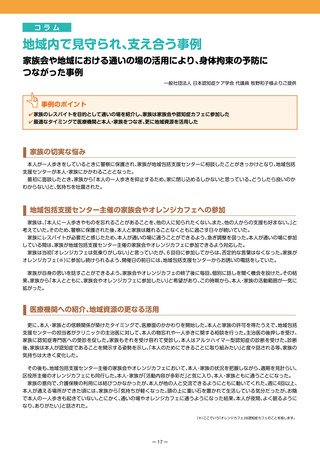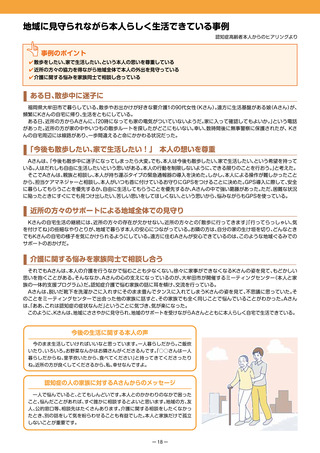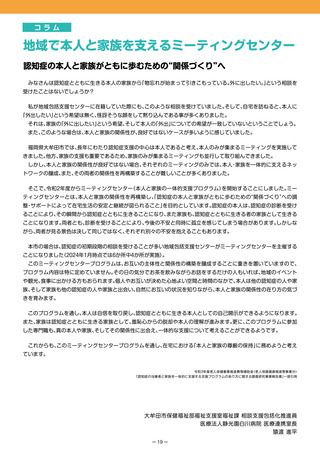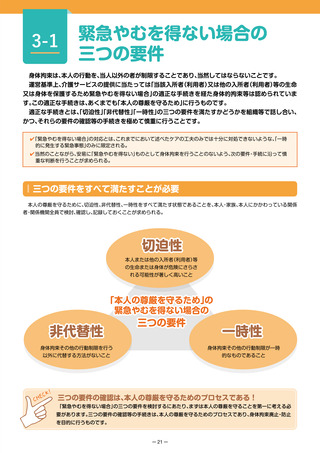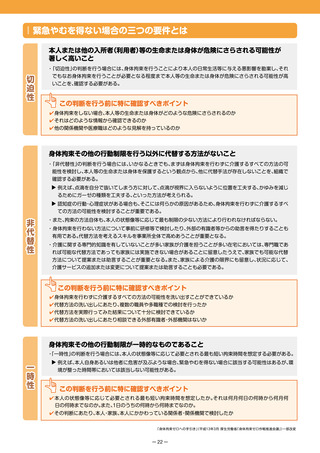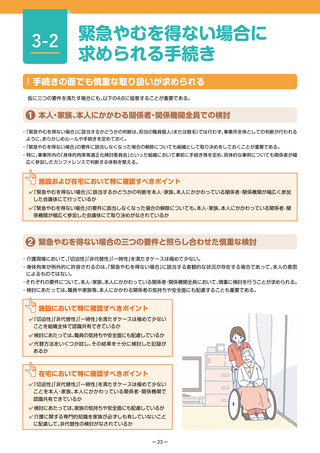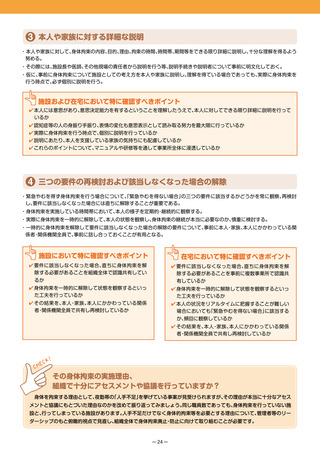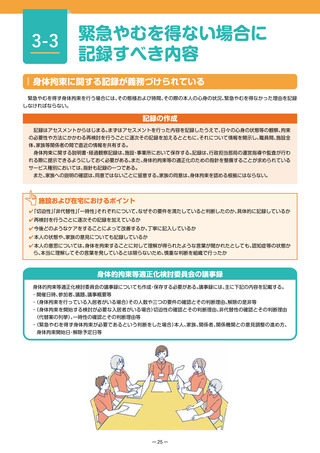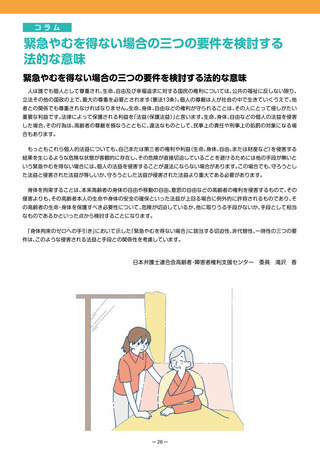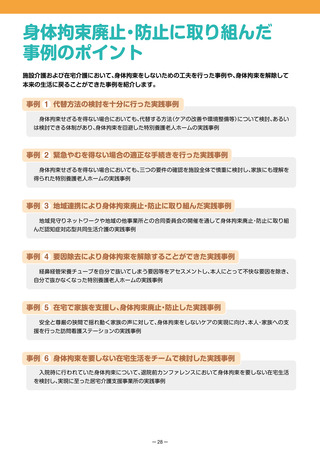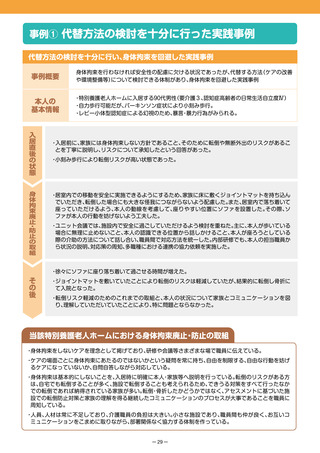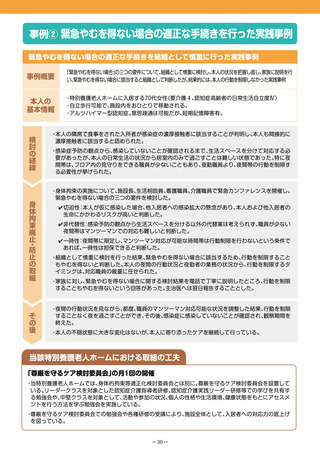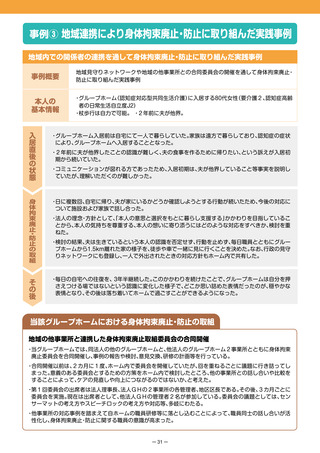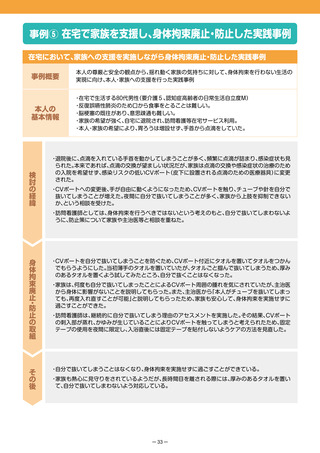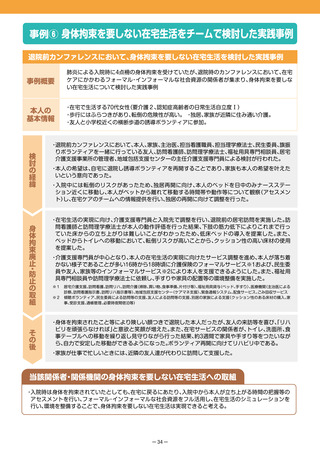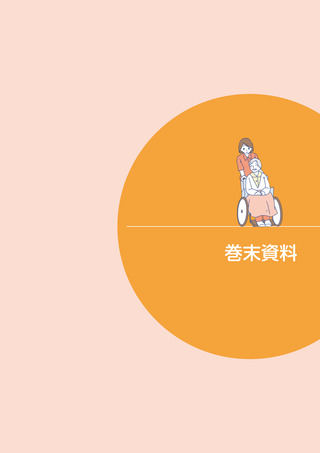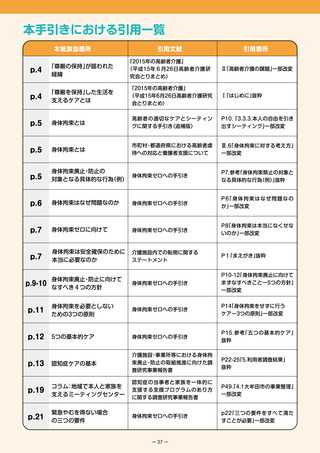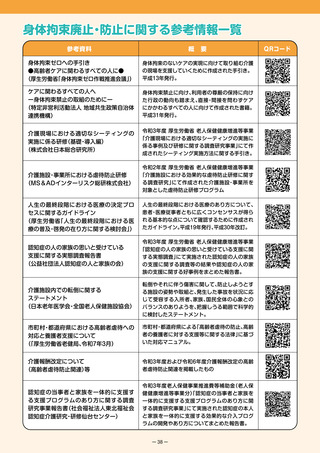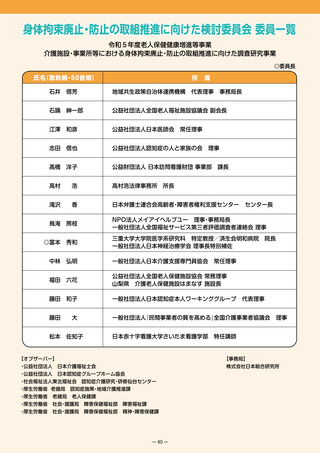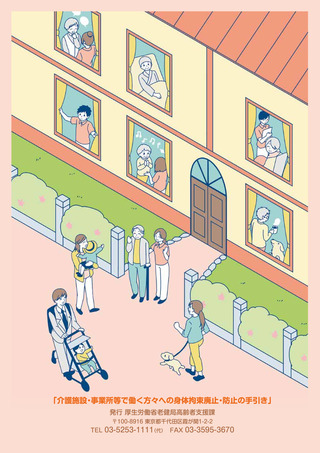よむ、つかう、まなぶ。
介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |
| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
コラム
地域内で見守られ、支え合う事例
家族会や地域における通いの場の活用により、身体拘束の予防に
つながった事例
一般社団法人 日本認知症ケア学会 代議員 牧野和子様よりご提供
事例のポイント
✔家族のレスパイトを目的として通いの場を紹介し、家族は家族会や認知症カフェに参加した
✔最適なタイミングで医療機関と本人・家族をつなぎ、更に地域資源を活用した
家族の切実な悩み
本人が一人歩きをしているときに警察に保護され、家族が地域包括支援センターに相談したことがきっかけとなり、地域包括
支援センターが本人・家族にかかわることとなった。
最初に面談したとき、家族から「本人の一人歩きを抑止するため、家に閉じ込めるしかないと思っている。どうしたら良いのか
わからない」と、気持ちを吐露された。
地域包括支援センター主催の家族会やオレンジカフェへの参加
家族は、
「本人に一人歩きやものを忘れることがあることを、他の人に知られたくない。また、他の人からの支援も好まない。」と
考えていた。そのため、警察に保護された後、本人と家族は離れることなくともに過ごす日々が続いていた。
家族にレスパイトが必要だと感じたため、本人が通いの場に通うことができるよう、急ぎ調整を図った。本人が通いの場に参加
している間は、家族が地域包括支援センター主催の家族会やオレンジカフェに参加できるよう対応した。
家族は当初「オレンジカフェは気乗りがしない」と言っていたが、6回目に参加してからは、否定的な言葉はなくなった。家族が
オレンジカフェ(※)に参加し続けられるよう、開催日の前日には、地域包括支援センターからお誘いの電話をしていた。
家族が自身の思いを話すことができるよう、家族会やオレンジカフェの終了後に毎回、個別に話しを聞く機会を設けた。その結
果、家族から「本人とともに、家族会やオレンジカフェに参加したい」と希望があり、この時期から、本人・家族の活動範囲が一気に
拡がった。
医療機関への紹介、地域資源の更なる活用
更に、本人・家族との信頼関係が築けたタイミングで、医療面のかかわりを開始した。本人と家族の許可を得たうえで、地域包括
支援センターの担当者がクリニックの主治医に対して、本人の物忘れや一人歩きに関する相談を行った。主治医の後押しを受け、
家族に認知症専門医への受診を促した。家族もそれを受け容れて受診し、本人はアルツハイマー型認知症の診断を受けた。診断
後、家族は本人が認知症であることを開示する姿勢を示し、
「本人のためにできることに取り組みたい」と度々話される等、家族の
気持ちは大きく変化した。
その後も、地域包括支援センター主催の家族会やオレンジカフェにおいて、本人・家族の状況を把握しながら、適期を見計らい、
区役所主催のオレンジカフェにも同行した。本人・家族が「活動内容が多彩だ」と気に入り、本人・家族ともに通うことになった。
家族の意向で、介護保険の利用には結びつかなかったが、本人が他の人と交流できるようにともに動いてくれた。週に4回以上、
本人が通える場所ができた頃には、家族から「気持ちが軽くなった。頭の上に重い石を置かれて生活している気分だったが、お陰
で本人の一人歩きも起きていない。とにかく、通いの場やオレンジカフェに通うようになった結果、本人が夜間、よく眠るように
なり、ありがたい」と話された。
(※)ここでいう「オレンジカフェ」は認知症カフェのことを指します。
ー 17 ー
地域内で見守られ、支え合う事例
家族会や地域における通いの場の活用により、身体拘束の予防に
つながった事例
一般社団法人 日本認知症ケア学会 代議員 牧野和子様よりご提供
事例のポイント
✔家族のレスパイトを目的として通いの場を紹介し、家族は家族会や認知症カフェに参加した
✔最適なタイミングで医療機関と本人・家族をつなぎ、更に地域資源を活用した
家族の切実な悩み
本人が一人歩きをしているときに警察に保護され、家族が地域包括支援センターに相談したことがきっかけとなり、地域包括
支援センターが本人・家族にかかわることとなった。
最初に面談したとき、家族から「本人の一人歩きを抑止するため、家に閉じ込めるしかないと思っている。どうしたら良いのか
わからない」と、気持ちを吐露された。
地域包括支援センター主催の家族会やオレンジカフェへの参加
家族は、
「本人に一人歩きやものを忘れることがあることを、他の人に知られたくない。また、他の人からの支援も好まない。」と
考えていた。そのため、警察に保護された後、本人と家族は離れることなくともに過ごす日々が続いていた。
家族にレスパイトが必要だと感じたため、本人が通いの場に通うことができるよう、急ぎ調整を図った。本人が通いの場に参加
している間は、家族が地域包括支援センター主催の家族会やオレンジカフェに参加できるよう対応した。
家族は当初「オレンジカフェは気乗りがしない」と言っていたが、6回目に参加してからは、否定的な言葉はなくなった。家族が
オレンジカフェ(※)に参加し続けられるよう、開催日の前日には、地域包括支援センターからお誘いの電話をしていた。
家族が自身の思いを話すことができるよう、家族会やオレンジカフェの終了後に毎回、個別に話しを聞く機会を設けた。その結
果、家族から「本人とともに、家族会やオレンジカフェに参加したい」と希望があり、この時期から、本人・家族の活動範囲が一気に
拡がった。
医療機関への紹介、地域資源の更なる活用
更に、本人・家族との信頼関係が築けたタイミングで、医療面のかかわりを開始した。本人と家族の許可を得たうえで、地域包括
支援センターの担当者がクリニックの主治医に対して、本人の物忘れや一人歩きに関する相談を行った。主治医の後押しを受け、
家族に認知症専門医への受診を促した。家族もそれを受け容れて受診し、本人はアルツハイマー型認知症の診断を受けた。診断
後、家族は本人が認知症であることを開示する姿勢を示し、
「本人のためにできることに取り組みたい」と度々話される等、家族の
気持ちは大きく変化した。
その後も、地域包括支援センター主催の家族会やオレンジカフェにおいて、本人・家族の状況を把握しながら、適期を見計らい、
区役所主催のオレンジカフェにも同行した。本人・家族が「活動内容が多彩だ」と気に入り、本人・家族ともに通うことになった。
家族の意向で、介護保険の利用には結びつかなかったが、本人が他の人と交流できるようにともに動いてくれた。週に4回以上、
本人が通える場所ができた頃には、家族から「気持ちが軽くなった。頭の上に重い石を置かれて生活している気分だったが、お陰
で本人の一人歩きも起きていない。とにかく、通いの場やオレンジカフェに通うようになった結果、本人が夜間、よく眠るように
なり、ありがたい」と話された。
(※)ここでいう「オレンジカフェ」は認知症カフェのことを指します。
ー 17 ー