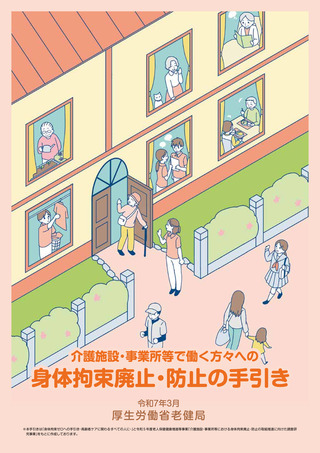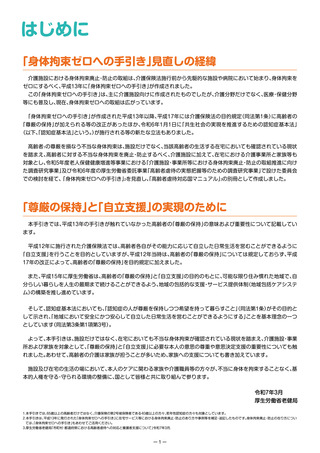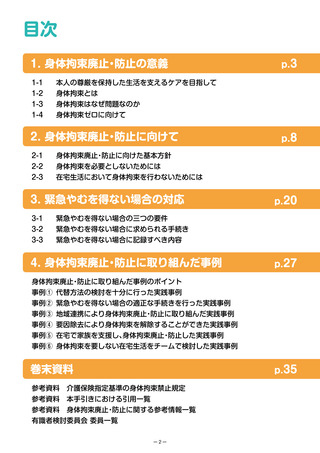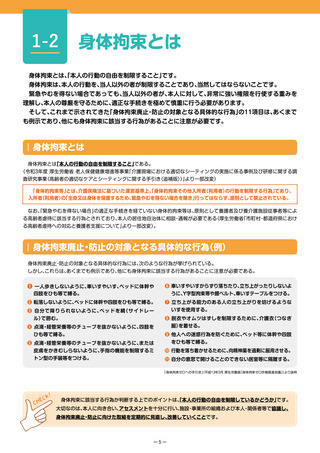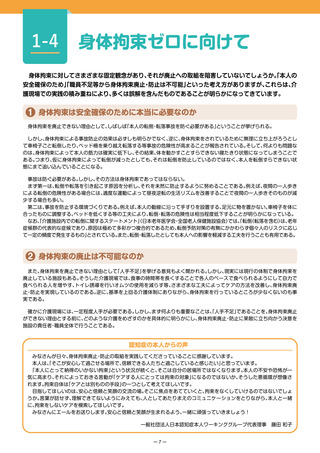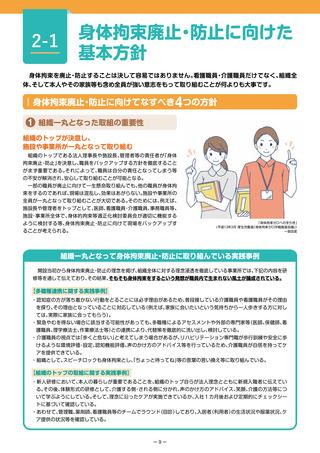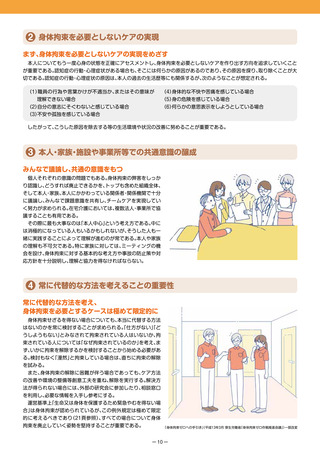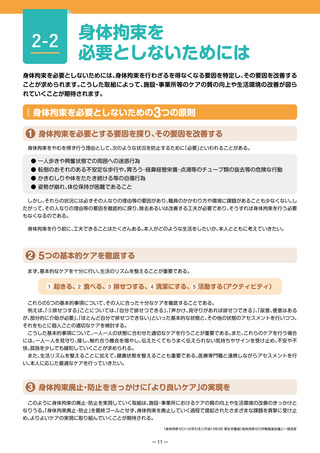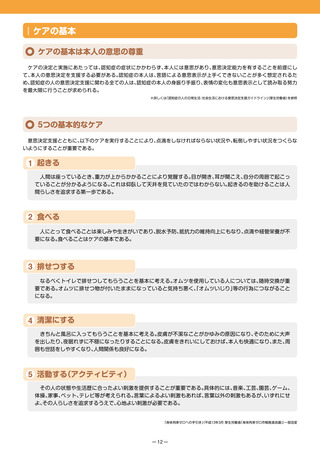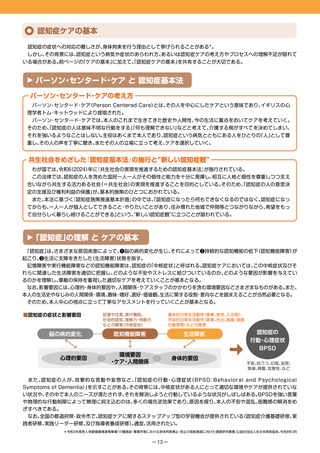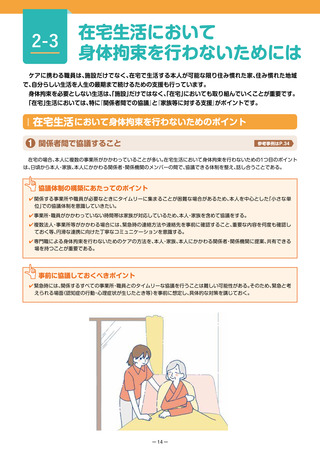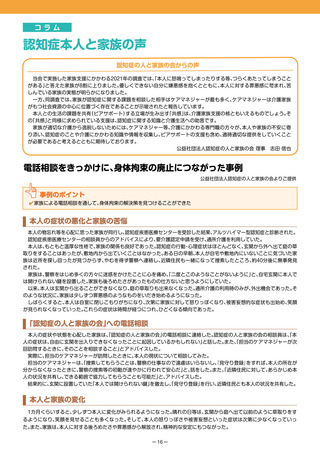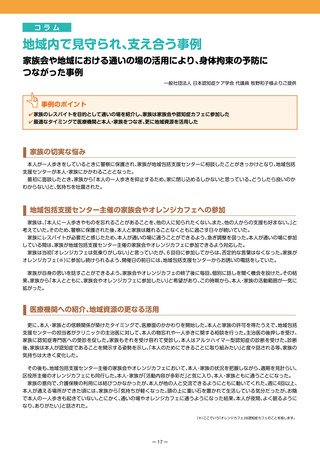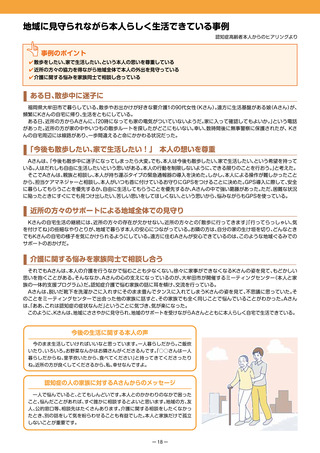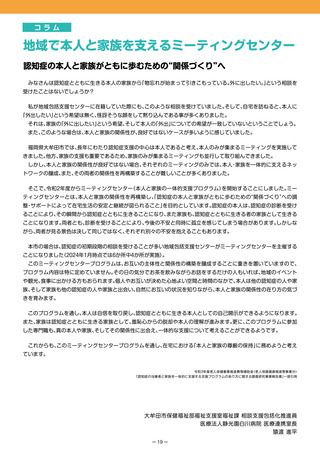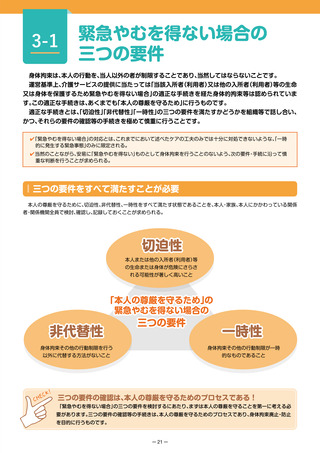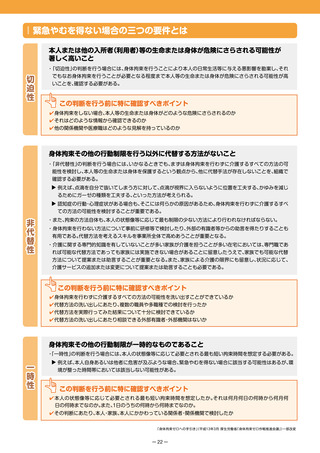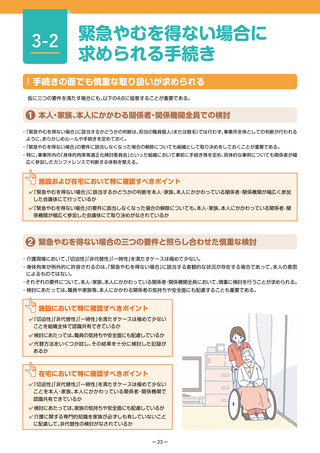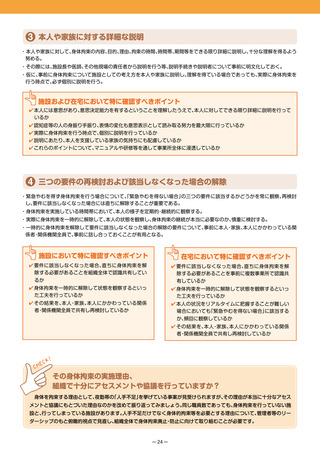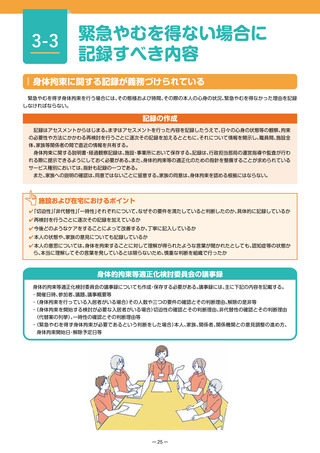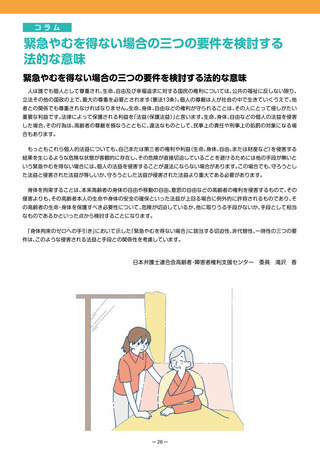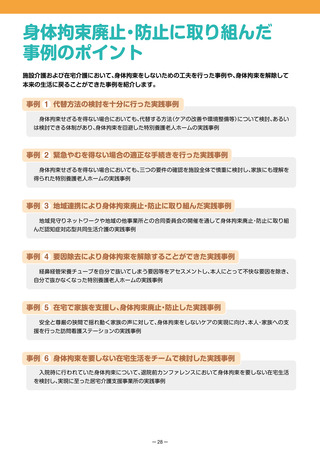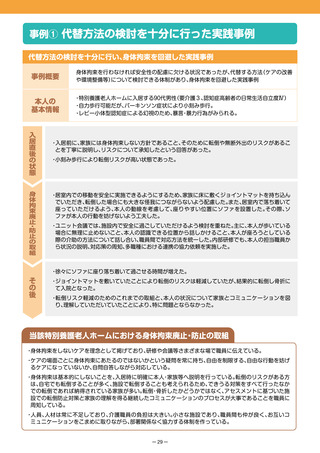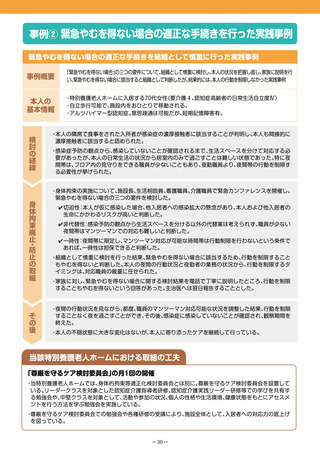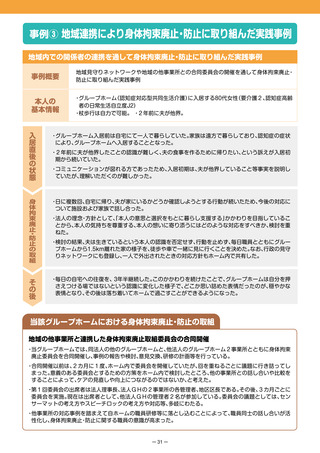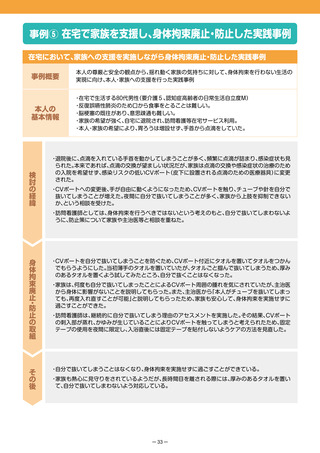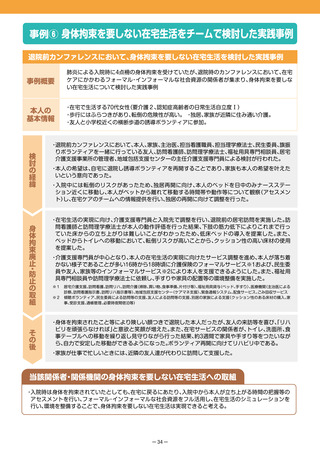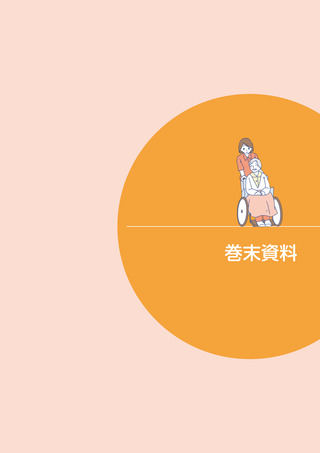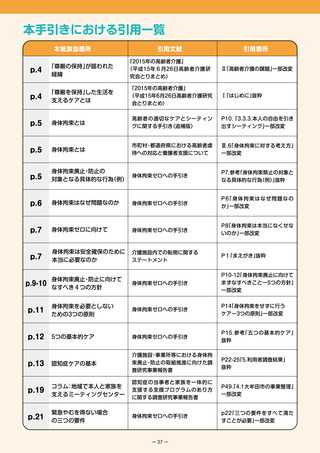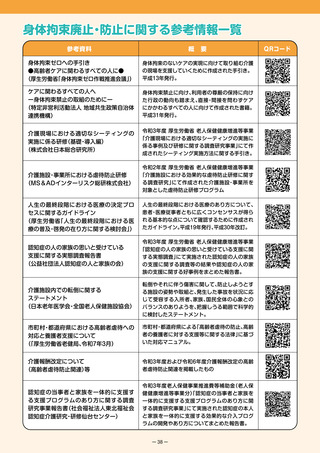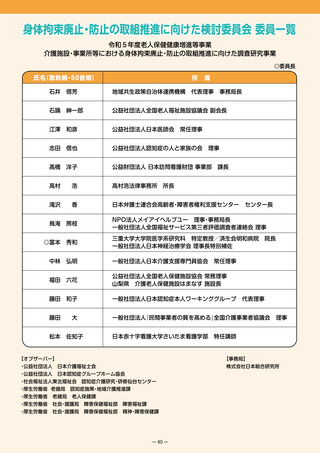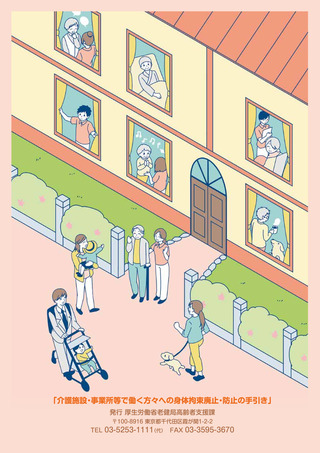よむ、つかう、まなぶ。
介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |
| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
はじめに
「身体拘束ゼロへの手引き」見直しの経緯
介護施設における身体拘束廃止・防止の取組は、介護保険法施行前から先駆的な施設や病院において始まり、身体拘束を
ゼロにするべく、平成13年に「身体拘束ゼロへの手引き」が作成されました。
この「身体拘束ゼロへの手引き」は、主に介護施設向けに作成されたものでしたが、介護分野だけでなく、医療・保健分野
等にも普及し、現在、身体拘束ゼロへの取組は広がっています。
「身体拘束ゼロへの手引き」が作成された平成13年以降、平成17年には介護保険法の目的規定(同法第1条)に高齢者の
「尊厳の保持」が加えられる等の改正があったほか、令和6年1月1日に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」
(以下、
「認知症基本法」という。)が施行される等の新たな立法もありました。
高齢者1の尊厳を損なう不当な身体拘束は、施設だけでなく、当該高齢者の生活する在宅においても確認されている現状
を踏まえ、高齢者に対する不当な身体拘束を廃止・防止するべく、介護施設に加えて、在宅における介護事業所と家族等も
対象とし、令和5年度老人保健健康増進等事業における「介護施設・事業所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向け
た調査研究事業」及び令和6年度の厚生労働省委託事業「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業」で設けた委員会
2を見直し、
「高齢者虐待対応国マニュアル」3の別冊として作成しました。
での検討を経て、
「身体拘束ゼロへの手引き」
「尊厳の保持」と「自立支援」の実現のために
本手引きでは、平成13年の手引きが触れていなかった高齢者の「尊厳の保持」の意味および重要性について記載してい
ます。
平成12年に施行された介護保険法では、高齢者各自がその能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように
「自立支援」を行うことを目的としていますが、平成12年当時は、高齢者の「尊厳の保持」については規定しておらず、平成
17年の改正によって、高齢者の「尊厳の保持」を目的規定に加えました。
また、平成15年に厚生労働省は、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」の目的のもとに、可能な限り住み慣れた地域で、自
分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステ
ム)の構築を推し進めています。
そして、認知症基本法においても、
「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと」
(同法第1条)がその目的と
して示され、
「地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるようにする」ことを基本理念の一つ
としています(同法第3条第1項第3号)。
よって、本手引きは、施設だけではなく、在宅においても不当な身体拘束が確認されている現状を踏まえ、介護施設・事業
所および家族を対象として、
「尊厳の保持」と「自立支援」に必要な本人の意思の尊重や意思決定支援の重要性についても触
れました。あわせて、高齢者の介護は家族が担うことが多いため、家族への支援についても書き加えています。
施設及び在宅の生活の場において、本人のケアに関わる家族や介護職員等の方々が、不当に身体を拘束することなく、基
本的人権を守る・守られる環境の整備に、国として皆様と共に取り組んで参ります。
令和7年3月
厚生労働省老健局
1.本手引きでは、65歳以上の高齢者だけではなく、介護保険の第2号被保険者である40歳以上の方々、若年性認知症の方々も対象としています。
2.本手引きは、平成13年に発行された「身体拘束ゼロへの手引き」に在宅サービス等における身体拘束廃止・防止のあり方や事例等を補足・追記したものです。身体拘束廃止・防止の在り方につい
ては、
「身体拘束ゼロへの手引き」もあわせてご活用ください。
3.厚生労働省老健局「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」令和7年3月.
ー1ー
「身体拘束ゼロへの手引き」見直しの経緯
介護施設における身体拘束廃止・防止の取組は、介護保険法施行前から先駆的な施設や病院において始まり、身体拘束を
ゼロにするべく、平成13年に「身体拘束ゼロへの手引き」が作成されました。
この「身体拘束ゼロへの手引き」は、主に介護施設向けに作成されたものでしたが、介護分野だけでなく、医療・保健分野
等にも普及し、現在、身体拘束ゼロへの取組は広がっています。
「身体拘束ゼロへの手引き」が作成された平成13年以降、平成17年には介護保険法の目的規定(同法第1条)に高齢者の
「尊厳の保持」が加えられる等の改正があったほか、令和6年1月1日に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」
(以下、
「認知症基本法」という。)が施行される等の新たな立法もありました。
高齢者1の尊厳を損なう不当な身体拘束は、施設だけでなく、当該高齢者の生活する在宅においても確認されている現状
を踏まえ、高齢者に対する不当な身体拘束を廃止・防止するべく、介護施設に加えて、在宅における介護事業所と家族等も
対象とし、令和5年度老人保健健康増進等事業における「介護施設・事業所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向け
た調査研究事業」及び令和6年度の厚生労働省委託事業「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業」で設けた委員会
2を見直し、
「高齢者虐待対応国マニュアル」3の別冊として作成しました。
での検討を経て、
「身体拘束ゼロへの手引き」
「尊厳の保持」と「自立支援」の実現のために
本手引きでは、平成13年の手引きが触れていなかった高齢者の「尊厳の保持」の意味および重要性について記載してい
ます。
平成12年に施行された介護保険法では、高齢者各自がその能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように
「自立支援」を行うことを目的としていますが、平成12年当時は、高齢者の「尊厳の保持」については規定しておらず、平成
17年の改正によって、高齢者の「尊厳の保持」を目的規定に加えました。
また、平成15年に厚生労働省は、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」の目的のもとに、可能な限り住み慣れた地域で、自
分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステ
ム)の構築を推し進めています。
そして、認知症基本法においても、
「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと」
(同法第1条)がその目的と
して示され、
「地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるようにする」ことを基本理念の一つ
としています(同法第3条第1項第3号)。
よって、本手引きは、施設だけではなく、在宅においても不当な身体拘束が確認されている現状を踏まえ、介護施設・事業
所および家族を対象として、
「尊厳の保持」と「自立支援」に必要な本人の意思の尊重や意思決定支援の重要性についても触
れました。あわせて、高齢者の介護は家族が担うことが多いため、家族への支援についても書き加えています。
施設及び在宅の生活の場において、本人のケアに関わる家族や介護職員等の方々が、不当に身体を拘束することなく、基
本的人権を守る・守られる環境の整備に、国として皆様と共に取り組んで参ります。
令和7年3月
厚生労働省老健局
1.本手引きでは、65歳以上の高齢者だけではなく、介護保険の第2号被保険者である40歳以上の方々、若年性認知症の方々も対象としています。
2.本手引きは、平成13年に発行された「身体拘束ゼロへの手引き」に在宅サービス等における身体拘束廃止・防止のあり方や事例等を補足・追記したものです。身体拘束廃止・防止の在り方につい
ては、
「身体拘束ゼロへの手引き」もあわせてご活用ください。
3.厚生労働省老健局「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」令和7年3月.
ー1ー