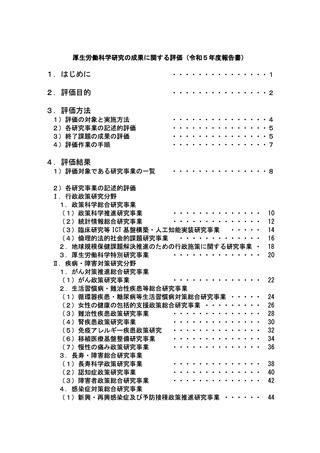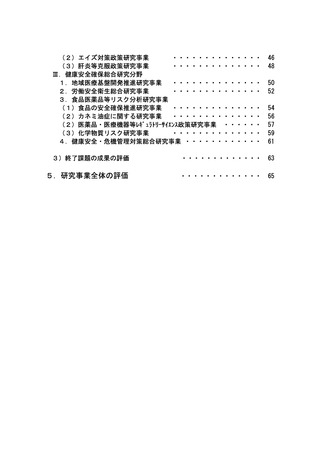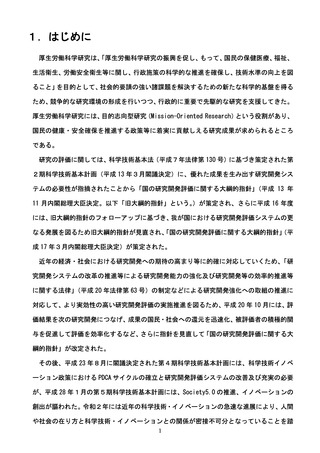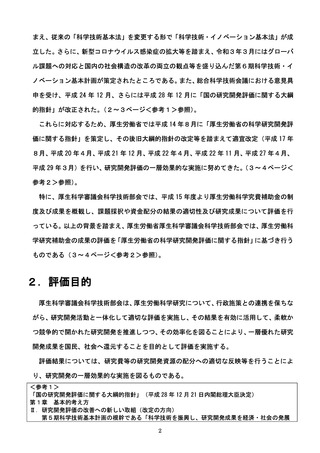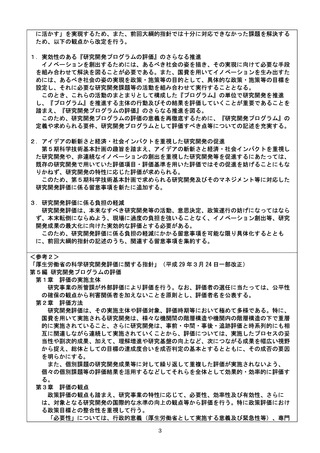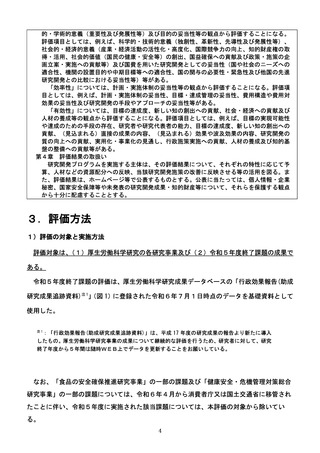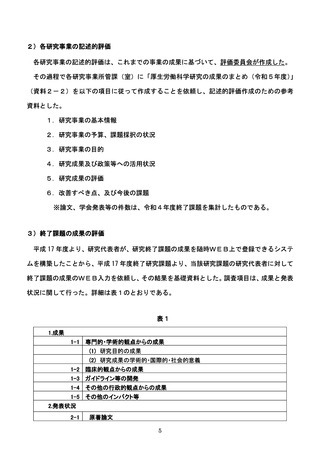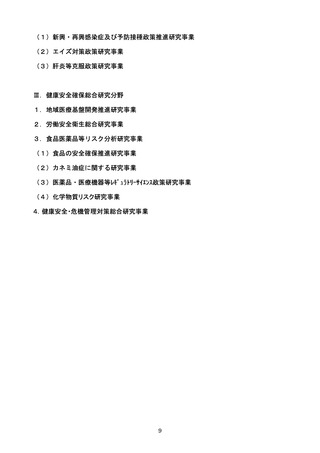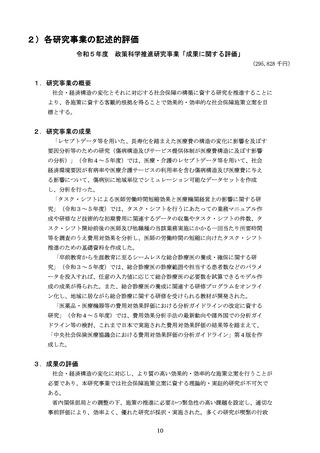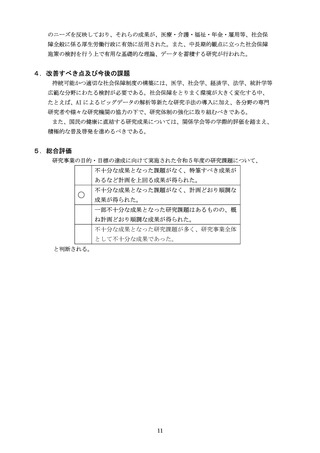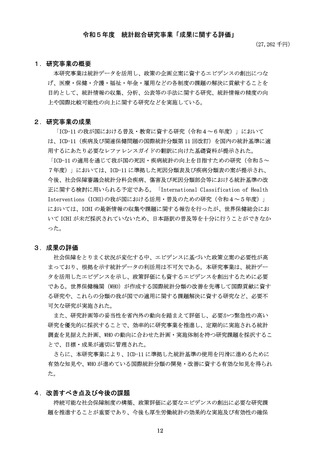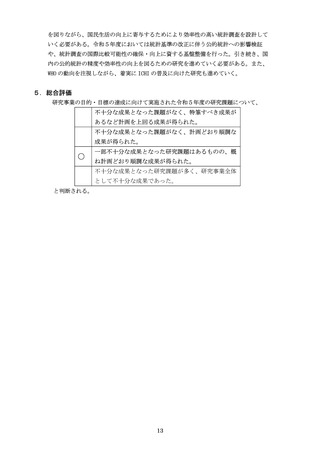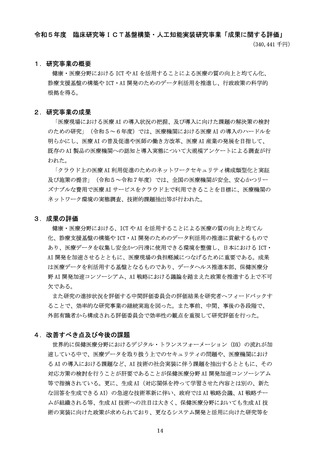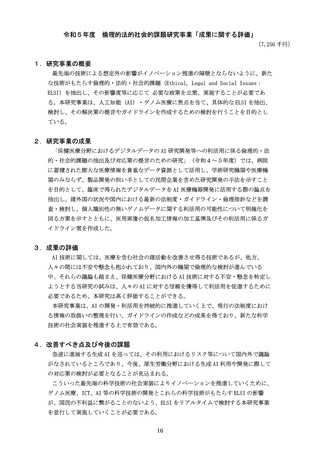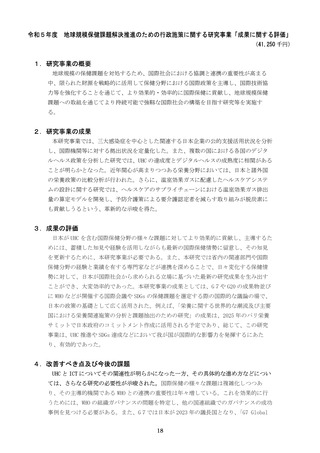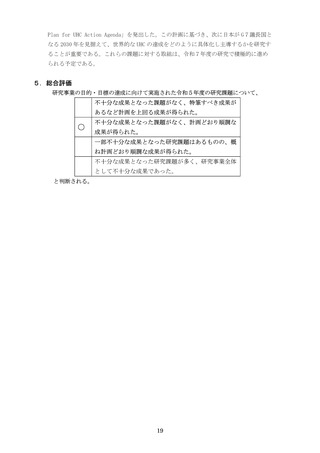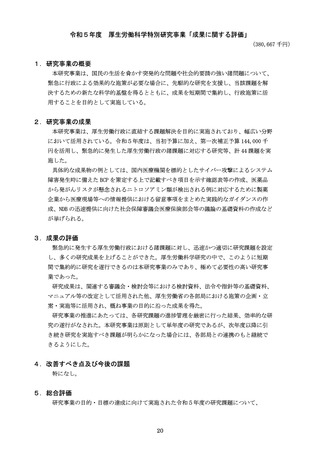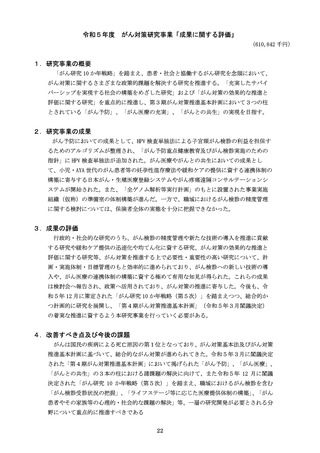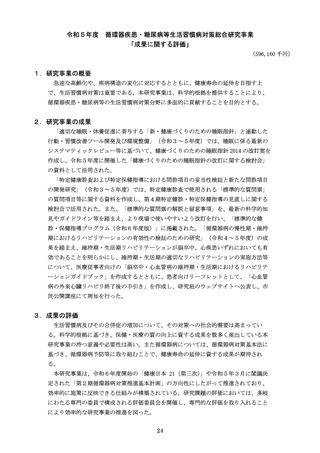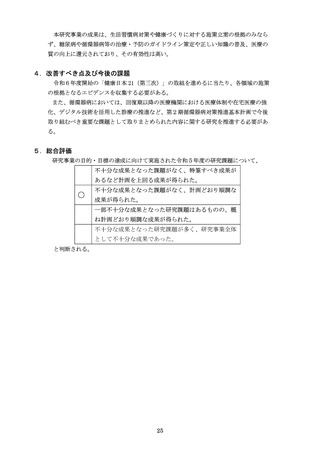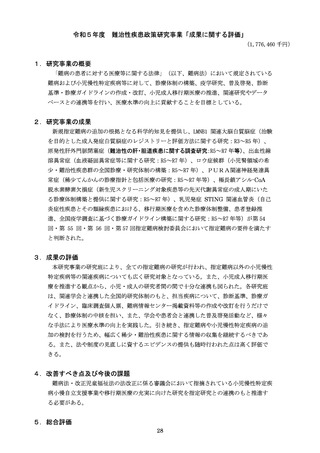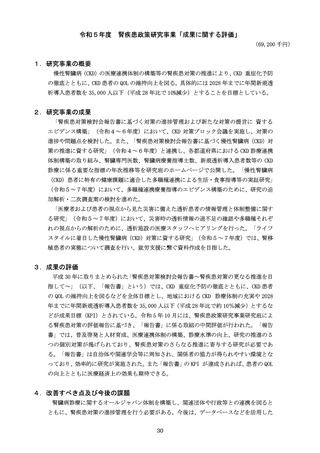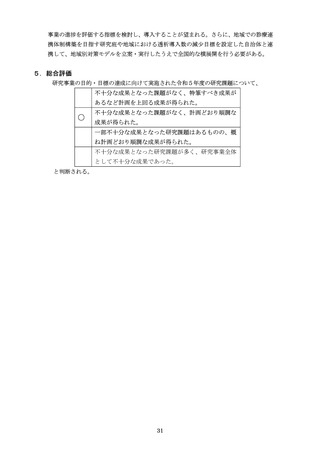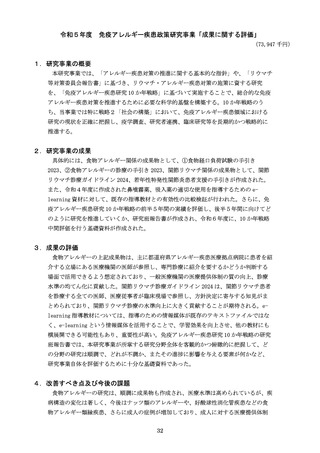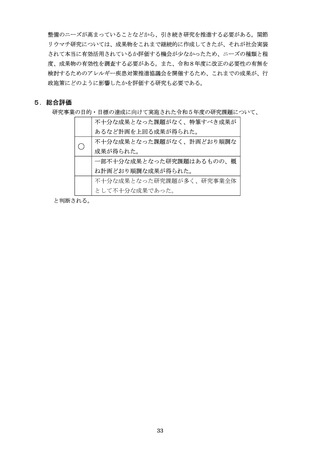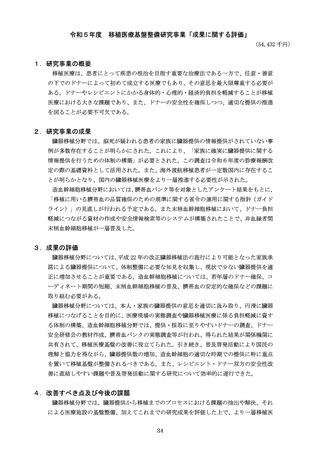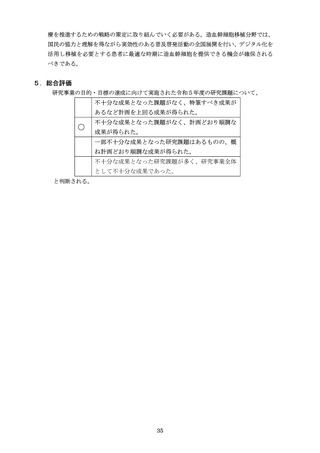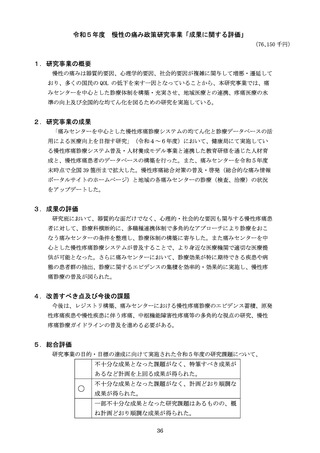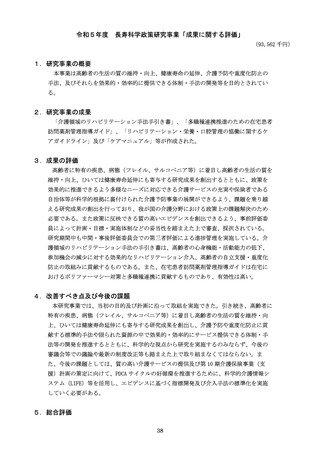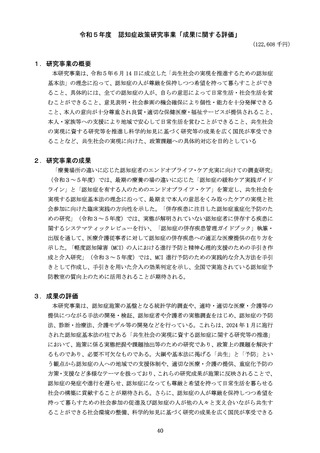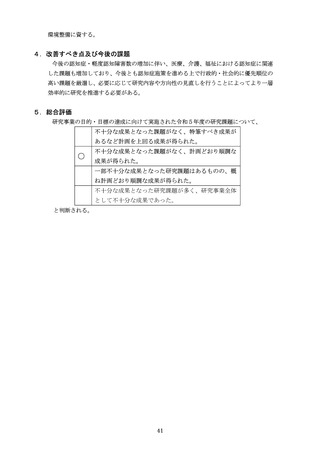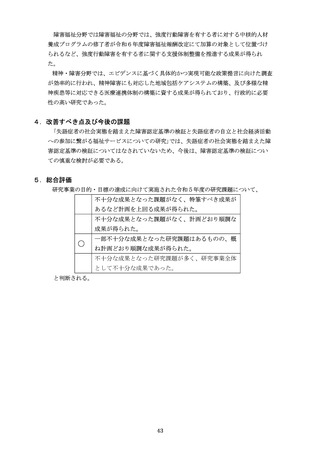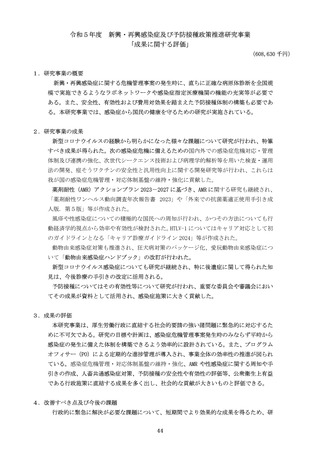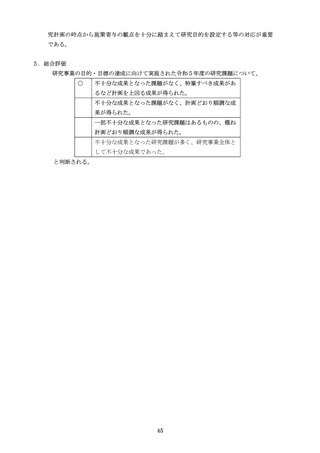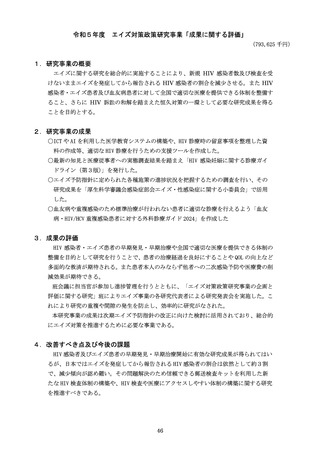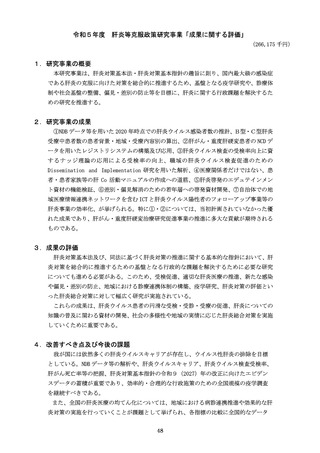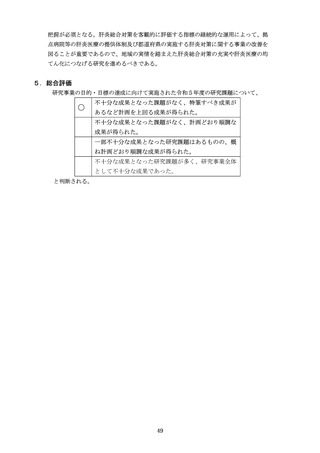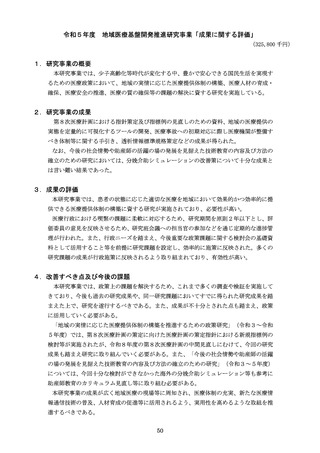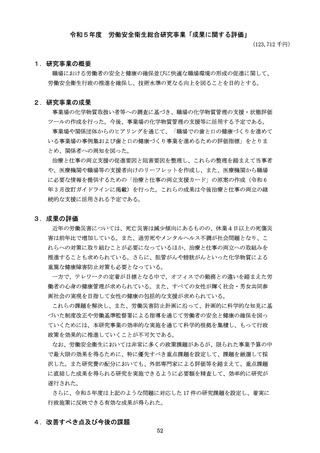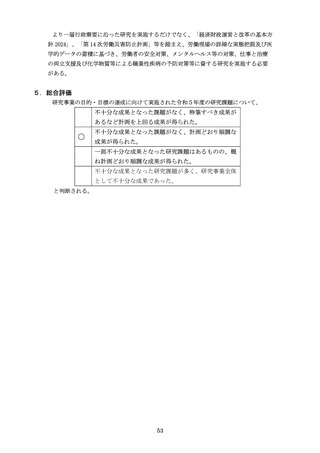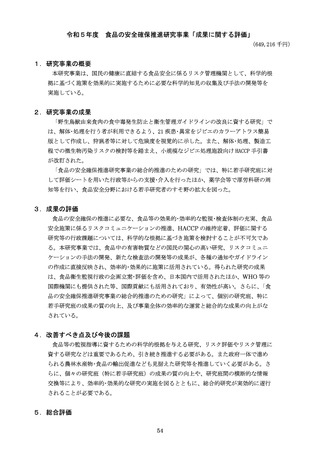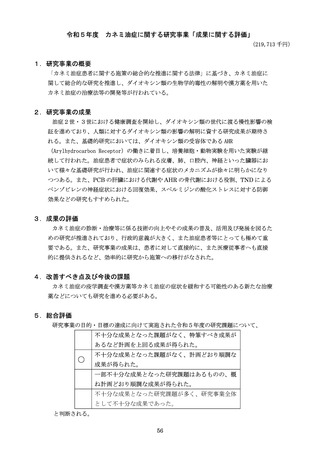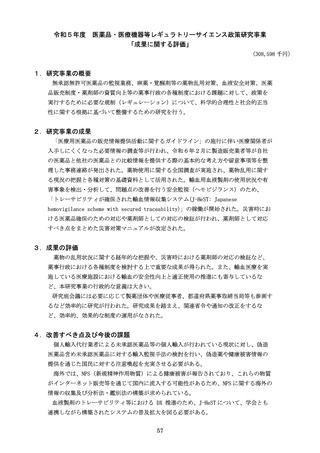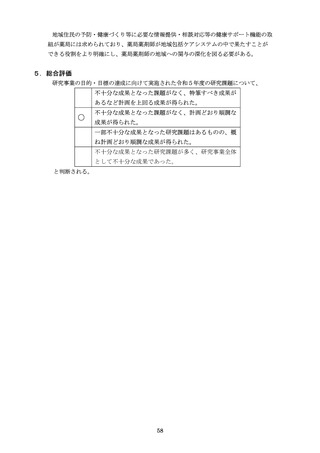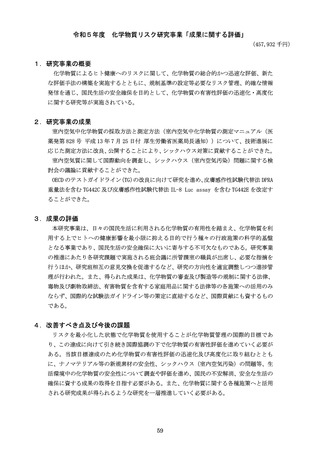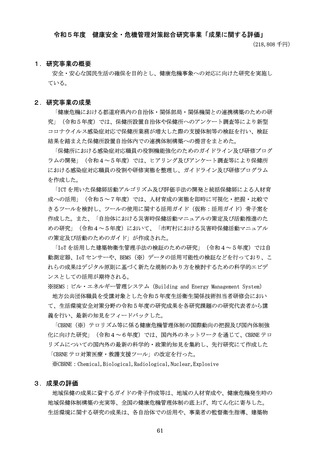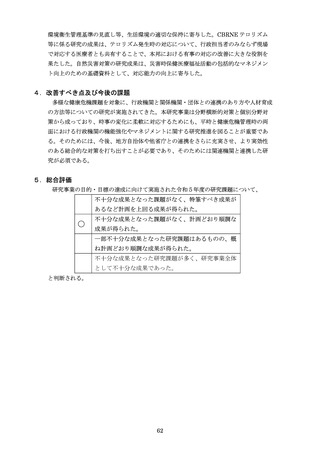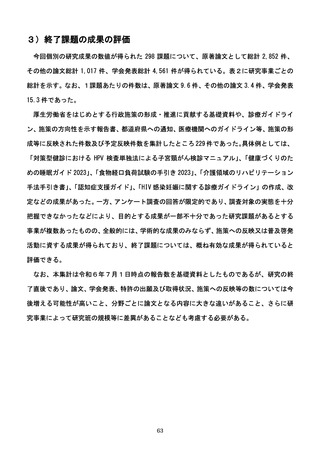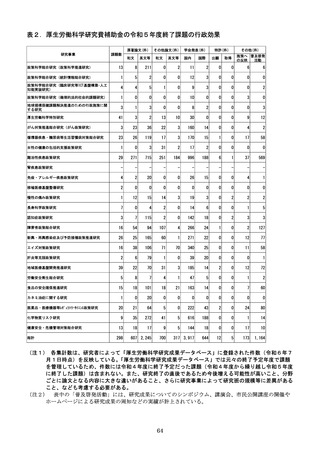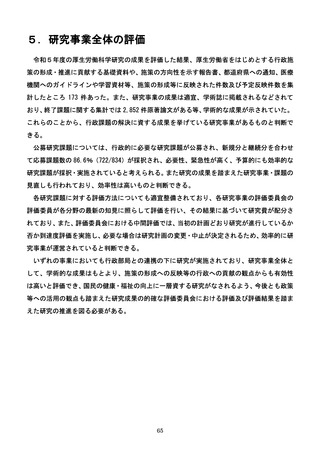よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4 厚生労働科学研究の成果に関する評価(令和5年度報告書) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31012.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会(第21回 2/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和5年度 地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業「成果に関する評価」
(41,250 千円)
1.研究事業の概要
地球規模の保健課題を対処するため、国際社会における協調と連携の重要性が高まる
中、限られた財源を戦略的に活用して保健分野における国際政策を主導し、国際技術協
力等を強化することを通じて、より効果的・効率的に国際保健に貢献し、地球規模保健
課題への取組を通じてより持続可能で強靱な国際社会の構築を目指す研究等を実施す
る。
2.研究事業の成果
本研究事業では、三大感染症を中心とした関連する日本企業の公的支援活用状況を分析
し、国際機関等に対する拠出状況を定量化した。また、複数の国における各国のデジタ
ルヘルス政策を分析した研究では、UHC の達成度とデジタルヘルスの成熟度に相関がある
ことが明らかとなった。近年関心が高まりつつある栄養分野においては、日本と諸外国
の栄養政策の比較分析が行われた。さらに、温室効果ガスに配慮したヘルスケアシステ
ムの設計に関する研究では、ヘルスケアのサプライチェーンにおける温室効果ガス排出
量の算定モデルを開発し、予防介護策による要介護認定者を減らす取り組みが脱炭素に
も貢献しうるという、革新的な示唆を得た。
3.成果の評価
日本が UHC を含む国際保健分野の様々な課題に対してより効果的に貢献し、主導するた
めには、蓄積した知見や経験を活用しながらも最新の国際保健情勢に留意し、その知見
を更新するために、本研究事業が必要である。また、本研究では省内の関連部門や国際
保健分野の経験と業績を有する専門家などが連携を深めることで、日々変化する保健情
勢に対して、日本が国際社会から求められる立場に基づいた最新の研究成果を生み出す
ことができ、大変効率的であった。本研究事業の成果としては、G7や G20 の成果物並び
に WHO などが開催する国際会議や SDGs の保健課題を選定する際の国際的な議論の場で、
日本の政策の基礎として広く活用された。例えば、
「栄養に関する世界的な潮流及び主要
国における栄養関連施策の分析と課題抽出のための研究」の成果は、2025 年のパリ栄養
サミットで日本政府のコミットメント作成に活用される予定であり、総じて、この研究
事業は、UHC 推進や SDGs 達成などにおいて我が国が国際的な影響力を発揮するにあた
り、有効的であった。
4.改善すべき点及び今後の課題
UHC と ICT についてその関連性が明らかになった一方、その具体的な進め方などについ
ては、さらなる研究の必要性が示唆された。国際保健の様々な課題は複雑化しつつあ
り、その主導的機関である WHO との連携の重要性は年々増している。これを効果的に行
うためには、WHO の組織ガバナンスの問題を特定し、他の国連組織でのガバナンスの成功
事例を見つける必要がある。また、G7では日本が 2023 年の議長国となり、「G7 Global
18
(41,250 千円)
1.研究事業の概要
地球規模の保健課題を対処するため、国際社会における協調と連携の重要性が高まる
中、限られた財源を戦略的に活用して保健分野における国際政策を主導し、国際技術協
力等を強化することを通じて、より効果的・効率的に国際保健に貢献し、地球規模保健
課題への取組を通じてより持続可能で強靱な国際社会の構築を目指す研究等を実施す
る。
2.研究事業の成果
本研究事業では、三大感染症を中心とした関連する日本企業の公的支援活用状況を分析
し、国際機関等に対する拠出状況を定量化した。また、複数の国における各国のデジタ
ルヘルス政策を分析した研究では、UHC の達成度とデジタルヘルスの成熟度に相関がある
ことが明らかとなった。近年関心が高まりつつある栄養分野においては、日本と諸外国
の栄養政策の比較分析が行われた。さらに、温室効果ガスに配慮したヘルスケアシステ
ムの設計に関する研究では、ヘルスケアのサプライチェーンにおける温室効果ガス排出
量の算定モデルを開発し、予防介護策による要介護認定者を減らす取り組みが脱炭素に
も貢献しうるという、革新的な示唆を得た。
3.成果の評価
日本が UHC を含む国際保健分野の様々な課題に対してより効果的に貢献し、主導するた
めには、蓄積した知見や経験を活用しながらも最新の国際保健情勢に留意し、その知見
を更新するために、本研究事業が必要である。また、本研究では省内の関連部門や国際
保健分野の経験と業績を有する専門家などが連携を深めることで、日々変化する保健情
勢に対して、日本が国際社会から求められる立場に基づいた最新の研究成果を生み出す
ことができ、大変効率的であった。本研究事業の成果としては、G7や G20 の成果物並び
に WHO などが開催する国際会議や SDGs の保健課題を選定する際の国際的な議論の場で、
日本の政策の基礎として広く活用された。例えば、
「栄養に関する世界的な潮流及び主要
国における栄養関連施策の分析と課題抽出のための研究」の成果は、2025 年のパリ栄養
サミットで日本政府のコミットメント作成に活用される予定であり、総じて、この研究
事業は、UHC 推進や SDGs 達成などにおいて我が国が国際的な影響力を発揮するにあた
り、有効的であった。
4.改善すべき点及び今後の課題
UHC と ICT についてその関連性が明らかになった一方、その具体的な進め方などについ
ては、さらなる研究の必要性が示唆された。国際保健の様々な課題は複雑化しつつあ
り、その主導的機関である WHO との連携の重要性は年々増している。これを効果的に行
うためには、WHO の組織ガバナンスの問題を特定し、他の国連組織でのガバナンスの成功
事例を見つける必要がある。また、G7では日本が 2023 年の議長国となり、「G7 Global
18