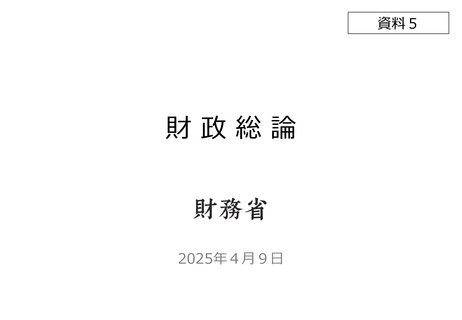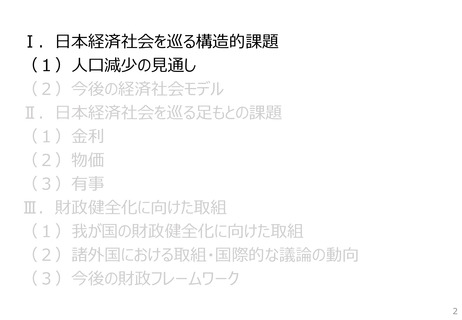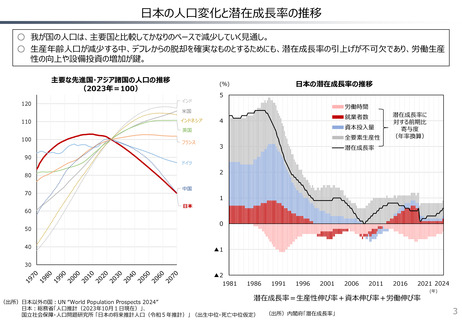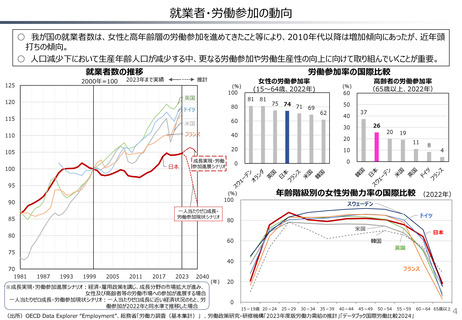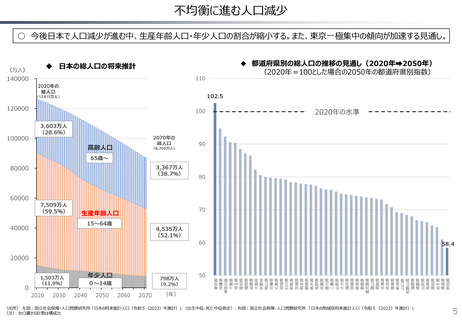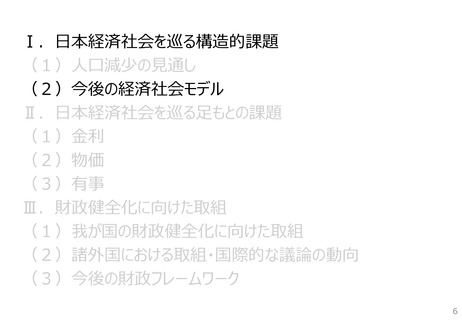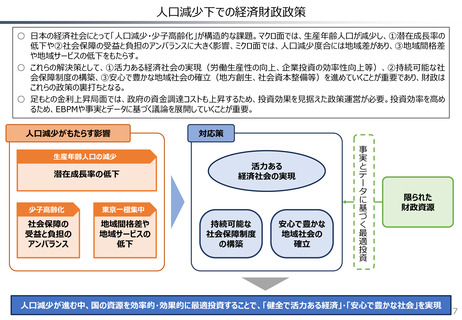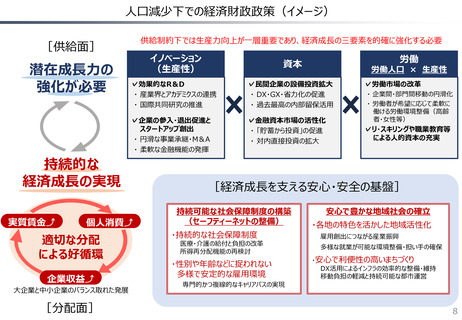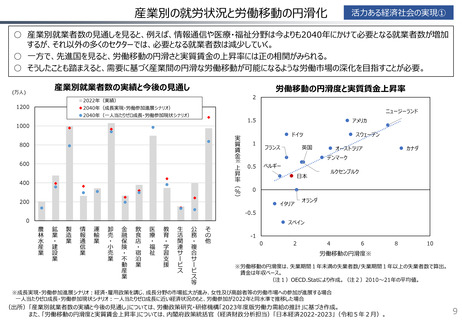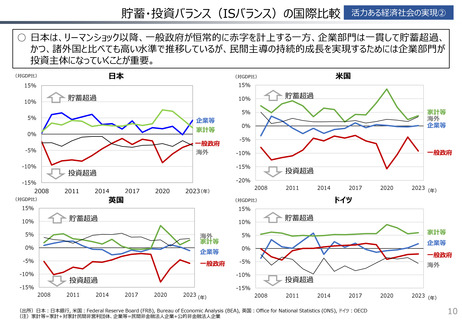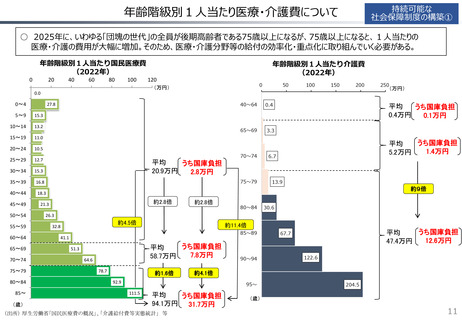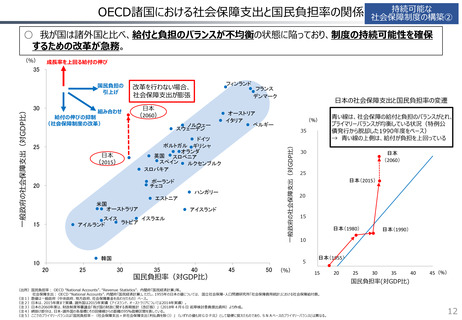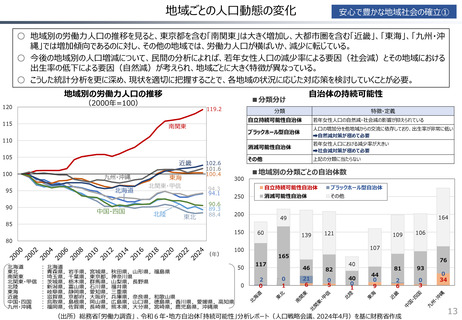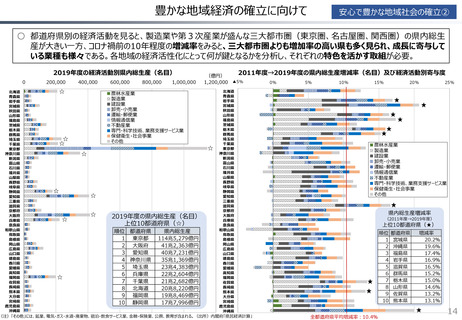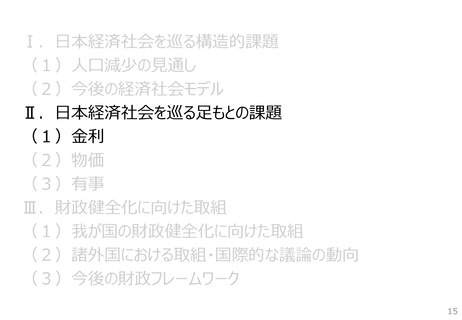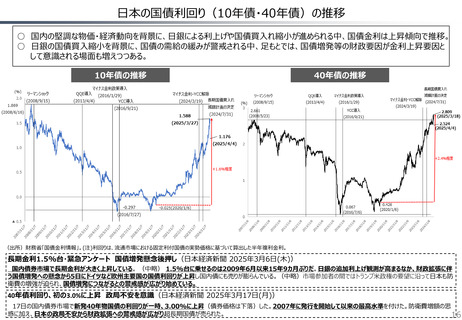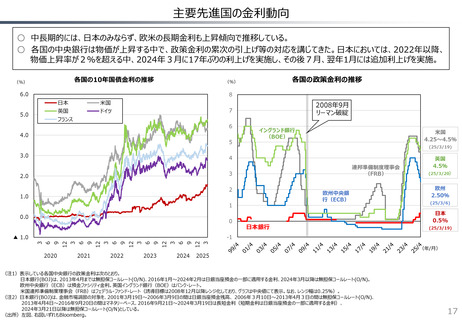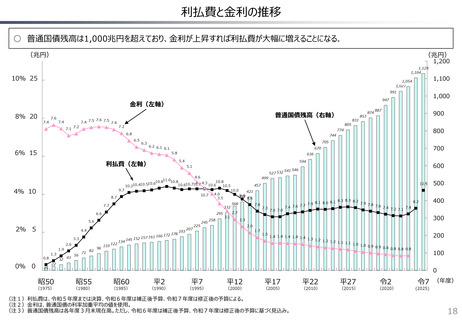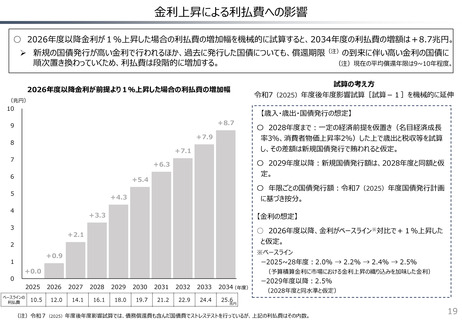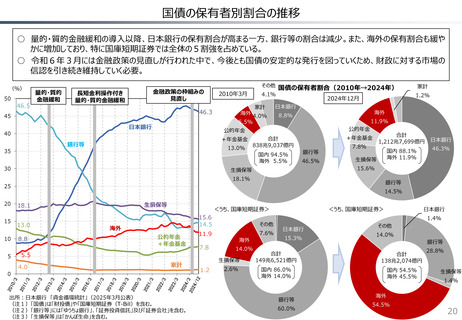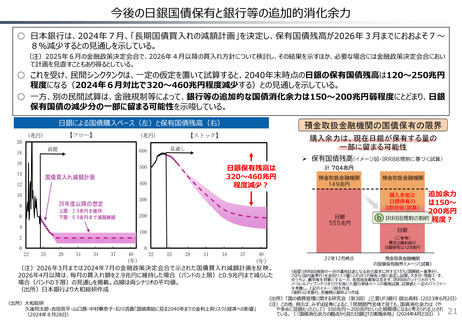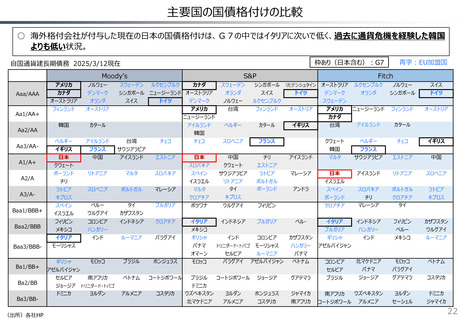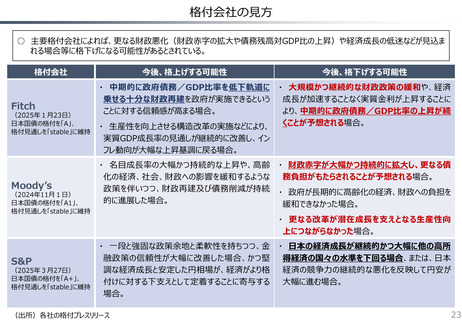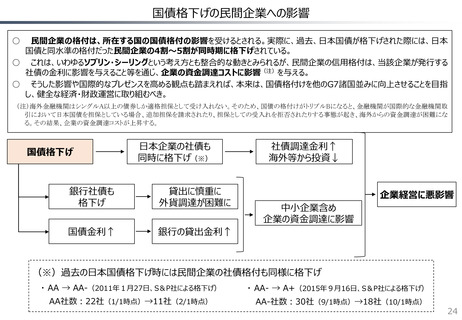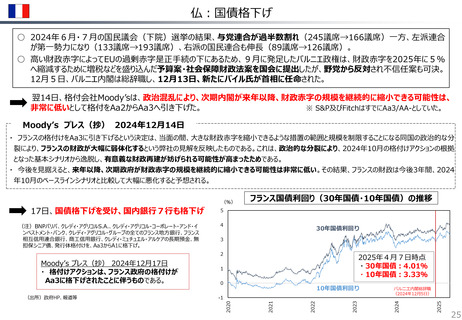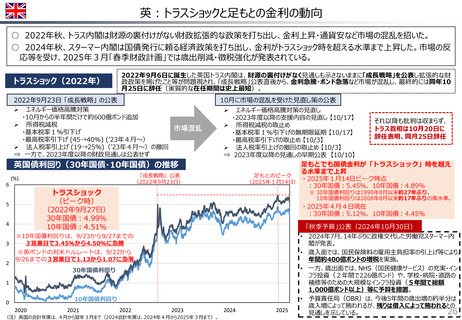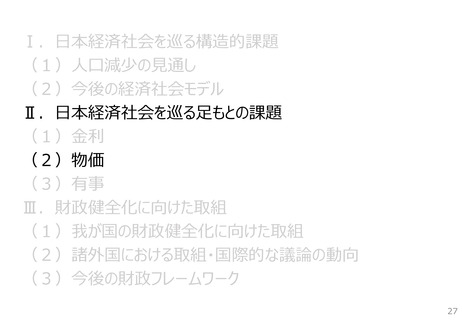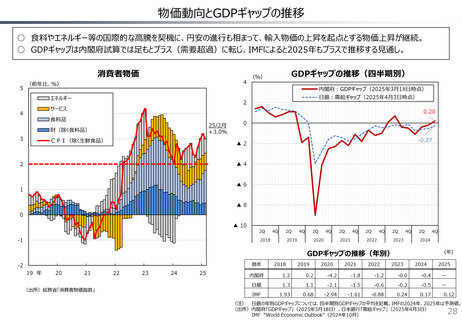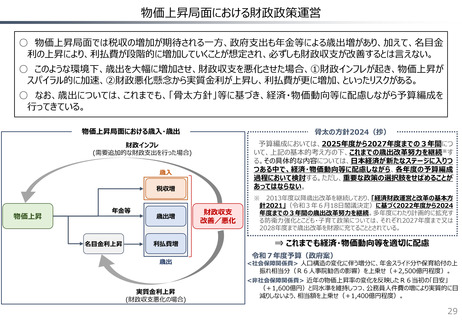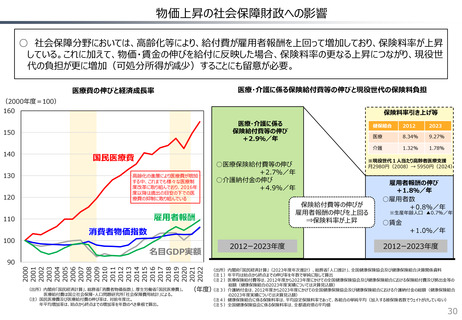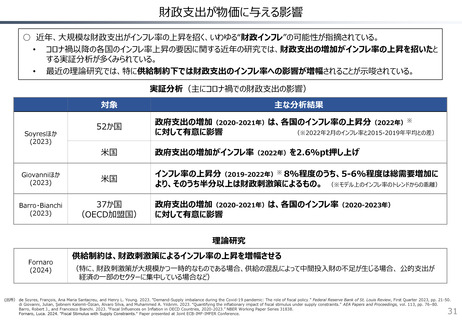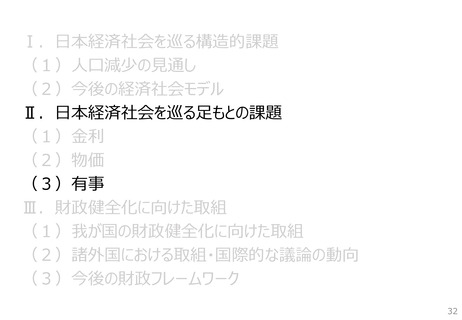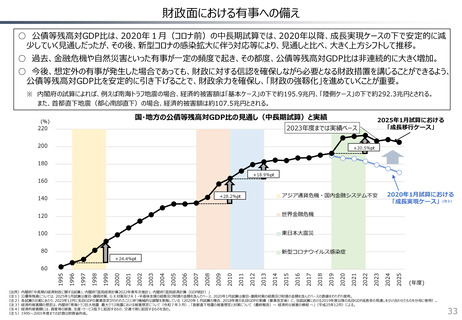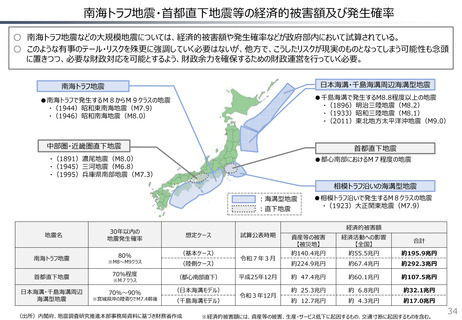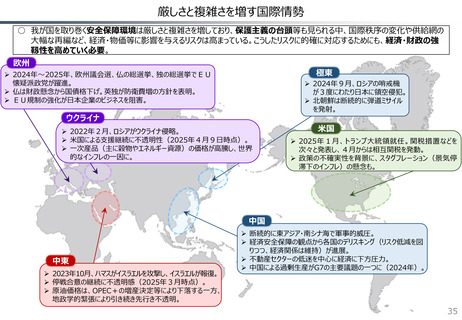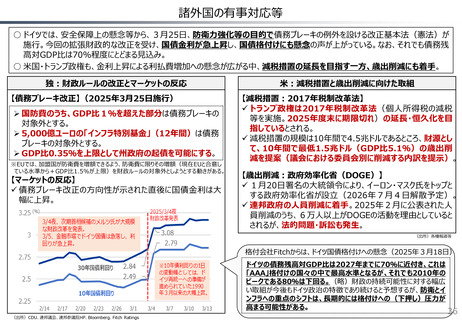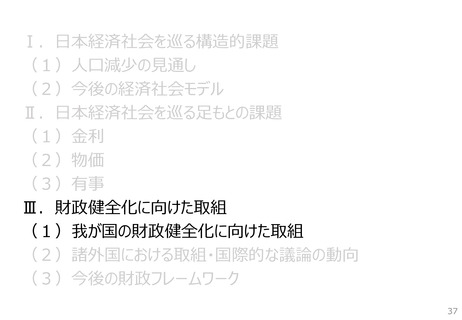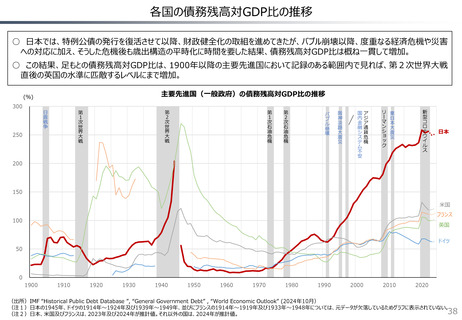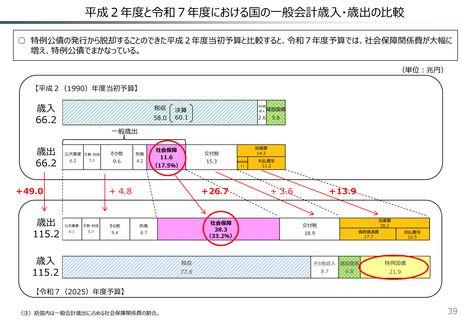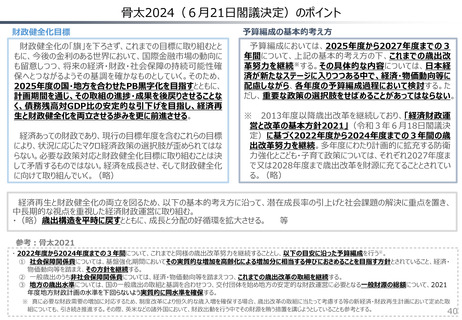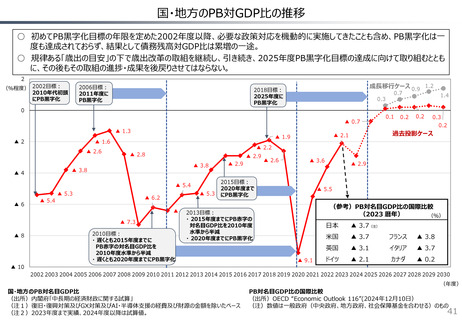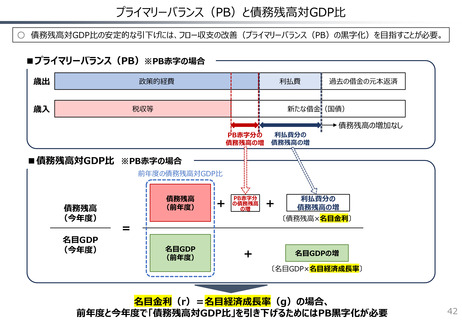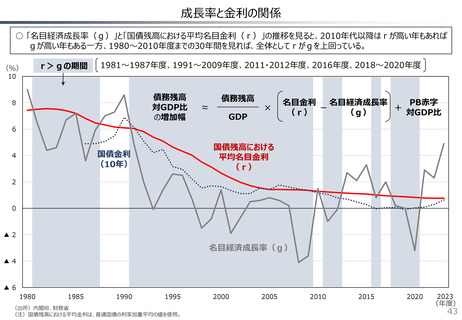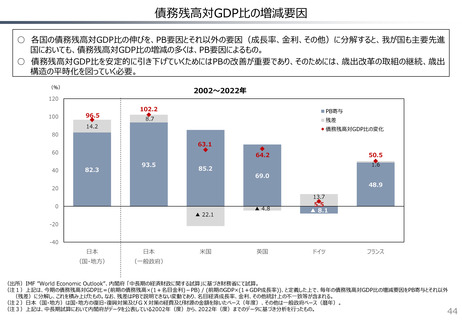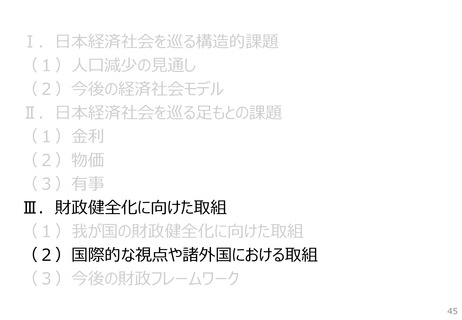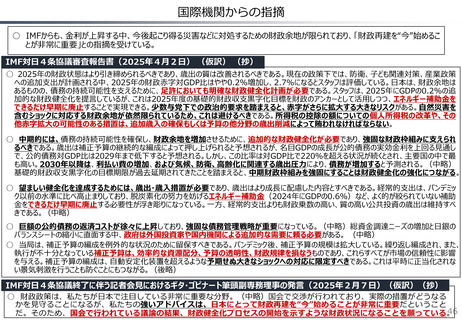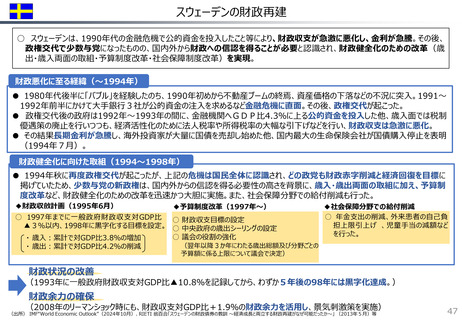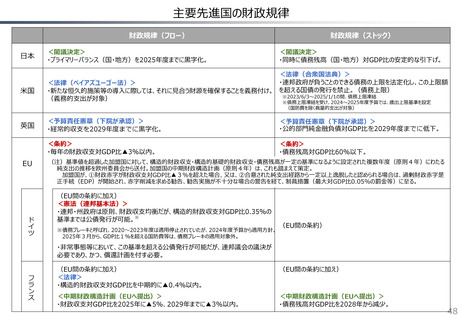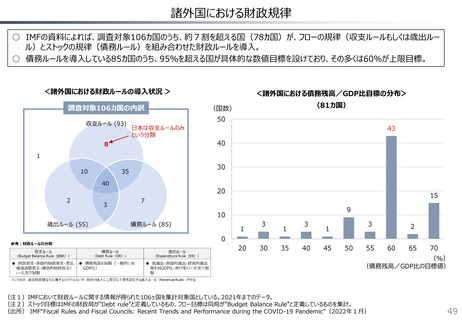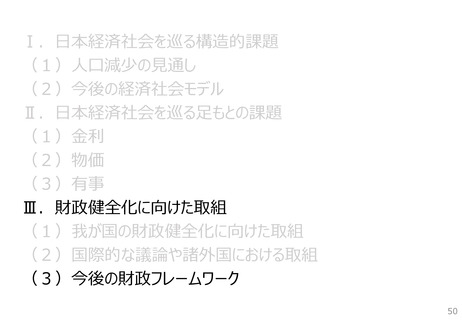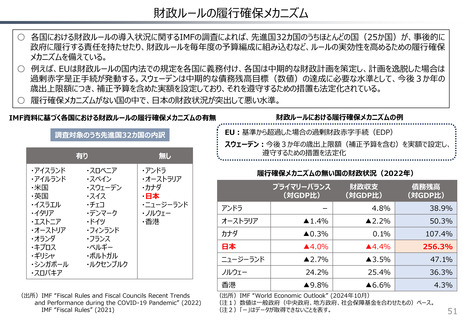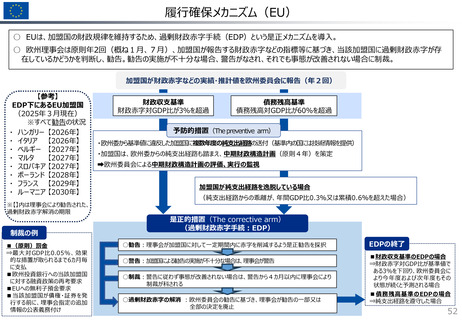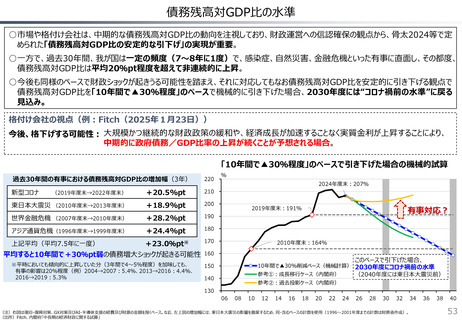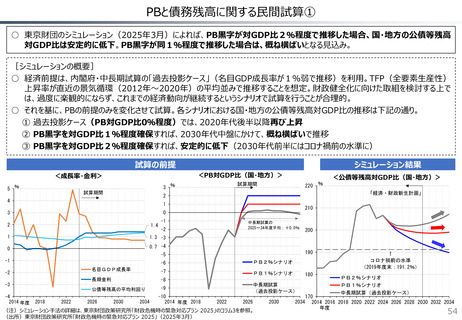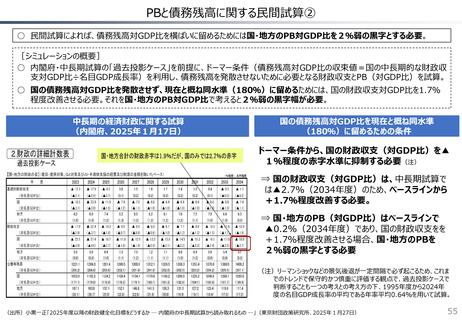よむ、つかう、まなぶ。
資料5 財政総論 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/202050409zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/9)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
債務残高対GDP比の増減要因
○ 各国の債務残高対GDP比の伸びを、PB要因とそれ以外の要因(成長率、金利、その他)に分解すると、我が国も主要先進
国においても、債務残高対GDP比の増減の多くは、PB要因によるもの。
○ 債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくためにはPBの改善が重要であり、そのためには、歳出改革の取組の継続、歳出
構造の平時化を図っていく必要。
(%)
2002~2022年
120
100
96.5
102.2
PB寄与
8.7
残差
14.2
債務残高対GDP比の変化
80
63.1
60
40
64.2
82.3
93.5
50.5
1.6
85.2
69.0
48.9
20
13.7
0
▲ 22.1
▲ 4.8
5.5
▲ 8.1
英国
ドイツ
-20
-40
日本
日本
(国・地方)
(一般政府)
米国
フランス
(出所)IMF ”World Economic Outlook”、内閣府 「中長期の経済財政に関する試算」に基づき財務省にて試算。
(注1)上記は、今期の債務残高対GDP比=(前期の債務残高×(1+名目金利)-PB) / (前期のGDP×(1+GDP成長率))、と定義した上で、毎年の債務残高対GDP比の増減要因をPB寄与とそれ以外
(残差)に分解し、これを積み上げたもの。なお、残差はPBで説明できない変動であり、名目経済成長率、金利、その他統計上の不一致等が含まれる。
(注2)日本(国・地方)は国・地方の復旧・復興対策及びGX対策の経費及び財源の金額を除いたベース(年度)、その他は一般政府ベース(暦年)。
(注3)上記は、中長期試算において内閣府がデータを公表している2002年(度)から、2022年(度)までのデータに基づき分析を行ったもの。
44
○ 各国の債務残高対GDP比の伸びを、PB要因とそれ以外の要因(成長率、金利、その他)に分解すると、我が国も主要先進
国においても、債務残高対GDP比の増減の多くは、PB要因によるもの。
○ 債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくためにはPBの改善が重要であり、そのためには、歳出改革の取組の継続、歳出
構造の平時化を図っていく必要。
(%)
2002~2022年
120
100
96.5
102.2
PB寄与
8.7
残差
14.2
債務残高対GDP比の変化
80
63.1
60
40
64.2
82.3
93.5
50.5
1.6
85.2
69.0
48.9
20
13.7
0
▲ 22.1
▲ 4.8
5.5
▲ 8.1
英国
ドイツ
-20
-40
日本
日本
(国・地方)
(一般政府)
米国
フランス
(出所)IMF ”World Economic Outlook”、内閣府 「中長期の経済財政に関する試算」に基づき財務省にて試算。
(注1)上記は、今期の債務残高対GDP比=(前期の債務残高×(1+名目金利)-PB) / (前期のGDP×(1+GDP成長率))、と定義した上で、毎年の債務残高対GDP比の増減要因をPB寄与とそれ以外
(残差)に分解し、これを積み上げたもの。なお、残差はPBで説明できない変動であり、名目経済成長率、金利、その他統計上の不一致等が含まれる。
(注2)日本(国・地方)は国・地方の復旧・復興対策及びGX対策の経費及び財源の金額を除いたベース(年度)、その他は一般政府ベース(暦年)。
(注3)上記は、中長期試算において内閣府がデータを公表している2002年(度)から、2022年(度)までのデータに基づき分析を行ったもの。
44