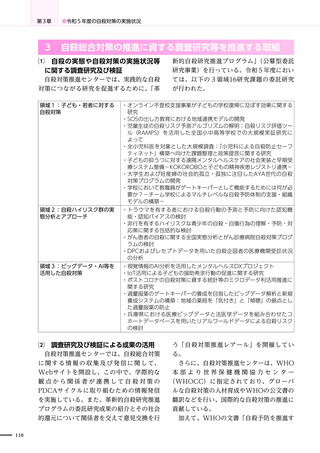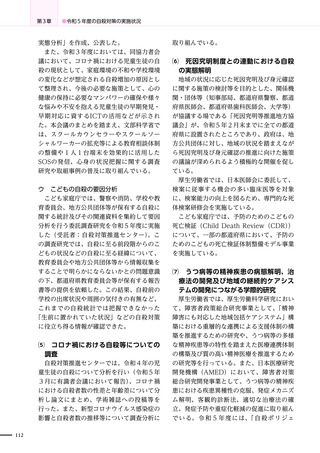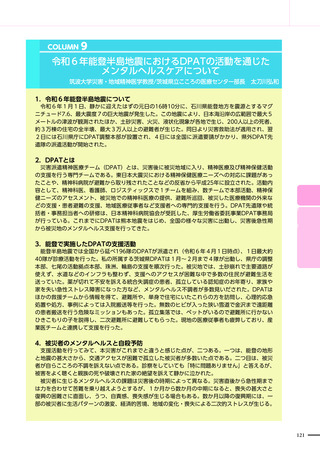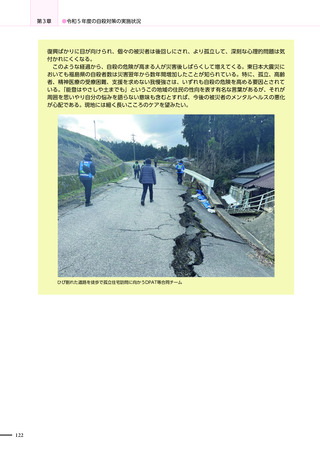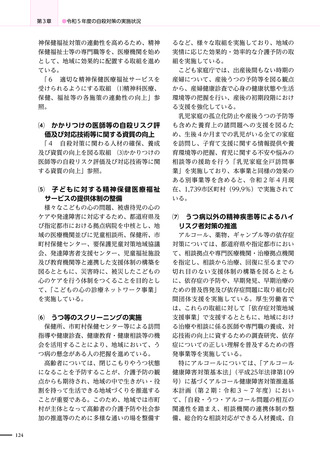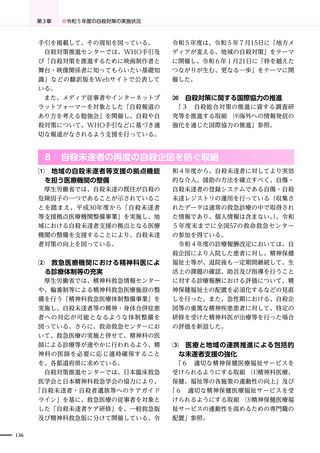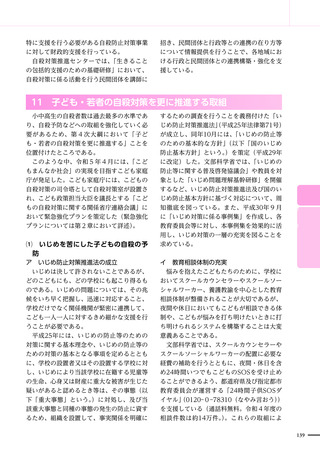よむ、つかう、まなぶ。
第3章 令和5年度の自殺対策の実施状況 本文 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
| 出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第3章
●令和5年度の自殺対策の実施状況
り、引き続き、教育相談体制の充実に努めて
いる。
なお、18歳以下の自殺は、学校の長期休
業明けにかけて増加する傾向があることか
ら、長期休業前から期間中、長期休業明けの
時期にかけて①学校における早期発見に向け
た取組、②保護者に対する家庭における見守
りの促進、③学校内外における集中的な見守
り活動、④ネットパトロールの強化を実施す
るよう各都道府県及び指定都市教育委員会等
に対して依頼した。
加えて、令和5年8月に、長期休業明け
に、児童生徒の自殺者数が増加する傾向を捉
え、様々な悩みや不安を抱える児童生徒に向
けて、悩みや不安を抱えていても決して一人
ではなく、周囲の人に悩みを話してほしい旨
のメッセージなどを、文部科学大臣より発出
した。
法務省の人権擁護機関では、「こどもの人
権SOSミニレター」(便箋兼封筒)を全国の
小中学校の児童生徒に配布し、手紙によりこ
どもたちの発するメッセージをいち早く受け
止め、悩みごと等に寄り添う事業を実施して
いるほか、「インターネット人権相談受付窓
口(SOS-eメール)」及びこどもの人権に関
する専用相談電話「こどもの人権110番」
(フ
リーダイヤル0120-007-110(全国共通))
の運用により、こどもたちがアクセスしやす
い体制の下で相談に応じ、いじめを始めとす
るこどもをめぐる人権問題の解決に努めてい
る(令和5年の「こどもの人権110番」によ
る相談件数は19,251件)。また、若年層にお
けるコミュニケーションツールが電話やメー
ル等からSNSへと変化している状況を踏ま
え、令和元年度から、チャットで相談を行う
「LINEじんけん相談」の運用を開始してい
る。
「7
社会全体の自殺リスクを低下させる
取組 ⒃相談の多様な手段の確保、アウト
リーチの強化」参照。
140
⑵
学生・生徒等への支援の充実
文部科学省では、不登校のこどもへの支援
として、令和5年3月に取りまとめた「誰一
人取り残されない学びの保障に向けた不登校
対策(COCOLOプラン)」に基づき、校内
教育支援センターの設置促進や教育支援セン
ターの機能強化、スクールカウンセラー等の
配置充実などを進めている。
また、高校中退者等を対象に、地域資源を
活用しながら高等学校卒業程度の学力を身に
付けさせるための学習相談及び学習支援等を
実施する地方公共団体の取組を支援する事業
を行っている。
「2 国民一人ひとりの気付きと見守りを
促す取組 ⑵児童生徒の自殺対策に資する教
育の実施」
、
「5 心の健康を支援する環境の
整備と心の健康づくりを推進する取組 ⑶学
校における心の健康づくり推進体制の整備」
、
「7 社会全体の自殺リスクを低下させる取
組 ⒃相談の多様な手段の確保、アウトリー
チの強化」及び「11 子ども・若者の自殺
対策を更に推進する取組 ⑴いじめを苦にし
た子どもの自殺の予防」参照。
⑶
SOSの出し方に関する教育等の推進
「2
国民一人ひとりの気付きと見守りを
促す取組 ⑵児童生徒の自殺対策に資する教
育の実施」及び「4 自殺対策に関わる人材
の確保、養成及び資質の向上を図る取組 ⑷
教職員に対する普及啓発等」参照。
⑷
子どもへの支援の充実
こども家庭庁では、親との離別・死別等に
より精神面や経済面で不安定な状況に置かれ
るひとり親家庭のこどもを対象に、放課後児
童クラブなどの終了後に、こどもの生活習慣
の習得支援・学習支援や軽食の提供をする
「こどもの生活・学習支援事業」を実施して
いる。
厚生労働省では、生活困窮世帯のこどもに
対し、生活困窮者自立支援法に基づく「子ど
もの学習・生活支援事業」により、学習支援
●令和5年度の自殺対策の実施状況
り、引き続き、教育相談体制の充実に努めて
いる。
なお、18歳以下の自殺は、学校の長期休
業明けにかけて増加する傾向があることか
ら、長期休業前から期間中、長期休業明けの
時期にかけて①学校における早期発見に向け
た取組、②保護者に対する家庭における見守
りの促進、③学校内外における集中的な見守
り活動、④ネットパトロールの強化を実施す
るよう各都道府県及び指定都市教育委員会等
に対して依頼した。
加えて、令和5年8月に、長期休業明け
に、児童生徒の自殺者数が増加する傾向を捉
え、様々な悩みや不安を抱える児童生徒に向
けて、悩みや不安を抱えていても決して一人
ではなく、周囲の人に悩みを話してほしい旨
のメッセージなどを、文部科学大臣より発出
した。
法務省の人権擁護機関では、「こどもの人
権SOSミニレター」(便箋兼封筒)を全国の
小中学校の児童生徒に配布し、手紙によりこ
どもたちの発するメッセージをいち早く受け
止め、悩みごと等に寄り添う事業を実施して
いるほか、「インターネット人権相談受付窓
口(SOS-eメール)」及びこどもの人権に関
する専用相談電話「こどもの人権110番」
(フ
リーダイヤル0120-007-110(全国共通))
の運用により、こどもたちがアクセスしやす
い体制の下で相談に応じ、いじめを始めとす
るこどもをめぐる人権問題の解決に努めてい
る(令和5年の「こどもの人権110番」によ
る相談件数は19,251件)。また、若年層にお
けるコミュニケーションツールが電話やメー
ル等からSNSへと変化している状況を踏ま
え、令和元年度から、チャットで相談を行う
「LINEじんけん相談」の運用を開始してい
る。
「7
社会全体の自殺リスクを低下させる
取組 ⒃相談の多様な手段の確保、アウト
リーチの強化」参照。
140
⑵
学生・生徒等への支援の充実
文部科学省では、不登校のこどもへの支援
として、令和5年3月に取りまとめた「誰一
人取り残されない学びの保障に向けた不登校
対策(COCOLOプラン)」に基づき、校内
教育支援センターの設置促進や教育支援セン
ターの機能強化、スクールカウンセラー等の
配置充実などを進めている。
また、高校中退者等を対象に、地域資源を
活用しながら高等学校卒業程度の学力を身に
付けさせるための学習相談及び学習支援等を
実施する地方公共団体の取組を支援する事業
を行っている。
「2 国民一人ひとりの気付きと見守りを
促す取組 ⑵児童生徒の自殺対策に資する教
育の実施」
、
「5 心の健康を支援する環境の
整備と心の健康づくりを推進する取組 ⑶学
校における心の健康づくり推進体制の整備」
、
「7 社会全体の自殺リスクを低下させる取
組 ⒃相談の多様な手段の確保、アウトリー
チの強化」及び「11 子ども・若者の自殺
対策を更に推進する取組 ⑴いじめを苦にし
た子どもの自殺の予防」参照。
⑶
SOSの出し方に関する教育等の推進
「2
国民一人ひとりの気付きと見守りを
促す取組 ⑵児童生徒の自殺対策に資する教
育の実施」及び「4 自殺対策に関わる人材
の確保、養成及び資質の向上を図る取組 ⑷
教職員に対する普及啓発等」参照。
⑷
子どもへの支援の充実
こども家庭庁では、親との離別・死別等に
より精神面や経済面で不安定な状況に置かれ
るひとり親家庭のこどもを対象に、放課後児
童クラブなどの終了後に、こどもの生活習慣
の習得支援・学習支援や軽食の提供をする
「こどもの生活・学習支援事業」を実施して
いる。
厚生労働省では、生活困窮世帯のこどもに
対し、生活困窮者自立支援法に基づく「子ど
もの学習・生活支援事業」により、学習支援