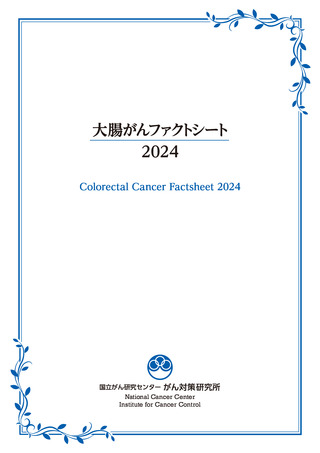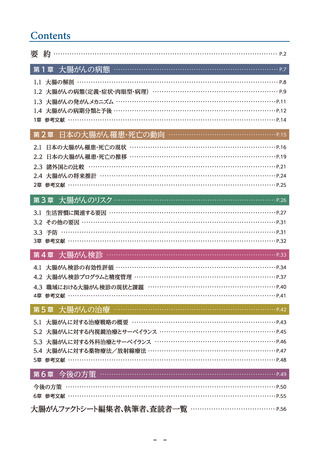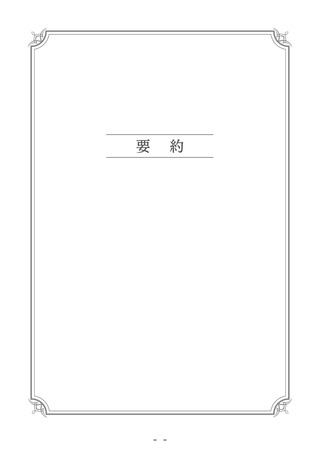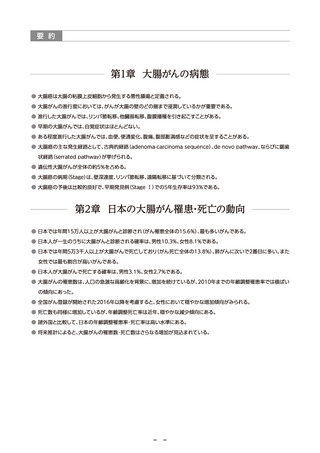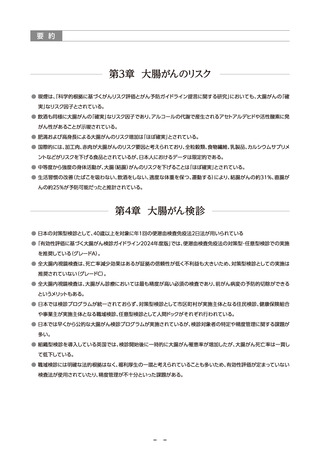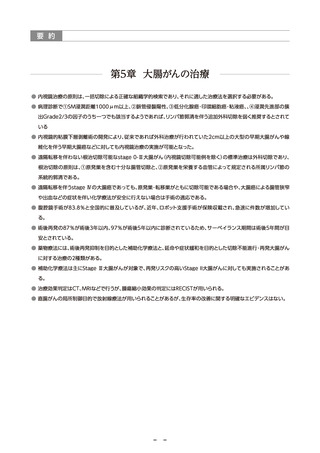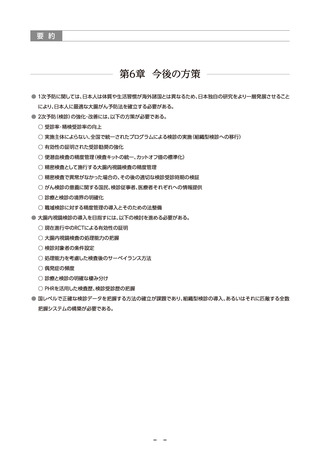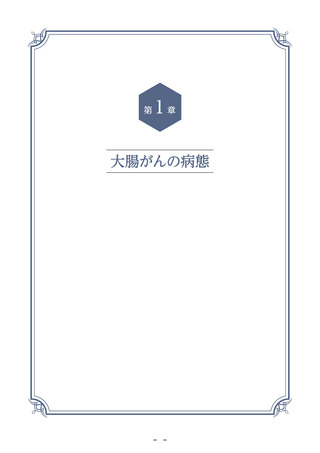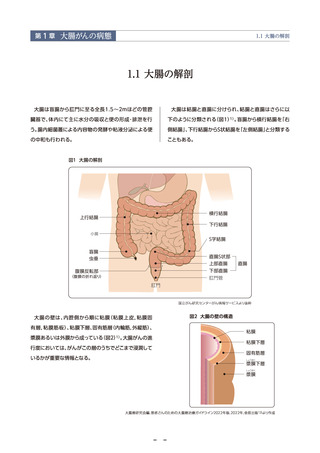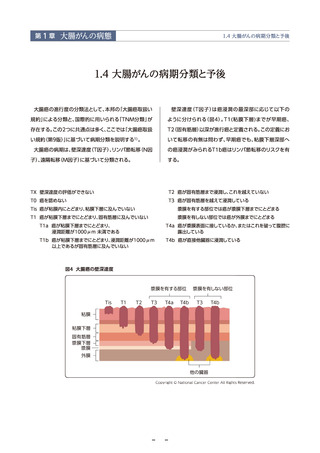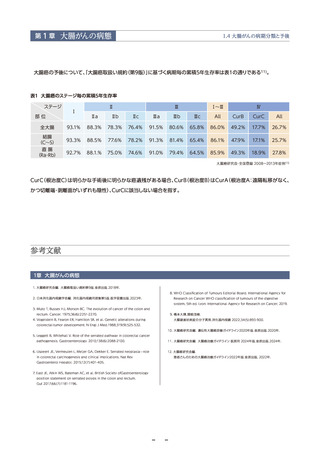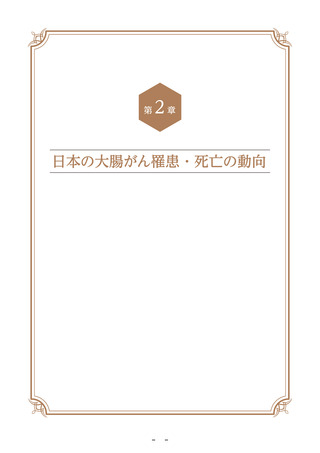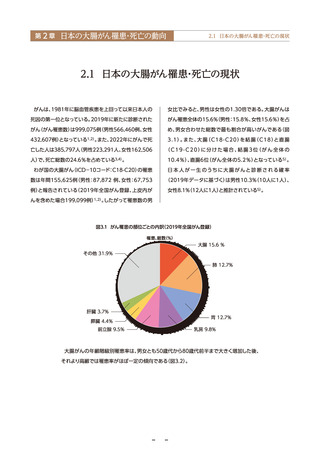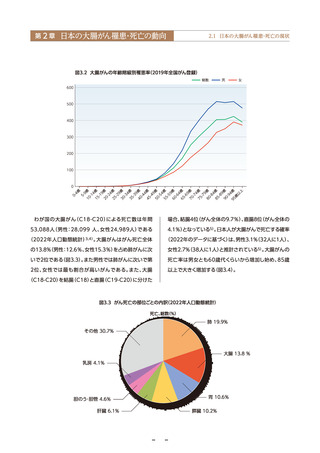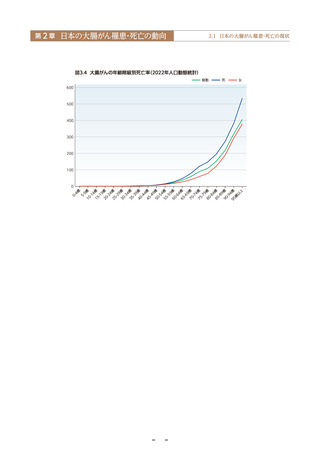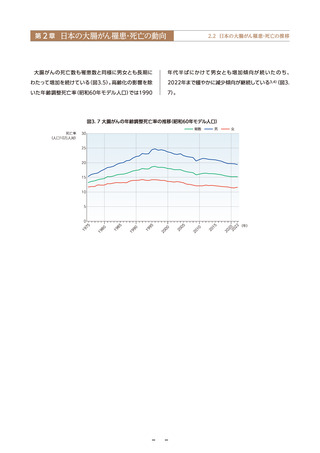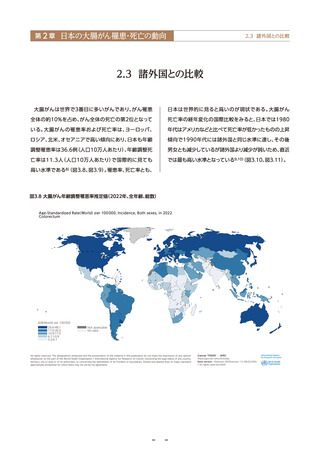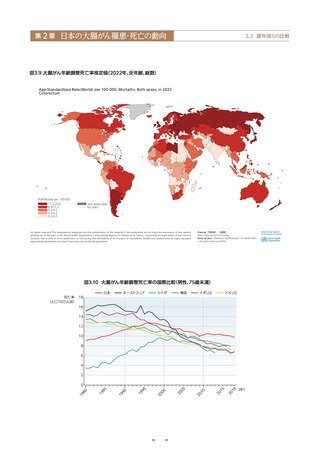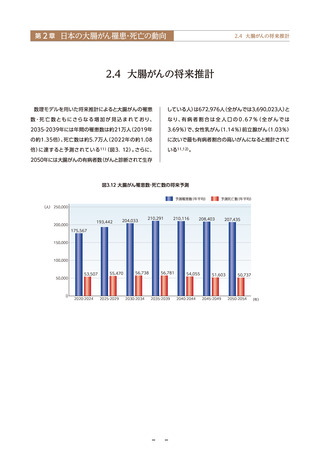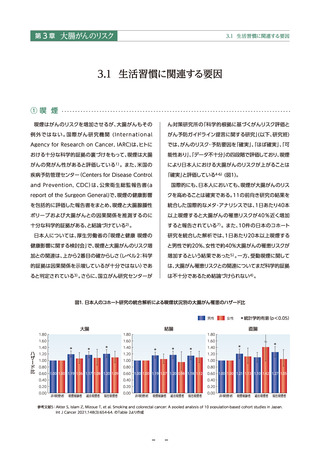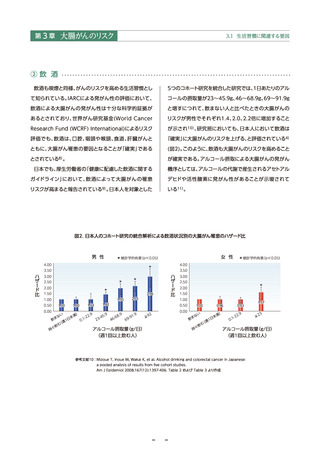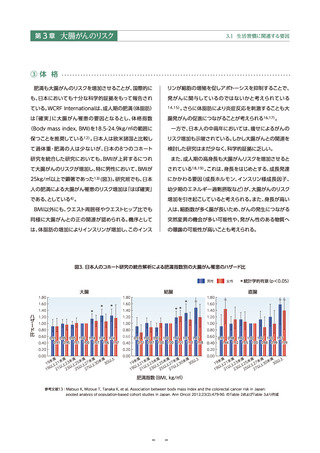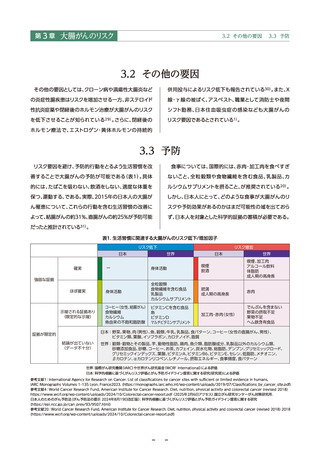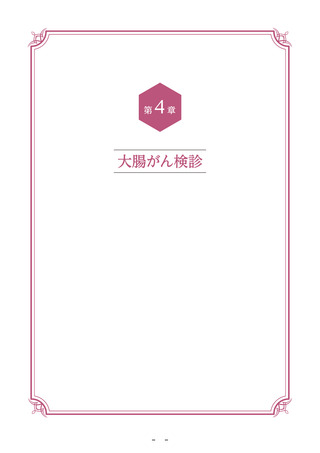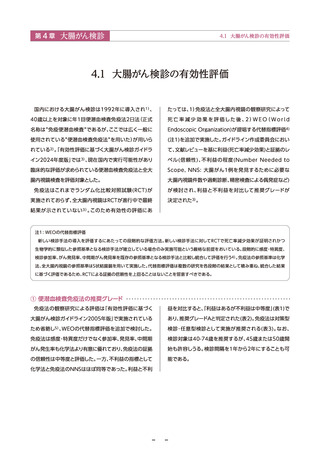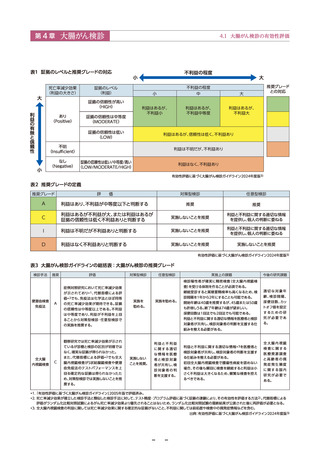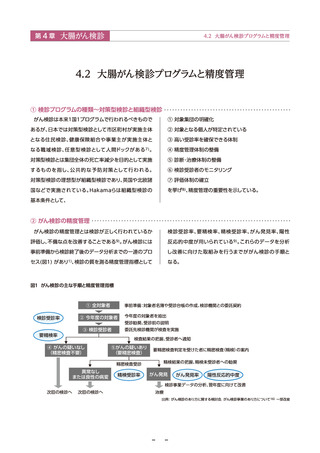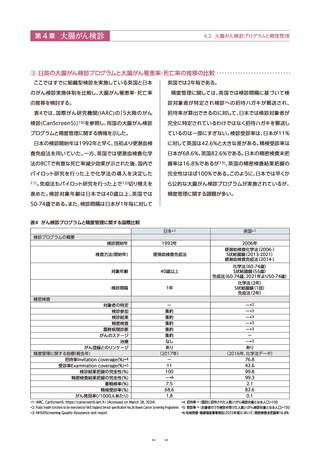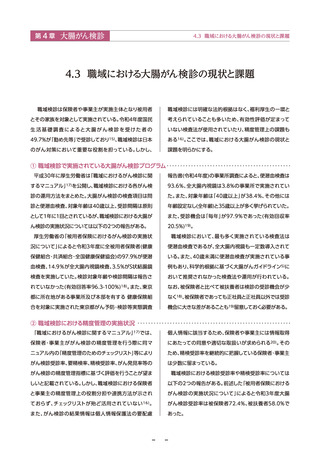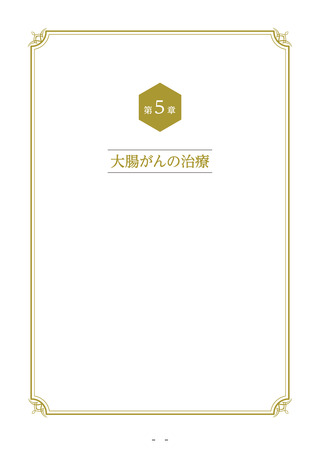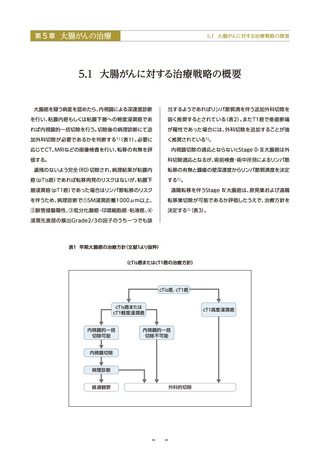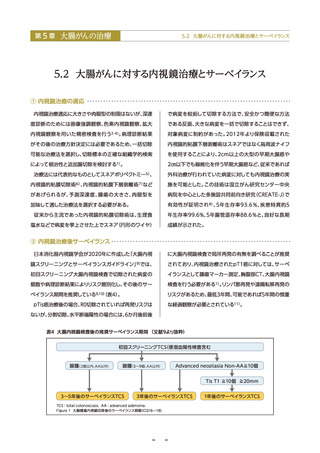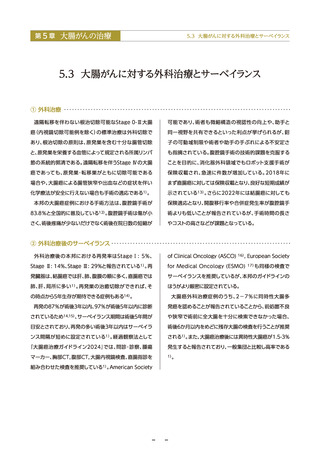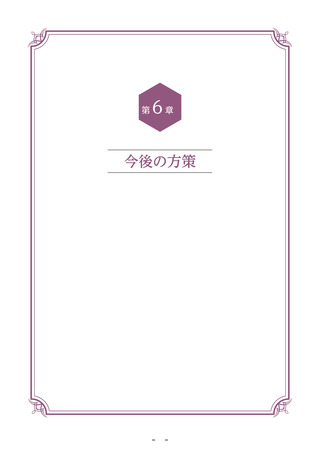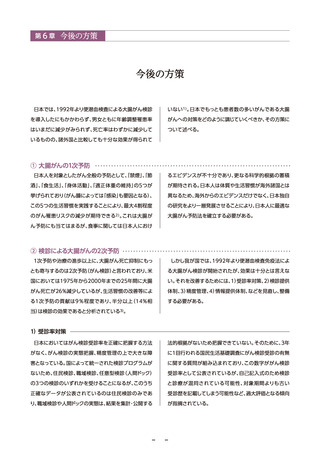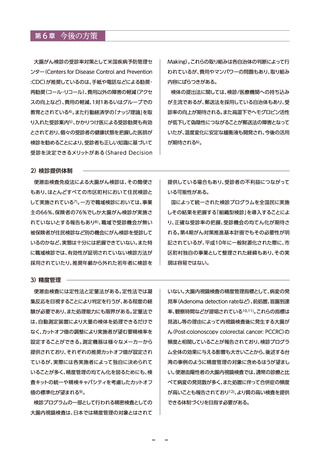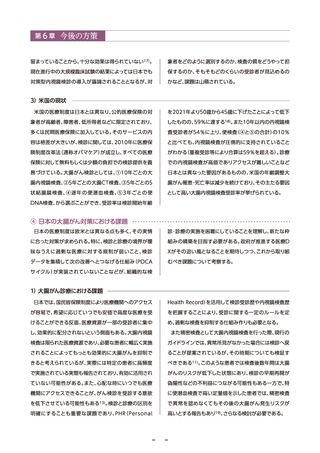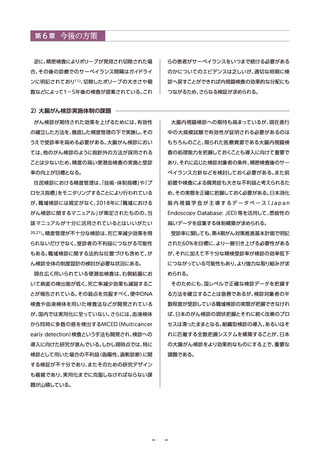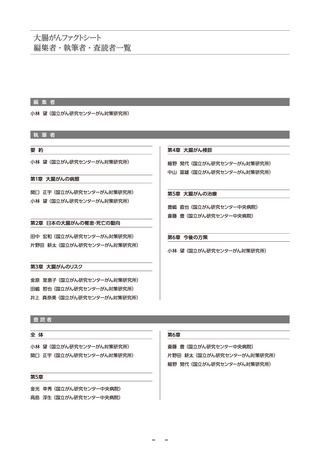よむ、つかう、まなぶ。
大腸がんファクトシート2024 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 大腸がん対策を推進するための「大腸がんファクトシート」公開(3/27)《国立がん研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第6章
今後の方策
大腸がん検診の受診率対策として米国疾病予防管理セ
Making)。これらの取り組みは各自治体の判断によって行
ンター(Centers for Disease Control and Prevention
われているが、費用やマンパワーの問題もあり、取り組み
:CDC)が推奨しているのは、手紙や電話などによる勧奨・
内容にばらつきがある。
再勧奨(コール・リコール)、費用以外の障害の軽減(アクセ
検体の提出法に関しては、検診/医療機関への持ち込み
スの向上など)、費用の軽減、1対1あるいはグループでの
が主流であるが、郵送法を採用している自治体もあり、受
教育とされている4)。また行動経済学の「ナッジ理論」を取
診率の向上が期待される。また高温下でヘモグロビン活性
り入れた受診案内5)、かかりつけ医による受診勧奨も有効
が低下して偽陰性につながることが郵送法の障害となって
とされており、個々の受診者の健康状態を把握した医師が
いたが、温度変化に安定な緩衝液も開発され、今後の活用
検診を勧めることにより、受診者も正しい知識に基づいて
が期待される6)。
受診を決定できるメリットがある(Shared Decision
2) 検診提供体制
便潜血検査免疫法による大腸がん検診は、その簡便さ
提供している場合もあり、受診者の不利益につながって
もあり、ほとんどすべての市区町村において住民検診と
いる可能性がある。
して実施されている7)。一方で職域検診においては、事業
国によって統一された検診プログラムを全国民に実施
主の66%、保険者の76%でしか大腸がん検診が実施さ
しその結果を把握する「組織型検診」を導入することによ
れていないとする報告もあり 8) 、職域で受診機会が無い
り、正確な受診率の把握、受診機会の均てん化が期待さ
被保険者が住民検診など別の機会にがん検診を受診して
れる。第4期がん対策推進基本計画でもその必要性が明
いるのかなど、実態は十分には把握できていない。また特
記されているが、平成10年に一般財源化された際に、市
に職域検診では、有効性が証明されていない検診方法が
区町村独自の事業として整理された経緯もあり、その実
採用されていたり、推奨年齢から外れた若年者に検診を
現は容易ではない。
3) 精度管理
便潜血検査には定性法と定量法がある。定性法では凝
いない。大腸内視鏡検査の精度管理指標として、病変の発
集反応を目視することにより判定を行うが、ある程度の経
見率(Adenoma detection rateなど)、前処置、盲腸到達
験が必要であり、また処理能力にも限界がある。定量法で
率、観察時間などが提唱されている10,11)。これらの指標は
は、自動測定装置により大量の検体を処理できるだけで
見逃し等の理由によって内視鏡検査後に発生する大腸が
なく、カットオフ値の調整により実施者が望む要精検率を
ん(Post-colonoscopy colorectal cancer: PCCRC)の
設定することができる。測定機器は様々なメーカーから
頻度と相関していることが報告されており、検診プログラ
提供されており、それぞれの推奨カットオフ値が設定され
ム全体の効果に与える影響も大きいことから、後述する台
ているが、実際には各実施者によって独自に決められて
湾の事例のように精度管理の対象に含めるほうが望まし
いることが多く、精度管理の均てん化を図るためにも、検
い。便潜血陽性者の大腸内視鏡検査では、通常の診療と比
査キットの統一や精検キャパシティを考慮したカットオフ
べて病変の発見数が多く、また処置に伴って合併症の頻度
値の標準化が望まれる9)。
が高いことも報告されており12)、より質の高い検査を提供
検診プログラムの一部として行われる精密検査としての
できる体制づくりを目指す必要がある。
大腸内視鏡検査は、日本では精度管理の対象とはされて
ー 51 ー
今後の方策
大腸がん検診の受診率対策として米国疾病予防管理セ
Making)。これらの取り組みは各自治体の判断によって行
ンター(Centers for Disease Control and Prevention
われているが、費用やマンパワーの問題もあり、取り組み
:CDC)が推奨しているのは、手紙や電話などによる勧奨・
内容にばらつきがある。
再勧奨(コール・リコール)、費用以外の障害の軽減(アクセ
検体の提出法に関しては、検診/医療機関への持ち込み
スの向上など)、費用の軽減、1対1あるいはグループでの
が主流であるが、郵送法を採用している自治体もあり、受
教育とされている4)。また行動経済学の「ナッジ理論」を取
診率の向上が期待される。また高温下でヘモグロビン活性
り入れた受診案内5)、かかりつけ医による受診勧奨も有効
が低下して偽陰性につながることが郵送法の障害となって
とされており、個々の受診者の健康状態を把握した医師が
いたが、温度変化に安定な緩衝液も開発され、今後の活用
検診を勧めることにより、受診者も正しい知識に基づいて
が期待される6)。
受診を決定できるメリットがある(Shared Decision
2) 検診提供体制
便潜血検査免疫法による大腸がん検診は、その簡便さ
提供している場合もあり、受診者の不利益につながって
もあり、ほとんどすべての市区町村において住民検診と
いる可能性がある。
して実施されている7)。一方で職域検診においては、事業
国によって統一された検診プログラムを全国民に実施
主の66%、保険者の76%でしか大腸がん検診が実施さ
しその結果を把握する「組織型検診」を導入することによ
れていないとする報告もあり 8) 、職域で受診機会が無い
り、正確な受診率の把握、受診機会の均てん化が期待さ
被保険者が住民検診など別の機会にがん検診を受診して
れる。第4期がん対策推進基本計画でもその必要性が明
いるのかなど、実態は十分には把握できていない。また特
記されているが、平成10年に一般財源化された際に、市
に職域検診では、有効性が証明されていない検診方法が
区町村独自の事業として整理された経緯もあり、その実
採用されていたり、推奨年齢から外れた若年者に検診を
現は容易ではない。
3) 精度管理
便潜血検査には定性法と定量法がある。定性法では凝
いない。大腸内視鏡検査の精度管理指標として、病変の発
集反応を目視することにより判定を行うが、ある程度の経
見率(Adenoma detection rateなど)、前処置、盲腸到達
験が必要であり、また処理能力にも限界がある。定量法で
率、観察時間などが提唱されている10,11)。これらの指標は
は、自動測定装置により大量の検体を処理できるだけで
見逃し等の理由によって内視鏡検査後に発生する大腸が
なく、カットオフ値の調整により実施者が望む要精検率を
ん(Post-colonoscopy colorectal cancer: PCCRC)の
設定することができる。測定機器は様々なメーカーから
頻度と相関していることが報告されており、検診プログラ
提供されており、それぞれの推奨カットオフ値が設定され
ム全体の効果に与える影響も大きいことから、後述する台
ているが、実際には各実施者によって独自に決められて
湾の事例のように精度管理の対象に含めるほうが望まし
いることが多く、精度管理の均てん化を図るためにも、検
い。便潜血陽性者の大腸内視鏡検査では、通常の診療と比
査キットの統一や精検キャパシティを考慮したカットオフ
べて病変の発見数が多く、また処置に伴って合併症の頻度
値の標準化が望まれる9)。
が高いことも報告されており12)、より質の高い検査を提供
検診プログラムの一部として行われる精密検査としての
できる体制づくりを目指す必要がある。
大腸内視鏡検査は、日本では精度管理の対象とはされて
ー 51 ー