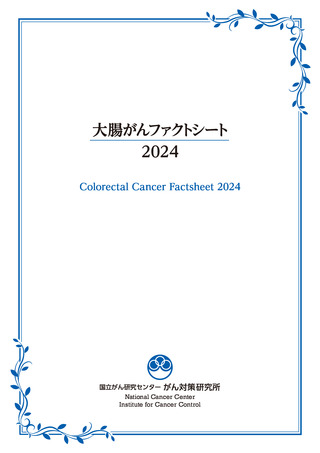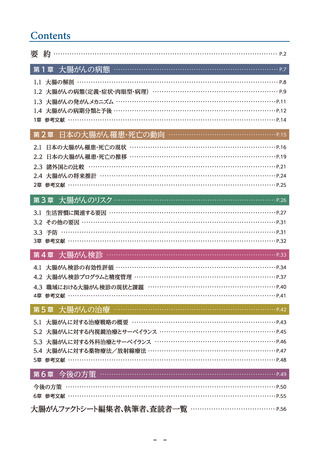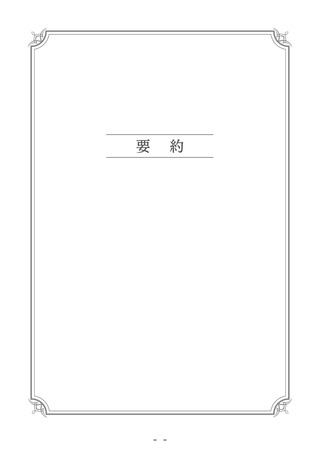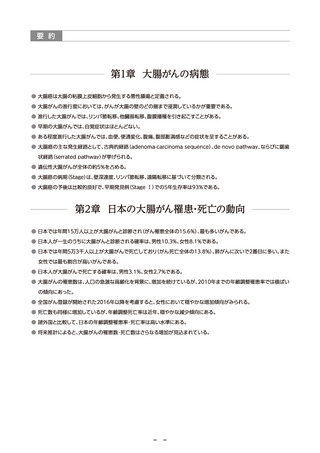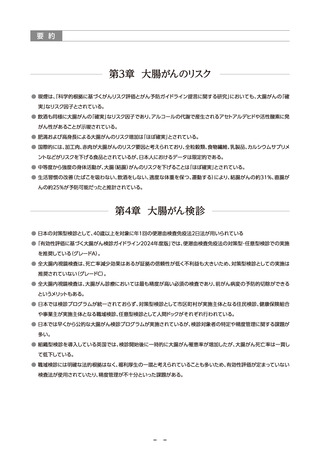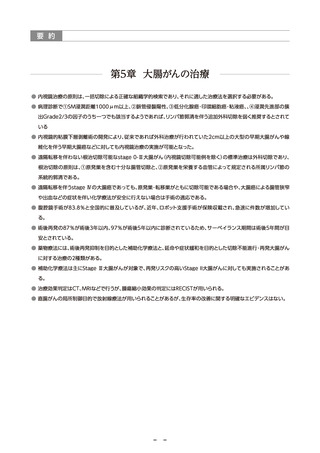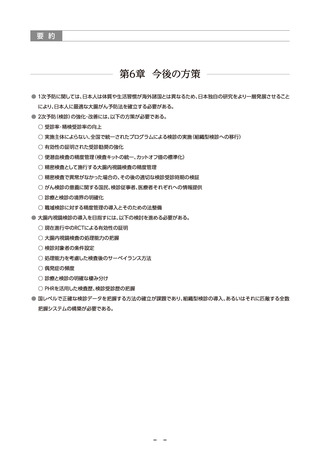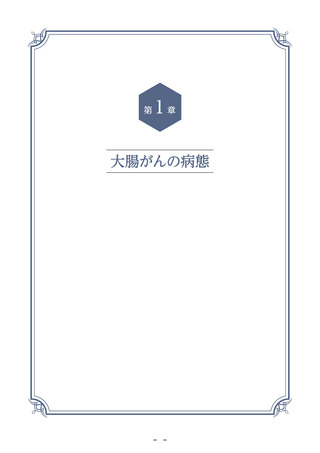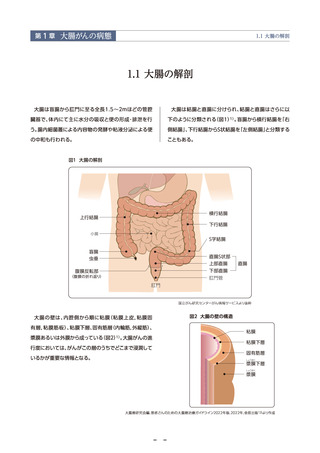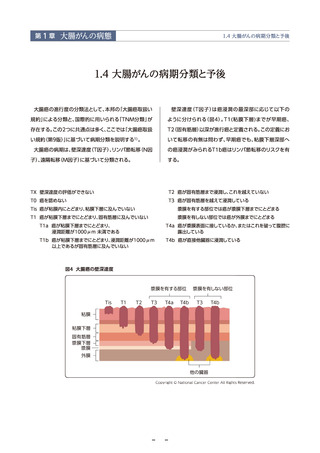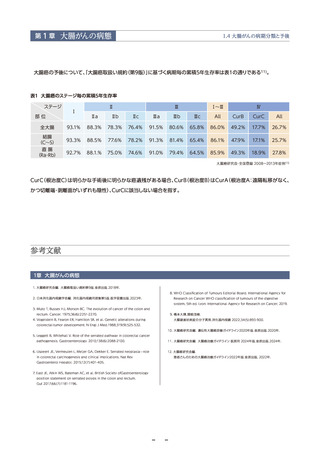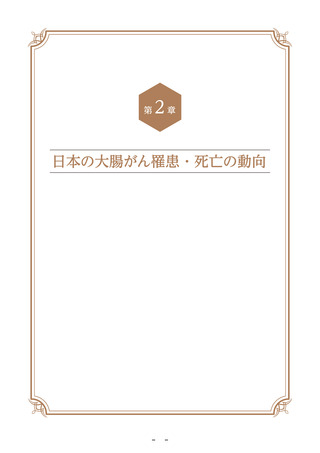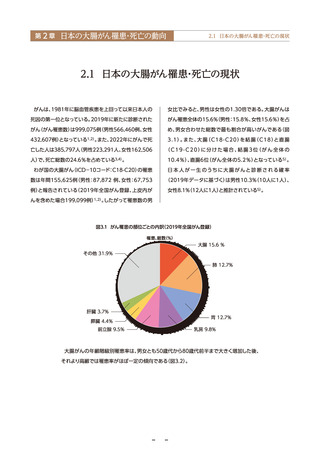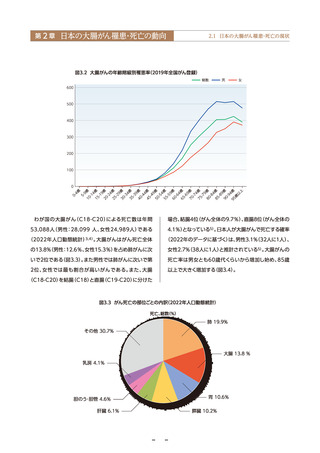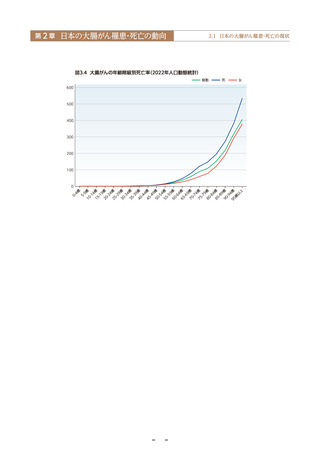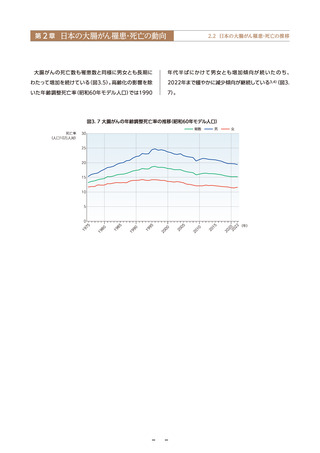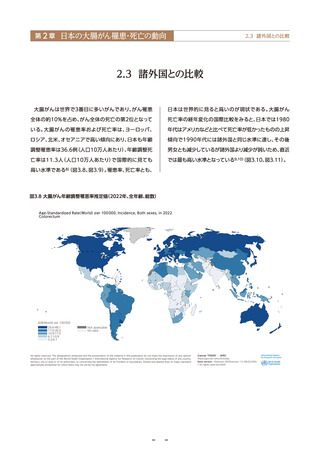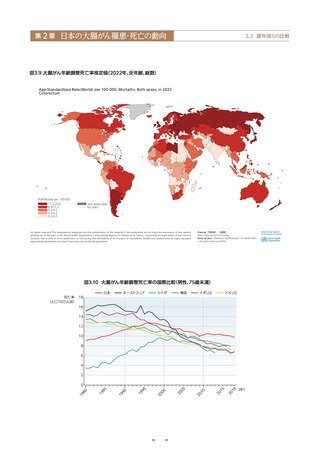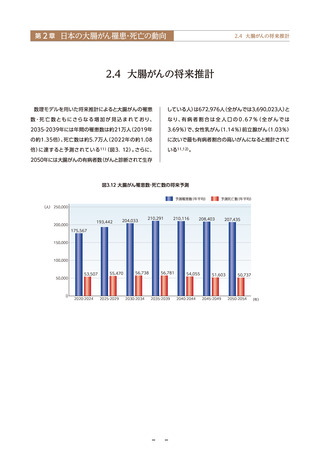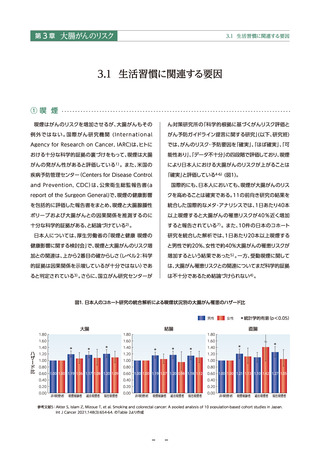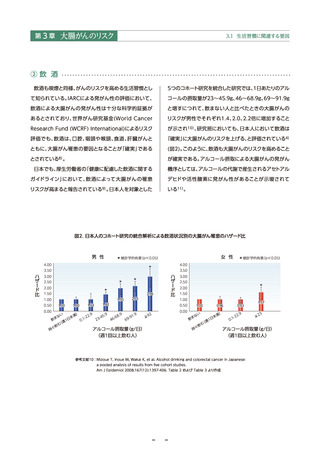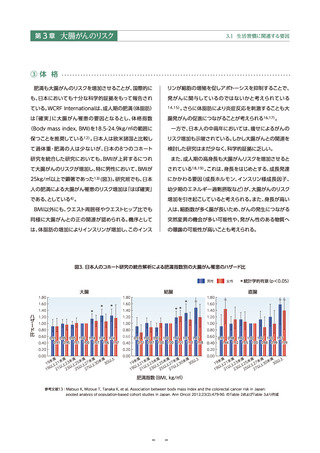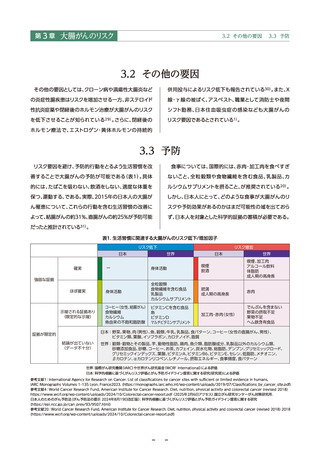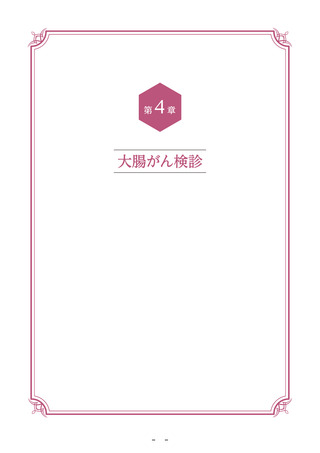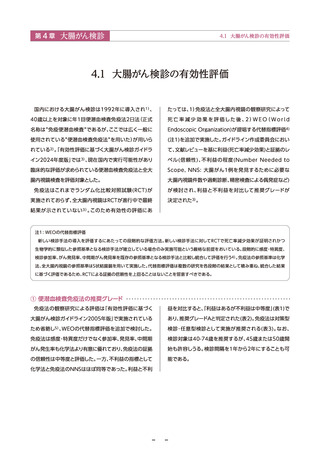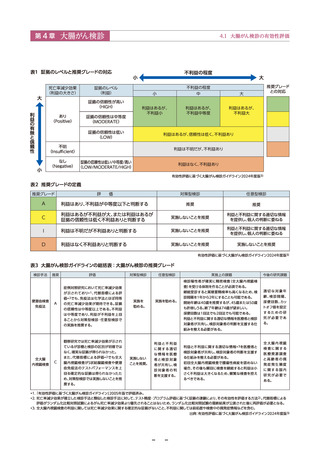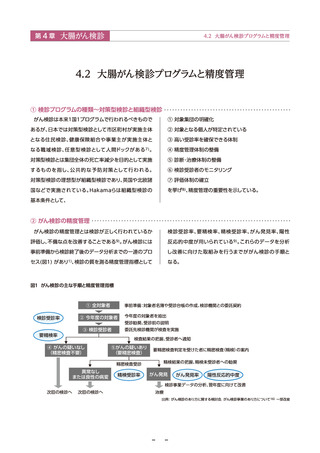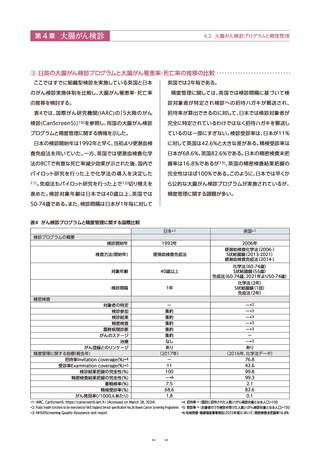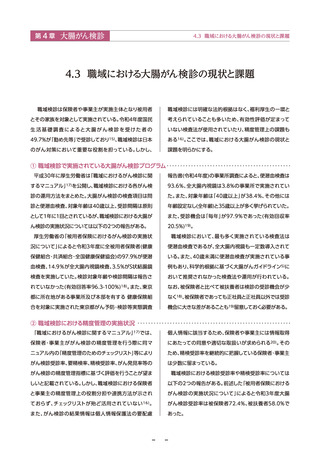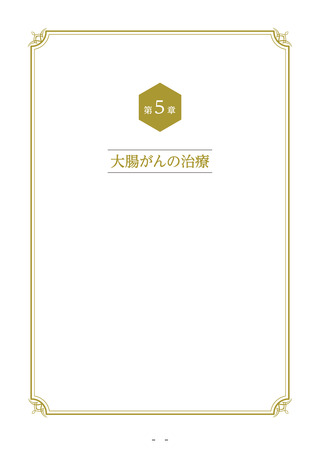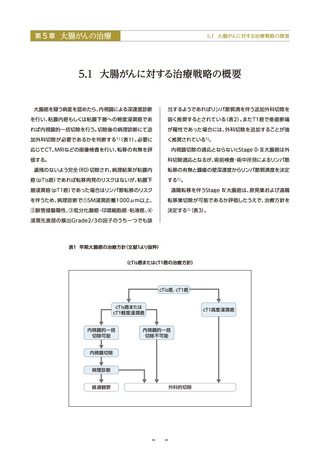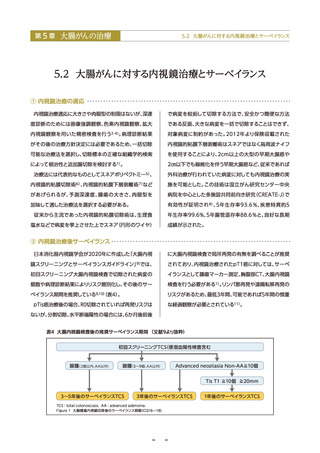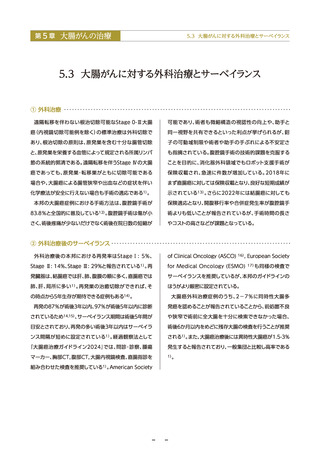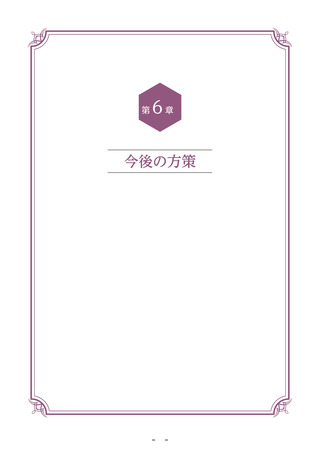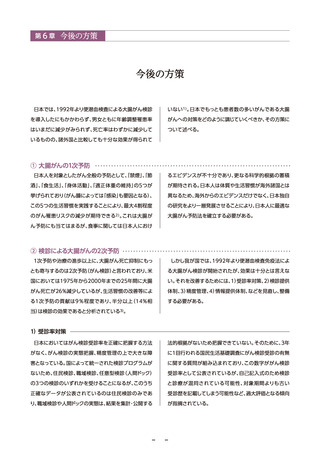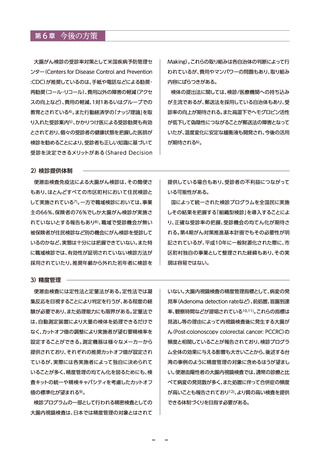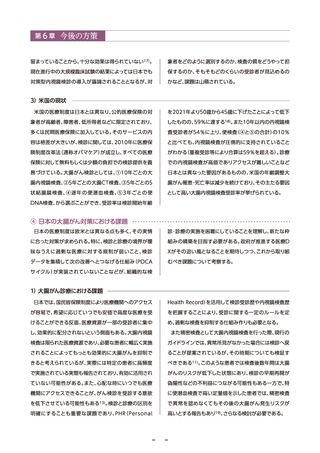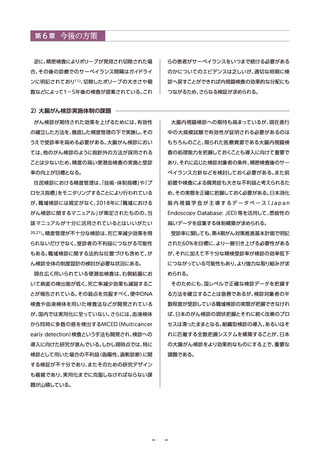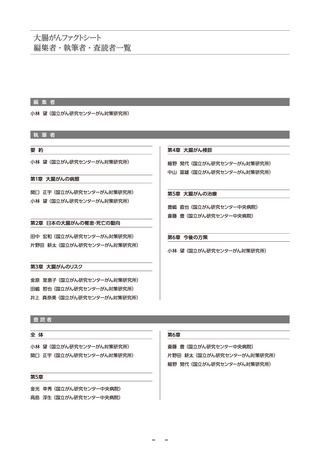よむ、つかう、まなぶ。
大腸がんファクトシート2024 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 大腸がん対策を推進するための「大腸がんファクトシート」公開(3/27)《国立がん研究センター》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第6章
今後の方策
留まっていることから、十分な効果は得られていない17)。
象者をどのように選別するのか、検査の質をどうやって担
現在進行中の大規模臨床試験の結果によっては日本でも
保するのか、そもそもどのくらいの受診者が見込めるの
対策型内視鏡検診の導入が議論されることとなるが、対
かなど、課題は山積されている。
3) 米国の現状
米国の医療制度は日本とは異なり、公的医療保険の対
を2021年より50歳から45歳に下げたことによって低下
象者が高齢者、障害者、低所得者などに限定されており、
したものの、59%に達する18)。また10年以内の内視鏡検
多くは民間医療保険に加入している。そのサービスの内
査受診者が54%に上り、便検査(④と⑤の合計)の10%
容は格差が大きいが、検診に関しては、2010年に医療保
と比べても、内視鏡検査が圧倒的に支持されていること
険制度改革法(通称オバマケア)が成立し、すべての医療
がわかる(重複受診等により合算は59%を超える)。診療
保険に対して無料もしくは少額の負担での検診提供を義
での内視鏡検査が高価でありアクセスが難しいことなど
務づけている。大腸がん検診としては、①10年ごとの大
日本とは異なった要因があるものの、米国の年齢調整大
腸内視鏡検査、②5年ごとの大腸CT検査、③5年ごとのS
腸がん罹患・死亡率は減少を続けており、その主たる要因
状結腸鏡検査、④逐年の便潜血検査、⑤3年ごとの便
として高い大腸内視鏡検査受診率が挙げられている。
DNA検査、から選ぶことができ、受診率は検診開始年齢
④ 日本の大腸がん対策における課題
日本の医療制度は欧米とは異なる点も多く、その実情
診・診療の実施を困難にしていることを理解し、新たな枠
に合った対策が求められる。特に、検診と診療の境界が曖
組みの構築を目指す必要がある。政府が推進する医療D
昧なうえに過剰な医療に対する規制が弱いこと、検診
Xがその追い風となることを期待しつつ、これから取り組
データを集積して次の改善へとつなげる仕組み(PDCA
むべき課題について考察する。
サイクル)が実装されていないことなどが、組織的な検
1) 大腸がん診療における課題
日本では、国民皆保険制度により医療機関へのアクセス
Health Record)を活用して検診受診歴や内視鏡検査歴
が容易で、希望に応じていつでも安価で高度な医療を受
を把握することにより、受診に関する一定のルールを定
けることができる反面、医療資源が一部の受診者に集中
め、過剰な検査を抑制する仕組み作りも必要となる。
し、効果的に配分されないという側面もある。大腸内視鏡
また精密検査として大腸内視鏡検査を行った際、現行の
検査は限られた医療資源であり、必要な患者に幅広く実施
ガイドラインでは、異常所見がなかった場合には検診へ戻
されることによってもっとも効果的に大腸がんを抑制で
ることが提案されているが、その時期についても検証す
きると考えられているが、実際には特定の患者に高頻度
べきである11)。このような患者では検査後数年間は大腸
で実施されている実態も報告されており、有効に活用され
がんのリスクが低下した状態にあり、検診の早期再開が
ていない可能性がある。また、心配な時にいつでも医療
偽陽性などの不利益につながる可能性もある一方で、特
機関にアクセスできることが、がん検診を受診する意欲
に便潜血検査で高い定量値を示した患者では、精密検査
を低下させている可能性もある13)。検診と診療の区別を
で異常を認めなくてもその後の大腸がん発生リスクが
明確にすることも重要な課題であり、PHR(Personal
高いとする報告もあり19)、さらなる検討が必要である。
ー 53 ー
今後の方策
留まっていることから、十分な効果は得られていない17)。
象者をどのように選別するのか、検査の質をどうやって担
現在進行中の大規模臨床試験の結果によっては日本でも
保するのか、そもそもどのくらいの受診者が見込めるの
対策型内視鏡検診の導入が議論されることとなるが、対
かなど、課題は山積されている。
3) 米国の現状
米国の医療制度は日本とは異なり、公的医療保険の対
を2021年より50歳から45歳に下げたことによって低下
象者が高齢者、障害者、低所得者などに限定されており、
したものの、59%に達する18)。また10年以内の内視鏡検
多くは民間医療保険に加入している。そのサービスの内
査受診者が54%に上り、便検査(④と⑤の合計)の10%
容は格差が大きいが、検診に関しては、2010年に医療保
と比べても、内視鏡検査が圧倒的に支持されていること
険制度改革法(通称オバマケア)が成立し、すべての医療
がわかる(重複受診等により合算は59%を超える)。診療
保険に対して無料もしくは少額の負担での検診提供を義
での内視鏡検査が高価でありアクセスが難しいことなど
務づけている。大腸がん検診としては、①10年ごとの大
日本とは異なった要因があるものの、米国の年齢調整大
腸内視鏡検査、②5年ごとの大腸CT検査、③5年ごとのS
腸がん罹患・死亡率は減少を続けており、その主たる要因
状結腸鏡検査、④逐年の便潜血検査、⑤3年ごとの便
として高い大腸内視鏡検査受診率が挙げられている。
DNA検査、から選ぶことができ、受診率は検診開始年齢
④ 日本の大腸がん対策における課題
日本の医療制度は欧米とは異なる点も多く、その実情
診・診療の実施を困難にしていることを理解し、新たな枠
に合った対策が求められる。特に、検診と診療の境界が曖
組みの構築を目指す必要がある。政府が推進する医療D
昧なうえに過剰な医療に対する規制が弱いこと、検診
Xがその追い風となることを期待しつつ、これから取り組
データを集積して次の改善へとつなげる仕組み(PDCA
むべき課題について考察する。
サイクル)が実装されていないことなどが、組織的な検
1) 大腸がん診療における課題
日本では、国民皆保険制度により医療機関へのアクセス
Health Record)を活用して検診受診歴や内視鏡検査歴
が容易で、希望に応じていつでも安価で高度な医療を受
を把握することにより、受診に関する一定のルールを定
けることができる反面、医療資源が一部の受診者に集中
め、過剰な検査を抑制する仕組み作りも必要となる。
し、効果的に配分されないという側面もある。大腸内視鏡
また精密検査として大腸内視鏡検査を行った際、現行の
検査は限られた医療資源であり、必要な患者に幅広く実施
ガイドラインでは、異常所見がなかった場合には検診へ戻
されることによってもっとも効果的に大腸がんを抑制で
ることが提案されているが、その時期についても検証す
きると考えられているが、実際には特定の患者に高頻度
べきである11)。このような患者では検査後数年間は大腸
で実施されている実態も報告されており、有効に活用され
がんのリスクが低下した状態にあり、検診の早期再開が
ていない可能性がある。また、心配な時にいつでも医療
偽陽性などの不利益につながる可能性もある一方で、特
機関にアクセスできることが、がん検診を受診する意欲
に便潜血検査で高い定量値を示した患者では、精密検査
を低下させている可能性もある13)。検診と診療の区別を
で異常を認めなくてもその後の大腸がん発生リスクが
明確にすることも重要な課題であり、PHR(Personal
高いとする報告もあり19)、さらなる検討が必要である。
ー 53 ー